MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2015.04.06
Medical Library 書評・新刊案内
福永 篤志 著
稲葉 一人 法律監修
《評 者》寳金 清博(北大大学院教授・脳神経外科学/北大病院病院長)
医師の視点から,実例に沿って法律を解説した稀有な一冊
 メディアを見ると,医療と法の絡んだ問題が目に入らない日はないと言っても過言ではない。当然である。私たちの行う医療は,「法」によって規定されている。本来,私たち医師は必須学習事項として「法」を学ぶべきである。しかし,医学部での系統的な教育を全く受けないまま,real worldに放り出されるのが現実である。多くの医師が,実際に医療現場に出て,突然,深刻な問題に遭遇し,ぼうぜんとするのが現状である。その意味で,全ての医師の方に,本書を推薦したい。このような本は,日本にはこの一冊しかないと確信する。
メディアを見ると,医療と法の絡んだ問題が目に入らない日はないと言っても過言ではない。当然である。私たちの行う医療は,「法」によって規定されている。本来,私たち医師は必須学習事項として「法」を学ぶべきである。しかし,医学部での系統的な教育を全く受けないまま,real worldに放り出されるのが現実である。多くの医師が,実際に医療現場に出て,突然,深刻な問題に遭遇し,ぼうぜんとするのが現状である。その意味で,全ての医師の方に,本書を推薦したい。このような本は,日本にはこの一冊しかないと確信する。
先日,若い裁判官の勉強会で講演と情報交換をさせてもらった。その際,医療と裁判の世界の違いをあらためて痛感させられた。教育課程における履修科目も全く異なる。生物学,数学は言うまでもなく,統計学や文学も若い法律家には必須科目ではないのである。統計学の知識は,今日の裁判で必須ではないかという確信があった私には少々ショックであった。その席で,いわゆるエビデンスとかビッグデータを用いた,コンピューターによる診断精度が医師の診断を上回る時代になりつつあることが話題になった。同様に,スーパーコンピューターなどの力を借りて,数理学的,統計学的手法を導入し,自然科学的な判断論理を,法の裁きの場に持ち込むことはできないかと若い法律家に聞いたが,ほぼ全員が無理だと答えた。法律は「文言主義」ではあるが,一例一例が複雑系のようなもので,判例を数理的に処理されたデータベースはおそらく何の役にも立たないというのが彼らの一致した意見であった。法律の世界での論理性と医療の世界での論理性は,どちらが正しいという以前に,出自の異なる論理体系を持っているのではないかと思うときがある。医師と法律家の間には,細部の違いではなく,次元の違う乗り越えられない深い溝が存在するのではというある種の絶望感が残った。
この若い裁判官たちとのコンタクトの後,偶然,幸運なことに本書に接する機会を得た。医師の論理の視点から,法律の論理を学ぶものとして,本書は,極めて価値が高く,稀有なものである。筆者の福永氏は,医師であり,法学を専攻された専門家であり,両方のロジックに精通するまれな専門家である。本書は,医師が,法律家の論理を理解するために,実にわかりやすく,丁寧に,しかも,実例に沿って書かれた力作である。本書に匹敵する成書を私は知らない。
その一方で,こうした優れた本が「稀有」なものであり,医学教育において「法学」が極端に欠如していることは,私たち,医師に警鐘を鳴らすものである。本書は「法」に興味のある医師に読まれるだけでなく,医学教育における法学の重要性を指摘するものとして,医学教育にかかわる関係者にも読まれるべきものである。そして,できることであれば,先日,語り合った若い裁判官の方々にも読んでもらいたいと願う。
B6・頁344 定価:本体2,200円+税 医学書院
ISBN978-4-260-02011-4


姫井 昭男 著
《評 者》宮崎 仁(宮崎医院院長)
こんなことをズバリと教えてくれる精神科医はいなかった
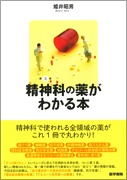 世の中には,「精神科の薬は,うさんくさい」と思っている人が多い。その中には,患者だけではなく,精神科を専門としない医師や対人援助職もたくさん含まれている。
世の中には,「精神科の薬は,うさんくさい」と思っている人が多い。その中には,患者だけではなく,精神科を専門としない医師や対人援助職もたくさん含まれている。
一方,精神科を専門としない医師や対人援助職が,精神科の薬のことを無視して,自分の仕事を進めることはできない。プライマリ・ケアの外来を受診する患者の3-4割は,何らかの精神疾患や精神科的問題を持っている。また,統合失調症のために精神科で薬物治療を受けている患者が,風邪をひいてくることもあるし,介護を要する状態になることだってある。「精神科の薬は,うさんくさい」と敬遠してはいられないのが,リアルな現場の状況なのである。
そこで,一念発起して,精神科の薬について真面目に勉強しようと,精神薬理学のテキストと格闘してみても,次々と登場するレセプターやら神経回路やらに翻弄され,頭の中は,ますますモヤモヤして,途方に暮れることになる。
そんなときこそ,本書『精神科の薬がわかる本』の出番だ。
冒頭に置かれた「『抗うつ薬』がわかる。」という章のページを開くと,いきなり「原因は未解明。実は対症療法なのです」という見出しの文字が目に飛びこんでくる。そうか,うつ病の薬物療法は「対症療法」だったのか。こんなことを,ズバリと教えてくれる精神科医はいなかった。これだけで,ずいぶんとスッキリする。
「ざっと知りたい」という初学者からのわがままな要望に応えるのが,初版以来の本書の優れたコンセプトであるが,精神...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.17
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
インタビュー 2026.02.10
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
