MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2014.12.22
Medical Library 書評・新刊案内
吉川 ひろみ,齋藤 さわ子 編
《評 者》大橋 秀行(埼玉県立大教授・作業療法学)
理念と手段を明示した,意味ある作業療法の実践書
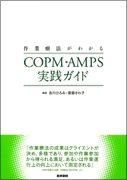 本書は,COPM(カナダ作業遂行測定)とAMPS(運動とプロセス技能評価)という評価法をどう使って作業療法を実践するかについて書かれた本である。COPMは,患者が生活の中の作業について,自身の価値観に基づいて患者自身が評価する方法である。AMPSは,患者が一人ひとりの異なった生活の中で作業がうまくできるかどうかを認定された作業療法士が評価する方法である。
本書は,COPM(カナダ作業遂行測定)とAMPS(運動とプロセス技能評価)という評価法をどう使って作業療法を実践するかについて書かれた本である。COPMは,患者が生活の中の作業について,自身の価値観に基づいて患者自身が評価する方法である。AMPSは,患者が一人ひとりの異なった生活の中で作業がうまくできるかどうかを認定された作業療法士が評価する方法である。
COPMやAMPSは評価法であるから,実際にどのように介入して,作業療法としてどのような結果を出したかがわからないと,なぜCOPMやAMPSが良いのかがわからない。そういう意味では,本書全体の約4割のページ数を割いたさまざまな分野の多数の事例から読み始めることも良いと思う。
現在,日本作業療法士協会は,作業療法の定義を約50年ぶりに新たにしようと検討中である。新しい定義を検討する上で,インパクトを与えているのは,本書が取り上げているCOPMやAMPSによって立つ考え,つまり,当事者にとって意味のある作業が生活の中で継続してできることに焦点を当てる作業療法の考え方であり実践である。医学的な意味の機能改善の手段として作業を使用するというこれまでの作業療法の定義とは異なる考え方である。私事だが,2011年の第45回日本作業療法学会の学会長をさせていただいた際に,テーマを「意味のある作業の実現」としたが,開催の準備期間中や開催後も,このテーマの主旨を重要視する人たちや社会的な動きが,一見無関係にいくつも存在することを知って驚いた経験がある。これは何か大きな必然性があるのではないかと思わざるを得なかった。もっと言えば,COPMやAMPSを開発した作業療法士たちの思いや考えの底にも流れている時代の潮流が存在するような感慨を持った。それは作業療法の世界にとどまらないもので,還元主義批判や客観的真理と価値観との関係性をめぐるような哲学的な認識の変化であるような気がする。
個々の作業療法士は,明確な作業療法の定義を自覚して日々の業務を行っているわけではない。新たな定義が権威ある組織から提出されても,個々の作業療法士が劇的に考え方や行動を変えるような事態は実際には起こらないだろう。むしろ,すでに行っ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。


