MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2013.09.16
Medical Library 書評・新刊案内
ストラクチャークラブ・ジャパン 監修
古田 晃,原 英彦,有田 武史,森野 禎浩 編
《評 者》吉川 純一(西宮渡辺心臓・血管センター院長)
SHDインターベンションを科学的に解説
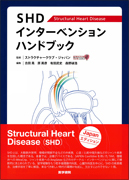 ストラクチャー・ハート疾患(SHD)とは,別に新しい疾患概念ではない。ただ,それに対するインターベンションが大きな時代の変革の到来を示唆しており,「新語」として登場したものと理解される。疾患でいえば,大動脈弁狭窄や僧帽弁逆流,僧帽弁狭窄,肺動脈弁狭窄,心房中隔欠損を中心とする先天性心疾患などである。これらの疾患群に対するインターベンションの中では,何といっても大動脈弁狭窄に対するカテーテル治療(TAVI)や僧帽弁逆流に対するMitraClipが鮮烈な印象を与える。
ストラクチャー・ハート疾患(SHD)とは,別に新しい疾患概念ではない。ただ,それに対するインターベンションが大きな時代の変革の到来を示唆しており,「新語」として登場したものと理解される。疾患でいえば,大動脈弁狭窄や僧帽弁逆流,僧帽弁狭窄,肺動脈弁狭窄,心房中隔欠損を中心とする先天性心疾患などである。これらの疾患群に対するインターベンションの中では,何といっても大動脈弁狭窄に対するカテーテル治療(TAVI)や僧帽弁逆流に対するMitraClipが鮮烈な印象を与える。
そのインターベンションに対して,わが国で初めてその概念や手技などの臨床を科学的に解説したテキストが登場した。私は心からそれを歓迎する。
本書の序文「はじめに」に森野禎浩先生が私の思うところを記載されている。すなわち,「冠動脈疾患に特化したステント治療は極めて安定した成績が得られ,これ以上の発展が難しいと思えるレベルまで成熟した。その結果としてデバイスの開発会社自体やその領域で働く研究者たちに閉塞感が生まれてきた」と述べておられる。そこに登場したのがSHDインターベンションである。若い有能な心臓病医が海外に渡り,主にヨーロッパ(特にフランス)で経験を積み,SHDインターベンションが日本でも開花しようとしている。森野先生は続けて「そうした若者のエネルギーに触れるにつけ,これからこの新しい領域はわれわれ世代を飛び越え,実質的には彼らが率いていくべきものと確信する」とまで述べておられる。立派である。私も執筆者の幾人かを知っているが,森野先生の言葉に恥じない人々ばかりである。
昨年,私自身も米国のコロンビア大学でTAVIを見学してきた。カテ室に入ると,異様な雰囲気である。とにかくカテ室に人が溢れるぐらい入っていて,いろんな言語が飛び交っている。熱気に溢れている。その中心にいるのが,経食道心エコー図を操る中国系米国人の女性医師であった。カテが始まると,部屋は静かになり,その女性医師と術者の声だけになった。あっという間にTAVIは成功裏に終わり,TAVIが優秀な治療法であることを確信した。
さて,SHDインターベンションには内科医にとって,誠に魅力的であることに間違いない。ただ,冠動脈インターベンションが普及したときに,外科医と内科医の間に,何ともいえぬ齟齬が生じたのを忘れてはならない。SHDインターベンションも,外科医と十分に討論の上施行されるべきである。従来,各科の医師が自分の専門領域の視点で治療法を決めてきたように思う。特に大学においてそうである。この点は,われわれ医師すべてが銘記すべきことと思われる。
皆さんには,まずわが国で最初のSHDインターベンションの科学的著作である本書で十分にSHDの診断や病態を学習し,次いでSHDインターベンションに関してしっかりと勉強してほしい。私は本法がインターベンションと心エコーを中心とする画像診断を結ぶ強力な技術であることとも絡み,SHDインターベンションを強力に支持する。
B5・頁240 定価6,825円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-01708-4


水澤 英洋,鈴木 則宏,梶 龍兒,吉良 潤一,神田 隆,齊藤 延人 編
《評 者》金澤 一郎(国際医療福祉大大学院長/東大名誉教授)
身近に1冊備えるべき神経疾患治療の教科書的書籍
 この度,医学書院から表題の本が上梓された。第2版である。だが,これがほぼ20年ぶりの改訂であることがすぐにわかる人は少ないだろう。亀山正邦・高倉公朋両先生編集による初版の序にすでに,神経学は「遺伝子レベルの研究が最も盛んな領域」であり,「高齢化によって,わが国では,神経疾患対策が強く要請されている」とある。その他に,この20年間に臨床や研究の内容が縦にも横にも著しく拡がった。例えば,認知症が増加した上にその鑑別診断も細分化したし,MRIをはじめとする画像診断が精緻化し,神経免疫学的病態の知見も増大した。疾患概念そのものが変わったものもある。精密になる一方の診断へのアルゴリズムも均てん化されてきた。当然,それに並行して治療法も進展した。新しい薬物や手術も開発され,治療の選択肢が多くなった。そればかりでなく,EBMの概念も定着し,いくつかの疾患について,「治療ガイドライン」も学会等の責任で作成されてきた。また,20年前にはそれこそ「夢物語」でしかなかった神経変性疾患の根本的治療も,遺伝子治療や細胞治療などによって「もしかしたら」と思わせるような時代になったことを忘れてはならない。
この度,医学書院から表題の本が上梓された。第2版である。だが,これがほぼ20年ぶりの改訂であることがすぐにわかる人は少ないだろう。亀山正邦・高倉公朋両先生編集による初版の序にすでに,神経学は「遺伝子レベルの研究が最も盛んな領域」であり,「高齢化によって,わが国では,神経疾患対策が強く要請されている」とある。その他に,この20年間に臨床や研究の内容が縦にも横にも著しく拡がった。例えば,認知症が増加した上にその鑑別診断も細分化したし,MRIをはじめとする画像診断が精緻化し,神経免疫学的病態の知見も増大した。疾患概念そのものが変わったものもある。精密になる一方の診断へのアルゴリズムも均てん化されてきた。当然,それに並行して治療法も進展した。新しい薬物や手術も開発され,治療の選択肢が多くなった。そればかりでなく,EBMの概念も定着し,いくつかの疾患について,「治療ガイドライン」も学会等の責任で作成されてきた。また,20年前にはそれこそ「夢物語」でしかなかった神経変性疾患の根本的治療も,遺伝子治療や細胞治療などによって「もしかしたら」と思わせるような時代になったことを忘れてはならない。
これほどの大きな進歩が,ものすごいスピードで進行している神経学領域での治療法の教科書的書籍の改訂に際して,東京医科歯科大学大学院脳神経病態学・水澤英洋主任教授をはじめとする6名の編集者のご苦労は並大抵ではなかったであろう。妙なことを言うが,取り上げない項目を決めるには,新幹線のように疾走する列車から飛び降りるような勇気がいるからである。改訂されたことがわかる点を挙げると,この20年間の臨床知見や画像知見を凝集させた「症候と鑑別診断」にページを割いていること,「治療方針」はガイドラインに沿って非常に具体的に記載されていること,薬物の商品名と一般名の対応表などの気配りが随所にあること,などであろうか。取り上げられた項目を見ると,神経内科以外に,脳神経外科,整形外科,小児神経科,神経耳科,神経眼科,など,関連診療科に関わる項目も豊富にあって非常に実用的である。これだけの内容を357名の執筆者が分担して書き上げたことを考えると,これ以上の内容を望むのは気の毒になるが,あえて注文をつけることにしよう。
1つは心療内科的あるいは精神科的な項目がもう少しまとまってあってもよかったのではないか。例えば「不安」に対する専門家の立場からのコメントや処方例が載っていると心強いだろう。また,個人的なことで気が引けるが,私が苦しんだ腰椎脊椎間狭窄症の項目を立てて,プロスタグランジン製剤による治療を紹介してくれても良かったかと思う。無論,こんな注文にいちいち応えていたらきりがないが,患者の心理だと許して欲しい。いずれにせよ,身近に1冊備えるべき必携の書である。それにしても,改訂までの20年はいかにも長すぎる。今後は,せめて5年に縮めて欲しいとお願いしておきたい。
A5・頁1136 定価15,750円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-01621-6


河合 忠,屋形 稔,伊藤 喜久,山田 俊幸 編
《評 者》本田 孝行(信州大教授・病態解析診断学)
ルーチン検査には本書の活用が欠かせない
 “検査値を読んでみたい”という衝動に駆られたことはないだろうか。その知的好奇心を十二分に満たしてくれるのが,河合忠先生,他編集の『異常値の出るメカニズム 第6版』である。1985年に第1版が発売され第6版を迎えるので,超ロングセラーに間違いなく,医療従事者にとって検査値を読むためのバイブルといっても過言ではない。第5版から5年目の早い改訂であり,河合先生の意欲が感じられる。
“検査値を読んでみたい”という衝動に駆られたことはないだろうか。その知的好奇心を十二分に満たしてくれるのが,河合忠先生,他編集の『異常値の出るメカニズム 第6版』である。1985年に第1版が発売され第6版を迎えるので,超ロングセラーに間違いなく,医療従事者にとって検査値を読むためのバイブルといっても過言ではない。第5版から5年目の早い改訂であり,河合先生の意欲が感じられる。
ルーチン検査(基本的検査)は血算,生化学,凝固線溶および尿検査などを含んでおり,世界中で最も頻繁に行われている。臨床検査部では正確な検査結果を返そうと努力しているが,患者の診断,治療に必ずしも十分に活用されているとはいえない。最大の理由として,ルーチン検査を読む教育が十分でないことが挙げられる。AST,ALTが上昇すれば肝機能が悪い,UN,クレアチニンが上昇すれば腎機能が悪いなど,ごく表面的な浅い解釈に留まっており,患者の病態を深く追求できていない。結果として十分に活用されない検査が大量に行われており,医療費の無駄遣いともいえる。
ルーチン検査では,1つの検査で1つの病態を解釈することは不可能である。複数の検査を組み合わせその変動を検討することにより,詳細に患者の病態が捉えられる。まず,全身状態,そして各臓器の病態を把握していくので理学所見をとるのに似ている。ただ,複数の検査項目を結び付けて考察する必要があり,各検査の異常値の出るメカニズムを熟知していなければならない。
本書以外に,個々のルーチン検査の異常値の出るメカニズムについて詳細に解説している本を知らない。検査値を読みたい,すなわち,ルーチン検査を十分に活用したいならば,本書を活用するしかない。信州大学医学部病態解析診断学では,16年前から本書を教科書としてReversed Clinicopathological Conference(R-CPC)の授業を行っている。私はR-CPCを始めるころに本書に出会い,授業で本書の内容を学生に伝えられれば十分だと直感した。10回以上本書を精読した後,R-CPCの授業を始めたころを昨日のように思い出す。今でも,ルーチン検査でわからないことがあれば本書を開いている。
河合先生は,第6版の...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第2回]糸結びの型を覚えよう!
外科研修のトリセツ連載 2024.12.02
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
