この先生に会いたい!! 自分の可能性を発見するために,外の世界に“寄り道”しよう!(齋藤昭彦,古賀俊介)
インタビュー
2013.07.08
【シリーズ】
この先生に会いたい!!自分の可能性を発見するために,
外の世界に“寄り道”しよう!
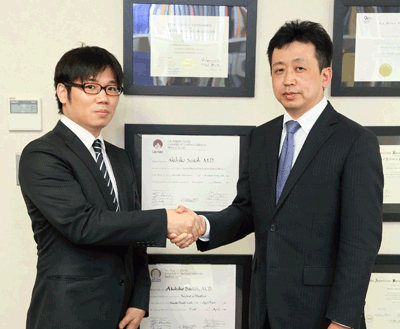
齋藤 昭彦氏
(新潟大学大学院教授・小児科学)
に聞く
<聞き手>古賀俊介さん
(筑波大学医学群医学類6年生)
日本人初の米国小児感染症専門医である齋藤昭彦氏。13年間に及ぶ米国での臨床医・研究者としてのキャリアを経て,帰国後は日本小児科学会が初めて発表した予防接種スケジュールの作成にかかわるなど,小児感染症分野のエキスパートとして活躍されています。米国と日本の文化や制度の違いを乗り越えてキャリアを積み重ねてきた氏が,いま若手医療者に期待することとは――? 医学生の古賀俊介さんが,齋藤氏のもとを訪ねました。
古賀 先生が小児科医を志したのはいつごろでしょう。
齋藤 医学部に入ったころからですね。もともとは小学生のときに素晴らしい担任の先生に出会い,小学校の教員になりたいと思っていました。それが,高校生になると生物の勉強がとてもおもしろく,生物学者に憧れた時期もあって,進路を決めるころになると“生物”としての人間を対象にする医学を勉強したいと強く思うようになっていました。小学校の先生になりたかったという夢とも相まって,大学入学後には小児科に進む希望を持っていたと思います。
古賀 小児科を志望する学生のなかには,子どもとうまくコミュニケーションをとれるか自信がない人もいます。先生はそのような不安は持っていませんでしたか。
齋藤 むしろその難しさが,実際に子どもを診る上での面白さではないでしょうか。子どもは嫌だったら「イヤ」って言うし,お世辞も言わない。嘘もつかないし,極めて純粋ですよね。
それに,この先,数十年も生きていく子どもたちを診ることは,未来の社会を支えることにつながります。社会の財産であり,これから活躍していく子どもたちを育む手助けができるというのは,小児科医だけが感じられる仕事のやりがいでしょう。
“無力感”がモチベーションに
古賀 米国への留学は学生時代から考えていたのですか。
齋藤 ええ。大学生のときにニューヨークに住んでいる親戚の家を訪ねたことがきっかけで,そのころから米国で研究,あわよくば臨床をしてみたいという漠然とした夢を持っていました。そのためには英語は必須ですから一生懸命自分なりに勉強していましたし,USMLE(米国医師国家試験)を意識しながら問題集を解いたりもしていましたね。ただ,共通の目標を持った人が周りにほとんどいなかったので,とにかく一人で悩む毎日でした。
古賀 渡米を決意されたターニングポイントは何だったのでしょうか。
齋藤 留学を決めた当時,私は聖路加国際病院の小児科レジデントをしていて,主に血液腫瘍疾患を持つ子どもたちを診ていました。治療中の子どもは免疫が低下し,重篤な感染症にかかりやすく,なかには感染症がきっかけで命を落とす子どももいました。
ちょうどそのころに,成人の米国感染症専門医である青木眞先生が帰国され,聖路加の内科に赴任されました。そのとき私は,移植後の原因不明の発熱に苦しむ子どもを担当しており,どうしても解決できなかったことから,すぐに先生に相談しました。すると青木先生から,アセスメントの不十分さを指摘され,厳しいお叱りを受けたのです。とてもショックでしたが,自分を奮い立たせるきっかけになり,それから青木先生の指導を受けるうちに,小児感染症をもっと勉強したいと思うようになりました。米国で臨床のトレーニング経験があった聖路加の松井征男先生や小児科の先生たちの後押しもあって,当時すでに小児感染症がサブスペシャリティとして確立されていた米国への留学を決意したのです。
古賀 学生の立場からすると,大学などの小児科では先天性の心疾患や血液腫瘍などの領域が主流であるようにみえるのですが,当時まだ日本では関心が低かった小児感染症の道にあえて進むことに,ためらいはありませんでしたか。
齋藤 全くなかったですね。確かに日本に戻ってからの職探しを考えれば,あまりよい選択ではなかったのかもしれませんが,感染症で患者さんを亡くしたときの無力感が,この道に進む強いモチベーションになりました。
寄り道のススメ
古賀 米国では,研究員を2年間,レジデントとクリニカルフェローを3年間ずつ,さらに指導医として5年間勤め,合計13年間も活動されたそうですね。
齋藤 最初から長くいると決めていたわけではありませんでした。渡米後,最初は無給研究員という立場だったのですが,渡米前に貯めたお金も徐々に減ってきて,帰国するかどうかの決断を迫られたとき,「まだまだ米国で学ぶことがあるのに,今の状態で日本に戻るのはもったいない」と思ったのです。でも,無給のままでは米国で生活できません。そこで初めて,日本の医師免許を持っていても米国では何もできないことを痛感しました。米国で生き残るために何ができるかを真剣に考え,資格を取らなければと思い,仕事をしながら本格的にUSMLEの勉強を始めたのです。
古賀 米国でキャリアを積もうと考えられたのは,実際に現地で生活し始めてからだったのですね。
齋藤 ええ。数か月,がむしゃらに勉強し,なんとか試験をパスして,海外の医師が米国で臨床医として働くための免許であるECFMG Certificationを取得しました。そのとき,「これでなんとか米国でもやっていける」と安堵したと同時に,「これだけつらい時期を乗り越えたのだから,簡単には日本に帰れないな」という意識も芽生えたのです。それまで米国に長く留まることを考えていなかった反動でしょうか。結局13年間も米国にいることになりました。
もし,あのとき日本に帰国していたら,その後の米国での素晴らしい経験ができなかったと考えると,お金がなくてつらくても米国に残る選択をして本当に良かったと思いますね。
古賀 最近では,海外留学によって自分のキャリアにブランクが生じることを気にする学生も多いと聞きます。先生の場合はいかがでしたか。
齋藤 キャリアについては特に気にしていませんでしたね。私の場合,渡米してすぐは無給であったがゆえに,研究員として果たすべき義務は限られていましたから,英語を学びつつ,何か次につながるきっかけが得られればいいなというような軽い考えで留学しました。
それに,当時の日本の研修システムに,あまり魅力を感じていませんでした。学生時代に卒後の...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
