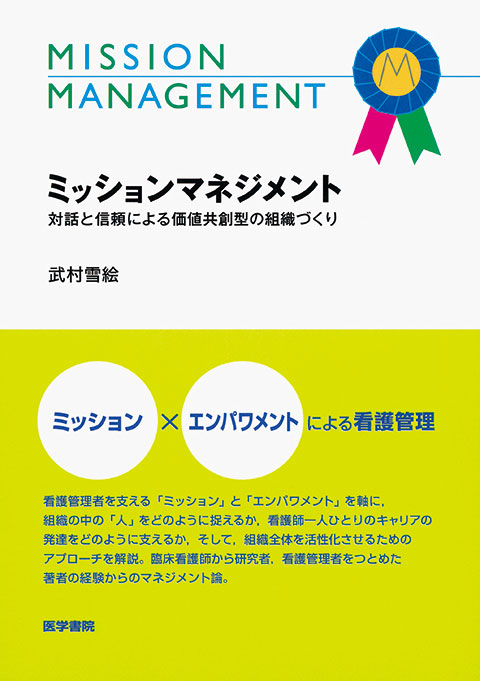出発点(武村雪絵)
連載
2011.04.18
多くの看護師は,何らかの組織に所属して働いています。組織には日常的に繰り返される行動パターンがあり,その組織の知恵,文化,価値観として,構成員が変わっても継承されていきます。そのような組織の日常(ルーティン)は看護の質を保証する一方で,仕事に境界,限界をつくります。組織には変化が必要です。そして,変化をもたらすのは,時に組織の構成員です。本連載では,新しく組織に加わった看護師が組織の一員になる過程,組織の日常を越える過程に注目し,看護師のキャリア発達支援について考えます。
小学生の頃から学校の先生になりたくて,大学でも中学校・高等学校教諭免許状に必要な単位を着々と取得していた私が,それまで全く考えていなかった看護師をめざすことになった。看護師と教師は似ている。対象は人間まるごと,道具も人間まるごと。人とかかわり,仕事を通じて他者の人生にほんの少し,時に大きく影響し,自分自身も他者から学び成長し続けられる。看護師のほうが教師よりも幅広い世代を対象にすることと,もともと人体の神秘に魅せられていたことが決め手になった。
2つの病院で看護師として働いた後,大学院に進学し大学教員となり,その後縁あって,病院で教育と管理に携わることになった。思いがけない重責を担うことになったが,大学院生・大学教員時代の研究が自分自身の役割適応と実践に大いに役立った。私の経験が,看護管理あるいは看護管理学研究に携わる方々に何らかの示唆を提供できれば幸せに思う。
"看護過程"が一つの道具になったとき
本題に入る前に,長くなるが,私の最初の研究テーマとの出会いを紹介させてほしい。私が看護師として働き始めた1990年代は日本で急速に看護診断が広がったときで,私は看護診断を勉強しながら,情報収集,看護問題の明確化,計画立案,計画の実施,評価という,いわゆる「看護過程」をきっちり展開することが看護の責任だと,情熱を持って取り組んでいた。もちろん,患者を全人的にとらえること,患者の立場に立ち患者の気持ちを第一に考えることを最重視し,どんなに忙しくてもベッドサイドに座って患者の話を聴き,患者に丁寧に説明することを心がけていた。
自分の看護にある程度の自信を感じるようになった看護師6年目の秋,ある女性患者に出会った。彼女は脳出血後の回復期で,片麻痺はあるものの意識障害はなく,リハビリテーション訓練を受けていた。いつも険しい表情をして,再出血予防の降圧剤の内服を拒否し,転倒予防のために看護師が付き添いたいと話しても,杖をつきながら一人で,しかも職員用の和式トイレに通っていた。私は何度も時間をつくって,なぜ薬を飲みたくないのか,なぜ一人でトイレに行きたいのか,彼女の気持ちを聞こうとし,彼女と一緒に彼女に合った看護ケアを考えようと試みた。しかし彼女は,「あんたたちにはわかりません。放っておいてください」「自分のことは自分が一番よくわかっています」と言うだけだった。
ある日,非番で病院にいた私は,彼女とただ話してみようと思った。ロビーに二人で座り耳を傾けると,彼女はこれまでの人生,今の思い,これからの夢を次々と語りはじめた。彼女は別人のように目をキラキラさせた。しばらくして,何か温かいものが二人の間に流れるのを感じ,私が驚いて彼女をみつめると,彼女も黙って口元に笑みをたたえて私をみつめた。
その日から彼女が変わった。ほかの看護師が「何があったの?」と驚くほど,看護師と親しく話し,笑い,提案に応じるようになった。それまで空回りしていた看護がやっと歯車がかみ合って回りはじめた。看護って,こんなに楽で楽しかった...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。