MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2011.02.21
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
大下 大圓 著
《評 者》眞嶋 朋子(千葉大教授・成人看護学)
瞑想の入り口に立つ
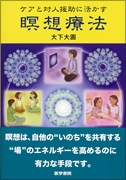 本書の筆者,大下大圓氏は,2008,2009年度千葉大学の普遍教育教養展開科目「いのちを考える」の講師としてお招きし,宗教を超えたスピリチュアルケアの考え方,方法について講義をしていただいた。人の苦悩に寄り添い,その人の内側からの力を引き出す大下氏の実践例から多くの学生が大変感銘を受けたというレポートの内容は,今も記憶に新しい。
本書の筆者,大下大圓氏は,2008,2009年度千葉大学の普遍教育教養展開科目「いのちを考える」の講師としてお招きし,宗教を超えたスピリチュアルケアの考え方,方法について講義をしていただいた。人の苦悩に寄り添い,その人の内側からの力を引き出す大下氏の実践例から多くの学生が大変感銘を受けたというレポートの内容は,今も記憶に新しい。
今回出版されることとなった『ケアと対人援助に活かす瞑想療法』は,医療,福祉,教育,企業,家庭内において,心身の安定,健康増進をめざす上で活用可能な瞑想の具体的な実践方法とその理論的背景を紹介したものである。
第I部は瞑想療法の実践編である。本格的に実践するためには,的確な指導者が必要とされているが,初心者であっても挑戦したい人であれば,瞑想するときの座り方,呼吸の仕方,身繕いなど,始める前の準備が具体的に記載されているので,本書を見ながら,瞑想への具体的なイメージが可能で,自分もやってみようかと取り組みへのハードルが下がる。
第II部では実践事例が示され,精神保健,緩和ケア,助産・子育て期,学童期,青年期,福祉,教育の現場,企業人育成,自死予防と家族支援を行う上での方法と留意事項が紹介されている。私は昨今の大学生の問題を見聞する立場にあるので,青年期の項に関心を持った。青年期においては「この時期,一番に気をつけてほしいのは,言葉巧みなカルトからの誘いです」と述べられ,正しい瞑想活動を身につけることの大切さが強調されている。瞑想は,カルトによるマインドコントロールにより人の心を縛るものではないとして,青少年が自由な選び取りの中から瞑想の有用性を知り,実践することの大切さが示されており,大圓氏の勧める瞑想療法の妥当性が表されている。
医療関係者は瞑想療法の効果の科学的根拠を求める者が多い。本書はその期待に応えるために,数多くの事例を用いて,瞑想療法の効果を示している。看護師に関連する内容でみると,第II部5章に,2009年に千光寺で開催された「自由な心の道場」で紹介された緩和ケアに従事する看護師のバーンアウトを回避するトレーニング例が取り上げられている。瞑想セッションに参加した緩和ケア認定看護師(13名)のアンケート結果によると,「瞑想はあなたの個人的感情(怒りとか悲しみ)などを調整するのに,有用であると思いますか」「瞑想の活用は,人生の意味や目的を考えるのに有用であると思いますか」に対し13名全員から肯定的な評価が示され,本トレーニングが効果的であることがわかる。本書はこのようなアンケートや,体験の内容の質的分析を通じて,瞑想療法による参加者の変化を詳細に例示していることは興味深い。
本書の後半部分は理論編となっているが,瞑想法に関連するストレス研究なども紹介されており,がん医療などの代替補完療法に関心のある研究者が瞑想療法やそれに類似した方法を採用する際の参考になる学術的内容が示されている。
また仏教のみならずユダヤ教,キリスト教,イスラム教等多くの宗教と瞑想との関連性にも触れられ,私のような仏教徒でない者であっても,瞑想に取り組むことが可能であると大変励まされた。最後の部分にマーガレット・ニューマンが本書で紹介されていることは看護研究者として感銘を受けた。大圓氏は,ケアされる者とケアする者が共に拡張され統合された意識に至ることの意義を,マーガレット・ニューマンの理論を通じて説明されている。個人の意思決定を優先する医療における現代の価値観とは異なるように思うが,個人主義的な考え方だけでは,健康支援は難しいことを痛感する。このように,本書の理論編は著者の本領域の豊富な知識と実践的技量がうかがえる。しかしながら,あまり深く頭を悩ませることもなく,本書を読ませていただきながら,静かな心になり,花や鳥や山や空の風景が心に浮かび,目を開けていても穏やかに過ごすことができ,瞑想の入り口に立った気がした。
A5・頁264 2,520円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-01178-5


中野 重行,中原 綾子 編
石橋 寿子,榎本 有希子,笠井 宏委 編集協力
《評 者》古川 裕之(山口大医学部附属病院薬剤部長)
CRCとしての現場での経験が詰まった書
 本書を初めて手にして,白い帯に書かれた「"創造性"と"コミュニケーション能力"に優れたスタッフになるために」というフレーズが目に留まった。"創造性"と"コミュニケーション能力"は,被験者,治験担当医師,院内関連部署のスタッフ,そして,立場の異なる製薬会社やCRO(開発業務受託機関)の開発担当者の間に立って仕事をしているCRCにとって,特に重要な要件と思っているからである。
本書を初めて手にして,白い帯に書かれた「"創造性"と"コミュニケーション能力"に優れたスタッフになるために」というフレーズが目に留まった。"創造性"と"コミュニケーション能力"は,被験者,治験担当医師,院内関連部署のスタッフ,そして,立場の異なる製薬会社やCRO(開発業務受託機関)の開発担当者の間に立って仕事をしているCRCにとって,特に重要な要件と思っているからである。
一体どんな人たちが書いているのだろうかと思い,早速,執筆者一覧を眺めてみた。なんと,全執筆者22人のうち19人がCRCである。彼らの仕事中の様子が目に浮かんできた。そういえば,AさんとBさんとは,2010年10月に別府で開催された「CRCと臨床試験のあり方を考える会議」の懇親会で話したことを思い出す。
つまり,本書は,CRCとして実際に現場で仕事をしている人たちが書いた本なのである。彼らの経験がいっぱい詰まっているのなら,これは期待できる。
内容を見てみる。(1)創薬育薬医療スタッフの連携,(2)チーム内の良好なコミュニケーションとトラブル予防策,(3)被験者保護とIRBのあり方,(4)臨床試験における適切なインフォームドコンセントの方法,(5)わかりやすい関連資料の作成法などについて,実例を示しながらわかりやすく書かれている。日常の仕事で直面する疑問へのヒントが満載である。目を引いたのは,本文のレイアウトである。各項目のポイントがオレンジ地で目立つように書かれている。このおかげで,文字ばかりのページでも,読んでみようという気になる。
それにしても,執筆者のほとんどを占めているCRCの皆さんが,わずか10年あまりでこのような書籍をまとめあげるだけの実力を身につけていることを,仲間の一人として,とてもうれしく感じている。
結論を言うと,本書は,『CRCテキストブック』(第2版,医学書院,2007年)で基礎を学び,そして,実際にCRCとして活躍し始...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
