MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2010.09.06
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


榊原 博樹 編
《評 者》飛田 渉(東北大保健管理センター所長)
睡眠時無呼吸症候群のすべて
――基礎から臨床まで
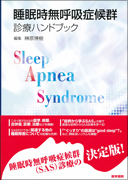 ヒトの1日は平均して覚醒が16時間,睡眠が8時間から成るサイクルで繰り返されている。したがって,人生の約3分の1は眠っていることになる。この睡眠時間は本人にとっても周囲にとっても身体の状態を把握できないブラックボックスの時間帯である。呼吸は随意的に調節できる意識下の調節系と,睡眠中の呼吸のように呼吸中枢自体のリズムに基づく無意識下の調節系の二重の調節系によって行われている。したがって,覚醒時には上位中枢による代償機序が働いているため異常所見を検出しづらいのに対し,睡眠中にはこの代償機序が低下するため呼吸中枢自体の異常を検出しやすくなる。
ヒトの1日は平均して覚醒が16時間,睡眠が8時間から成るサイクルで繰り返されている。したがって,人生の約3分の1は眠っていることになる。この睡眠時間は本人にとっても周囲にとっても身体の状態を把握できないブラックボックスの時間帯である。呼吸は随意的に調節できる意識下の調節系と,睡眠中の呼吸のように呼吸中枢自体のリズムに基づく無意識下の調節系の二重の調節系によって行われている。したがって,覚醒時には上位中枢による代償機序が働いているため異常所見を検出しづらいのに対し,睡眠中にはこの代償機序が低下するため呼吸中枢自体の異常を検出しやすくなる。
睡眠中に呼吸異常を来す疾患として睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome ; SAS)がある。2003年2月26日に起こった山陽新幹線運転手の居眠り運転事件は大きな事故に至らなかったものの,SASが社会的問題になった出来事として記憶に新しい。SASの頻度は欧米では男性で4%,女性で2%と言われており,重症例は働き盛りの40-50代の男性に多いとされている。わが国においても欧米に匹敵するSASがみられている。SASは決して珍しい疾患ではなく,私たちの周りに多くの隠れたSAS患者がいる。SASは肥満,高血圧,糖尿病,高脂血症などいわゆる生活習慣病との合併例が多く,睡眠中の無呼吸に伴う低酸素血症により,種々の重要臓器に障害をもたらすだけでなく,頻回な断眠により過眠,活動度の低下,認知機能の低下などの精神異常を来す。過眠による種々の事故やニアミスの原因になるとして,今や大きな社会問題にもなっている。こうした状況の中,わが国においても睡眠医療を専門とする診療科やクリニックが開設されるようになり,また医学部においても睡眠学を専門とする講座が開設されるなど,睡眠学,睡眠医療が急速に進歩しつつある。
このような時期に発刊された本書は,SASについて基礎から臨床応用まですべてを学ぶことのできるテキストである。4部構成になっており,第I部「SASの概念・疫学・発症機序」では睡眠障害の新しい分類を紹介し,睡眠呼吸障害としてのSASをわかりやすくまとめている。第II部「SASの病態と臨床的諸問題」ではSASと肥満,循環器疾患,糖尿病等との関連のみならず精神障害との関連や小児,高齢者,妊婦におけるSASの問題も取り上げている。さらに自動車事故,産業事故などの社会問題や,医療経済,診療連携,各国のSAS診療の実態についても述べている。第III部「SASの診断と治療」ではSASの診療について包括的にまとめている。第IV部は本書の特徴でもあるが,「症例から学ぶSAS」として,著者がこれまで経験した14例の症例を解説しており,実際の睡眠呼吸障害の診療のあり方を自然と学ぶことができる。
本書はページをめくると,図表や写真が多くて非常に読みやすく,理解しやすい構成になっている。また,章立ての構成がわかりやすく,どの章からでも読み始められる。各章ごとに多くの論文を挙げていることも評価したい。14のコラムの内容も興味あるものばかりで,読んでいて楽しくなる。編者である榊原博樹先生のこれまでの睡眠呼吸障害に関する豊富な研究,臨床経験を基本にまとめあげられた魅力的なテキストである。私どもにこのような素晴らしいテキストを提供してくださった榊原先生に心から「ありがとう」と御礼を述べたい。
睡眠医療にかかわっている医師,看護師および臨床検査技師などコメディカルの皆さん,職場や学校の健康管理に携わっているスタッフの皆さん,これから睡眠医療を学ぼうとしている医療従事者の方々や医療系学生の皆さん,ぜひ本書を一度手に取って読んでみていただきたい。手離すことができなくなる内容であることがすぐに理解できるだろう。
B5・頁336 定価5,670円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-01025-2


奥坂 拓志,羽鳥 隆 編
《評 者》中尾 昭公(名大大学院教授・消化器外科学)
第一線で活躍中の臨床医が治療のポイントを伝授
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編
外科研修のトリセツ連載 2025.05.05
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。

