新研修医に贈る 院内を駆け回るための15のTips(原田賢治,山中喜代治,黒木信之,大谷道輝,阿南誠)
寄稿
2009.04.06
【特集】
新研修医に贈る
院内を駆け回るための15のTips
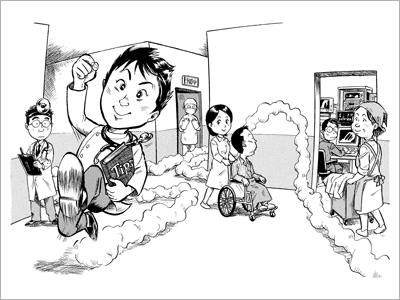
新研修医のみなさん,いよいよ病棟に配属ですね。忙しく院内を駆け回るに際して,まず大事なのは院内コミュニケーション。医師としての知識や技術も大事ですが,まずはホウレンソウ(報告・連絡・相談)や指示出し,タイムマネジメントなど,社会人としての基本ルールを学びましょう。今回は,病院各部署の専門家5名に,院内を気持ちよく駆け回るためのTips(ヒント)を3つずつ伝授してもらいました。
原田 賢治(東京大学医学部附属病院医療安全対策センター長 医師)

Tips1 できることと,できないことを,謙虚に見極める
うまくいかない場合の引き際の見極めや,わからないことは聞き直す,できないことは助けてもらう,知らないこと・やったことのないことは教えてもらう謙虚さが大事です。
悪い例:
・患者さんが痛い痛いと言っているのに,点滴を入れようと何度も針を刺した(神経損傷や動脈損傷など事故のもとです)。
・使ったことのない器械を,似たような器械を使ったことがあるから,と考えて使った。
・「坐薬を5錠処方しておいて」と言われて,一度に5錠挿入しようとした。
・「5mgを10に増やして」と言われて,5mg(1アンプル分)から50mg(10アンプル分)に増やした(わからないならば,「10というのは,10mgですか,10アンプルですか?」と聞き直すべきです)。
Tips2 伝えたくないこと,良くないことこそ,早く伝える
うまくいかなかったときに,どう対処するかがプロとアマの違いです。想定外のことが起こった場合,特に失敗した場合には,「伝えたくない」という気持ちになるかもしれません。しかし,うまくいかなかった,という焦りが,さらに次のミスを引き起こす危険性があります。うまくいかなかったときは,自分だけで対応せず,指導医の指示を仰ぎましょう。
伝達のコツとして,状況・背景・評価・提案の4項目を意識して伝える,ということが大事です。中島和江先生(大阪大学)の『アニメで学ぶ医療安全 「生死を分けるコミュニケ-ション技術」』(DNPアートコミュニケーションズ)がわかりやすく,参考になります。
Tips3 キーとなる人やポイントをつかむ
忙しさに流されないために,節目節目をしっかり押さえて自分でコントロールしましょう。作業の分岐点,特に,患者への影響が出る分岐点を意識しましょう。
良い例:
・ナースに連絡を行う場合に,そのフロアのリーダーナースを把握しておく。
・指示変更は,指示書(指示システム)を変えるだけでなく,ナースにもひと言「変えたよ」(手数をかけて申し訳ないけど,の気持ちで)と伝える。
・不在のときは,誰が代理かを,フロアのナースにも伝えておく。
・点滴をつなぐ直前に,ボトルの患者氏名と薬剤を再確認する(間違いを,患者への影響が出る前に見つける)。
・自分でオーダーした検査の結果は,自分で見る,記録する。
・患者さんの家族にキーパーソンを見つける。
・健康診断,予防接種(HB,インフルエンザ)は必ず受ける(自分のためだけでなく,患者を守るためでもある)。
・メモ書きや,スケジュール帳を活用する。
・日々のあいさつ(開始と終了を意識する)。
◆ひと言メッセージ
Know howとKnow whyの両方を学んで,どうやったらうまくいくかだけでなく,どうやったら危ないかを予測できる,謙虚でかつ熱意を持った医師をめざしてください。
山中 喜代治(大手前病院医療技術部長・臨床検査技術部長 臨床検査技師)

Tips1 餅は餅屋。物事は専門家に聞け
研修医は広域基礎知識を身につけて現場に配属されますが,一気に多方面からの情報が押し寄せ,混乱すると思います。人工呼吸器の使い方とメンテ,MDRP感染症治療,嚥下障害のケア,放射線治療へのアプローチ,細胞診や組織診の判断,生体検査や検体検査の流れ,栄養指導,リハビリの進め方などなど,上司に聞きにくい場合や緊急的判断の助言が必要なときは,医療技術系のスタッフ(各専門家)を頼りにしてください。
Tips2 美顔で美声が最高
決してイケメン顔やモデル顔,そしてウグイス嬢になることを勧めているわけではありません。《親のしつけが問われるような態度》を指摘されないよう注意したほうが得です。
すなわちできるだけ,ニコニコ(ニヤニヤではない)していること。できれば毎朝鏡を見ながら確認するとよいでしょう。そして,電話は丁寧な会話と少し高いトーンの美声で,最後に「ありがとう」を加えると喜んでもらえます。
Tips3 画面より顔面
電子カルテによるオーダー,患者管理の膨大なデータ分析を画面上ですべて処理しているのが現状です。ですから,ついつい患者さんの顔を見る時間が少なくなり,訴えを聞く態度もおろそかになってしまいます。さらに,看護師さんへの指示も検査処置指示も画面で済ませてしまうことになります。どんな先生かも知られないうちに2年間の研修を終えてしまうことにならないよう,患者さんとその家族,そしてスタッフの顔を“いちばんにみてあげてください”。
◆ひと言メッセージ
医師は科学者であり,哲学者であれ。哲学“Philosophy”はギリシア語で「愛」と「知」という言葉から成り立ったそうです。「知を愛し」,ノーベル賞をめざしてください。
黒木 信之(名古屋第二赤十字病院 医療社会事業課課長 医療ソーシャルワーカー)

Tips1 急性期病床からの転院は複雑。患者の条件に合う転院先を選択しよう
医療機関は,医療機能分化,出来高払いや包括払いの導入で大きく変化している。患者の条件(年齢・病名・ADL・医療依存度・薬の量など)により,受け入れ先は,一般病床(出来高払い),亜急性期病床(包括払い),回復期リハビリテーション病床(包括払い),療養病床(包括払い),緩和ケア病床(包括払い)など大きく変わる。
急性期治療の終了後,治療継続が必要か,機能回復が必要か,また長期介護が必要か,緩和ケアが必要かの評価で転院先が決まってくる。患者の条件に合う転院先を選択しないと相手の医療機関とトラブルが生じてしまう。地域連携パスの診療報酬評価で...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
対談・座談会 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由
林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16
-
医学界新聞プラス
[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?
研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?
『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。


