MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2009.02.23
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


《シリーズ ケアをひらく》
発達障害当事者研究
ゆっくりていねいにつながりたい
綾屋 紗月,熊谷 晋一郎 著
《評 者》西村 ユミ(阪大コミュニケーションデザイン・センター・准教授
「自閉的な」作業でゆっくりつながる
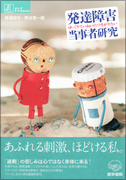 「リンゴが話しかけてくる」「草花と言葉が通じる」「月とはよくおしゃべりをする」。なぜかモノとは接しやすい。が,無数の看板たちに襲われたり,「モノの自己紹介」に頭を埋め尽くされ,感覚が飽和することもある。
「リンゴが話しかけてくる」「草花と言葉が通じる」「月とはよくおしゃべりをする」。なぜかモノとは接しやすい。が,無数の看板たちに襲われたり,「モノの自己紹介」に頭を埋め尽くされ,感覚が飽和することもある。
一方,人はなかなか手ごわい。「集団のなかでの過ごし方がわからない」「声がうまく出せない」「人と交わっている気がしない」けれども「だれかとつながってこそ人」なのだとも思う。「自分はいったい何者だろう」。
――当事者研究はこのような経験と疑問に基づいている。
◆各々の困難を重ね合わせた共同研究
「当事者」というと,どんな問題を抱えている人なのだろう,と思うかもしれない。あえて言うならば,著者の綾屋さんは,アスペルガー症候群という困難を背負っている。自分で発見し,その当事者になることを選び取った。が,脳性まひ当事者であり小児科医でもある熊谷さん(共著者)が指摘するとおり,「表面に現れ出る徴候として定義されるアスペルガー症候群」の説明は,当事者の経験を矮小化こそすれ反映してはいない。自らの脳性まひも,身体の動きの障害というより,例えば「便意を催している」という「身体の自己紹介のまとめあがり」の困難と言ったほうが,経験をうまく言い当てている。
「手話」を介して知り合った二人の共同研究は,綾屋さんが自身の経験をていねいに言葉に置き換える,その経験に,熊谷さんが自らの困難を重ね合わせていくことで進められている。本書はそのような「対話」から生み出された。
◆言葉を「発見」し,「編み出す」旅へ
例えば綾屋さんのフリーズやパニックは,専門家の言説では感覚鈍麻や感覚過敏と呼ばれるが,ていねいに経験をひもといてみると,身体内外からのたくさんの訴えかけによる感覚飽和がそれを招いていることがわかる。身体感覚やモノの訴えを過剰に取り込みすぎて「情報を絞り込み,意味にまとめあげる」ことが間に合わないのだ。
同様に,行為をまとめあげるのも難しい。人に話しかける場合にも,「どのくらいの声量で?」「声質で?」「呼吸との兼ね合いは?」「どんな表情をしながら?」などの決定すべき項目に迫られ,「発声」という行動に結実させることに手間どる。その困難が綾屋さんを「手話」へと誘ったようだ。
他者とのつきあいも難しい。他者と一緒にいることで,相手の表情や動作,話し方の癖,あるいは「キャラ(全体像)」に侵入され,「私」が乗っ取られそうになる。二人は,こうした経験の分析を通して,〈夢侵入〉〈水フィルター〉〈エイエンモード〉〈ヒトリ反省会〉などの新しい概念を編み出していく。これまで難しかった,楽しさ,うれしさ,せつなさなどの感情が伝わってくる,豊かな身体表現を伴った「手話歌」にも出合う。
身体を動かせない熊谷さんには,この感覚が伝わらない。そのことから,似たような動きをすることで,似たような心理的感覚を味わっていることも発見する。
◆「月夜の森」に誘われて……
本書にはじめて触れたときは,綾屋さんと自分の感覚との相違点,類似点を分析しながら読み進んだ。二度目には,当事者研究というスタイルに触発されて,自分の感覚のまとめあげを探す旅に連れ出されてしまった。
「個」を探求する研究は,私たちに何をもたらすのだろうか?
当事者研究は,読み手の経験を「分解」し,新たな意味に「まとめあげる」ことを促す。なんだか「月夜の森」に身を浸したくなってきた。まだ出会っていない著者たちと,私自身のまとめあげを通してつながったような気がする。
A5・頁228 定価2,100円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00725-2


宮子 あずさ 著
《評 者》名郷 直樹(東京北社会保険病院臨床研修センター長
悩むのは自分である。
 いきなり表紙に「看護師専用」とある。これは看護師以外こそ読め,という意味だと理解して,読むことにする。
いきなり表紙に「看護師専用」とある。これは看護師以外こそ読め,という意味だと理解して,読むことにする。
すると,前書きからして,びっくりである。部分だけを取り出すので,誤解があるかもしれないが,あえてそうしてみる。
「看護師はけっこういじいじ悩みます。例えば患者さんを心から好きになれない,みたいなことですよ。これに対して元スチュワーデスのおねえさんから『口の端っこが持ち上がるように,ニコッと笑いましょう』などとアドバイスをされても,『けっ!』と思いませんか?」
これはこの先を読むしかない。すると,以下のような記述に出くわす。
「患者さんの言うことがいつも正しいとは絶対にかぎらないのです」
そうすると,もうあとは私の琴線に触れる言葉のオンパレードだ。
「『思考停止の技術』とも言うべき操作が,命ぎりぎりの現場で働く私たちには,どうしても必要になってくるのです」,「患者さんとのかかわりは,時にそれが終わったあとも続くということ」,「酒飲みのQOLは,しょせん酒が飲めてこそなのだ」,「看護には『する』看護もあれば,『あえて,しない』看護もあると思います」,「反省はあっても後悔はなし」,「闇もあなたの一部」,「医師としてダメなのではなく,人間としてダメなのだ!」,「母の言う『わかってもらおうは乞食の心なのよ!』という言葉を,実践して生きている」,「人間はいつか死ぬ。でも,だから医療はいらんという話にはならないでしょう?」,「その人の嫌なところを事細かに話すのではなく,あなた自身の感情について話すのです」,「私たちの仕事は患者やその家族の選択について,善し悪しを云々するのは範囲外なのです。仲間内で嘆いてもいいし,議論は大いにしたほうがいいと思います。けれどもその選択に対しては直接何もいえない。これが私たちの定めなのです」
どうです。もはや書評として私が追加することはないと思う。
ただ本書のお悩みは,著者が前書きで述べているように,「私が答えたいと思ったお悩み」ということらしい。そうなると,私自身が一番知りたいのは,著者の選から漏れたお悩みに,どんなものがあったのだろうか,というところである。外来診療の中で,自分自身の答えたいと思った問題についてのみ答えている自分に対して,ちょっと後ろめたさがあるからだ。この私の悩みに対して,本書はどのように答えてくれるのだろうか。と書いて,はたと思い当たる。なんだ,私もお悩み外来の患者の1人なのだ。悩むのは自分である。他人の悩みを云々することはできない。しかし,自分の悩みを云々することはできる。それについては大いに議論したほうがいい。そんなとき,その人の嫌なところ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
