『免疫学の巨人 イェルネ』を読む(矢原一郎)
寄稿
2008.08.11
【特別寄稿】
矢原 一郎(医学生物学研究所)
ニールス・カイ・イェルネ(Niels Kaj. Jerne, 1911-1994)
1911年デンマーク人の両親のもとロンドンで生まれる。バナナ会社勤務,ライデン大物理学部卒後,医学を学ぶことを決意し,34年にコペンハーゲン大医学部に入学。43年,デンマーク国立血清研究所に秘書として入り研究を進め,抗体形成理論により国際的に評価される。56年にWHO,その後米国ピッツバーグ大微生物学教室主任教授を4年間勤めた後,バーゼル免疫学研究所の開所に携わり10年間所長を務める。84年,モノクローナル抗体の作製法を開発したセザール・ミルシュタインおよびジョルジュ・ケーラーとともに,免疫制御機構に関する理論の確立でノーベル生理学・医学賞を受賞。免疫学の「巨人」として名高い。
■世界を揺るがした免疫学者 イェルネの謎
自己演出にかけた科学者の物語
 著者によると,イェルネは,肺腺癌の病床においても,死後の名声がどうなるか非常に気にしていた。著者が,この本の書名を『逃れようとする何たる抗い』としたいと言うと,気に入らないという。イェルネは,「ジョン・キーツの詩から取ったのでは」と,「そうです」と著者。「その前の行は,『狂おしい何たる追求』だね」とイェルネ。「そうです」と著者。「それは,フランシス・クリックの自伝の書名だな」。「そうです」。著者のいぶかるのに対し,イェルネは「クリックの後塵を拝するのはごめんだ」と,はっきりと言った。
著者によると,イェルネは,肺腺癌の病床においても,死後の名声がどうなるか非常に気にしていた。著者が,この本の書名を『逃れようとする何たる抗い』としたいと言うと,気に入らないという。イェルネは,「ジョン・キーツの詩から取ったのでは」と,「そうです」と著者。「その前の行は,『狂おしい何たる追求』だね」とイェルネ。「そうです」と著者。「それは,フランシス・クリックの自伝の書名だな」。「そうです」。著者のいぶかるのに対し,イェルネは「クリックの後塵を拝するのはごめんだ」と,はっきりと言った。
死の2か月前。これが,イェルネと著者の最後の会話となったという。
まさしく本書は,どこまでも自己演出にかけた科学者の物語であり,いろいろな読み方ができる。
例えば,女性遍歴だけとってみても,並の物語ではない。イェルネのサイエンスが開花したのは,芸術家であった妻チェックが自殺してからであるが(1945年10月),彼女はイェルネの心の伏流となって,最後まで彼の生き方を支配した。イェルネの長男イヴァールによれば,イェルネは「チェックは天才だった」といい,同時に「私もただ者ではない」と回想していた。
一方で,イェルネはチェックの友人である既婚者アッダとの情事に,「支配する」(実際のSM的な意味も含めて)よろこびを見出していた。その後,イェルネはアッダと再婚し(公的な記録はないが),マックス・デルブリュックが君臨するCaltechで一年間過ごした(1954年8月)。
 16歳のとき,ロッテルダムで,ジャニンに夢中になって以来,イェルネは一貫して性的な面では,ありふれた言い方をすれば,奔放であった。ただ,これもイェルネが自己を演出した結果と思われるふしがある。
16歳のとき,ロッテルダムで,ジャニンに夢中になって以来,イェルネは一貫して性的な面では,ありふれた言い方をすれば,奔放であった。ただ,これもイェルネが自己を演出した結果と思われるふしがある。
ちなみに,イェルネはその生涯にわたって,手紙やメモなどを何百ものスーパーマーケットの袋に入れて屋根裏部屋に保存して,自伝を書くために用意していた。もちろん,著者もこの資料を使わせてもらったが,抜けていたところがあった(イェルネが意図的に捨てた)。イェルネの女性関係と彼のサイエンスとの相関は,面白い分析対象ではあるが,私の最大の関心対象であるサイエンスそのものの問題に触れなければならないので,これ以上深入りは止めておく。
キェルケゴールに強い影響を受ける
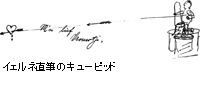 さて,イェルネが「抗体の選択説」の親であることは,だれもが知っていることである。イェルネがこの説を想起したのは,1954年3月の夕方,コペンハーゲンの国立血清研究所からアマリエの家に戻る途中(クニッペル橋を渡っているとき)ということになっている。これは,1966年デルブリュックの還暦を記念してコールドスプリングハーバー研究所から出版された“Phage and the Origins of Molecular Biology”にイェルネ自身が書いていることである。この芝居がかった発見物語も,3月ではなくもっと後(8月)でないと辻褄の合わないことが明らかになり,イェルネ本人も認めたという。なぜ,時期を早めにしたかというと,選択説のアイデアが,デルブリュックの研究室に加わってから生まれたのではないことを,はっきり示したかったのだという。そうして,Pasadenaに発つ前に,イェルネは「抗体の選択説」を記した書類を机の引き出しに入れて,「遺書」として保管した(遺言執行人として,上司であったO.モーレーとデルブリュックを指定した)。デルブリュック還暦記念のイェルネ論文の文頭には,セーレン・ケルケゴール(キェルケゴール)の「哲学的断片」の考察を引用してある。この本から離れて,ケルケゴールの本によって以下,説明する。
さて,イェルネが「抗体の選択説」の親であることは,だれもが知っていることである。イェルネがこの説を想起したのは,1954年3月の夕方,コペンハーゲンの国立血清研究所からアマリエの家に戻る途中(クニッペル橋を渡っているとき)ということになっている。これは,1966年デルブリュックの還暦を記念してコールドスプリングハーバー研究所から出版された“Phage and the Origins of Molecular Biology”にイェルネ自身が書いていることである。この芝居がかった発見物語も,3月ではなくもっと後(8月)でないと辻褄の合わないことが明らかになり,イェルネ本人も認めたという。なぜ,時期を早めにしたかというと,選択説のアイデアが,デルブリュックの研究室に加わってから生まれたのではないことを,はっきり示したかったのだという。そうして,Pasadenaに発つ前に,イェルネは「抗体の選択説」を記した書類を机の引き出しに入れて,「遺書」として保管した(遺言執行人として,上司であったO.モーレーとデルブリュックを指定した)。デルブリュック還暦記念のイェルネ論文の文頭には,セーレン・ケルケゴール(キェルケゴール)の「哲学的断片」の考察を引用してある。この本から離れて,ケルケゴールの本によって以下,説明する。
ソクラテスは「メノン」の中で,「...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
サルコペニアの予防・早期介入をめざして
AWGS2025が示す新基準と現場での実践アプローチ寄稿 2026.03.10
-
寄稿 2026.03.10
-
対談・座談会 2026.03.10
-
医療者の質をいかに可視化するか
コンピテンシー基盤型教育の導入に向けて対談・座談会 2026.03.10
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
対談・座談会 2026.03.10
-
医療者の質をいかに可視化するか
コンピテンシー基盤型教育の導入に向けて対談・座談会 2026.03.10
-
対談・座談会 2026.03.10
-
医療を楽しく知る・学ぶ社会をめざして
おもちゃAED「トイこころ」開発への思い
坂野 恭介氏に聞くインタビュー 2026.03.10
-
寄稿 2026.03.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
