第33回日本脳卒中学会開催
2008.04.28
脳卒中医療の現状を直視する
第33回日本脳卒中学会開催
第33回日本脳卒中学会が3月20-22日,橋本信夫会長(前京大・国循総長)のもと国立京都国際会館(京都市)にて開催された。「Stroke2008」として脳卒中の外科学会(会長=奈良県立医大・榊寿右氏),スパズムシンポジウム(会長=岡山大・伊達勲氏)と合同開催された本会では,脳卒中の外科学会との合同シンポジウムをはじめ,他学会,他科との連携を感じさせるプログラムが組まれた。
脳卒中領域の近年の動向
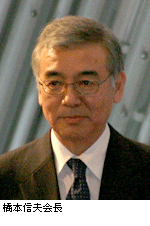 このたびの診療報酬改定に伴い,脳卒中領域にも新たな加算が設けられた。具体的には「超急性期から回復期にわたる脳卒中医療の総合的評価」として,「t-PAによる超急性期の治療」「急性期後の入院治療」「地域連携診療計画(地域連携クリティカルパス)の対象疾患への追加」「回復期リハビリテーション病棟の質に着目した評価」の4点が対象となる。
このたびの診療報酬改定に伴い,脳卒中領域にも新たな加算が設けられた。具体的には「超急性期から回復期にわたる脳卒中医療の総合的評価」として,「t-PAによる超急性期の治療」「急性期後の入院治療」「地域連携診療計画(地域連携クリティカルパス)の対象疾患への追加」「回復期リハビリテーション病棟の質に着目した評価」の4点が対象となる。
理事長講演「日本脳卒中学会――最近の動きと将来計画」で篠原幸人氏(立川病院)は,昨年度中の学会における新しい動きと今後の課題について言及した。氏が理事長就任翌年の2004年に提示したマニフェスト20のうち大部分はすでに達成。例えば,英文誌“J Stroke CVD”のNational Library of Medicineへの採択,他学会との連携,などが実現した。また,国民啓蒙に向けて,患者・一般向け治療ガイドラインの作成も現在進行中であるという。
今後の課題としては「脳卒中専門医の標榜獲得」「日本からのデータ発信の強化」「脳卒中教育」などを挙げ,これらの実現へ向けての意気込みを語った。加えてこれからの脳卒中治療はチーム医療がカギとなると述べ,今後のコメディカルへの教育の必要性を強調した。
来年は島根にて開催予定の第34回日本脳卒中学会。会長の小林祥泰氏(島根大)によれば,コメディカル向けのプログラムも盛り込む予定とのこと。あゆみは着実に進みつつある。
■脳卒中医療をめぐる問題とその対策
今回の総会テーマである「Facing Stroke-脳卒中医療の現状を直視する」をタイトルに掲げた特別シンポジウム(座長=橋本氏,小林氏)では,脳卒中医療をめぐる問題と今後の課題が議論された。
シンポジウムに先立ち座長の橋本氏は,脳卒中医療における需要と供給の不均衡により,現場は非常に疲弊していると訴えた。最先端の脳卒中医療と実際に一般病院で行われている医療のギャップをどう埋めていくかといっ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
医学界新聞プラス
[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!
『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22
-
子どもの自殺の動向と対策
日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
最新の記事
-
2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説
マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー
制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13
-
新年号特集 免疫の謎を解き明かす
臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
