MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2007.11.19
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


中村 正人 編
《評 者》山口 徹(虎の門病院長)
より安全で効果的なPPI普及のために
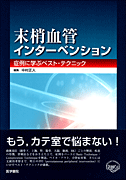 末梢血管に対するインターベンション治療について,現時点でのテクニックを中心にまとめたモノグラフである。インターベンションの名前が示すように,末梢血管インターベンション(PPI)は冠動脈インターベンションの発展に引っ張られて進歩してきた分野である。しかし冠動脈インターベンションは,実は下肢動脈の閉塞性疾患へのカテーテル治療から始まったものである。
末梢血管に対するインターベンション治療について,現時点でのテクニックを中心にまとめたモノグラフである。インターベンションの名前が示すように,末梢血管インターベンション(PPI)は冠動脈インターベンションの発展に引っ張られて進歩してきた分野である。しかし冠動脈インターベンションは,実は下肢動脈の閉塞性疾患へのカテーテル治療から始まったものである。
1960年代にDotterにより硬性カテーテルによる動脈硬化性閉塞病変の拡張術が開発されたが,冠動脈インターベンションの創始者であるGruentzigはこれを改良してポリ塩化ビニール製バルーンにより下肢閉塞性動脈硬化症に対する経皮的血管形成術を1974年に成功させた。Gruentzigはバルーンカテーテルをさらに改良して,末梢動脈,さらに腎動脈の狭窄を拡張することに成功した後に冠動脈への応用を開始し,1977年に初めての冠動脈形成術を成功させたのである。それとは逆に今日のPPIは,冠動脈インターベンションに十分な経験を有する医師たちが冠動脈インターベンションでの洗練されたデバイス,テクニックを駆使して昔の領域へ再挑戦した賜であり,正に30年の歴史の妙である。
本書は,鎖骨下動脈,上腕動脈,腎動脈,腸骨動脈,大腿動脈,膝窩動脈,さらに末梢動脈まで大動脈からのすべての分枝を網羅し,豊富な症例呈示を伴って具体的なテクニックが示されている。各章は総論,Basic Technique,Complication Techniqueで構成されている。総論は疾患概念に始まり,診断,評価,インターベンションの適応,治療効果などが要領よくまとめられている。Basic Techniqueの項では,穿刺法,シース,ガイドワイヤーのテクニックに始まり,ステント留置,末梢塞栓予防策,血管内エコーや体表面エコーのガイド法などすべてのインターベンションテクニックがまとめられている。Complication Techniqueの項では,生じうる合併症とその予防策,対応策が示されている。テクニックは,症例を中心に具体的な方法をアプローチ,テクニカルポイントの順でまとめられており,冠動脈インターベンションに習熟した読者にはこの症例のみを拾い読みしても十分にエッセンスを理解し習得することができるであろう。本書のタイトル通り症例に学ぶスタイルで,多くの読者が冠動脈インターベンションの術者でもある点を考えると無駄のない構成である。
本書は冠動脈インターベンションの経験がある循環器医がPPIを始めようとする際の絶好のテクニック指南書である。冠動脈インターベンション経験者がしばしば陥りやすい,PPIは簡単だという錯覚をしないためにも,本書を一読することをお勧めする。より安全で効果的なPPIが普及することに本書が大きく貢献することを期待する。
B5・頁288 定価7,875円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00489-3


大野 裕 訳
《評 者》伴 信太郎(名大教授・附属病院総合診療部)
対患者アドバイスにも活きるCBTを深く理解する
 「認知行動療法セミナー」という,何回かのシリーズのセミナーに参加したかのような思いにさせてくれる本である。決して安価な本ではない(定価12,600円)が,その何倍もの価値がある。
「認知行動療法セミナー」という,何回かのシリーズのセミナーに参加したかのような思いにさせてくれる本である。決して安価な本ではない(定価12,600円)が,その何倍もの価値がある。
認知行動療法(cognitive-behavior therapy, CBT)はコモンセンス(常識)に基づくアプローチであり,以下の二つの中心的な教えに基盤を置いている。(1)認知は情動と行動に対して支配的影響力をもつ,(2)活動や行動の仕方が思考パターンや情動に強い影響を及ぼす可能性がある。
例えて言えば「コップの水が半分に減ってしまった」と心配するのではなく,「未だ半分残っている」と安心するような考え方の切り替えや,「眠れない時は,時間を決めて早起きをしましょう。」といった行動へのアドバイスを,体系的な治療法に組み上げたものと言える。
CBTでは自動思考の同定と修正に焦点を当てる(ここで言う自動思考とは,私たちがある状況に置かれた場合に,心のなかをすばやく通過する認知のこと)。治療者はこうして内々に放置されがちな認知の流れについて患者を教育し,患者が自己内対話できるように支援するのであるが,その支援のための種々のスキルが懇切ていねいに解説される。
非専門家がCBTを精神療法として使おうとすると「生兵法は大怪我のもと」ということになるかもしれないが,「CBTの基本的技法を患者・家族へのアドバイスに生かす」という観点からの活用は,非常に広い適応範囲を有すると思う。CBTにおける治療関係の基本とされる“協同的経験主義collaborative empiricism”という治療者と患者がともに問題点を明らかにし,解決法を探索していく協同作業は,医療者-患者関係の築き方にもきわめて有用な示唆を与えてくれる。その意味で,本書はメンタルヘルスの専門家以外の医療従事者に広く読んでいただきたい。CBTという精神療法に対する理解が深まるとともに,日常の対患者アドバイスに活かすこともできると思う。
訳文はよくこなれていて,翻訳本の読み難さはほとんどない。同じ原語に対して時に異なった訳語が当てられていて(【例】認知,思考)評者には少し読みづらかったが,訳者の意図があったのかもしれない。ところで,「良好な治療同盟はきわめて重要な治療の要素である。(中略)認知療法家も有能な治療者に共通の資質である誠実さ,温かさ,肯定的配慮,及び的確な配慮を治療環境で生かそうとする。」とされている。こうなると,どれほどがCBT独特の認知的/行動的アプローチの効果で,どれほどがこの治療同盟の築き方の効果なのだろうかというところが興味深い疑問として残った。
ちなみに,本書付属のDVDは海外で臨床をしてみたいという希望を持...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
