MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2007.10.29
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


芳野 純治,浜田 勉,川口 実 編
《評 者》上西 紀夫(東大大学院教授・消化管外科学)
内視鏡に携わるすべての人に教科書・辞書となる必携の書
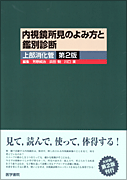 もう30年以上前になりますが,教室の前身である東大分院外科で研修していたとき,毎週木曜日に諸先輩や内視鏡診断に意欲のある先生方が症例を持ち寄って内視鏡の読影についての勉強会があり,わからないながらも参加していました。そしてあるとき,当時の順天堂大学教授でおられた城所仂先生から,「内視鏡でいちばん重要なのはGedankengangだ」と教えていただき,この考え方が内視鏡診断の原点となっています。
もう30年以上前になりますが,教室の前身である東大分院外科で研修していたとき,毎週木曜日に諸先輩や内視鏡診断に意欲のある先生方が症例を持ち寄って内視鏡の読影についての勉強会があり,わからないながらも参加していました。そしてあるとき,当時の順天堂大学教授でおられた城所仂先生から,「内視鏡でいちばん重要なのはGedankengangだ」と教えていただき,この考え方が内視鏡診断の原点となっています。
つまり,内視鏡像を読み取って疾患を診断し,その病変の範囲や病態を頭に描き,そのうえで1枚1枚の内視鏡写真が見る人へのメッセージとなるよう,その疾患がわかりやすいように提示することが大事であるということです。その意味で,内視鏡写真はまさに芸術でありアートです。しかしながら,最近ではコンピュータ上で何枚でも撮影でき,また,消去できるためか,よく考えもせずにやみくもに写真を撮り,その後でゆっくりと見て診断しようという傾向があるように思えます。また,色素内視鏡や拡大内視鏡,NBI(Narrow Band Imaging)などさまざまな方法が開発され,より病変が見やすくなっていることもこの傾向を助長しているように思われます。すなわち内視鏡診断の基本であるGedankengangが少し疎かになっているのでは,と老婆心ながら危惧しています。
さて,このGedankengangをしっかりとし,そして表現するために必要なことは,数多くの内視鏡像を見ること,また数多くの疾患を経験することです。しかしながら,実際に1人で経験できる症例やその数には限りがあります。その点において,本書は,305例の症例提示という数はもちろんのこと,通常よく経験する症例のみならず比較的少ないが鑑別診断として知っておくべき症例が数多く提示されており,大変参考になります。
本書の構成としては6つの章から成っており,まず第1章から第3章までは,咽頭から十二指腸までの上部消化管内視鏡における基本的事項が書かれています。続いて第4章で咽頭・喉頭と食道,胃・十二指腸の疾患について,豊富な内視鏡像や病理組織像が提示されています。第5章では,内視鏡医にとって決して疎かにしてはならない生検組織診断についてわかりやすく解説がなされています。そして最後の第6章では,内視鏡診断や治療において知っておくべき各種の分類や規約,用語などが掲載されています。まさに内視鏡診断と治療に関する辞書と言えます。
特に本書の中心となるのが第4章の「所見からみた診断へのアプローチ」です。その最大の特徴は疾患名,病名を列挙してそれに関する画像を提示しているよくあるパターンではなく,実際の内視鏡検査をしている立場から記載されていることです。すなわち病変が盛り上がっているのか,陥凹しているのか,また狭窄病変であるのか出血している病変であるのか,といった観点から豊富な症例が提示されています。そして何よりも,その所見の説明や解説においてGedankengangが簡潔に記載されており,内視鏡診断の原点が示されていることが特色です。
もうひとつ本書の目玉としては,食道癌,胃癌の深達度診断について詳しく記載されていることです。この深達度診断はGedankengangが基礎であり,治療をするうえできわめて大事であることは言うまでもありませんが,最近ではEMRやESDが比較的容易,かつ安全にできるようになったこともあり,診断的治療としてやや安易に行われていることが問題です。その意味でも,深達度診断について内視鏡像のみならずX線造影写真,そして切除標本も示しながら解説されており,教科書としても価値の高い内容となっています。
したがって,これまでに経験しなかったような内視鏡所見に遭遇した場合,内視鏡検査の合間に本書を手に取りページをめくっていくだけで大変勉強になり,また診断の向上にもつながります。このようなすばらしい内容にするためには,編集や執筆に当たられた先生方の大変なご努力があったものと思います。心より敬意を表します。
以上より,本書は初心者から超ベテランまで,内視鏡に携わるすべての人にとって教科書であり,辞書でもあり,必携の書として強く推薦いたします。
B5・頁432 定価12,600円(税5%込)医学書院
ISBN978-4-260-00313-1


福永 肇 著
《評 者》明石 純(流通科学大教授・経営学)
資金をひきつける病院経営の指南書
 一般的に経営の3大要素として,ヒト・モノ・カネが挙げられている。しかし,病院経営においては,ヒトやモノのマネジメントと比較して,お金のマネジメントにはあまり注目されてこなかったように見受けられる。お金に関係する業務には,大きく分けて,組織体の財政状態や経営成績を測定し記録する「会計(accounting)」と,資金そのものの調達や運用を行う「財務(finance)」があるが,本書は後者の中の資金調達について詳しく解説したものである。
一般的に経営の3大要素として,ヒト・モノ・カネが挙げられている。しかし,病院経営においては,ヒトやモノのマネジメントと比較して,お金のマネジメントにはあまり注目されてこなかったように見受けられる。お金に関係する業務には,大きく分けて,組織体の財政状態や経営成績を測定し記録する「会計(accounting)」と,資金そのものの調達や運用を行う「財務(finance)」があるが,本書は後者の中の資金調達について詳しく解説したものである。
従来から民間病院の設備資金の主要な調達先であった福祉医療機構などの公的金融機関は縮小傾向にあり,医療費抑制政策によって病院の採算性が低下し,運転資金の必要性が増加している。つまり医療機関は,民間の金融機関からの資金調達に依存する傾向が今後さらに高まっていくことになる。また,このような資金需要をまかなうため,病院債や資産の証券化のような金融市場からの調達も一部始まろうとしている。
第1部の各章では,バブル経済崩壊後の銀行の変化,医療制度の変化と病院の設備投資,病院の借入の現状と課題など,病院の資金調達に伴う背景が述べられている。第2部の各章では,福祉医療機構など公的金融機関および銀行など民間金融機関からの資金調達について,実務的に詳しく説明されている。第3部の各章では,診療報酬債権や不動産の流動化,病院債などの新しい資金調達の手法についての現況がまとめられている。
本書は,金融と医療経営の双方に造詣が深い著者によって,病院の資金調達のあらゆる側面についてていねいにまとめられた労作である。全体としての重点は民間銀行からの資金調達にあり,随所に銀行側の見方が散りばめられていることは,借入側である病院関係者にとって参考になるであろう。全30章にわたって,わかりやすく具体的に記述されており,全体を通読すれば病院の資金調達の全体像と詳細が把...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
