研修医教育をへき地医療の現場でも(橋本淳)
へき地医療研修愛知モデルの試み
寄稿
2007.10.29
【寄稿】
研修医教育をへき地医療の現場でも
へき地医療研修愛知モデルの試み
橋本 淳(愛知県がんセンター愛知病院総合内科)
「お疲れさま,へき地診療所の研修はどうだった?」
「楽しかったです。病院とは違った,地域医療をしている医師のやりがいがわかった気がします」
1か月のへき地医療研修の最終日,研修を終える研修医と印象に残った出来事の振り返りをしている。在宅医療,生活習慣指導,救急対応,介護する家族の問題などテーマは様々だが,臨床研修病院にいる時とは違った視点で患者の問題を考えるようになっている。
愛知県では5年前からへき地医療研修のシステム化に取り組んできた。今年度は94名の研修医が県内のへき地医療の現場で地域保健・医療研修を受けることになっている。
臨床研修病院とへき地医療機関双方にメリット
愛知県の医師数は全都道府県中5位,研修医数も4位と医師不足とは無縁のようだが,人口10万人当たりの医師数は全国37位で,特に都市部に集中する傾向がある。臨床研修病院も名古屋を中心とする県の西半分に集中しており,東の三河部は医師不足が特に深刻である。
私の勤務する愛知県がんセンター愛知病院は三河部にある唯一の県立病院として,県のへき地医療対策を行う「へき地医療支援機構」が設置されている。またへき地医療拠点病院の一つとして代診などのへき地支援事業のほか,へき地医療研修を希望する研修医の受け入れなども行っている。
現在の臨床研修制度になって,地域保健・医療が初期臨床研修プログラムに含まれることになった。へき地・離島診療所はこの研修の研修施設の一つとなっているが,都市部の臨床研修病院にとって研修協力施設となるへき地の医療機関を探すことは容易ではない。一方で,へき地の医療機関では医師確保が重要な課題となっており,このような機会に研修医がへき地の医療を経験することは,将来の医師確保のために役立つものと期待される。
愛知県ではへき地の医療機関と協力し,県内の臨床研修病院の研修医がへき地で地域保健・医療研修を受けられるよう支援・調整する「愛知県へき地医療臨床研修システム」(以下,システム)を構築し,以下の手順で運用している(図)。
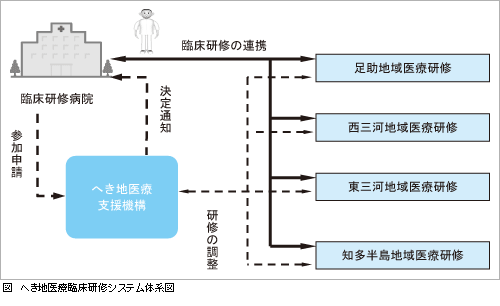
1)へき地の病院,診療所が包括的な地域保健・医療研修プログラムを作成し,へき地医療支援機構に届け出る。
2)へき地医療支援機構が県内の臨床研修病院に上記の情報を周知し,研修申請を受け付ける。
3)へ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
