第103回日本精神神経学会開催
精神医学と精神医療の発展に向けて
2007.07.02
精神医学と精神医療の発展に向けて
第103回日本精神神経学会開催
第103回日本精神神経学会が5月17-19日の3日間,井上新平会長(高知大)のもと,高知県立県民文化ホール(高知市)ほかで開催された。うつ病をはじめとする精神疾患患者は増加の一途をたどっており,地域・社会が精神科領域に期待する医療の質,形態も多様化している。このような時勢を受け,今学会はテーマを「精神医学へのこれからの期待・精神医療の新たな試みの発信」とし,最先端の病態研究の知見から,退院・地域移行支援の方策まで,さまざまなセッションが開催された。
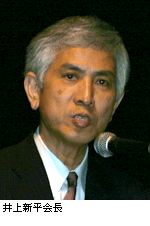 1998年以降,国内での自殺者は増加が続き,年間3万人を超えている。昨年,自殺対策基本法が成立。実効性のある施策は国民全体の願いである。重篤な自殺企図者の8-9割は企図時点で何らかの精神疾患を発症しているといわれ,精神科の担う役割は大きい。本学会でもシンポジウム「自殺問題と予防対策」で,厚生労働科研費補助金の研究課題「自殺対策のための戦略研究」(略称J-MISP)が進める社会保障制度の整備に向けた自殺対策研究について報告がなされた。
1998年以降,国内での自殺者は増加が続き,年間3万人を超えている。昨年,自殺対策基本法が成立。実効性のある施策は国民全体の願いである。重篤な自殺企図者の8-9割は企図時点で何らかの精神疾患を発症しているといわれ,精神科の担う役割は大きい。本学会でもシンポジウム「自殺問題と予防対策」で,厚生労働科研費補助金の研究課題「自殺対策のための戦略研究」(略称J-MISP)が進める社会保障制度の整備に向けた自殺対策研究について報告がなされた。
“避けることのできる死”を減らすために
はじめに山田光彦氏(国立精神・神経センター)が,J-MISPのフレームワークを概説。社会的な要因が複雑に絡み合う自殺のリスクファクターを分析したうえで,地域への包括的な介入,ハイリスク者への直接介入などさまざまな切り口での自殺対策の必要性を訴えた。続いて,J-MISPを構成する2つの研究試験の具体的な取り組みについて講演が行われた。
◆NOCOMIT-J
「NOCOMIT-J」は自殺者の多い地域で複合的な自殺対策プログラムを,行政や地域団体などさまざまな社会資源と連携し包括的に行う地域介入試験。
大野裕氏(慶大)は地域への介入事例として,過去の自殺対策にもかかわらず自殺死亡率が高い南九州地区などでの取り組みを解説。「(自殺対策を通じた)“ある種の地域起こし”が必要」とした。
粟田主一氏(仙台市立病院)は都市部での介入事例として,仙台市で予防対策の施策化が進んだ要因を分析。同市での先行事例,法整備と連動した国・県の動きなどの背景に支持されたほか,都市部では豊富な民間社会資源の有効活用が複合的に奏功したと解説した。
◆ACTION-J
自殺者の約半数に自殺未遂歴があるとされ,自殺企図は最大の危険因子だ。
「ACTION-J」は精神医学と救急医療が連携して,自殺...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
