吉良健司氏に聞く
インタビュー
2007.05.21
【interview】
吉良健司氏(在宅りはびり研究所・所長/理学療法士)
に聞く
在宅は急性期ほどの機能回復はない。
でも,人間としての復権,本当の意味でのリハビリテーションがここにある。
2000年に始まった介護保険制度も7年目を迎えるが,訪問リハビリテーションのサービス提供量は当初期待されたほど増えていない。制度創設当初から危機を訴えてきた吉良健司氏は,仲間の療法士らとともに訪問リハの人材育成カリキュラム作成に着手。このたび,その成果を『はじめての訪問リハビリテーション』として一冊の本にまとめた。編者の吉良氏に,在宅で求められるスキルや仕事の醍醐味について聞いた。
■訪問リハの人材育成が進まない理由
――いま,訪問リハビリテーション(以下,訪問リハ)はどのような現状でしょうか。吉良 高齢化が急速に進む中,国としては「病院から在宅へ」というねらいでさまざまな制度の見直しを進めています。しかし制度改革のスピードに,訪問リハを担う人材の育成が追いついていません。
その変化の煽りをもっとも受けていているのは,高齢者・要介護者ではないでしょうか。急性期・回復期の後,受け皿となる在宅でのサービスが不足していて十分なリハビリができず,思い描いたような生活ができていないのが現状です。
――介護保険において,訪問リハの普及は伸び悩んでいるのでしょうか。
吉良 介護給付費実態調査(2005年12月審査分)のデータをもとに推計すると,居宅サービスのうち訪問リハは,病院・診療所・老人保健施設からの訪問と,訪問看護からの訪問を合わせても3.5%に過ぎません(図)。ちなみに,訪問介護は44%,訪問看護は10%です。
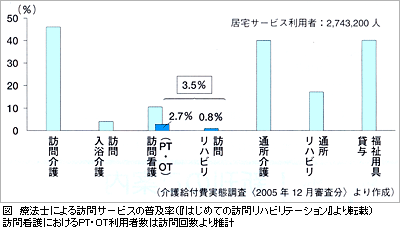
訪問リハのニーズが本来どのくらいなのか不明な部分はあります。ただ,リハビリは要支援から重度まで対象の幅が広いですし,訪問看護と同程度かそれ以上,つまり10%を超えるくらいの潜在的なニーズがあるのではないかと考えています。
医学的視点だけでは在宅の問題は解決できない
――なぜ人材育成が進まないのでしょう。吉良 興味を持つ療法士はたくさんいるのですが,みんな二の足を踏んでしまうのが現状です。病院と在宅の違いにとまどって,何をやればいいかわからなくなってしまうのですね。
在宅は,医学的な視点だけでは解決できない問題がたくさんあります。機能低下を起こす要因がたくさんあって,それが医学的なものに限らないというのが重要な点です。例えば,住宅環境です。部屋の入り口の敷居に2cmの段差があるだけでも,歩行の不安定な人を転倒に至らしめます。あるいは転倒に至らずとも,骨折して寝たきりになるのが恐いので,用心して動かなくなります。
――療法士の役割としては,まずその原因に気づくことでしょうか。
吉良 そうですね。ご自宅に帰られる時には,皆さん希望を持っています。病院の平行棒で歩くことができれば,家でも歩けると考えます。でも,実際に家で歩いてみると,じゅうたんが敷いてあったり,ゴミ箱が置いてあったり,電動ベッドの配線があったりと,いろいろなバリアがあるんですね。そうしたものにつまずいたりして恐怖感を持つと,歩かなくなってしまうのです。訪問に行き始めたら「その人がなぜ歩行を恐がっているか」と,気持ちの奥底にひっかかっている部分を探る必要があります。
――原因は,ご本人の口から出てこないかもしれないですね。
吉良 原因を自覚している場合とそうでない場合があるので,こちらがアセスメントして突き止めていかなければいけません。原因がわかったら,次は恐怖感を取り去るように対処します。例えば,敷居を越える動作練習を反復したり,場合によっては手すりの設置をしたりして,「これだったら大丈夫だね」と安心してもらうのです。
ベッドから起きたくない,歩きたくない……。こうした場合に原因を探っていくと,実は歩いてつまずいたとか,小さなトラウマが原因になっていることがあります。結果的に廃用性の機能低下を起こしてしまう。昔はできていたことができなくなって,家庭の中での役割が果たせなくなる。それで精神的に落ち込み,ひどい人は認知症の症状が出てくることもあります。
――悪循環ですね。
吉良 そうです。急性期・回復期で高めてきた身体機能・生活能力を在宅につなげていく,その専門的な介入が訪問リハビリテーションです。そこでは,医学的視点だけではない,いわば“ひとりの生活者をみる視点”が必要ではないでしょうか。しかし,こうしたことが専門技術として十分に体系化されていない現状なので,若い療法士がつまずいてしまうのだと思います。
社会人としてのスキルが必要
吉良 それと,訪問サービスの特性に基づく立ち居振る舞いを習得することも必要でしょう。病院はいわば医療者の「城」ですから患者さんは「治してもらっている」という意識が強くて,本音を言わず我慢します。ところが在宅はご本人の「城」なので,医療者が不快な行動を取ると,たちまち怒られます。病院の中でずっと働いていると,サービス業従事者としての立ち居振る舞い,社会人としての基本的マナーが十分にトレーニングされずにきてしまうことがあります。在宅では,こういったマナーもスキルとして身につけておかないと,技術を提供する以前の問題として,受け容れこの記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
