MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2007.05.14
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


大野 義一朗 監修
《評 者》大曲 貴夫(静岡県立静岡がんセンター・感染症科)
本当に大切な部分に目を向け現場で使える感染対策書
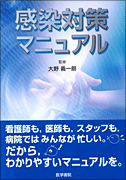 「プロ向けのマニュアル」は使えない!
「プロ向けのマニュアル」は使えない!
「院内感染対策を病院の職員に教育する」。これは実際にやってみると結構大変です。実際の医療現場では,感染対策の手引きとして院内マニュアルや,すでに出ている成書・教科書などがありますが,残念ながら,これらの評判はあまりよろしくありません。感染対策に関わっている方であれば,現場から以下のような不満の声を何度となく聞いたことがあるはずです。
「接触感染対策に使ったエプロンとか手袋って,どうやって脱ぐのですか? 着るのは簡単ですけど……」
「N95マスクってどうやって使うんですか? 病棟に置いてはありますけど,使い方がわかりません」
「うちのマニュアルは分厚すぎて,どこに何が書いてあるかさっぱりわかりません」
「感染対策で疑問点があって教科書で調べたけど,書いてあるのは難しいことばかり。結局具体的にどうすればいいか,さっぱりわかりません」
感染対策を皆に浸透させるにはマニュアルを整備すればいい,マニュアルを作れば何とかなる,そう思っている人は多いはずです。でもそう簡単にはいきません。マニュアルを読んだだけで,内容をきちんと理解して,正確に実行できる人なんて,まずいないでしょう。
なぜでしょうか? 答えは簡単です。マニュアルが理解しにくいからです。実は,多くのマニュアルは「感染対策のプロがプロ向けに書いた」ものになってしまっています。マニュアルを作ったはいいけれど,現場ですぐ引けて使える手引きの形にまでこなれていないのです。これでは実際現場で感染対策を行う人には難しすぎて理解してもらえないし,活用してもらえないのです。
「使えない!」から,「現場で使える!」マニュアルへ
例えば最近の電化製品では,薄くて写真の多い,わかりやすい導入用パンフレットがついていて,これを見ればすぐにその製品が使えるように工夫してあります。これは便利です。分厚いマニュアルは別に用意してあって,必要に応じてその都度読めばいいわけです。これを感染対策にも応用できないでしょうか。
そこで手にしたのが,この『感染対策マニュアル』です。感想をひと言で言えば,「これは,現場で使える!」マニュアルです。
この本のいいところは,二つあります。一つめは,現場で疑問が生じたときにどうすべきかが,写真付きできわめてわかりやすく書いてあるという点です。これだけわかりやすく書いてあれば,現場でさっと眺めるだけで,今自分がどうすべきかのイメージがすぐにつかめます。
二つめは,取り上げてある項目が現場で行う頻度の高い,重要な感染対策の手技・方法に絞り込まれているという点です。微生物ごとの感染対策も,すべてべったりと記載するのではなく,実際の医療現場で遭遇する頻度の高い微生物に対する感染対策に絞って記載してあります。これならば圧倒されないし,マスターできる気もしてくるというものです。
院内感染対策において本当に必要なことは,行う頻度が高くて,しかも効果が高いことを,皆が確実に行えるということ。手指衛生がその代表的なものです。
感染対策に関するあまりに多くの情報(しかも中には根拠の怪しいモノもある!)に目をくらまされて,本当に重要なことに目がいかないようでは,まったく意味がありません。本テキストは感染対策の「本当に大切な部分」に目を向けて「誰でもできるようにする」ために書かれているという点で,これまでのマニュアル類とは一線を画する,画期的な内容に仕上がっています。


尾藤 誠司 編
《評 者》辻本 好子(NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長)
「異文化コミュニケーション」への新たなエネルギーが湧く
 タイトルの斬新さに目を引かれ,つぎに「患者と医師のすれ違いのキーワードは異文化コミュニケーション」とある帯の文字で,時代の変化を実感。10年以上前,ある学会のシンポジウムで発言した私に,学会長が「深い河はともかく,異文化圏という言葉は医療者に対して失礼ですヨ」と諭すようなご指摘。それが今や「キーワード」なのです。
タイトルの斬新さに目を引かれ,つぎに「患者と医師のすれ違いのキーワードは異文化コミュニケーション」とある帯の文字で,時代の変化を実感。10年以上前,ある学会のシンポジウムで発言した私に,学会長が「深い河はともかく,異文化圏という言葉は医療者に対して失礼ですヨ」と諭すようなご指摘。それが今や「キーワード」なのです。
そして執筆者一覧のなかに,かつてどうにも議論がかみ合わず,心密かに「イシアタマ!」と思ったことのある方々(失礼!)のお名前が。しかし時代の変化とともに「柔らかアタマ」に変身されていました。
うんうんと共感を覚えて読み進むうちに,20年ほど前,COMLを立ち上げるときに何度も相談に乗ってくださった故中川米造先生のお言葉がよみがえってきました。「21世紀は専門家のカリスマベールが剥ぎ取られる時代。だから医療現場にも新しい患者と医療者の関係づくりが必要になる。がんばりなさい!」と励ましてくださいました。
COMLが17年間,4万件に余る患者や家族からの電話相談に対応するなかで,最近とみに感じる患者の急激な意識変化。誤解を恐れずに言えば,スタート当初に届いた「なまの声」はヨチヨチ歩きの幼子のよう。パターナリズム医療に身を任せ,長年受け身に甘んじていた患者が少しずつ目覚め,次第に情報を得ることで自分の気持ちを言葉に置き換え始めました。ところがここ2-3年は,まるで思春期・反抗期の頃の自分を見るような「訴え」が目につきます。このまま患者の権利要求だけが高まって,日本の医療崩壊につながるようなことがあってはなりません。この危機をチャンスに,患者が一日も早く思春期・反...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
