地域で医師を育てる(川越正平)
寄稿
2007.05.14
【寄稿】
地域で医師を育てる
川越正平(あおぞら診療所所長)
「君はどんな医師になりたいのか」
筆者は,医学部卒業前から,「どんな医師になりたいのか」,「どうすれば優れた医師になることができるのか」という命題について仲間と議論を重ね,医師卒後研修問題に取り組んできた。のちに医師法改正に連なる10年にわたる議論の中で,医学書院より『君はどんな医師になりたいのか』をはじめ,3冊の本を出版させていただいた。その中で,「疾患の種類によらず心身各部の診療の求めに応じ,地域において患者の生命と生活に責任を持ち続ける医師」こそ,最も必要とされていると考え,『主治医』という概念を提唱した。自らそのような医師としての実践を志し,人生で最も困難なEnd of Lifeというステージを支える在宅医療を中心に据えた地域での開業を決意した(図)。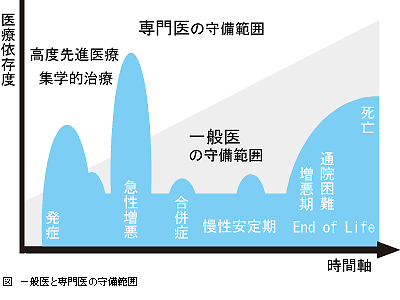
あおぞら診療所の概要と重層的な医師研修の取り組み
1999年4月,東京都心から約20km,電車で約30分,首都圏のベッドタウンである千葉県松戸市に,医師3名によるグループ診療の診療所を開設した。人口47万人の松戸市全域を守備範囲としている(およそ直径10km,車で30分以内で到達可能なエリア)。地域に貢献する診療実践を行うこと,「地域で医師を育てる」ことをめざして,日々の臨床と教育実践に取り組んでいる。2004年11月には市内に分院を設立し,「地域が病棟」との理念のもと,2つの診療拠点で常勤医師6名,非常勤医師4名,研修医2名の陣容で,約400名の在宅患者の診療に取り組んでいる。
医学生や看護師の実習,研修医の地域保健・医療研修はもちろんのこと,3年目以降の医師を対象とした継続的な在宅医療研修や,在宅医療のノウハウを学び独立開業をめざす医師のための開業前研修など,重層的な医師研修に取り組んでいる。
当院における地域保健・医療研修の実際
地域ネットワーク構築を指向する当院にとって,訪問看護ステーションやケアマネジャー,各種介護保険事業者,行政などとの連携,そして病診連携,診診連携は生命線である。在宅医療を研修の中心に据え,地域の資源を可能な限り動員して,現場で織りなされる地域医療や在宅ケアの醍醐味を盛り込むことをめざしている。虎の門病院が新医師臨床研修制度にのっとったプログラムを1年前倒しして導入したことに伴い,全国に先駆けて2004年度に12名の地域保健・医療研修を受け入れた。05年度以降は虎の門病院に加えて,東京医科歯科大学医学部附属病院,みさと健和病院の3つの病院から研修医を受け入れている。これまでの修了者は3年間で通算58名に達している(05年度21名,06年度25名)。
1か月間という短い期間ではあるが,学生実習のような見学中心ではなく,体験型の研修を盛り込むべく,さまざまな工夫を行っている。1週目は指導医の訪問診療に同行し,当院の在宅診療の流れや地域の医療事情を把握することに注力する。2週目からはデイサービスや訪問看護ステーション等での院外研修を織り込む。そして,月の後半には,研修医の到達度を確認しつつ,訪問診療を担当させたり,訪問看護師の臨時対応に同行するなどの体験型研修の比率を増やしてゆく。
研修医に訪問診療を担当させるにあたっては,必ず常勤看護師を同行させ,接遇を監視するのはもちろんのこと,病状の変化や治療方針の決定に際しては,携帯電話を用いて現場から指導医に報告,相談する形で,体験型研修の機会と診療の継続性や質を担保している。
多様な経験のための工夫
さらに,癌終末期患者の診療期間がきわめて短いことを鑑み,月初に依頼のあった患者1名を厳選し,副主治医としてのかかわりを実践している。その結果,より頻繁に医師が診療することは患者にとってもメリットが多く,かつ研修医にとっても初診から(場合によっては看取りまで)より深いかかわりを経験することができる。また,地域の優れた家庭医に外来診療の研修をお願いし,地域医療において重要な位置をしめる家庭医療,特に小児プライマリケア(外来診療,乳児健診,予防接種等)についての研修機会を確保している。
その他,往診時に現...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2020.02.03
-
VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを
寄稿 2025.05.13
-
医学界新聞プラス
[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編
外科研修のトリセツ連載 2025.03.24
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
