MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2007.04.23
NURSING LIBRARY 書評・新刊案内


浦河べてるの家 著
《評 者》宮地 尚子(一橋大教授・精神科医(文化精神医学))
「べてるの家」の核心をつく本
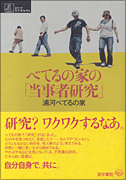 写真がいい。
写真がいい。
絵解きがいい。
言葉がいい。
本書の魅力を簡単に表現するなら,この3行に尽きる。と,ここで書評を終えてしまえたらラクなのだが,そういうわけにもいかないか……。
今回取り上げる『べてるの家の「当事者研究」』は,べてるの家に関する多くの出版物の中でも特に,べてるの家のスピリットの核心をつく本ではないかと思う。それは「当事者研究」というところに,真正面から光を当てているからである。
例えば,山本賀代さん(自己病名=依存系自分のコントロール障害)と下野勉さん(自己病名=依存系爆発型統合失調症)のカップルは,同居生活の中でケンカがどんどん過激さを増し傷つけ合ってしまうことにとまどい,自分たちのケンカのメカニズムを明らかにする当事者研究を始める。はじめは研究自体が新たなケンカのきっかけになってしまうくらいだったが,徐々にケンカに「一貫性」と「法則性」があることが分析の中で見えてくる。もちろん,だからといってケンカが収まるわけではなく,それぞれの生育歴を振りかえったり,新たな事件を引き起こしながら,やがて「前向きな別居」という方向性を見出していく。
そういったプロセスがていねいに山本さん自身の手で記され,文章の横にはなぜか二人の写真が添えられている。べてるの家の総会でパンチング・グローブを賞品にもらい,二人のユニット名が「パンチン'グローブ」になった時の写真。雪景色を背景に,それぞれが別方向を向きながらタバコを吸っている写真。どちらも味がある。
そして,言葉である。例えば,《くどうくどき》は,《幻聴さん》や否定的認知によってくどくなってしまう症状に林さん自身がつけたニックネームであり,どんな時に《くどうくどき》が騒ぐのかを仲間と分析する中で,悩み・疲れ・暇・寂しさ・お金お腹お薬(の不足)という《なつひさお》自己チェック法を見出す。そして《なつひさお》への自己対処法は,食べる,仲間,語る・体を動かす,休む,すぐ相談・すぐ受診,おろす・送ってもらうという《たなかやすお》にまとめられる。
このほかにも紹介したい言葉は限りないほどだ。こういった名付けは,もちろん心理学的手法としての「外在化」ともいえるし,グラウンディッド・セオリー法という質的研究法の基本分析プロセス,「コーディング」とも重なるものがある。けれども,なんだかそういった説明の仕方がばからしくなるほど,言葉そのものが楽しくて,生き生きしていて,力を与えてくれるように思う。
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
