MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2007.04.02
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


目黒 泰一郎 編
《評 者》延吉 正清(小倉記念病院長)
左アプローチの利点から術中・術後の要所を詳細に記載
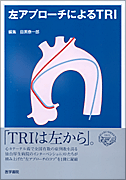 冠動脈インターベンションを世界で最初に行ったのは,Gruentzigである。彼は1977年にスイスのチューリッヒで右股動脈穿刺に細いカテーテルを用い,前下行枝の高度狭窄の拡張に成功した。そしてこの手技を,Percutaneous Transluminal Coronary AngioplastyすなわちPTCAと命名した。
冠動脈インターベンションを世界で最初に行ったのは,Gruentzigである。彼は1977年にスイスのチューリッヒで右股動脈穿刺に細いカテーテルを用い,前下行枝の高度狭窄の拡張に成功した。そしてこの手技を,Percutaneous Transluminal Coronary AngioplastyすなわちPTCAと命名した。
その後,ステントやロータブレーター,DCAなどの出現によりPTCAをPCI(Percutaneous Coronary Intervention)と呼ぶようになった。歴史的には股動脈穿刺の後,Stertzerらにより右前腕穿刺で行うPTCAも普及した。
1992年8月14日 アムステルダムのKiemeneij(kimney)によって,初めて経橈骨動脈冠動脈インターベンションが行われた。当時,Campeauにより経橈骨動脈冠動脈造影(TRA)が紹介され,さらに1990年代初めにステント植え込みは十分な後拡張なしで行われていたため,ステント血栓症を防ぐ強力な抗凝固療法が必要であった。そこで,出血の合併症を減少させるために,工夫されたのがTRIなのである。
わが国においても,齋藤滋先生が右経橈骨動脈よりのTRIを普及させておられるが,左アプローチによるTRIは目黒泰一郎先生によって初めて行われたのである。当時左からのアプローチは一般的ではなかったが,目黒先生を中心とするグループがカテーテルシース,圧迫帯などを研究し,現在ではradial approachは左経橈骨動脈からになってきている。
目黒先生編集の『左アプローチによるTRI』には,何千例と行われた症例の結果が平易にまとめられている。
まずは,なぜ左アプローチなのかに始まり,左アプローチに必要なデバイス,穿刺法,ガイディングカテーテルの選択や操作のコツ,ご自分たちで開発されたシースレスガイディングカテーテルの用い方,DCAやロータブレーターの場合の使用方法とコツ,複雑病変に対するPCIや急性心筋梗塞に対する左アプローチの考察,合併症とその対策など,手技のすべてについて非常に詳細に,しかも初心者が気をつけなければならない点をも含めて書かれている。例えば,左経橈骨動脈のTRIでは,カテーテル操作時に右手が遠くなるが,特別なアームレストを使用されており,術者と左経橈骨穿刺部位が離れない工夫をされておられる。このような目黒グループの独特な工夫は,他の追随を許さない一流の仕事であると考える。
PCIを行う初心者の方にはぜひともお薦めしたい1冊である。


金澤 一郎,北原 光夫,山口 徹,小俣 政男 総編集
《評 者》井村 裕夫(京大名誉教授/先端医療振興財団理事長)
進化する内科学 進化する教科書
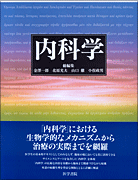 「教科書も進化する」というのが,医学書院の新刊,『内科学I・II』を手に取った時の第一印象であった。図表を数多く入れて理解を助けていること,系統ごとに「理解のために」という項を設けて,基礎研究の進歩,患者へのアプローチ,症候論,疫学,検査法などをまとめていること,疾患ごとの記載でも疫学を重視し,新しい試みを導入していること,などであろう。膨大な内科学の情報を,2巻に凝縮した編集の努力も,大変なものであったと推測される。その意味で,新しい内科学教科書の1つの型を作り上げたと言えよう。
「教科書も進化する」というのが,医学書院の新刊,『内科学I・II』を手に取った時の第一印象であった。図表を数多く入れて理解を助けていること,系統ごとに「理解のために」という項を設けて,基礎研究の進歩,患者へのアプローチ,症候論,疫学,検査法などをまとめていること,疾患ごとの記載でも疫学を重視し,新しい試みを導入していること,などであろう。膨大な内科学の情報を,2巻に凝縮した編集の努力も,大変なものであったと推測される。その意味で,新しい内科学教科書の1つの型を作り上げたと言えよう。
序文にもあるように,内科学は医学の王道であると言ってもよい。病気を正確に把握し,できるだけ患者に負担をかけない,侵襲の少ない方法で治療するのが,医学の究極の目標だからである。この目標...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
