2型糖尿病治療における膵β細胞機能保全の視点(吉岡成人)
寄稿
2007.03.19
【Medical Frontline】
2型糖尿病治療における膵β細胞機能保全の視点
吉岡成人(北海道大学助教授・第二内科)このコーナー(Medical Frontline)では,臨床-研究各領域の最先端のTopicsを,各分野の一線で活躍する執筆者が解説します。
糖尿病は1型,2型の2つのタイプに大きく分類することができます。
医学部における講義でも,「1型糖尿病=自己免疫機序による膵β細胞の破壊」,「2型糖尿病=インスリン分泌とインスリン抵抗性によるインスリン作用の不足」と解説していると思います。
1型糖尿病では多くの場合,何らかの免疫反応を契機に,膵β細胞の機能が荒廃に至ると考えられています。Eisenbarthが1986年に発表した総説1)には,ウイルス感染などの何らかの誘因をきっかけとして,膵β細胞の総量が徐々に減少し,残存膵β細胞量が10%前後となった時に糖尿病を発症すると記載されています(図1)。20年以上も前の総説ですが,自己免疫機序によってβ細胞が徐々に減少するというストーリーは明快で,現在でも色褪せることのないすばらしい総説です。
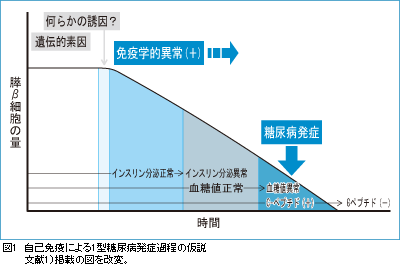
2型糖尿病におけるβ細胞機能低下
最近,Eisenbarthの作成した図と同じような図(図2)が2型糖尿病の臨床経過を示すものとして注目されています2)。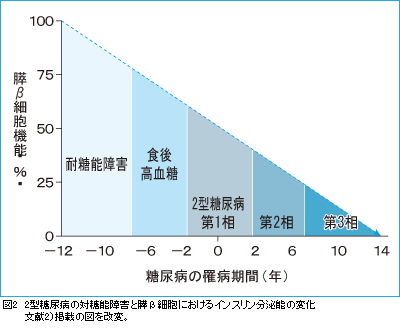
これは最新版のジョスリン糖尿病学の第14章,糖尿病における経口薬治療の部分に掲載されているもので,Lebovitsが作成したものです。UKPDS(United Kingdom Prospective Diabetes Study)の患者データをもとに,HOMA-β指数[(IRI(U/ml)×360)/(FPG(mg/dl)-63)]を算出し,推定した膵β細胞機能を縦軸に,横軸に罹病期間をとっています。
2型糖尿病患者のβ細胞機能は診断時点ですでに正常の50%前後であり,年間約4%の割合で機能が低下し,β細胞機能が15%前後となった時点で経口薬の効果は期待できず,インスリン治療が必要となるというのです。確かに,UKPDSでは,スルホニル尿素薬(SU薬)で治療していた患者のうち,6年間で53%,9年間で80%がインスリン治療に移行したと報告されています。ただ,UKPDSに参加した患者では9.8%もの高い頻度でGAD抗体が陽性(注1)であったため3),いわゆる緩徐進行1型糖尿病患者(SPIDDM: slowly progressive insulin dependent diabetes mellitus)が含まれていた可能性は否定できないと思われます。
アポトーシスが原因?
本当に,2型糖尿病患者の場合も1型と同じようにβ細胞機能が低下していくのでしょうか?私たちの周りには,食事療法のみで何年間も良好な血糖コントロールを保っている患者さんもたくさんいらっしゃいますし,比較的少量のSU薬で血糖コントロールが安定している患者さんもいらっしゃいます。
しかしLebovitsのように,2型糖尿病では膵β細胞機能が減少しているのではないかという考えを支持する研究成果も多く発表されています。Rhodesが2005年の『Science』に執筆した総説には,新生児期に膵β細胞の新生・再生・増生が盛んに行われ,その後,10歳から60歳代までは,β細胞の容量やサイ...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
