MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
2007.02.12
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


酒田 英夫,山鳥 重,河村 満,田邉 敬貴 著
山鳥 重,彦坂 興秀,河村 満,田邉 敬貴 シリーズ編集
《評 者》入來 篤史(理研 脳センター/東医歯大教授/ロンドン大)
Yellow-Red-Blue あるいは頭頂葉の風景
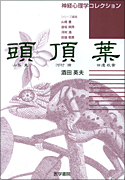 酒田英夫先生の研究の足跡は,世界の頭頂葉研究の歴史そのものである。そして,その集大成を象徴するのが,本書最終章に掲げられた,セザンヌの『サン・ヴィクトワール山』に見る線遠近法の妙技であり,フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』に込められた陰影の魔術なのである。つまり,「頭頂葉を通してみた世界の風景」はかくあり,ということなのだと思う。どのようにしてこの境地に辿りつかれたのか,その歩みの一歩一歩に込められた想いを,希望を,信念を,本書の聞き手の山鳥重,河村満,田邊敬貴の三先生が巧みな質問で聞き出してゆき,酒田先生ははるか遠くに視線を投げながら,そのときどきの世界の研究現場の人間模様を回想しつつ物語ってゆく。
酒田英夫先生の研究の足跡は,世界の頭頂葉研究の歴史そのものである。そして,その集大成を象徴するのが,本書最終章に掲げられた,セザンヌの『サン・ヴィクトワール山』に見る線遠近法の妙技であり,フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』に込められた陰影の魔術なのである。つまり,「頭頂葉を通してみた世界の風景」はかくあり,ということなのだと思う。どのようにしてこの境地に辿りつかれたのか,その歩みの一歩一歩に込められた想いを,希望を,信念を,本書の聞き手の山鳥重,河村満,田邊敬貴の三先生が巧みな質問で聞き出してゆき,酒田先生ははるか遠くに視線を投げながら,そのときどきの世界の研究現場の人間模様を回想しつつ物語ってゆく。
ここには酒田英夫先生の,自然に対する畏敬の念が満ちている。真の研究者かくあるべし,という真摯な態度である。そんな中で,私の心に残ることばがある。本書にも出てくる『ニューロンに聞く』という,脳に対する謙虚な研究姿勢である。まずは仮説を立てて,神経活動を検証するための手段として用い,精密に定式化されたモデルを構築してゆく,という現在一般的になった神経生理学の手法とは,明確に一線を画するこの態度は,いまや「酒田学派」のスローガンといってもよいだろう。
そのような酒田先生の薫陶を受けて頭頂葉研究に足を踏み入れた私であるが,冒頭の絵画に表現されるような風景を作り出す,頭頂葉のメカニズムはどのようになっているのかを,日々考えている。私はいま,自室の壁に掛かる,カンディンスキーの『Yellow-Red-Blue』を眺めている。私の「頭頂葉」機能のメカニズムはこんなイメージである。この画家ご本人が何を意図したかはさておき,私は自分の頭の中も,こんな風になっているのではないか,とふと感じたりもする。私自身も頭頂葉を研究のフィールドとするようになって以来,だんだんと醸成されてきたイメージなのである。本書を読み進めていただくと,この意味をご理解いただけるのではないか。そのさわりはというと,以下のようになるのではないかと思う。
霊長類になって特に発達した頭頂葉では,顔の前で巧みな操作をすることができるようになった手指によって形作られる空間構造を,両眼視による精密な三次元視覚情報解析によって,多種感覚を統合してその情報の持つ「意味」を抽出する装置が進化した。この機能は,しかし,空間の形や構造の解析にとどまるものではなかろう。われわれはより高度な概念や思想を,空間操作のアナロジーでもって考えるではないか。カンディンスキーのこの絵は,そんなありさまを描いているように見えるのだ。頭頂葉は思索の立体交差である。これが,いわば私が酒田先生から教わり,いま抱いている「世界から見た頭頂葉の風景」なのである。


大熊 輝雄,松岡 洋夫,上埜 高志 著
齋藤 秀光,三浦 伸義 執筆協力
《評 者》飛松 省三(九大大学院教授・臨床神経生理学)
臨床脳波判読の手順・知識が自然と身につく良書
 脳機能イメージングの進歩により,脳の形態異常を画像として捉えることは容易になってきた。しかし,画像として捉えにくい機能的神経疾患群,特にてんかんの診断と治療には脳波は欠かせない補助診断法であり,代謝性脳症,脳死の診断にも有用な検査法である。コンピュータの進歩により,心電図の自動判読は可能となったが,脳波はまだ実用化にいたっていない。この理由は比較的単純な波形が反復する心電図に比べると,脳波を構成する波の周波数,振幅,波形などが意識レベルの変動や病態により複雑に変化すること,さらに頭皮上の多くの部位からの長時間にわたる記録を総合的に把握しなければならないためであると考えられる。その意味で,脳波判読法の学習は,一朝一夕では成しえず初学者にとっては厄介な存在である。
脳機能イメージングの進歩により,脳の形態異常を画像として捉えることは容易になってきた。しかし,画像として捉えにくい機能的神経疾患群,特にてんかんの診断と治療には脳波は欠かせない補助診断法であり,代謝性脳症,脳死の診断にも有用な検査法である。コンピュータの進歩により,心電図の自動判読は可能となったが,脳波はまだ実用化にいたっていない。この理由は比較的単純な波形が反復する心電図に比べると,脳波を構成する波の周波数,振幅,波形などが意識レベルの変動や病態により複雑に変化すること,さらに頭皮上の多くの部位からの長時間にわたる記録を総合的に把握しなければならないためであると考えられる。その意味で,脳波判読法の学習は,一朝一夕では成しえず初学者にとっては厄介な存在である。
著者らは「脳波の判読も基本的な事柄を一つずつ順序を踏んで学んでいけば,決して難しいものではない」という考えのもとに『脳波判読step by step入門編』を20年前に世に送り出した。本書の姉妹書である『脳波判読step by step 症例編』は,この入門編で得た判読のための基礎知識を応用して,一歩進んだ臨床脳波判読の学習をするために,代表的な脳波アトラスを集め,その読み方を解説したものである。1986年の初版以来,「入門編」「症例編」はともに好評であり,改訂第4版が2006年暮れに出版されるにいたった。
「入門編」は「脳波の基本の理解」に焦点をあてたテキストである。これから脳波の読み方を勉強しようとする学生,医師,技師のために,脳波の構成要素,記録法,アーチファクト,脳波の賦活法,正常(小児,成人,老年者)脳波,異常脳波を網羅し,判読の第一歩から手ほどきをしている。脳波を基礎から,しかし必要以上に生理学的な事柄には触れず,大変実用的な内容になっており,脳波判読の基本を短期間である程度身につけられるように配慮されている。第3版から第4版への主な改訂点は,
1)冒頭に「脳波を学ぶ」の章を新設し,その中で脳波とはなにか,学習の手引き,脳波判読の手順を解説している,
2)正常か異常かの区別,臨床的意義に議論が多く,初学者にはわかりにくい「特殊な脳波パターン」について章を独立させている,
3)ほとんどすべての脳波に導出法を図示し,判読の際に必要な脳波の頭皮上分布を視覚的に理解しやすくしている,
4)用語は日本脳波・筋電図学会(現・日本臨床神経生理学会)の用語集(1991年)および国際臨床神経生理学連合(IFCN)の用語集(1999年)を原則としている。
これらの改訂により基本的な知識と技術を獲得できる一冊となった。
「症例編」は,姉妹書の「入門編」を読み終えた読者が,その基礎知識を応用して臨床脳波判読の訓練をすることに焦点をあてたテキストである。しかし,一通り脳波判読の基本をマスターした方が,てんかん,脳腫瘍,意識障害,頭部外傷,精神科・内科的疾患,薬物服用時などの症例を経験することで,より実践的な知識,技術を獲得できる高度な内容となっている。第3版から第4版への主な改訂点は,
1)冒頭に「脳波でわかること」の章を新設し,脳波の臨床的意義について解説している,
2)近年,注目されている疾患(レビー小体型認知症,白質脳症)の脳波を追加している,
3)薬物の脳波への影響は判読の上で,重要であるので,新しい薬物(SSRI,第二世代抗精神病薬)に関する脳波を追加している,
4)入門編と同様,脳波の導出法を図示し,判読の際に頭皮上分布が視覚的に理解できるようにしている。
これらの改訂により,精神科,神経内科,脳外科,小児神経専門医をめざす方,あるいは認定医,認定技師をめざす読者の試験対策にも最適な一冊となった。
以上,書名のstep by stepが示すように,「入門編」と「症例編」を読破することにより,読者が脳波判読の階段を一段ずつ上ってゆけば,自然と臨床脳波判読の総合的な手順と知識が身につくように配慮されている。脳波に興味ある方はぜひ手元に2冊おき,相互に参照しながら利用していただきたい。最後に,著者らの「脳波判読」普及に対する情熱と深い造詣に敬意を表したい。
入門編 B5・頁468 定価7,875円(税5%込)医学書院
症例編 B5・頁404 定価9,450円(税5%込)医学書院


岡田 正人 著
《評 者》狩野 庄吾(自治医大名誉教授)
著者自身の生涯研修の成果をまとめた実践書
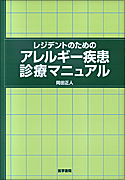 『レジデントのためのアレルギー疾患診療マニュアル』は,アレルギー専門医をめざすレジデントだけでなく,他の分野に進む臨床研修医,プライマリケア医にもお勧めしたい本である。
『レジデントのためのアレルギー疾患診療マニュアル』は,アレルギー専門医をめざすレジデントだけでなく,他の分野に進む臨床研修医,プライマリケア医にもお勧めしたい本である。
著者の岡田正人氏は,医師免許取得後,横須賀米海軍病院で卒後研修生として1年間臨床研修を受けた。1991年に渡米してNew YorkのBeth Israel Medical Centerで3年間内科レジデントとして臨床のトレーニングを受け,さらにYale Universityで3年間フェローとしてリウマチ学とアレルギー学の臨床と研究に従事した経歴を持つ。米国の内科専門医,アレルギー・臨床免疫科専門医,リウマチ科専門医の資格を取得している。その後,フランスのAmerican Hospital of Parisで内科,アレルギー,リウマチの診療を続け,2006年4月から聖路加国際病院のアレルギー膠原病科に勤務している。日本,米国(コネチカット州),フランスの医師免許を取得している。
本書は,アレルギー疾患診療に関して米国で受けた体系的な臨床研修の体験を基盤にして,その後の日米仏における診療の中で身につけた臨床経験と,アレルギー全般に関する著者自身の生涯研修の成果をまとめたものであり,アレルギー診療を行うための実践書である。
アレルギー疾患は,全身性疾患であり,小児から高齢者まで幅広い年齢層が罹患する。わが国ではアレルギー疾患の教育が,小児科,内科,皮膚科,耳鼻咽喉科,眼科など別々のアプローチで行われることが通常である。本書では,アレルギー医は全身を診ることが重要であることを強調し,「アレルギー疾患の診方・考え方」を最初に...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術
<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24
-
対談・座談会 2025.08.12
-
寄稿 2024.10.08
-
医学界新聞プラス
[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編
外科研修のトリセツ連載 2025.04.07
-
対談・座談会 2025.12.09
最新の記事
-
波形から次の一手を導き出す
多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10
-
健康危機に対応できる保健人材養成
COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10
-
対談・座談会 2026.02.10
-
取材記事 2026.02.10
-
インタビュー 2026.02.10
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。
