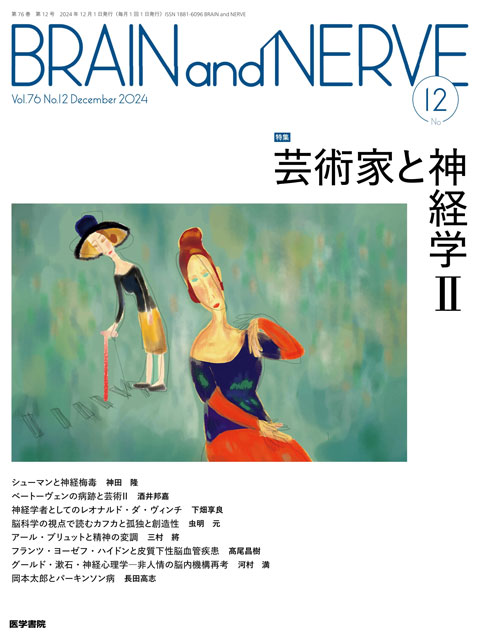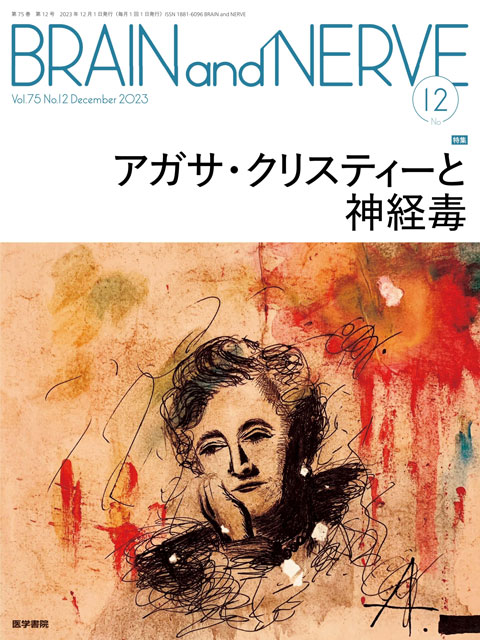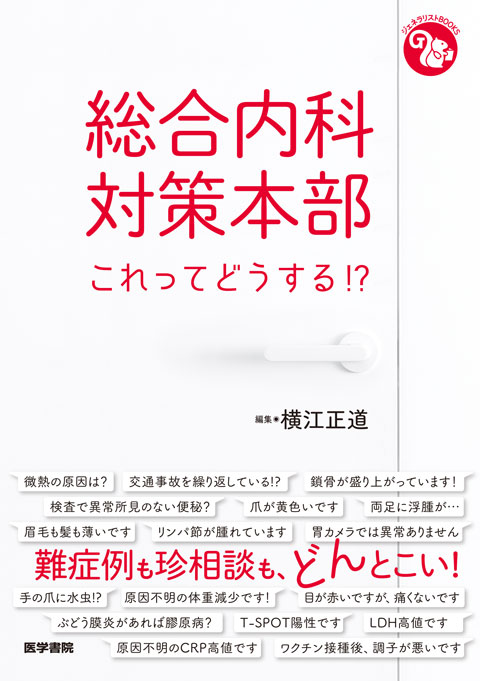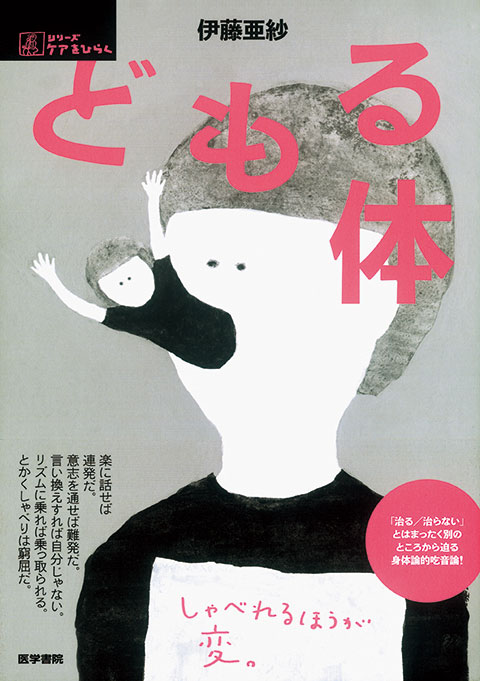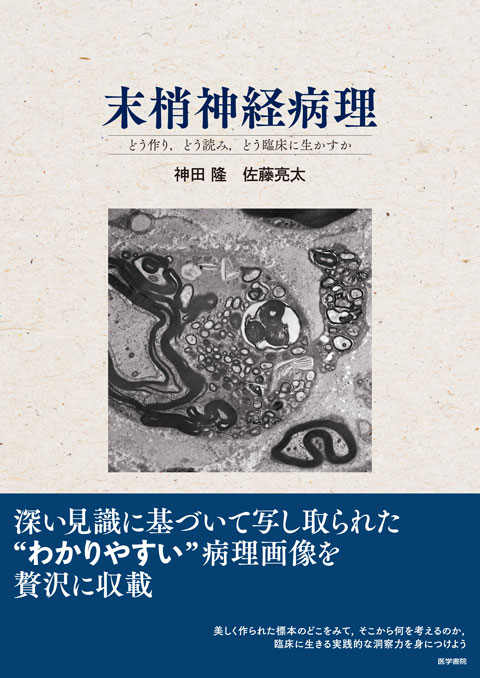- HOME
- 雑誌
- BRAIN and NERVE
- BRAIN and NERVE Vol.76 No.12
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 特集の意図
- 収録内容
特集の意図
開く
普段とは異なる神経学の一面を楽しんでいただくために開始したクリスマス特集も,本年で4回目を迎えた。今回は初回の2021年12月号に特集した「芸術家と神経学」の続編をお届けする。音楽家,画家,作家たちと神経学の交差する物語について,資料を基にしながら著者それぞれが自由に考察を巡らせている。芸術家と神経学との接点を紐解きながら,神経学の魅力を存分に味わっていただければ幸いである。
シューマンと神経梅毒 神田 隆
ベルト・シューマン(1810-1856)は梅毒に罹患していた可能性の高い大作曲家の1人として有名な存在である。梅毒罹患は当時にあっても名誉なことではなく,シューマンの信奉者を中心に感染そのものを否定,または,感染の可能性を示す証拠を隠滅する動きがあって,いまだに確固たる証拠が示されたわけではない。しかし,死後130年を経て明らかになった精神病院入院中の記録などから,現時点では彼の梅毒感染はほぼ確実なことと見なされている。この小論の目的は,シューマンの音楽を愛する一愛好家として,梅毒感染から進行麻痺発症まで,この感染症がシューマンの創作活動にどのように影響を与えたかを考察することにある。
ベートーヴェンの病跡と芸術Ⅱ 酒井 邦嘉
音楽家ベートーヴェンは進行性の難聴と腹痛を患ったが,どちらの症状も鉛中毒によって説明できる。Beggら(2023)はゲノム解析により,5房の毛髪がベートーヴェンの真正な遺髪であると認定して,彼の重い肝臓病の原因を解明した。またRifaiら(2024)は,真正な毛髪の房から異常に高い濃度の鉛を検出した。これらの新たな証拠により,ベートーヴェンを悩ませた病の原因は鉛中毒であったと結論できる。
神経学者としてのレオナルド・ダ・ヴィンチ 下畑 享良
レオナルド・ダ・ヴィンチは万能の画家であるが,医学,特に脳の研究にも情熱を傾けた。脳室を詳細に研究し,魂の在り処を追求した。彼に関する病跡学では,鏡文字の使用や注意欠如多動症と考えられることが注目され,非凡な創造性と仕事を完遂できない性格に寄与した可能性が議論されている。彼の死因は脳卒中と考えられているが,晩年に絵画を描けなくなった右上肢麻痺の原因としては尺骨ないし正中神経麻痺が推測されている。
脳科学の視点で読むカフカと孤独と創造性 虫明 元
フランツ・カフカは現在のチェコ出身の小説家で,現代世界文学を象徴する人物の一人とされ,今年でちょうど没後100年である。彼は多くの作品を遺し,それらは100年以上前の作品であっても,現代社会を予見するかのような先見性を示し,非人間的な巨大システムの中で翻弄される個人を,独創的で非日常的な設定と極めて写実的な表現を用いて描いている。そのようなカフカの独創性と孤独な内面性の関係を,脳科学的に考察した。
アール・ブリュットと精神の変調 三村 將
アール・ブリュット Art Brutの概念,提唱者であるジャン・デュビュッフェの考え,やや独自な展開を遂げてきた日本でのアール・ブリュットに関する取組み,日本の精神医学界におけるアール・ブリュットの話題について触れた。アール・ブリュットは精神障害者アートに限定されるものではない。アール・ブリュットは既存の文化や潮流に影響されない「生の」独創的なアートであり,実際にはその作品の多くに精神医学的背景が見出されるという点を強調した。さらに,アール・ブリュットの画家として代表的な佐伯祐三を取り上げ,ジャン・フォートリエとの類似点について述べた。最後に主に神経科学の視点から精神疾患,特に統合失調症を持つ人のアール・ブリュットにおける創造性について,遺伝的要因や脳機能の変調,精神疾患と創造性の相互作用といった観点から考察した。アール・ブリュットは「ぶるっと」くる体験をもたらす芸術そのものであるが,精神医療の観点からは,作品を創造することに伴うアートセラピーが精神疾患を持つ人の治療・ケア・福祉において二次的に重要な意味を持ってくる。精神医療と芸術の関係は未知の部分も多いが,今後の発展が大いに期待されている。
フランツ・ヨーゼフ・ハイドンと皮質下性脳血管疾患 髙尾 昌樹
フランツ・ヨーゼフ・ハイドンは1700年代後半の音楽家である。一部の研究者によりハイドンが皮質下性の脳血管疾患であったという推察がある。こういった解釈は,残された伝記的な記載などから検討されたもので,あながち間違ってもいないのであろう。しかし,77歳という高齢で死亡したことを考慮すれば,現在言われている複数の脳病理学的変化を伴っていても不思議ではないし,むしろその可能性が高いように思われる。偉人というものは死後200年経っても,持病が何だったか興味を持たれるのだから安らかな眠りというわけにもいかない。
グールド・漱石・神経心理学—非人情の脳内機構再考 河村 満
グレン・グールドはカナダのピアニストで,コンサート・ドロップアウトとして知られているが,録音に残された演奏は現在でも高い評価を得ている。グールドが夏目漱石の『草枕』を愛読していたのは有名で,その理由は漱石の「非人情」に対する共感である。本稿では,グールドと漱石の共通感覚・生きる姿勢である非人情の背景にある知・情・意の脳内機構について神経心理学的に考察した以前の筆者自身の論稿を再度掘り下げた。
岡本太郎とパーキンソン病 長田 高志
芸術家,岡本太郎は,パーキンソン病を患っていた。パーキンソン病に関連した顔のパレイドリアは,「顔のグラス」の発想につながった。色覚障害,コントラスト感度の低下は,絵画の色彩に影響を与え,絵画から陶芸,彫刻などへ創作活動の中心をシフトさせた。彼の創造性に抗パーキンソン病薬が与えた影響を検討した。また,彼の死因である急性呼吸不全の原因についても考察を行った。
収録内容
開く
医書.jpにて、収録内容の記事単位で購入することも可能です。
価格については医書.jpをご覧ください。
特集 芸術家と神経学II
シューマンと神経梅毒
神田 隆
ベートーヴェンの病跡と芸術II
酒井邦嘉
神経学者としてのレオナルド・ダ・ヴィンチ
下畑享良
脳科学の視点で読むカフカと孤独と創造性
虫明 元
アール・ブリュットと精神の変調
三村 將
フランツ・ヨーゼフ・ハイドンと皮質下性脳血管疾患
髙尾昌樹
グールド・漱石・神経心理学──非人情の脳内機構再考
河村 満
岡本太郎とパーキンソン病
長田高志
■総説
マルチタスクの効用──ワーキングメモリから知能研究への展開
渡邉 慶
●スーパー臨床神経病理カンファレンス
第11回 進行性の左上下肢の使いにくさとふらつきを呈した51歳男性例
松原知康,他
●原著・過去の論文から学ぶ
第9回 脳の障害は「できないこと」だけを引き起こすのだろうか?──N.KapurのParadoxical Functional Facilitationをめぐって
緑川 晶