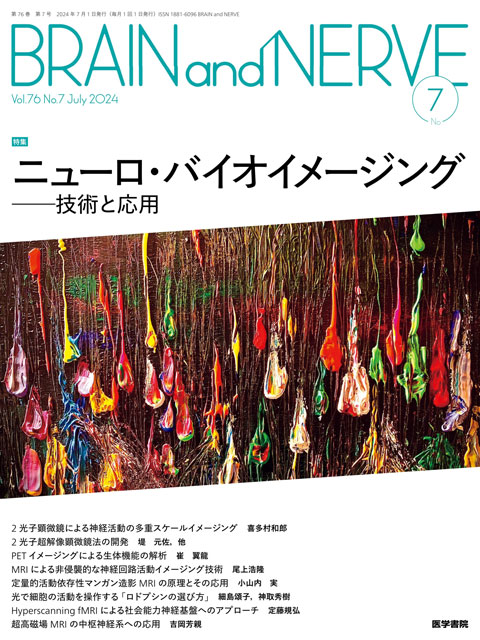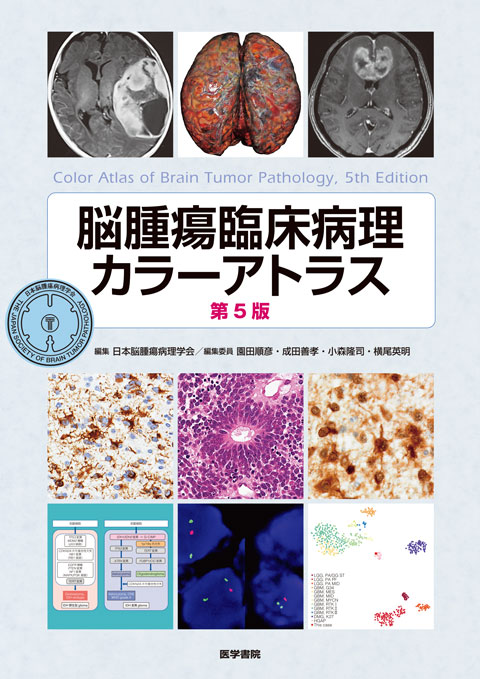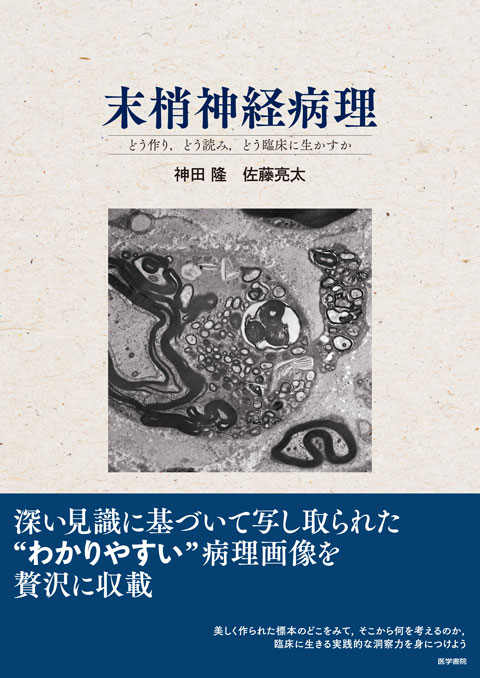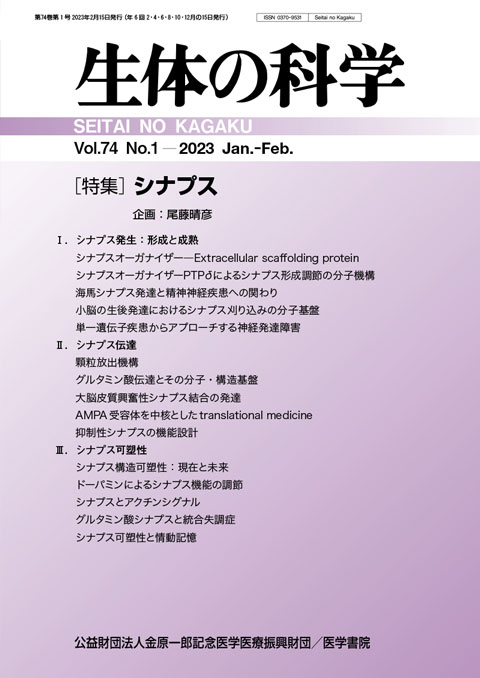- HOME
- 雑誌
- BRAIN and NERVE
- BRAIN and NERVE Vol.76 No.7
特集 ニューロ・バイオイメージング 技術と応用
| ISSN | 1881-6096 |
|---|---|
| 定価 | 3,080円 (本体2,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 特集の意図
- 収録内容
特集の意図
開く
近年,バイオイメージング分野では,生体をそのままの状態で計測できる技術の発展がめざましく,これまで観察することのできなかった生体内の微細な構造や機能を可視化することで,新たな可能性を切り拓いている。しかしその高度な専門性ゆえに,技術面と応用面の双方を理解するのは容易ではない。そこで本特集では,超解像度の顕微鏡技術,PET,MRI,分子プローブの開発による最近の技術動向と,それらが脳神経系へどのように応用されているかについて,各分野を牽引する研究者にわかりやすく解説していただいた。脳科学,医学とバイオイメージング技術の接点を探究しながら,バイオイメージングの進歩がもたらす未来をともに考える機会としたい。
2光子顕微鏡による神経活動の多重スケールイメージング 喜多村 和郎
2光子カルシウムイメージングは,動物の脳における神経活動観察法の1つとして広く用いられている。近年,2光子顕微鏡やカルシウム指示分子の改良などにより高感度化や高速化,広視野化が進み,動物個体脳内に3次元的に存在する神経細胞の活動をマイクロメートルからミリメートルのスケールで大規模に観察することが可能になっている。本論では,これらの新しい2光子観察法とその神経科学へのアプリケーションを紹介する。
2光子超解像顕微鏡法の開発 堤 元佐 , 石井 宏和 , 根本 知己
生体組織の深部イメージングを可能にする2光子励起顕微鏡技術は,神経科学の分野を中心にさまざまな医学・生命科学分野の研究への応用が広がっている。一方で,神経細胞の微細形態の観察には従来の2光子励起顕微鏡法では空間分解能が不足しており,研究の足かせになっていた。本論では,近年の筆者らの研究グループにおける成果を示しながら,2つの異なるアプローチによる2光子励起超解像顕微鏡法の開発について紹介する。
PETイメージングによる生体機能の解析 崔 翼龍
PETイメージングは,非侵襲的に体外から標的分子の時空間的な動態変化を高い感度で定量評価できるイメージング技術である。本論では,PETイメージングの基本原理,高い感度や定量性について解説し,PETイメージングを基軸とした統合的な方法論を用いた精神神経活動の神経生物学的基盤の解明,さらには薬物動態解析やセラノスティックスなど新規医薬品開発への展開について概説した。
MRIによる非侵襲的な神経回路活動イメージング技術 尾上 浩隆
脳は複雑なネットワークであり,特殊な機能を持つ解剖学的に異なる脳領域が互いに協力し合い,さまざまな認知プロセスを支えている。したがって,ネットワークの観点から脳を理解することは非常に重要である。機能的磁気共鳴画像法(functional MRI:fMRI)は,脳の機能に関する豊富な情報を提供する技術として急速に普及,発展している。特に安静時(resting-state)fMRI(rsfMRI)は,タスクがないときの脳活動をマッピングするfMRIの中核技術の1つである。rsfMRIは,データ収集が容易で,非侵襲的であり,自発的な神経活動から洞察に満ちた信号を得られることから,さまざまなヒトの疾患に応用されている。機能的に相関のある領域を包含する脳機能ネットワークは,通常,機能的結合性(FC)として示される。rsfMRIデータのFC解析によって,いくつかの内在的な安静時ネットワーク(RSN)や,精神疾患の患者の異常なネットワーク構造の証拠など多くの情報と知識が明らかになっている。ネットワーク情報は脳についての理解を深めるだけでなく,精神疾患,神経変性疾患がもたらすネットワーク変異の評価に有用である。
定量的活動依存性マンガン造影MRIの原理とその応用 小山内 実
脳機能発現メカニズムを解明するためには,機能発現に伴って活動が変化する領域を同定する必要がある。このための非侵襲全脳神経活動履歴イメージング法が,定量的活動依存性マンガン造影MRI(qAIM-MRI)である。qAIM-MRIはMn2+をCa2+の代理マーカーとして利用する擬似Ca2+イメージング法である。本論ではqAIM-MRIの原理とその応用例およびこの手法の限界を解説する。
光で細胞の活動を操作する「ロドプシンの選び方」 細島 頌子 , 神取 秀樹
光で細胞の活動を操作し,さらに光で計測する時代が到来した。オプトジェネティクス(光遺伝学)は,細胞の活動を光で操作する技術である。代表的な光遺伝学ツールとして藻類などが持つ微生物ロドプシンが挙げられる。近年,新たな機能を持った微生物ロドプシンの発見が相次ぎ,多様性は爆発的に拡がった。ここでは光遺伝学ツールとして使われている微生物ロドプシンの特徴や,最新の研究について紹介する。
Hyperscanning fMRIによる社会能力神経基盤へのアプローチ 定藤 規弘
Hyperscanning fMRIは社会能力の神経基盤探求を動機として開発された。複数被験者の脳活動を同時に撮像することにより,リアルタイムの相互作用やコミュニケーションの神経基盤を解析することが可能となった。個体に還元できない現象としての個体間同期を始めとして,社会的な相互作用の神経基盤を明らかにする方法であり,私たちの生活の大部分を占める社会的相互作用を支える神経メカニズムの研究を可能にしつつある。従前の個体と環境の間の相互作用としての「一人称」の脳科学から,個人間の関係性を脳科学的手法で研究するという意味での「二人称」の脳科学へと展開するうえで,重要な方法論の1つとなり得る。開発の背景,現状と将来展望について概説する。
超高磁場MRIの中枢神経系への応用 吉岡 芳親
MRI装置の高性能化を目指した開発において,最も重要であるのは基盤となる静磁場の超高磁場化である。超高磁場化には,ハード的にも,ソフト的にも,予算的にも難しい点があるが,超高磁場においてようやく得られると思われる情報もある。本論では,超高磁場化でもたらされる効果を概説し,超高磁場での利点を生かして得られた画像やスペクトルについて解説する。
収録内容
開く
医書.jpにて、収録内容の記事単位で購入することも可能です。
価格については医書.jpをご覧ください。
特集 ニューロ・バイオイメージング──技術と応用
2光子顕微鏡による神経活動の多重スケールイメージング
喜多村和郎
2光子超解像顕微鏡法の開発
堤 元佐,他
PETイメージングによる生体機能の解析
崔 翼龍
MRIによる非侵襲的な神経回路活動イメージング技術
尾上浩隆
定量的活動依存性マンガン造影MRIの原理とその応用
小山内 実
光で細胞の活動を操作する「ロドプシンの選び方」
細島頌子,神取秀樹
Hyperscanning fMRIによる社会能力神経基盤へのアプローチ
定藤規弘
超高磁場MRIの中枢神経系への応用
吉岡芳親
■総説
ベンチャーサイエンティストのすすめ
藤井直敬
●スーパー臨床神経病理カンファレンス
第6回 認知機能障害に加えて歩行障害を呈するパーキンソニズムを認めた89歳男性
木村 朴,他
●原著・過去の論文から学ぶ
第4回 知覚対側転位症候の原著を探る
河村 満
●LETTERS
ALSの分子病理最前線──TDP-43とStathmin2のクロストーク
森 望