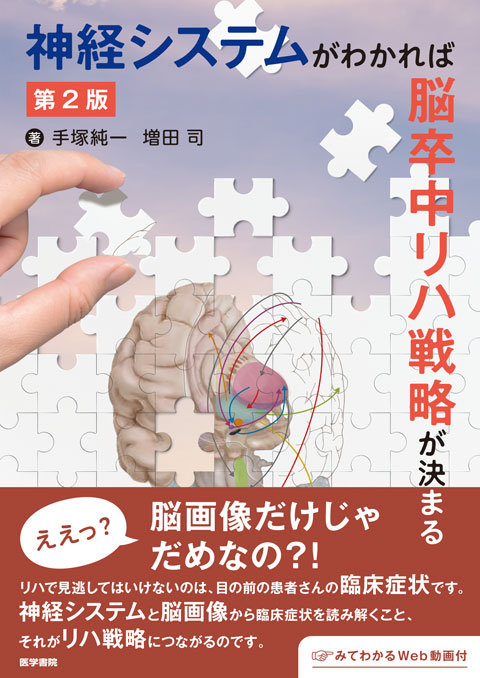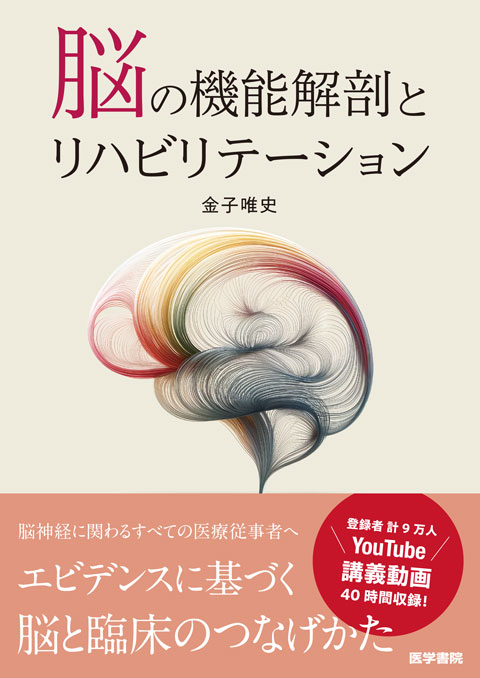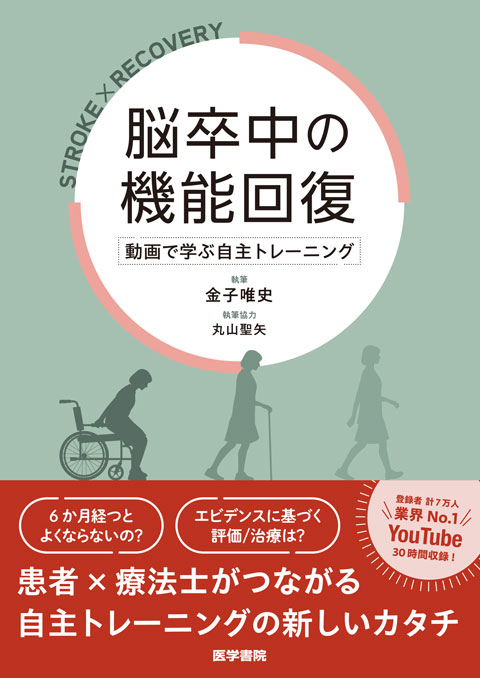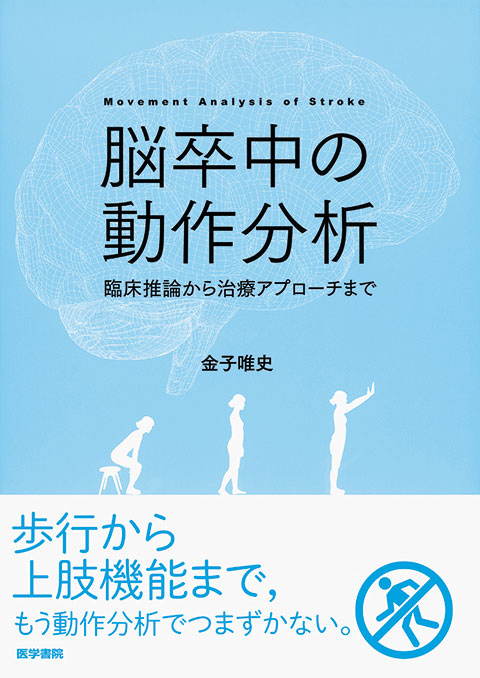神経システムがわかれば脳卒中リハ戦略が決まる 第2版
神経システムと脳画像から臨床症状を読み解くこと、それがリハ戦略につながります
もっと見る
「神経システム+脳画像=リハ戦略」ではなかった?! リハで見逃してはいけないのは目の前の患者さんの臨床症状です。神経システムと脳画像所見から臨床症状を読み解くこと、それが効果的なリハ戦略につながるのです。本書によってアプローチの選択肢は確実に増えます。それは臨床現場で絶対的な武器となるでしょう。脳画像の見かたや運動療法がみてわかるWeb動画付き。
更新情報
-
2025.10.27
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
第2版発刊によせて
本書が世に出るきっかけとなった2017年の第52回日本理学療法学術大会 神経理学療法学会シンポジウムの登壇から,はや7年の月日が経ちました.「脳に何が起こっているのかを画像で捉え,神経システムの知識をもってリハ戦略の可能性と限界を見出せ」という吉尾雅春先生(千里リハビリテーション病院・副院長)のメッセージに触発されて,熱を帯びたディスカッションを行ったことは,鮮明な記憶として残っています.しかし,脳科学や神経システムの分野はアカデミックな内容になりがちで,臨床現場では理解されにくいという課題も示されました.
そうした折に,医学書院から臨床家向けのわかりやすい神経システムの書籍をとの提案があり,本書の企画が始まりました.編集会議では議論を重ね,「神経システム・脳画像・実際の臨床につながる治療戦略を三位一体で,わかりやすく伝える」ことをミッションとして構成しました.特に見えない脳の中をイメージしやすいように,イラストは何度も修正を重ねました.完成までには4年の歳月を要しましたが,その甲斐あって直感的にわかりやすいものに仕上がったと自負しています.第1版発行の際は,この思いが読者にどれだけ伝わるか不安でしたが,予想以上の反響をいただき,第2版の発刊に至ることができました.
脳とは? 神経システムとは?
脳は目に見える器官ではなく,「神経システム」という概念もどこか抽象的であることから,結局のところ何を捉えてどうするべきかがわからないという声をよく耳にします.
そもそも神経システムとは何か? それは「相互に影響し合う要素から構成される神経系のまとまりであり,しくみ全体のこと」と定義することができます.つまり,運動や認知など特定の機能を発揮するための神経の全体像であり,相互に影響を与える集合体として考えていこうというものです.ひとたび脳を損傷すると,問題となる要因は多岐にわたり,かつ複雑に関連し合うため,病態の把握が難しくなります.神経システムを知っていれば,症状の原因(メカニズム)を理解したうえで,解決すべき問題をどの手順で紐解いていくかという治療戦略を立てることができます.
改訂でどう変わったのか?
本書では,神経システムを理解するために脳の部位ごとに章立てし,システムの概要,脳の基本構造,神経システムの解説,画像のみかたを解説し,最後に具体的な症例を通じて治療戦略の立て方を示しています.第2版では,新たに2つのテーマを加えました.
第9章では,脳血管の灌流領域という視点から複数の神経システムにまたがる脳梗塞・脳出血を取り上げました.実際の脳卒中では灌流障害が要因であることが多く,臨床に役立つ内容となっています.
第10章ではパーキンソン病を取り上げました.パーキンソン病はドパミン神経の障害による進行性疾患です.ドパミン作動性の神経システムが障害されることで様々な症状を呈することから,神経システムを理解する上でもわかりやすい内容となっています.
そのほか,読みやすさやわかりやすさを考慮して,全体的なブラッシュアップを試みました.また,新たに脳画像や実際のリハビリテーションの様子を解説する付録動画を加えました.あわせてご視聴いただくことで,理解が深まることと思います.
患者さんの小さな答えを見逃さないこと
脳卒中のリハで最も重要なことは,患者さんがどのように反応するかを理解することです.その反応はとても小さくて,場合によっては見落としてしまうこともあります.しかし,その反応こそが,患者さんの身体や脳が返してくれている重要な情報(答え)です.脳科学や脳画像の知識は,この反応を理解する手助けとなります.
本書では,これらの評価や治療戦略に役立つ材料として脳科学や脳画像の知識をまとめ,その捉え方や活用方法の具体例を示しています.著者らは脳科学者でもなければ,脳画像解析の専門家でもありませんが,臨床家としてこれらの知識を携えてどのように臨床に挑むのか? その姿勢が重要だと考えています.
神経システム+脳画像≠リハ戦略?!
セラピストが神経システムを知ることの意義は,リハ戦略のヒントを得ることだと,私は捉えています.ここまできて「“リハ戦略が決まる”じゃないのかよ!」とツッコミが聞こえてきそうですが,最終的には臨床の現象をしっかりと解釈することで戦略を決めるプロセスが必要です.
神経システムの知識は,現象を解釈して最も適切なリハ戦略を見極めるヒントになるのです.さらに,神経システムの視点によって,アプローチの選択肢は確実に増えます.そしてそれは,臨床現場で絶対的な武器となります.
目の前の患者さんのために本書を活用していただければ,著者としてこれ以上の幸せはありません.
2024年8月
増田 司
目次
開く
本書の使い方
プロローグ 脳の基本構造と機能
1 脳の主な領域 /2 大脳皮質の外観 /3 脳の内部構造 /
4 脳の局在機能:灰白質の構造 /5 脳のネットワーク:白質の構造
MEMO:脳画像の基礎知識
第1章 運動野が関わる神経システム
1.運動野が関わる神経システムの概要
2.運動野と関連領域の構造
1 一次運動野 /2 高次運動野:運動前野と補足運動野 /
3 高次運動野:帯状回運動野 /4 放線冠 /5 内包
3.運動野が関わるシステム
A.随意運動システム:錐体路系
1 外側皮質脊髄路 /2 前皮質脊髄路 /3 皮質核路
B.高位運動制御システム:皮質-錐体外路系投射線維
C.随意運動システムと高位運動制御システムの連携
4.運動野の脳画像の見かた
1 皮質レベル /2 半卵円中心レベル /3 ハの字レベル /
4 モンロー孔レベル /5 中脳レベル /6 橋(脳幹)レベル
5.症例でみるシステム障害とリハ戦略
(症例1) 一次運動野の損傷によって低緊張と分離運動障害を呈した症例
(症例2) 脳出血による皮質網様体路損傷で姿勢筋緊張障害を呈した症例
第2章 脳幹が関わる神経システム
1.脳幹が関わる神経システムの概要
2.脳幹の構造
1 中脳:赤核 /2 中脳:上丘(視蓋) /3 橋・延髄:網様体 /
4 橋:前庭核 /5 橋:橋核 /6 脳神経核
3.脳幹が関わるシステム
1 姿勢安定化システム:網様体脊髄路 /2 バランス反応システム:前庭脊髄路 /
3 眼球-頭頸部協調システム:視蓋脊髄路 /4 随意運動サブシステム:赤核脊髄路 /
5 皮質連合野サブシステム:皮質橋 /6 覚醒維持システム:上行性覚醒系
4.脳幹の脳画像の見かた
1 中脳レベル /2 ダビデの星レベル /3 橋レベル /4 延髄レベル
5.症例でみるシステム障害とリハ戦略
(症例1) 同側の筋緊張低下と対側の筋緊張亢進を伴うlateropulsionを呈した一例
(症例2) 橋出血により,上小脳脚が損傷されて顕著な失調症状が出現した症例
第3章 小脳が関わる神経システム
1.小脳が関わる神経システムの概要
2.小脳の構造
1 小脳の概要 /2 小脳の構造 /3 小脳の入出力
3.小脳の機能と神経システム
1 前庭小脳システム /2 脊髄小脳(虫部)システム:体幹の随意運動制御 /
3 脊髄小脳(中間部)システム:四肢の随意運動制御 /
4 大脳小脳システム:運動学習 /
5 大脳小脳システム:認知機能・非運動機能
4.小脳の脳画像の見かた
1 小脳上部 /2 小脳中部 /3 小脳下部 /4 損傷部位の全体像
5.症例でみるシステム障害とリハ戦略
(症例1) 小脳出血により運動失調とめまいを呈した症例
(症例2) 小脳出血により高次脳機能障害を呈した症例
第4章 視床が関わる神経システム
1.視床が関わる神経システムの概要
2.視床の構造
1 視床の概要 /2 視床の亜核
3.視床の機能と神経システム
1 体性感覚システム(脊髄視床路) /2 小脳ネットワーク:運動ループ /
3 小脳ネットワーク:認知ループ /4 基底核ネットワーク:筋骨格運動ループ /
5 基底核ネットワーク:前頭前野ループ /6 基底核ネットワーク:辺縁系ループ
4.視床に関連する脳画像の見かた
1 感覚神経線維の通り道 /2 視床
5.症例でみるシステム障害とリハ戦略
(症例1) 視床梗塞により感覚障害と注意障害を呈した症例
(症例2) 視床出血により注意・情動・遂行機能障害を呈した症例
第5章 大脳基底核が関わる神経システム:運動系ループ
1.大脳基底核が関わる神経システムの概要
2.大脳基底核の構造
1 大脳基底核 /2 大脳基底核による情報の収束と統合
3.大脳基底核が関わる神経システム:運動系ループ
1 大脳皮質-基底核回路:運動ループ /2 眼球運動ループ
4.大脳基底核の脳画像の見かた
1 モンロー孔~松果体レベル /2 乳頭体レベルの前額断(冠状断)
5.症例でみるシステム障害とリハ戦略
(症例1) 被殻出血によって痙縮を伴う随意運動障害を呈した症例
(症例2) 被殻出血後,一側の眼球運動障害を伴った左半側空間無視を呈した症例
第6章 前頭前野・大脳辺縁系が関わる神経システム:認知系ループ
1.前頭前野・大脳辺縁系が関わる神経システムの概要
1 前頭前野ループ:基底核ネットワークと小脳ネットワーク /2 辺縁系ループ
2.前頭前野と認知関連領域の構造
1 前頭前野 /2 尾状核 /3 視床 /4 内包前脚
3.大脳辺縁系の構造
1 側坐核 /2 淡蒼球内節 /3 海馬 /4 腹側被蓋野 /5 扁桃体
4.前頭前野・大脳辺縁系が関わる神経システム
1 前頭前野ループ:基底核ネットワークと小脳ネットワーク /2 辺縁系ループ /
3 前頭前野ループと辺縁系ループの障害
5.前頭前野と大脳辺縁系の脳画像の見かた
1 皮質レベル~半卵円中心レベル /2 中脳レベル /
3 ダビデの星レベル /4 前額断:下垂体レベル
6.症例でみるシステム障害とリハ戦略
(症例1) くも膜下出血後,性格が変わり“キレやすく”なった症例
第7章 頭頂連合野・視覚野が関わる神経システム
1.頭頂連合野・視覚野が関わる神経システムの概要
2.頭頂連合野・視覚野の構造
1 頭頂連合野の概要 /2 頭頂連合野の皮質 /3 視覚野の概要 /
4 視覚野の皮質 /5 頭頂連合野の連合線維
3.頭頂連合野・視覚野の機能と神経システム
1 後頭葉と視覚 /2 頭頂連合野と視覚野が関連する視覚情報処理システム /
3 背背側視覚経路 /4 腹背側視覚経路 /5 頭頂葉と身体情報 /6 腹側視覚経路
4.頭頂連合野の脳画像の見かた
1 皮質レベル 180/2 側脳室レベル
5.症例でみるシステム障害とリハ戦略
(症例1) 右中大脳動脈梗塞により運動麻痺,感覚障害,半側空間無視を呈した症例
(症例2) 左中大脳動脈梗塞により観念運動失行を呈した症例
第8章 歩行関連領域が関わる神経システム
1.歩行関連領域が関わる神経システムの概要
2.歩行関連領域の構造
1 視床下部領域:視床下部歩行誘発野(SLR) /
2 脳幹神経核:中脳歩行誘発野(MLR) /
3 小脳(室頂核):小脳歩行誘発野(CLR) /4 脊髄運動細胞と介在ニューロン
3.歩行関連領域の神経システム
1 随意歩行発現システム:高次運動野-網様体投射系 /
2 歩行生成システム:歩行誘発野-網様体脊髄路系 /
3 歩行パターンシステム:セントラルパターンジェネレーター(CPG)
4.歩行関連領域の脳画像の見かた
1 視床下部歩行誘発野:SLR /2 中脳歩行誘発野:MLR(PPN & CNF) /
3 小脳歩行誘発野:CLR
5.症例でみるシステム障害とリハ戦略
(症例1) 慢性硬膜下血腫によりパーキンソニズムを呈し,歩行困難となった症例
第9章 複数の神経システムにまたがる脳梗塞・脳出血
1.複数の神経システムにまたがる脳梗塞や脳出血のパターン
2.脳血管の構造
1 主幹動脈 /2 穿通枝
3.脳梗塞や脳出血のパターンと損傷を受けやすい神経システム
1 前大脳動脈領域の梗塞・出血 /2 中大脳動脈領域の梗塞・出血 /
3 後大脳動脈領域の梗塞・出血 /4 心原性脳塞栓による多発性脳梗塞 /
5 視床出血による進展方向の違い /6 被殻出血による進展方向の違い
4.複数の神経システムにまたがる脳梗塞や脳出血の脳画像の見かた
1 前・中・後大脳動脈の支配領域
5.症例でみるシステム障害とリハ戦略
(症例1) 交通外傷から脂肪塞栓症による多発性脳梗塞を発症した症例
(症例2) 多発性脳梗塞により運動麻痺,感覚障害,高次脳機能障害を呈した症例
第10章 神経システムがわかれば,神経疾患のリハ戦略も決まる
1.パーキンソン病の概要
1 パーキンソン病の症状 /2 パーキンソン病の治療法
2.パーキンソン病の関連領域の構造
1 黒質 /2 黒質緻密部(SNc) /3 黒質網様部(SNr)
3.パーキンソン病が関わる神経システム
1 大脳基底核回路の機能不全 /2 寡動,すくみ足 /3 筋強剛 /
4 振戦 /5 パーキンソン病関連認知症
4.パーキンソン病の脳画像の見かた
1 MRI /2 核医学(RI)検査
5.症例でみるシステム障害とリハ戦略
(症例1) 精神症状を伴う活動性の低下を呈し,精査治療目的で入院となったPD患者
エピローグ 脳損傷後の回復理論
1 急性期における機能回復のメカニズム~血流動態の変化~ /
2 早期離床に関するエビデンス /
3 発症早期の有酸素運動は脳卒中後の病変を減少させる /
4 脳損傷後の回復理論:神経の可能性と再構成 /
5 神経の再構成に必要なリハビリテーションの要素 /
6 リモデリング・代替経路・機能代行 /
7 非麻痺側への影響 /8 Diaschisis(遠隔性機能障害) /
9 半球間抑制からの解放 /10 もう1つのリハ戦略:行動学的補償 /
11 運動機能回復のための介入方法 /12 可塑性のメカニズムと回復プロセス
索引
COLUMN
リハ戦略とは?
「錐体路障害=痙縮」ではない!
皮質脊髄路と皮質網様体路,どちらの損傷が多いのか?
課題難易度の設定:運動要素
課題難易度の設定:姿勢レベル
小脳における協調性への関与
量的評価と質的評価
主な中枢神経系の伝達物質
実用性の5大要素
サッケード(急速眼球運動)
Kinesie paradoxale(矛盾運動)
ワーキングメモリー
行動制御の処理システム
恐怖は人を萎縮させる
情動と記憶の関係
運動学習における3つのアルゴリズム
やる気は運動機能の回復を促進させる?
注意ネットワーク説に基づく半側空間無視の発現メカニズム
歩行速度と伸張反射
歩行における力学的エネルギーの利用
パーキンソン病患者と小脳
書評
開く
複雑な神経システムを理解し,臨床実践に生かすための一冊
書評者:大瀧 亮二(山形済生病院リハビリテーション部主任)
『神経システムがわかれば脳卒中リハ戦略が決まる 第2版』は,脳卒中リハビリテーションに携わる療法士にとって,知識の深化と実践力向上を図るために有用な一冊である。本書は,手塚純一先生と増田司先生が,臨床現場の目線を大切にして執筆されたものであり,神経システムという複雑で難解な内容を,臨床に直結する形でわかりやすく解説している。
第2版では,新たに追加された第9章「複数の神経システムにまたがる脳梗塞・脳出血」と第10章「神経システムがわかれば,神経疾患のリハ戦略も決まる」が,特に目を引く。第9章では,脳血管の灌流領域とそれに伴う症状,さらにそのリハビリテーションについて深く掘り下げられている。臨床現場では,病巣部位だけでなく,複数の神経システムが複雑に絡み合った結果として現れる症状を理解する必要がある。本章はそのヒントを的確に提供している。また,第10章では,パーキンソン病に関する基礎知識から具体的なアプローチまでをわかりやすくまとめており,神経システムを幅広く理解できる。
本書の構成は非常に体系的である。脳の部位ごとに章が分けられ,それぞれの章で神経システムの概要,構造,脳画像の見方,そして症例を交えたリハビリテーション戦略の立て方が具体的に解説されている。特にイラストや図表が豊富で,視覚的に脳や神経の働きを理解しやすいよう工夫されている点も魅力である。また,第2版ではWeb動画の存在が学習の大きな助けとなる。脳画像の解説や実際のアプローチの様子を視覚的に理解できるため,紙面上の情報が実践的な知識として定着しやすい。
読者を惹きつけるのは,解説の平易さと,臨床での応用を強く意識した内容である。例えば,症例解説では患者の動作や症状を具体的に分析し,それに基づいたリハビリテーション戦略を示している。「なぜ,このような症状が現れるのか?」「なぜ,このアプローチが有効なのか?」といった疑問に対し,神経システムの視点から丁寧に答えており,著者らの臨床現場に同席しているかのような感覚で学ぶことができる。
本書を通じて得られるのは単なる知識だけではない。神経システムや脳画像を的確に読み解き,患者の臨床症状や背景に応じたリハビリテーション戦略を立案する「思考力」である。この思考力を培うためのツールとして本書は大いに役立つであろう。
第2版での内容の充実に加え,多岐にわたる工夫の数々には改めて驚かされる。知識の提供だけにとどまらず,療法士としての実践力を引き上げてくれる本書は,脳卒中リハビリテーション分野における道標となる一冊である。
脳と神経システムを読み解き,治療法へとつづく道を照らす「ひかり」
書評者:網本 和(仙台青葉学院大教授・リハビリテーション学)
かつて評者が新人だった頃(およそ半世紀前),CTなどの脳画像では病変部位が明確ではないのに,右片麻痺や言語症状が出現している症例を担当したことがあった。そのとき,指導してくれた神経内科医に,「こういう場合は内頸動脈狭窄があるかもしれない」と指摘され,実際に狭窄が存在していたことがあり,脳血管障害の奥は深いと驚いた。以来,臨床症状と脳画像を見比べつつ,理学療法を進めることの重要性を痛感してきた。
星辰は巡り,脳画像描出の技術の革新的進歩に伴って多くの知見が重ねられてきた。
2021年に手塚純一先生と増田司先生という若き臨床家によって『神経システムがわかれば脳卒中リハ戦略が決まる』の初版が上梓された時,ともすれば難解な脳と神経システムについて大変わかりやすく示されていること,そして何よりもその美しさに目を見張ったことが昨日のことのようである。
それからわずか3年後の今日,ブラッシュアップされた『神経システムがわかれば脳卒中リハ戦略が決まる 第2版』を手にすることができる幸運に感謝している。神経システムについて,増田先生は「相互に影響し合う要素から構成される神経系のまとまりであり,しくみ全体のこと」と述べている。初版と同様に,まず脳の構造・部位と機能障害,臨床症状のマトリックス(インデックス)が提示される。脳損傷の部位から,あるいは逆に症状から辞書を引くように本文へと入り込めることがユニークな特徴である。
第2版では,脳血管の還流領域の視点から「複数の神経システム」について述べる第9章,および「パーキンソン病」に関する第10章が新たに追加され,一層の充実がもたらされている。さらに,それぞれの脳構造(例:「ダビデの星」レベルで留意すべきことは?)の解説,特徴的な臨床症状(例:lateropulsionなど)のワンポイント解説などが,36編のWeb動画(各々2~8分程度)として視聴できる。
大学で「神経理学療法」を教育する立場から,これまでも初版を活用させていただいてきたが,この第2版は,教員だけでなく学生にも大変役立つものと考えられる。もちろん,本来の読者である,日々臨床現場で脳卒中患者のリハビリテーションに携わる方々にとって,本書が,脳と神経システムを読み解き,治療法へとつづく困難な道を照らす,いわば「ひかり」であるといっても過言ではない。
「学ぶ手がかり」が惜しみなく収載された待望の良書
書評者:増田 知子(千里リハビリテーション病院セラピー部部長)
中枢神経ではさまざまな機能を持つ神経回路が相互に連関し,システムとしてはたらいています。脳卒中者のリハビリテーションにおいて,この神経システムの理解が不可欠であることは,今や関連職の共通認識でしょう。また,脳画像を的確に読み解いて得られる情報が,効果的・効率的な治療の鍵を握ることも同様です。
しかし,臨床の理学療法士・作業療法士にとって,神経システムや脳画像の理解が大きな難関であることは間違いありません。神経回路の連関は難解かつ数が膨大であり,「学ぶ手がかり」を探すこと自体がすでに困難です。構造や機能局在の解説にとどまらない,臨床に役立つ神経回路の知識がまとめられた書籍が希少であることも,学びの障壁になっていると感じます。
本書は,そのような状況で奮闘する理学療法士・作業療法士に対して,まさに「学ぶ手がかり」を惜しみなく授ける待望の良書です。
まず,本書の最大の特長の1つである症状別のインデックスが,神経システムの知識とその活用を格段に身近なものにしています。これは,複雑多岐にわたる神経回路を,目の前の患者さんの症状と即時に結び付けて探究できる,貴重なツールです。部位別インデックスと照合できる仕様も実践的です。このインデックスによって,臨床の傍らで手引きとするのに最適な,使い勝手の良さが際立つ1冊となっています。
全10章の構成のうち,脳の部位別に分けられた前半の7章では,驚くほど多くの神経システムが網羅されています。圧倒される情報量ですが,中でも臨床で知識が必要な機能は重点的に解説されており,非常に実用的な内容です。後半の3章では,「複数の神経システムにまたがる脳梗塞・脳出血」といった,学び進んだ次の段階での神経システムの解説が用意されています。各章の終盤では,症例の脳画像の理解から評価,リハ戦略の組み立てまでの流れが提示されており,その章で得た知識を患者像に投影して,知識を臨床に落とし込む際に役立ちます。
また,全ページにわたって色彩豊かな図表が豊富に配置され,システムを視覚的にイメージできます。脳の立体的なイラストにより,経路の走行や位置関係を3次元的に把握できます。第2版からは「みてわかるWeb動画」が収載され,さらに臨床とのリンクが強固になったと感じます。
神経システムと脳画像に関して,これほど系統立てて整理し,リハ戦略へと導く書籍の著者が,共に臨床の理学療法士であることには,驚きを禁じ得ません。その一方で,お二人が強い熱意と責任感を持って臨床経験を重ねられてきたからこそ生まれた構成・内容であるとも感じます。手塚純一先生,増田司先生の類いまれな探求心と脳卒中リハへの真摯な取り組みの結晶である本書が,リハ関連職を通じて多くの脳卒中者のために役立てられることを切に願います。