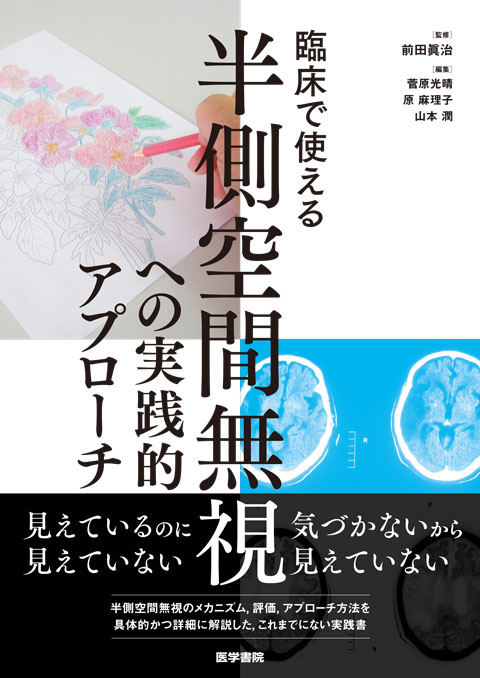高次脳機能障害学 第4版
言語聴覚士をめざす学生が高次脳機能障害学を学ぶ最初の教科書
もっと見る
令和6年「言語聴覚士学校養成所指定規則」改正を踏まえ改訂。高次脳機能障害学の理論・技術を網羅かつ体系化した標準的な教科書という大前提を堅持しつつ、今版では新たな知見を盛り込んだ。章頭の「エピソードと臨床推論の視点」、章末の事例紹介を通して、学生が多彩な高次脳機能障害領域における臨床推論の過程を学べる。さらに一部の章には、視覚的にイメージできるグラフィック動画も収載。卒後の臨床場面でも使える充実版。
*「標準言語聴覚障害学」は株式会社医学書院の登録商標です。
更新情報
-
正誤表を掲載しました
2025.12.11
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
第4版の序
高次脳機能,すなわち認知機能は人の日常生活および社会生活を支える.高次脳機能障害は,脳損傷に起因する注意,記憶,言語,行為,認知,判断,遂行機能,社会的認知,行動などの高次の精神活動の障害である.高次脳機能障害は,障害の種類や程度が同じでも個別性が高く,患者の生活様式や障害のとらえ方によって,対応すべき問題が異なることが多い.高次脳機能障害のリハビリテーションは,各々の病態を正しく評価・診断し,質の高い生活を目指すための訓練や各種の支援を行うことが求められる.
本書は,2009年に初版が刊行され,2015年に第2版,2021年に第3版と改訂された標準言語聴覚障害学『高次脳機能障害学』の第4版である.2021年に改訂されてから4年が経過し,このたび第4版として大幅な改訂を行った.今版では,令和5年「言語聴覚士国家試験出題基準」,令和6年改正「言語聴覚士学校養成所指定規則」に則って構成を刷新し,および高次脳機能障害の新しい知見を学生にわかりやすく盛り込んだ.言語聴覚士を目指す学生がテキストとして使用できるよう,言語聴覚士国家試験の出題基準改正を踏まえて高次脳機能障害に関する基本的知識,重要な理論・技術を網羅することを目指した.言語聴覚士をめざす学生あるいは若い言語聴覚士が,何を学ぶべきか,学んだことをいかに臨床現場で活かすかを,第一線でご活躍される先生がたに解説いただいた.さらに,初学者だけでなく,新しい知識を得たいと考える臨床家や研究者のために,最新の研究から得られた知見も学ぶことができるようにした.
第4版では,第1章4節を「高次脳機能障害のリハビリテーションの基本原則」と改訂し,高次脳機能障害に対するチームでのアプローチの必要性を述べた.理論から臨床への応用を念頭におき,第3版同様に事例をとおして,評価の留意点やリハビリテーション的介入に向けた観点の実際を示した.また,新たな試みとして,巻頭ページにおいて「第3章視空間障害」と「第6章記憶障害」の「エピソードと臨床推論の視点」で取り上げた事例を,イラスト付きで解説した.高次脳機能障害における臨床推論の具体的なプロセスを理解する一助としていただきたい.
初版,第2版,第3版同様に,執筆者は高次脳機能障害のリハビリテーションの第一人者の先生がたである.医師,作業療法士の先生がたが,言語聴覚士の先生がたとともに,研究や臨床の裏付けをもつ貴重な内容をご執筆くださった.本書が高次脳機能障害のリハビリテーションのさらなる発展に貢献することを願っている.
最後に,ご執筆いただいた先生がたに,心からの御礼を申し上げる.また,医学書院編集部の方々には,多大なるご支援,ご協力をいただいた.ここに深謝申し上げる.
2025年9月
編集
阿部晶子
吉村貴子
目次
開く
第1章 総論
1 高次脳機能障害とは
1.日常生活・社会生活を支える高次脳機能
2.高次脳機能障害とは
A 高次脳機能障害の定義
B 行政的支援の対象としての高次脳機能障害
3.高次脳機能障害の主要症状と背景症状
A 主要症状
B 背景症状
2 脳と高次機能
1.脳という「形」,生ける脳の「活動」,立ち現れる「こころ」
2.脳の形──機能を支える構造
A 脳の概観
B 大脳
3.高次脳機能と画像診断
A 病巣マッピング
B 機能的磁気共鳴画像法(fMRI)
C 拡散テンソル画像法
D その他の画像診断
4.高次脳機能障害の原因疾患
3 神経心理学的な考え方
A 乖離ということ
B 大脳機能の左右非対称性──側性化ということ
C 離断症候群
D 局在論,ネットワーク論,全体論
E 並列分散処理とニューラルネットワーク
F ボトムアップ処理とトップダウン処理
G 陰性症状と陽性症状
H 顕在性認知と潜在性認知
I 意識の心理学と行動の心理学
4 高次脳機能障害のリハビリテーションの基本原則
1.高次脳機能障害のチームアプローチ
A 高次脳機能障害のリハビリテーションにおけるチームアプローチ
B 高次脳機能障害のリハビリテーションの一連の流れ
C 高次脳機能障害の評価と訓練での留意点
2.チームにおける言語聴覚士の役割
A 高次脳機能障害のリハビリテーションにおける言語聴覚士の役割
B 各病期の言語聴覚療法の特徴
第2章 失認
1 視覚性失認
1.視覚の情報処理過程:視覚伝導路と視覚認知
A 知覚と認知
B 視覚伝導路(網膜から一次視覚皮質までの情報伝達)
C 一次視覚皮質以降の視覚情報処理の3つの軸
2.視知覚障害
A 皮質盲
B 大脳性色覚障害
C 幻視と錯視
3.視覚認知障害
A 視覚性失認
B 視覚性失語
C 相貌失認
D 色彩失認
4.視覚性認知障害の評価とリハビリテーション
A 皮質盲
B 大脳性色覚障害
C 幻視・錯視
D 視覚性失認
E 相貌失認
F 色彩失認
事例1 視覚性失認
2 聴覚性失認
A 聴覚の情報処理過程:聴覚伝導路と聴覚認知
B 聴覚認知障害
C 聴覚性失認の評価とリハビリテーション
事例1 聴覚性失認
3 触覚性失認および多様式失認
A 体性感覚の情報処理過程と触覚認知
B 触覚性失認および多様式失認
C 触覚性失認および多様式失認の評価とリハビリテーション
事例1 統覚型触覚性失認
第3章 視空間障害
1 視空間障害
2 半側空間無視
A 基本概念
B 症状
C 責任病巣と発症メカニズム
D 評価・診断
E リハビリテーション
3 地誌的失見当(地誌的見当識障害)
A 街並失認
B 道順障害
C 評価・診断
D リハビリテーション
4 バリント症候群
A 基本概念
B 症状
C 責任病巣
D 評価・診断
E リハビリテーション
5 構成障害
A 基本概念
B 症状
C 原因と発症メカニズム
D 評価・診断
E リハビリテーション
事例1 左半側空間無視
第4章 身体意識・病態認知の障害
1 身体図式
2 ゲルストマン症候群
A 原因
B 責任病巣
C 発現頻度とメカニズム
D 症候
E 鑑別すべき失語症との関連
F 評価・診断
G リハビリテーション
3 病態失認
A 原因と発症時期
B 責任病巣
C 症状
D 合併症状
E 評価・診断
F 発症メカニズム
G リハビリテーション
事例1 ゲルストマン症候群
第5章 動作・行為の障害
A 動作・行為の障害と失行
B 動作・行為理解のための基礎知識
C 古典的な失行の考え方(リープマンの失行論)
D 古典的失行論から脱却して今日の見方へ
E 失行と失行関連障害の今日のとらえ方
F リハビリテーション
事例1 観念性失行の事例
第6章 記憶障害
1 記憶の基本概念と分類
A はじめに
B 記憶の処理過程──3つの過程
C 記憶の種類と機能
2 記憶障害の症状と原因疾患
A 記憶障害の種類
B 記憶障害の症状と原因疾患──健忘症候群について
3 記憶障害の評価とリハビリテーション
A 記憶障害の評価の流れ
B リハビリテーション
事例1 記憶障害
第7章 前頭葉と高次脳機能障害
1 前頭葉の構造と機能
A 前頭葉の構造
B 前頭葉の機能
2 前頭葉損傷による主要な高次脳機能障害
A 前頭葉機能障害の原因
B 前頭葉の損傷で出現する症候
3 前頭葉機能障害の評価とリハビリテーション
A 評価・診断
B リハビリテーション
事例1 ワーキングメモリ障害による遂行機能障害の事例
第8章 半球離断症候群
1 脳梁の構造と機能
A 脳梁とは
B 大脳機能の側性化と脳梁の役割
2 半球離断症候群の原因疾患
3 半球離断症候群の分類
A 左半球優位症状
B 右半球優位症状
C 左右半球間連合症状
D 左右半球間抑制症状
E 意図の抗争
4 半球離断症候群の評価とリハビリテーション
A 左半球優位症状
B 右半球優位症状
C 左右半球間連合症状
D 左右半球間抑制症状
E 意図の抗争
事例1 半球離断症候群
第9章 認知症
1 正常な加齢と認知症による社会生活水準の低下
A 認知症を取り巻く背景
B 生理的な加齢と認知症の違い
C 認知症とMCI・フレイル
2 認知症の基本概念と分類
A 認知症の概要・定義・医学的診断手順
B 認知症の診断基準
C 認知症の病型と認知症に間違われやすい病態
D 認知症でみられる認知機能障害
3 認知症性疾患の薬物療法と非薬物療法の概要
4 認知症に対するアプローチの今後の展望
5 認知症の評価とリハビリテーション
A 認知症の評価
B 認知症の評価の流れと情報収集,検査
C 認知症のリハビリテーション
事例1 認知症
第10章 外傷性脳損傷の高次脳機能障害
1 外傷性脳損傷とは
2 原因疾患と病態
A 外傷性脳損傷をきたす外力とは
B 外傷性脳損傷の分類
C 病態
3 症状
A 注意障害
B 記憶障害
C 前頭葉機能障害
D 社会的行動障害・情動に関連する障害・精神症状
E 自己洞察力の障害
4 外傷性脳損傷による高次脳機能障害の評価とリハビリテーション
5 各高次脳機能障害の評価とリハビリテーション
A 意識障害・注意障害
B 記憶障害
C 前頭葉機能障害
D 社会的行動障害
E 自己洞察力の低下
6 高次脳機能障害支援事業
7 自動車運転再開支援
事例1 外傷性脳損傷による高次脳機能障害
第11章 認知コミュニケーション障害
1 外傷性脳損傷に伴う認知コミュニケーション障害
A 外傷性脳損傷の病態と障害
B 外傷性脳損傷に伴うCCDについての理解
C 評価
D 介入
事例1 記憶障害などの高次脳機能障害およびCCDを呈した事例
2 右半球損傷に伴う認知コミュニケーション障害
1.基本概念と症状
A コミュニケーションの要素と右半球機能
B 右半球損傷によるコミュニケーション障害の特徴
C 発症メカニズム
2.評価
A 評価のポイント
B 評価の内容
3.訓練
A 家族に対する支援
B 患者への直接介入
事例1 右半球損傷による認知コミュニケーション障害
3 認知症によるコミュニケーション障害
A Speech Chain(ことばの鎖)に基づいた談話障害のとらえ方
B 評価
C リハビリテーション
事例1 補聴器装用とメモリーブックを用いた談話への介入
4 筋萎縮性側索硬化症に伴う認知コミュニケーション障害
A 基本概念
B 原因と発症メカニズム
C ALSに伴う高次脳機能障害の症状
D 評価・診断
E リハビリテーション
事例1 認知機能障害(失書)を伴うALS-ci例
事例2 認知機能障害(意味処理障害)を伴うALS-ci からALS-D へ移行した例
事例3 認知症を伴うALS-D例
5 パーキンソン病に伴う認知コミュニケーション障害
A 基本概念
B 原因と発症メカニズム
C パーキンソン病に伴う非運動症状と3つの基底核大脳皮質回路
D パーキンソン病にみられる情動・認知・行動障害
E 評価・診断
F リハビリテーション
事例1 嗅覚低下で発症したレビー小体型認知症(DLB)
事例2 認知症を伴うパーキンソン病(PDD)例
▪ Pointの解答例
▪ 参考図書
▪ 高次脳機能障害学の授業プラン
▪ 索引
▪ 『標準言語聴覚障害学』全10巻の特長と構成
Note一覧
① Hebbの法則
② 情報が評価や訓練にもたらす意味
③ ベースラインの設定と数値化した反応の推移──アウトカム評価
④ 高次脳機能障害と加齢
⑤ アントン症候群
⑥ 対座法による視野測定
⑦ 表出性失音楽症 expressive amusia
⑧ 読話
⑨ 音の方向感に影響を及ぼす要因
⑩ 視覚失調と視覚性運動失調
⑪ ゲルストマン症候群の研究史
⑫ 義手を用いた病態失認の仮説検証
⑬ 意図性と自動性の乖離
⑭ 原始反射
⑮ 「他人の手徴候」という用語・概念について
⑯ 記憶の処理水準と脳内処理
⑰ 一過性全健忘と全生活史健忘
⑱ エビングハウスの忘却曲線
⑲ ウェルニッケ脳症
⑳ ワーキングメモリの評価
㉑ 短期記憶の限界 Magical Number Seven, Plus or Minus Two
㉒ 葉性萎縮
㉓ Exnerの書字中枢
㉔ 脳梁離断術
㉕ メタ認知
㉖ treatable dementia(治療可能な認知症)
㉗ FTLDとbvFTD
㉘ 高次脳機能障害と認知症
㉙ 感度・特異度
㉚ 認知症と短期記憶障害
㉛ メモリーブック
㉜ 運転免許の更新制度
㉝ 地域包括ケアシステムと認知症基本法
㉞ 認知症予防と認知予備能
㉟ てんかん発作時の対応と観察のポイント
㊱ 右半球言語能力検査(RHLB)
㊲ 心の理論
㊳ ポジティブな思い出
㊴ 日本版ALS機能評価スケール ALS Functional Rating Scale Japanese version(ALSFRS-R Japanese version)
㊵ 会話明瞭度
㊶ 類義語判断検査と類音的錯書
㊷ 意味的線画連合検査 Pyramid and Palm Trees Test
㊸ 失語症構文検査
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。
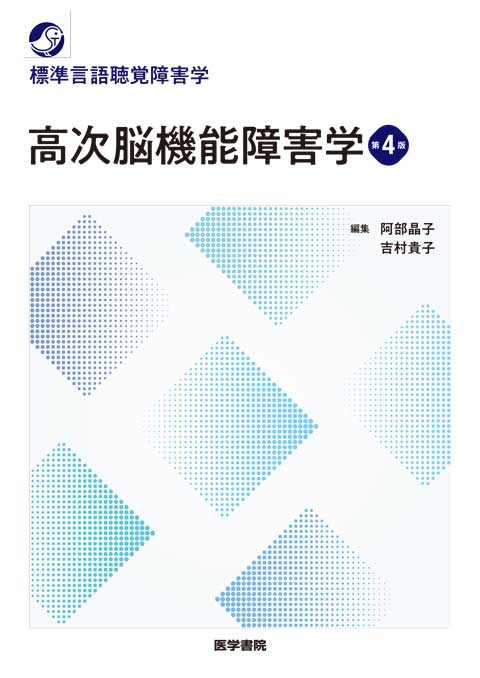
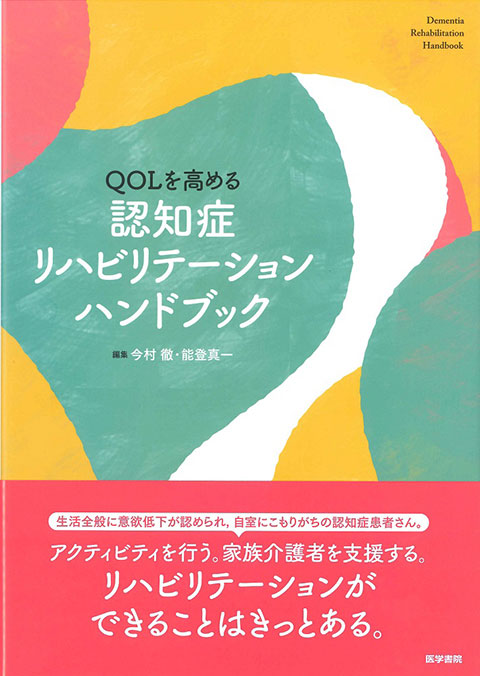
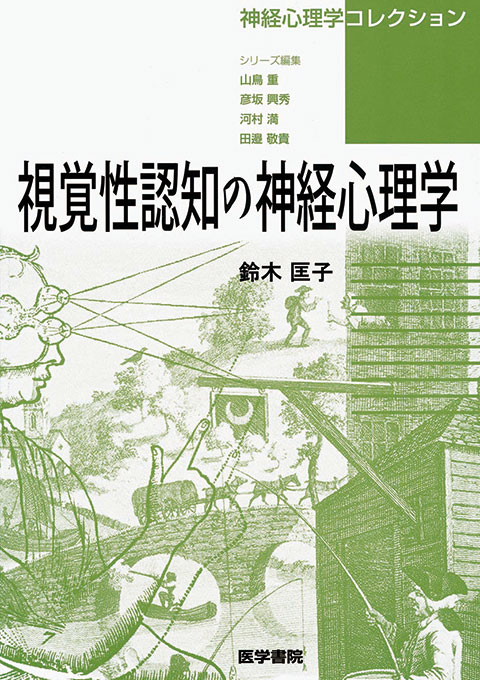
![Evidence Based で考える認知症リハビリテーション2 BPSDの評価と介入戦略[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6417/2792/9404/113680.jpg)