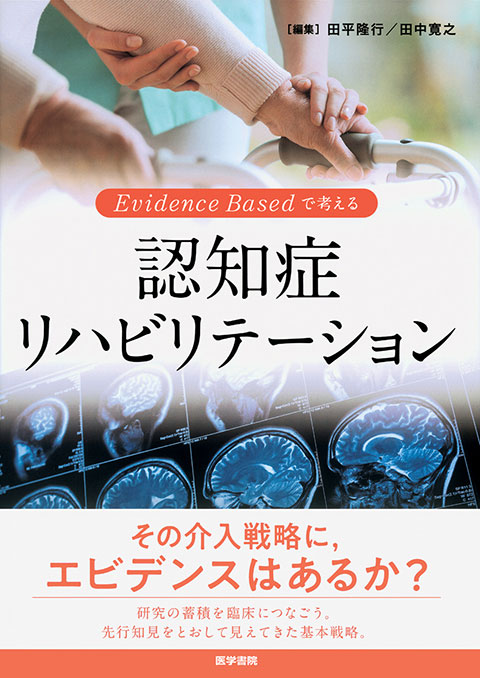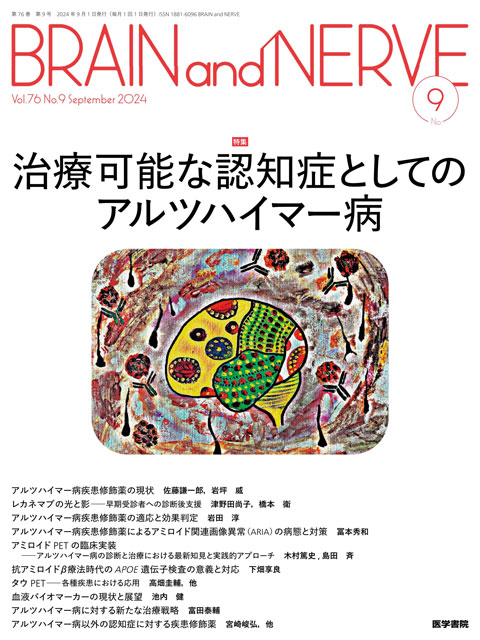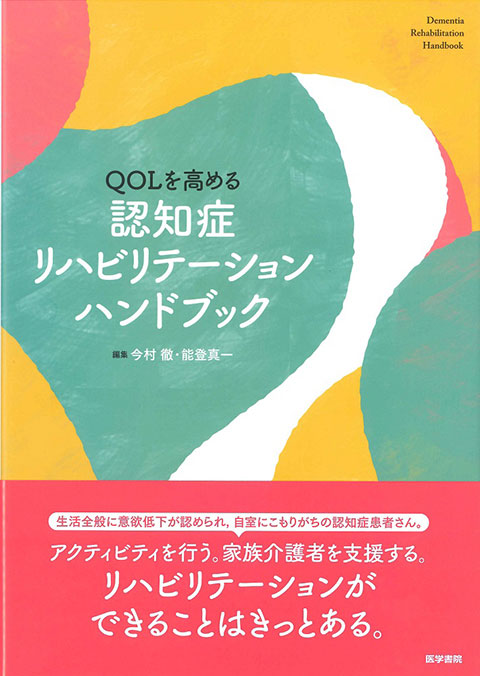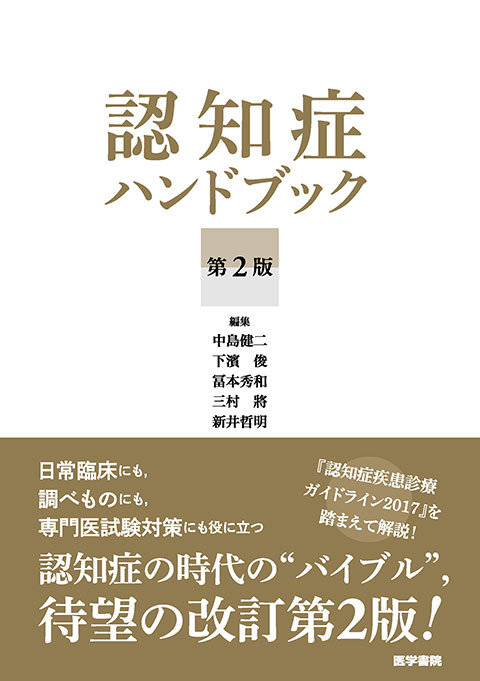Evidence Based で考える認知症リハビリテーション2 BPSDの評価と介入戦略[Web動画付]
認知症新時代に求められるエビデンスベースのBPSDリハビリテーション・ケア
もっと見る
好評を得た『Evidence Basedで考える認知症リハビリテーション』の第2弾。前作同様、「臨床と研究をつなぐ」「エビデンスベースド」をコンセプトに、認知症者の行動・心理症状である「BPSD」を深く掘り下げる。症状ごとの出現要因や適切な解釈、最新の知見をもとにした妥当な介入戦略の数々を紹介。各項目収載のレクチャー動画も理解の助けとなる。認知症リハビリテーション・ケア分野の医療従事者必携の1冊。
更新情報
-
【2025年3月27日開催終了】出版記念Webセミナーを開催しました
2025.03.28
- 序文
- 目次
- 書評
- 付録・特典
序文
開く
序
私たちが編集した前書『Evidence Basedで考える認知症リハビリテーション』が刊行されてから5年が経過しました.前書は,認知機能,ADL,BPSDの疫学や誘因,事例を含めたリハビリテーションについて最新の情報を網羅的にレビューしました.リハビリテーション専門職を中心に,エビデンスに基づいた介入戦略の参考になったなど多くの感想をいただきました.心より感謝申し上げます.
その間,認知症疾患修飾薬の開始や認知症に関する政策の進展など,認知症は新たな時代を迎えています.認知症施策推進大綱,日本認知症官民協議会の設置,2024(令和6)年には認知症基本法が施行され,内閣府を中心とした全省庁,つまり国民一人ひとりに対する社会全体の課題として認知症対策が進められています.「当事者の意見を尊重する本人ミーティング」,「発症を遅らせ,進行を緩徐にするための認知症予防」,「見守り等介護ロボットの開発,普及」,「超早期の診断と診断後支援」などがそれに当たります.リハビリテーション分野においても2024年,訪問による認知症短期集中リハビリテーション実施加算が新設され,より住み慣れている地域で暮らし続けることへの支援が強化されました.
一方,在宅だけではなく病院や施設で支援されているリハビリテーション・ケア従事者も多くいます.ケア従事者,家族介護者からは,介護負担の要因としてしばしば行動・心理症状(BPSD)が挙げられ,支援に悩んでいる方は相当数にのぼると思われます.パーソンセンタードケアなどの基本的な考え方は普及してきましたが,クライエントの個人因子や環境因子の影響も大きく,各論的なエビデンスはいまだ不十分です.
そのような声を受け,現段階でのリハビリテーション・ケアの国内外のエビデンスを集約する目的で,私たちは本書を出版することとしました.基本的には前書でBPSDについてまとめた部分を深く掘り下げ,新しい研究や実践を加え,理論,評価,介入方法を理解しやすいように構成しています.
本書の特徴は大きく3つ挙げられます.
1つ目は,BPSDは症候の理解と要因分析が介入戦略に最も重要であることから,各症候の疫学,種類,誘因を概説したうえで,出現・マネジメントモデル(支援理論)を詳しく紹介している点です.各種モデルは基本的な理論から最新の理論まで他書にはないボリュームで紹介しています.リハビリテーション職種のみならず日常ケアに難渋しているケア従事者にもぜひ一読してほしい内容です.
2つ目は,介入方法論において古典的な非薬物療法は最小限とし,ここ10年エビデンスが構築されてきたものを厳選し,「療法」ありきではなく,理論と実践をセットにすることで,より現場で活用しやすいものになっています.適応と限界を踏まえ,介入選択の一助としてもらえればと思います.また,本人だけでなく家族や介護者,地域の方々への支援教育についても触れるなど幅広い内容となっています.
3つ目は,現場の皆様により使っていただきやすいよう,各節のまとめの短編動画を付録につけました.読んだ後のまとめとしての記憶保持,斜め読みの際のアウトライン把握などの目的で積極的に活用していただければ幸いです.
本書が皆様の日々の臨床における実践の確認や理解の強化,そして悩みを解決する一助となれば編者としてこの上ない喜びです.また,忌憚のないご意見もぜひお寄せいただければと思います.
最後に,本書にご執筆いただきました認知症専門医,言語聴覚士,作業療法士の先生方に厚く御礼申し上げます.また,企画から発刊まできめ細かく編集のご支援をいただきました医学書院の北條立人氏に深謝申し上げます.
2024年9月吉日
田平隆行・田中寛之
目次
開く
chapter 1 BPSD総論/基礎的知識
1 BPSDとは何か
2 認知症の各疾患,重症度,およびBPSDの特徴
A アルツハイマー型認知症,血管性認知症,レビー小体型認知症,前頭側頭型認知症
Column:BPSDと認知症者本人を取り巻く環境づくり
B 軽度認知障害(MCI),主観的認知機能低下(SCD)
Column:SCDを取り巻くさまざまな要因
C 軽度行動障害(MBI)
D 若年性認知症
Column:若年性認知症の人に対する就労支援の現在
3 BPSDのもう1つの理解
──チャレンジング行動(挑戦的行動) challenging behavior──
Column:BPSDの本当の症状は?
4 BPSDの背景要因
Column:ひもときシート
chapter 2 BPSDの種類/評価/介入戦略
1 BPSDの種類,評価尺度(症状特異的),発現機序からリハ・ケア介入戦略の立案まで
A 妄想
Column:その他の代表的な妄想
B 幻覚
Column:その他の代表的な幻覚
C agitation(焦燥性興奮)
Column:agitationと不穏
D 脱抑制・易刺激性(易怒性)
Column:認知症者の怒り
E うつ・アパシー
Column:多元的なアパシーの評価
F 不安
Column:認知症者の不安の負の連鎖を,認知症ポジティブの正の連鎖へ
G 異常行動
Column:徘徊に対するさまざまなサポート
H 睡眠-覚醒障害・概日リズム障害
Column:人の概日リズム機構と休息や活動のパターン
I 食行動
Column:よく観察すれば,どこかにヒントが落ちている?
Column:BPSDのクラスター分類
2 BPSDの出現モデル・マネジメントモデル
A 学習理論──ABC分析を含めて
Column:スタッフ・サポート・システム(SSS)とは
B unmet needs model
Column:在宅認知症高齢者の unmet needsについての報告
C DICEアプローチ
D model of imbalance in sensoristasis(BACEアプローチ)
E Progressively Lowered Stress Threshold model(PLST model)
F Comprehensive Process Model of Engagement(CPME)
3 BPSDの評価尺度
A Neuropsychiatric Inventory(NPI)
Column:リハビリテーションにおけるNPIの使用法
B 認知症困りごと質問票(BPSD+Q)
C Behavioral Pathology in Alzheimer's Disease(BEHAVE-AD)
Column:BEHAVE-ADの応用
D Dementia Behavior Disturbance Scale(DBDスケール)
Column:認知症初期集中支援チームでの活用
chapter 3 BPSDの介入手順/具体的な方法論
1 BPSDの介入手順
A ステップに沿ったBPSDへの対応
B BPSDの薬物療法(代表的薬剤,効果,副作用)
Column:抗精神病薬の使用は悪なのか?
Column:agitationとは?
2 BPSDの非薬物的介入の具体的な方法論
A BPSDに対する非薬物的介入の概要
B 音楽介入
Column:音楽がその人の生活に寄与すること
C 回想法
Column:VRを用いた新しい回想法
D Tailored Activity Program(TAP)
E 認知行動療法
Column:認知行動療法のセッションの進めかた
F ルーチン化療法
Column:クライエントの「その後」を追えないセラピストの務め
G Simulated Presence Therapy(SPT)
Column:オンラインツールの活用
H 物理的環境支援・介入
Column:環境音は認知症のケアへ応用できるのか?──新たな挑戦
I DEMBASEを用いたケアプログラム
J ICT・ロボット介入
Column:遠隔でクライエントを見守るロボットシステム
K 家族支援・教育介入
Column:教育介入が効果的な介護家族のタイプ
L 医療・介護従事者への支援・教育介入
Column:医療・介護従事者への支援・教育の現場で
M 多職種連携(チーム)による介入
Column:誰のためのリハビリテーション? ケア?
索引
書評
開く
BPSDの「ブラックボックス」に挑む:エビデンスに基づく新しい実践ガイド
書評者:友利 幸之介(東京工科大教授・作業療法学)
本書は,認知症の行動・心理症状(BPSD),例えば興奮,怒り,うつ,不安,徘徊といった「ブラックボックス」に対し,エビデンスに基づく明確な視座から理解と介入の手掛かりを示した,本邦初の書籍といえるでしょう。
ここ10年ほどで認知症者に対する非薬物療法に関する研究は格段に進歩し,作業療法の効果も示されています。しかし,その事実が本邦の作業療法士には十分に浸透しておらず,いまだ認知症者の支援は経験則に基づいて行われることが多いのが現状です。このエビデンス-実践ギャップ(Evidence-Practice Gap)をどうにか解消できないかと私も考えていたところ,本書がまさにその問題に応えてくれました。
いくらエビデンスで効果があるとされる介入でも,認知症者への支援は個別性が非常に高く,結局は対象者一人ひとりをどのように理解するかが重要になります。システマティック・レビューで「この介入には統計的に効果があります」と言われても,臨床家にとって現場で即座に活用できる内容(情報量)ではありません。つまりエビデンスと臨床の間を埋める「翻訳作業」が必要です。
そこで本書では,認知症者のBPSDの理解に焦点を当て,現時点で得られている最新かつ膨大なエビデンスを基に,BPSDの病態や症状の解説から始まり,BPSDの各症状に対応する28の評価方法と12の介入法が紹介されています。紹介されている図表も多く,個人的にはリーズニングを促すためのフローチャートがBPSDの理解を容易にしていると感じました。評価表も多く取り上げられており,エビデンスに基づく実践の第一歩として,BPSDの定量化から始める際にも役立つでしょう。ここまでで既に,エビデンスと臨床の間を埋める「翻訳作業」としては十分な内容ですが,さらに本書の新たな取り組みとして,各章においてWeb上で視聴可能な著者陣による動画解説が提供されており,紙面の内容を視覚的・聴覚的に補完する工夫もされています。
このように,認知症リハビリテーションを経験則から脱却して科学的に解明していきたいという編者や著者たちの熱量が,本書の至るところから伝わってきます。ここまで膨大なエビデンスを,1)BPSD総論/基礎的知識,2)BPSDの種類/評価/介入戦略,3)BPSDの介入手順/具体的な方法論,と理解しやすい流れで,かつ統一感のある構成に仕上げた皆さまの尽力に,心からの敬意を表します。
総じて,本書は認知症リハビリテーションにかかわる全ての医療従事者にとって,前作『Evidence Basedで考える認知症リハビリテーション』に続き(前作以上に!?),欠かせない一冊になることは間違いありません。特に作業療法士には,本書を読み込み,認知症チームを牽引する役割を担ってくれることを期待しています。
認知症共生社会の実現に必要なエッセンス
書評者:山田 実(筑波大教授・老年学)
認知症。世界随一の長寿大国であるわが国において,この対策は最重要課題の一つに位置付けられている。高齢者人口の増加に伴い,認知症を有する方は今後さらに増加することが予想されており,予防,治療,介護のそれぞれの領域で対策方法の模索が続いている。そのようななか「認知症と共生する社会」の実現が強調されるようになった。これに向けては,認知症を正しく理解することが不可欠であることはいうまでもない。そして,この理解を困難にさせているのがBPSDであろう。
医療・介護従事者は,BPSDを正しく理解できているのだろうか。BPSDの症状は多岐にわたり,個人や環境によってもその症状は大きく異なることから,その臨床像は複雑である。十分な臨床経験を有する従事者は,これまでの経験に基づき対応することは可能だろう。ただし,その経験に学術的知見が加われば,その対応の質をさらに高められるかもしれない。一方,そのような臨床経験がなければ,目の前で起こるさまざまな事象を客観的に受容することすら難しいかもしれない。こういった点で,本書は初学者から十分な経験を有する方まで,幅広い従事者が抱える課題の解決につながるバイブル的存在になる可能性を秘めている。
私が本書を手にとった際,最初に感じたのが「厚み」である。BPSDの非薬物療法に関する情報だけで280ページ。BPSDの基本情報に始まり,臨床症状,評価,介入まで,実に丁寧にそのエビデンスがまとめられている。ボリュームだけでなく,視認性を高めながら適切に整理がなされていることで,必要な情報へアクセスしやすいのもポイントの一つとなっている。
そして,次に感じたのが「温もり」である。各項目に38の短編動画が準備されており,それぞれ執筆担当者自身が解説。執筆者の声を提供することで,絶妙な距離感での学習機会を付与している。そして秀逸なのが,随所にちりばめられた32のコラム。このコラムによって臨床場面の解像度を高め,エビデンスという無機質な情報に彩りを加えられている。
認知症,特にBPSDの理解は容易ではない。しかし,この書籍は「難しい」から「何とかしよう」「何とかしたい」と思えるきっかけを与えてくれるはずである。この書籍とともに「認知症と共生する社会」が実現することを期待して。
![Evidence Based で考える認知症リハビリテーション2 BPSDの評価と介入戦略[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/6417/2792/9404/113680.jpg)