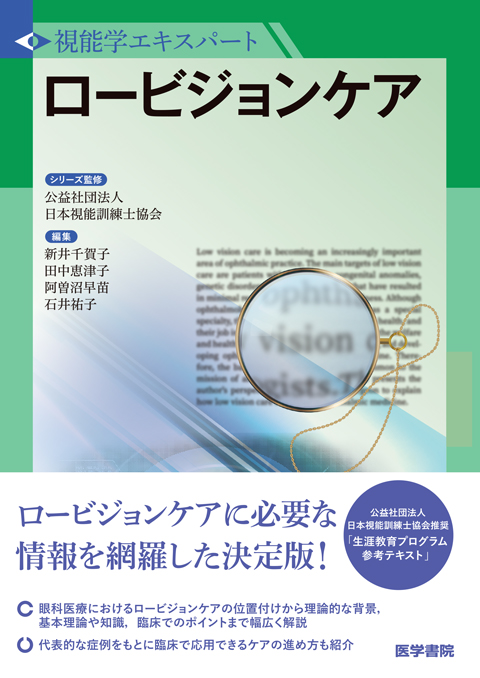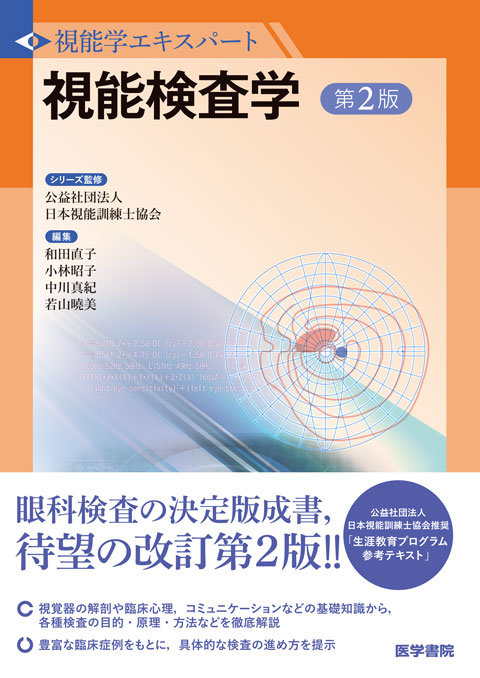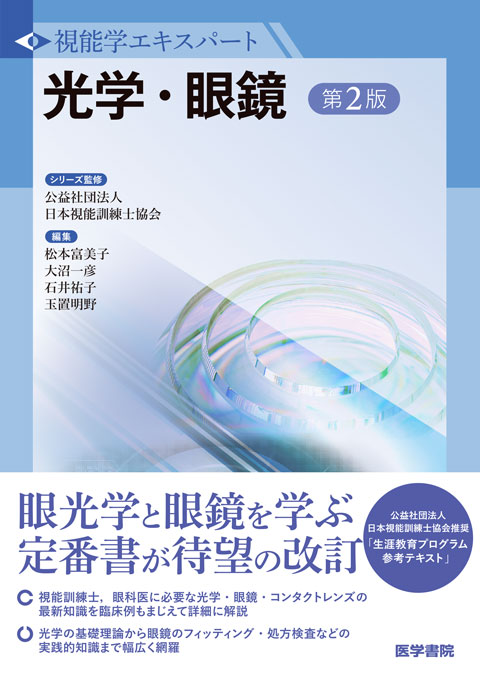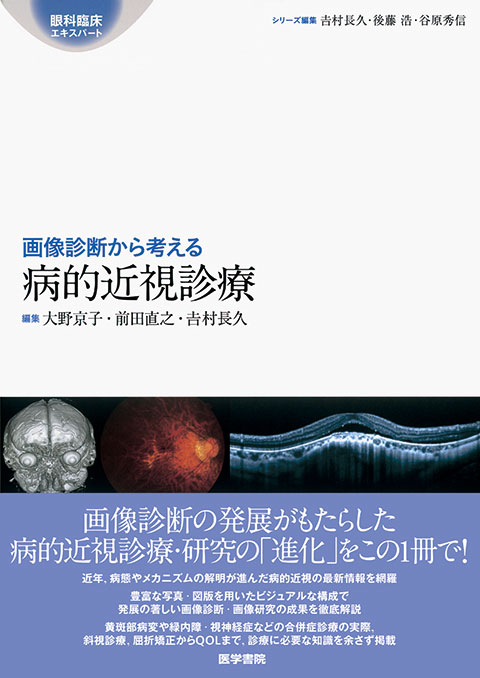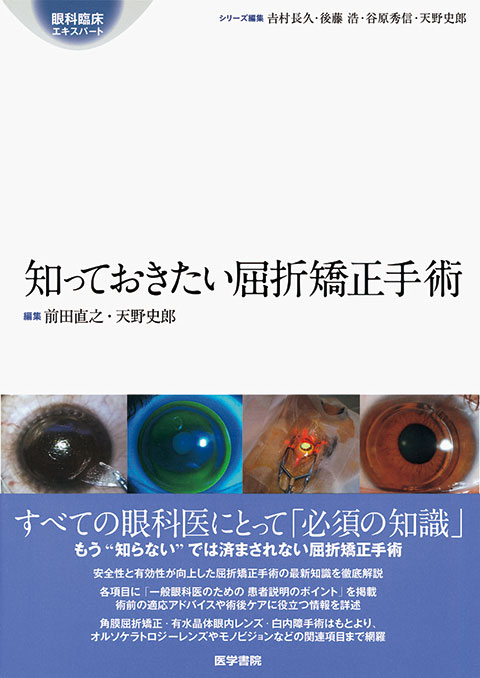ロービジョンケア
ロービジョンケアの基礎と臨床への応用が幅広く学べる体系的な専門書がついに誕生!
もっと見る
日本視能訓練士協会監修による新時代の視能訓練士向け専門書シリーズの1冊。視能訓練士に必要な学際的関連領域の基礎理論とその臨床への応用を掲載した初学者の教科書であり、かつ充実した症例をもとにした解説によりロービジョンケアの臨床に関わっている方々の日常臨床の疑問に答えられる専門書でもある。視能訓練士・視能訓練学生・眼科医・視覚研究者に役立つ内容。視能訓練士協会推奨の生涯教育プログラム参考テキスト。
更新情報
-
正誤表を掲載しました。
2024.06.01
- 序文
- 目次
- 書評
- 正誤表
序文
開く
視能学エキスパートシリーズ 第2版刊行にあたって(南雲 幹)/序
視能学エキスパートシリーズ
第2版刊行にあたって
このたび,《視能学エキスパート》シリーズは第2版を刊行することになりました.本シリーズは,視能訓練士に必要とされる視能検査学,視能訓練学,光学・眼鏡に関する様々な知識を集積し,すでに臨床で活躍している方々が日常業務を行ううえで熟思する際の参考に,またこれから視能訓練士を目指す学生の卒前教育にも広く役立てていただいています.
初版が刊行されてから約5年が経ち,この間,2021(令和3)年には厚生労働省で視能訓練士学校養成所カリキュラム等改善検討会が実施されました.指定規則および教育ガイドラインの一部改正について検討が行われ,視能訓練士のさらなる資質の向上が求められています.年々,医療技術や検査機器は高度化しており,また加速する人口減少による社会構造の変化および国民のための医療,保健,福祉等へのニーズの高まりに対応できる視能訓練士であるためには,日々努力し専門性を向上させる必要があることは言うまでもありません.
第2版では,可能な限り基礎から最新情報までを網羅し「具体的症例を取り入れた臨床に応用できる内容」「常に手元に置きたい教本」というコンセプトを踏襲し,各シリーズの内容のさらなる充実や,最新知識のアップデートを中心に企画し,臨床・研究の第一線でご活躍の先生方に改訂のご執筆のお願いをいたしました.
この《視能学エキスパート》シリーズ第2版のすべての巻が研鑽を続ける視能訓練士の皆様の一助となること,また日本の国民がその長寿な人生においてできる限り快適な視能を保持するために貢献できることを心より願っております.
2024年,本シリーズに『ロービジョンケア』が新たに加わることとなりました.『ロービジョンケア』は「視る能力」の専門職である視能訓練士にとって重要な業務領域です.既刊の3タイトルとともに皆様の必携の一冊となることを期待しております.
2023年1月
(2024年1月更新)
公益社団法人 日本視能訓練士協会
会長 南雲 幹
序
眼疾患によって視機能が低下しているが完全な失明(blind)ではなく活用可能な視機能があるロービジョン(low vision)という視覚の状態があり,対応したケアが必要であるという考えが生まれたのは20世紀後半のことです.眼科医療の歴史から考えるとロービジョンケアは非常に新しい領域になります.現在,多くの先進国では長寿による高齢患者の増加と医学の進歩による完全な失明の減少によりロービジョンの患者人口は増加し,ロービジョンケアの必要性は高まっています.
わが国では2000年に日本ロービジョン学会が設立され眼科医療におけるロービジョンケアの推進力になりました.それに呼応するように日本視能訓練士協会では,生涯教育事業のロービジョンケアの講義を充実してきました.このような背景から,本書は既刊の3領域の「視能学エキスパート」シリーズと同様に視能訓練士のロービジョンケアの教科書として企画されました.この領域は,現在も成長しており今後も新しい知見や方法論が生まれてくる余地があります.そのため,視能訓練士の教育に貢献できる教科書を作る作業は想像以上に難航し,他の3領域から大幅に遅れた刊行となってしまいました.
本書では,医療機関において患者のもつ視機能をできるだけ引き出しその活用を支援するロービジョンケアを中心に取り扱いました.医療は診断と治療に加え,ロービジョンケアに重要な視機能の活用度の評価が検査データに基づいて提供でき,福祉や教育サービスとの連携のハブにもなりうる立場でもあります.したがって,視能訓練士の技術が活かされる光学的な理論背景や知識に力点をおいた構成になっています.また,ロービジョンケアは医療だけではない幅広い範囲の知識と連携が求められる学際的領域であることを念頭におき,医療以外の他職種への理解を深める項目も含めました.これらの項目は視機能の活用が非常に困難な重度のロービジョンや全盲(blind)の患者への対応にも応用できます.
第1部の総論では,視能訓練士がロービジョンケアを眼科医療の中で展開する位置付けと理論的な背景,第2部の各論ではロービジョンケアに必要な基本理論や知識を,第3部のロービジョンケアの実際では臨床に応用できる代表的な症例のケアについてロービジョンケアを担当している視能訓練士に解説いただきました.また,福祉サービスでの日常生活訓練,歩行訓練,パーソナルコンピュータやタブレットなどのIT機器の活用訓練,学校教育での子どもの学習や発達の支援などの周辺知識も各章に加えてあります.
無理なお願いを聞いていただき長期にわたる編集作業にご協力をいただきましたご執筆の先生方,発刊まで気長にお待ちいただいた関係者の皆様には心より感謝申し上げます.
ロービジョンの研究もロービジョンケアの臨床も,長い眼科医療の歴史の中ではまだまだスタートしたばかりです.この本を視能訓練士の臨床で活用いただき,新たな研究成果や臨床知見によってブラッシュアップされ,よりレベルアップしたロービジョンケアの教科書へと読者の皆様に育てていただければと願っております.
2024年1月
編集者一同
目次
開く
第1部 ロービジョンケア総論
第1章 総論
I 眼科医療とロービジョンケア
II 視能訓練士とロービジョンケア
III 視覚科学とロービジョンケア
第2章 基礎的な理論と知識
I 視覚科学
II QOL評価
III 視覚リハビリテーション
IV ロービジョンの心理
V ケースワークの基礎知識
VI 社会福祉制度
VII 学校教育制度
VIII 疫学
第3章 チーム医療と学際的連携
I 視覚以外の障害の基礎知識
A. 知的障害,肢体不自由,盲ろう(聴覚障害の知識も含む)
B. 神経発達症(発達障害),高次脳機能障害,認知症
第2部 ロービジョンケア各論
第4章 ロービジョンの視機能と行動
I ロービジョンケアにおける視機能検査
II 視力・中心視野障害と偏心視域
III 周辺視野障害
IV コントラスト感度
V 羞明と光順応
VI 眼球運動障害・眼球振盪
A. 眼球運動障害へのロービジョンケア
B. 眼球振盪へのロービジョンケア
VII ロービジョンと色覚異常
VIII 行動観察による視機能評価
第5章 プランニング
I インテークとニーズの把握
II ライフステージとロービジョンケア
III ロービジョンケアのプランニング
第6章 読書の法則・理論とロービジョン
I ロービジョンと読書の関係
II 読書評価
第7章 ロービジョンエイドの基礎知識
I レンズ光学の基本
II 網膜像拡大の理論
III 近見光学補助具の構造と適応
IV 遠見光学補助具の構造と適応
V 弱視眼鏡の構造と適応
VI 遮光レンズの原理と適応
VII 拡大読書器の構造と適応
A. 据え置き型拡大読書器
B. 携帯型拡大読書器
VIII 電子的拡大機器の構造と適応
IX 非光学的補助具による視覚活用
X 義眼
A. 小児の義眼
B. 成人の義眼
第8章 ロービジョンエイドの選定の理論
I 選定の手順
II 読字と書字のエイド選定方法
第9章 ロービジョンの移動と運転
I 安全な移動方法と公共交通機関の利用
II ロービジョンと運転
第10章 視覚障害リハビリテーションとロービジョンケア
I 視覚活用から他の感覚器官の活用への移行
II 歩行訓練
III 日常生活訓練
IV 聴覚と触覚による読み書き訓練
第11章 高度医療とロービジョンケア
第3部 ロービジョンケアの実際
第12章 ロービジョンエイドの選定の実際
I 眼鏡と近見加入
II 置き型拡大鏡
III 手持ち拡大鏡
IV 弱視眼鏡
V 単眼鏡
VI 拡大読書器
VII 遮光眼鏡
VIII デジタル機器の活用
第13章 主な疾患のロービジョンケア
I 緑内障
II 加齢黄斑変性
III 網膜色素変性
IV 病的近視
V 小児のロービジョン
VI 糖尿病網膜症
VII 角膜疾患
第14章 ロービジョンケアケースワーク
I 他施設連携
II 視覚以外の障害・疾病が合併する場合
巻末資料
索引
書評
開く
ロービジョンケアを多角的に学ぶことができる専門書
書評者:臼井 千惠(帝京大教授・視能矯正学)
医療技術者は自らの業務に責任を持ち,たゆまぬ自己研鑽を通じて国民に安心・安全な医療を提供する責務があり,視能訓練士も例外ではない。そこで公益社団法人日本視能訓練士協会は,さまざまな臨床経験の視能訓練士に対応できる教育制度として2006年度から生涯教育制度を導入した。カリキュラムは新人教育プログラム(主に国家資格取得後5年以内の者),基礎教育プログラム(新人教育プログラム修了者),専門教育プログラム(基礎教育プログラム修了者)の3段階で構成され,専門教育プログラムは「視能検査」「視能訓練」「視能障害」「光学・眼鏡」の4領域における将来のリーダーを育成することを目的として2017年から開始された。その際,4領域の学修には基礎知識に加え,より専門性の高い知識が必要との意図で発刊された専門書が「視能学エキスパート」シリーズである。
本シリーズは上記4領域から各1冊を発行することとし,『視能検査学』『視能訓練学』『光学・眼鏡』の3冊は2018年に初版が,2023年に第2版が発行されている。そして2024年,待望の『ロービジョンケア』初版が満を持して発行された。
『ロービジョンケア』が本シリーズの他領域と大きく異なるのは,真の意味で多職種連携が必要な領域であることだろう。視能訓練士は医学的な見地から医師の指示の下でロービジョンケアを眼科で行うが,実際は視覚リハビリテーションとして医学的,社会的,職業的,教育的,工学的リハビリテーションと横断的に関連し,それぞれに従事する専門家と情報を共有し,連携する必要がある。「餅は餅屋」ということわざがあるが,正にロービジョンケアには患者を中心とするチーム医療が欠かせない。本書は第1部「総論」,第2部「各論」,第3部「実際」の3部構成になっているが,第1部「総論」にチーム医療としてのロービジョンケアを集約させたことに,編集者の本書に対する並々ならぬ思い入れを感じた。
第2部以降は眼科領域を中心とした内容で構成され,眼科臨床で行われている諸検査をロービジョン患者の視機能評価のための検査としてとらえ直して検査手技を工夫・応用する方法,患者の読書能力を評価する意義,ロービジョンエイドの眼光学知識や選定のポイント,ロービジョン患者の移動(誘導法や歩行訓練)などが具体的に解説され,さらに再生医療など最先端の高度医療からみたロービジョンケアに対する考え方も掲載されており,ロービジョンケアの経験が浅い者から豊富な者まで各自のレベルに応じ必要な知識を得ることができる。続く第3部もロービジョンケアの実例がロービジョンエイド別,疾患別に具体的な症例を通じて説明されている実践編で,対処ポイントや選定方法は読者が臨床で患者に対応する際の心強いガイドになるであろう。
ただ,一読して感じたのは,情報量の多さである。ロービジョンケアに興味を持つ者が本書を読むことで,逆に自分にはハードルが高すぎると尻込みするのではないかと心配になるほど微に入り細を穿つ情報が掲載されている。それが本書の良い意味でのこだわりなのだろうが,一方で,臨床でもっと積極的にロービジョンケアにかかわってほしいと願う編集者の意図とは逆の影響を読者に与える懸念もあるように感じた。
しかし,本書第1部に掲載された言葉を借りると,ロービジョンケアは「臨床の場では,見え方で困っている人はすべて対象になる」「眼科のなかに治療とは違う視点で自分を支援してくれるLVCという部門があり,そこにケアの専門家がいる」ことが重要になる。本書を手にする読者は,どうか情報量の多さに臆せず,自分が知りたいロービジョンケアの知識や技術は第2部・第3部から適宜学びつつ,第1部をロービジョンケアにかかわる者の心構えとして通読してほしい。きっと眼科の枠を越えてロービジョンケアを大きな視点でとらえることができるだろう。
眼科医療者の使命を説き,ロービジョンケアの本質に迫る一冊
書評者:白根 雅子(しらね眼科院長)
ロービジョンケアは,眼科医療の力が及ばず視覚障害を背負った患者さんが,保持する能力を最大限に活用して充実した社会生活を営むためにある。患者さんは視力を失う過程で必ず眼科で治療を受けている。眼科医,視能訓練士をはじめ,看護師,社会福祉士,その他全てのメディカルスタッフには,患者さんの視機能や心理,身体の状況に応じた適切な対応が求められる。
本書では,ロービジョンケアのスタートとして,視力,視野,コントラスト感度,光順応,眼球運動,色覚といった残存視機能を評価し,その結果に基づいて年齢や生活背景に合った視覚補助具を選定する流れが詳細に解説されている。また,患者さんが希望する仕事や社会活動を遂行するために,保有視機能はもとより,聴覚,触覚などの他の能力も加味した読書能力を評価し,目的に応じた読書訓練を行う手順がわかりやすく記述されており,一読すると視覚リハビリを習得できる。
タブレット,暗所視ゴーグル,RETTISSA® display IIなどの新しいテクノロジーを搭載したロービジョン支援機器の紹介もあり,時代に即したケアの情報を得ることができる。外出に際しては,視覚障害者の心理や環境を踏まえ,社会で安全に活動するための白杖,盲導犬を用いた歩行訓練の進め方,さらにはinternet of thingsの活用や視野障害を抱える人への運転アドバイスの言及もあり,ロービジョン者の行動範囲を広げる未来志向のケアが示されていることを評価したい。
障害者総合支援法に基づく障害支援区分,自立支援医療,居宅介護,就労移行支援,補装具,日常生活用具に関する解説をはじめ,介護保険法,年金制度(障害年金),「難病の患者に対する医療等に関する法律」などの記述もあり,関連する制度を理解して行政の福祉サービスを活用し,適切な生活訓練,就労支援につなげることも可能となる。
加えて,就学前から初等中等教育,大学等への進学に至る学校教育の制度と合理的配慮といった,障害者の生活を支える基本となる教育的支援の重要性にも言及されていることに注目したい。
最終章では,医療機関以外の施設との連携や,聴覚障害,四肢の運動機能障害,知的障害,高次脳機能障害を重複する障害者のケアのポイントが示されており,障害者ケアに携わる者として,広く深い知識を習得する重要性が示されている。
本書は,人の視覚を守ることを専門とする眼科医療者の使命を説き,ロービジョンケアの本質に迫る書籍である。
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。