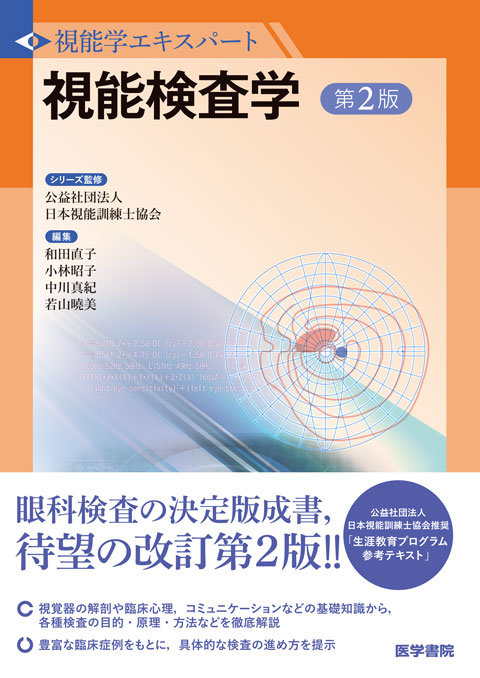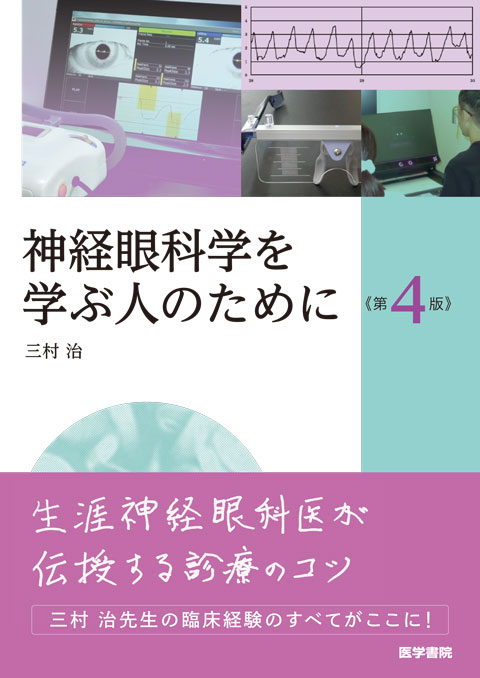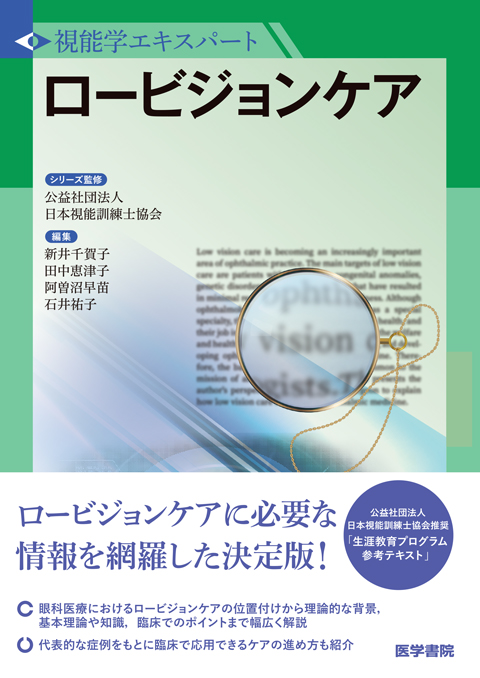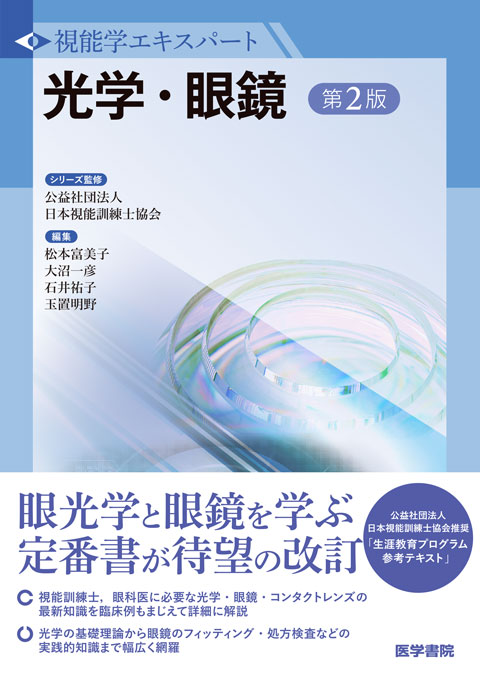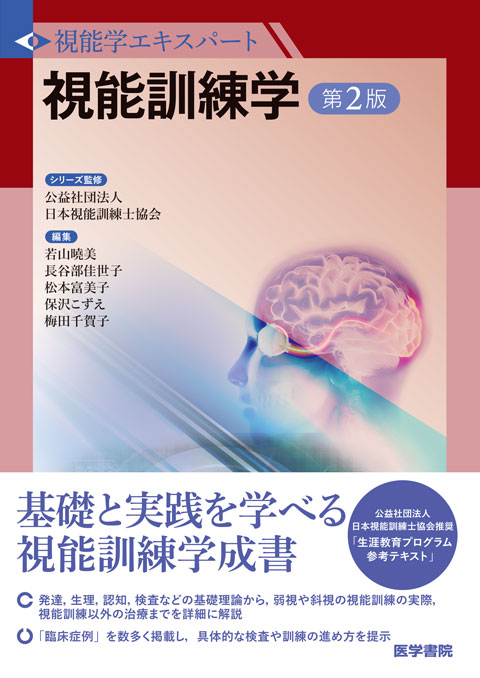視能検査学 第2版
眼科検査の基本から実際の進め方までを詳細に解説した必携書、待望の改訂!
もっと見る
日本視能訓練士協会監修による視能訓練士(C.O)向け専門書シリーズ、待望の改訂第2版。視覚器の解剖や臨床心理、コミュニケーションなどの基礎知識から、各種検査の目的・原理・方法などを徹底解説。臨床症例を数多く掲載し、具体的な検査の進め方を提示する。卒後のC.Oはじめ、視能訓練学生・眼科医・視覚研究者にとっても有用なテキスト。日本視能訓練士協会推奨の「生涯教育プログラム参考テキスト」にもなっている。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
視能学エキスパートシリーズ 第2版刊行にあたって(南雲 幹)/第2版の序
視能学エキスパートシリーズ
第2版刊行にあたって
このたび,《視能学エキスパート》シリーズは第2版を刊行することになりました.本シリーズは,視能訓練士に必要とされる視能検査学,視能訓練学,光学・眼鏡に関するさまざまな知識を集積し,すでに臨床で活躍している方々が日常業務を行ううえで熟思する際の参考に,またこれから視能訓練士を目指す学生の卒前教育にも広く役立てていただいています.
初版が刊行されてから約5年が経ち,この間,2021(令和3)年には厚生労働省で視能訓練士学校養成所カリキュラム等改善検討会が実施されました.指定規則および教育ガイドラインの一部改正について検討が行われ,視能訓練士のさらなる資質の向上が求められています.年々,医療技術や検査機器は高度化しており,また加速する人口減少による社会構造の変化および国民のための医療,保健,福祉等へのニーズの高まりに対応できる視能訓練士であるためには,日々努力し専門性を向上させる必要があることは言うまでもありません.
第2版では,可能な限り基礎から最新情報までを網羅し「具体的症例を取り入れた臨床に応用できる内容」「常に手元に置きたい教本」というコンセプトを踏襲し,各シリーズの内容のさらなる充実や,最新知識のアップデートを中心に企画し,臨床・研究の第一線でご活躍の先生方に改訂のご執筆のお願いをいたしました.
この《視能学エキスパート》シリーズ第2版のすべての巻が研鑽を続ける視能訓練士の皆様の一助となること,また日本の国民がその長寿な人生においてできる限り快適な視能を保持するために貢献できることを心より願っております.
2023年1月
公益社団法人 日本視能訓練士協会
会長 南雲 幹
第2版の序
《視能学エキスパート》シリーズは,2006年4月から開始された公益社団法人日本視能訓練士協会の生涯教育制度の教育内容に対応できる,視能訓練士に必要な専門性の高い専門書として作成されました.本書『視能検査学』は,生涯教育におけるすべての領域の基本となるものです.
2018年の本書刊行から5年が経過しました.この間にも医療機器の開発や検査技術の進歩はありましたが,それと同時に私たちを取り巻く環境も大きく変化してきました.
昨今視能訓練士が検査に携わることの多い光干渉断層計,光学式眼軸長測定の機器の開発には目覚ましいものがあります.新しい医療機器が開発されることは疾患の理解を深めるよい機会になります.しかし,正確に検査を行うためには機器を使いこなせることが必要であり,日々勉強し続けることが求められます.またこれからはAI化が進み,検査も簡便・簡素化し,器械がすべてを行ってくれる時代が来るかもしれません.その成果を上げるためにも今検査に携わる視能訓練士が責任をもって検査結果を見極めていく姿勢が求められます.本書はその一助となるべく解剖をはじめ視能訓練士がかかわる検査を網羅できるよう努めました.そして,患者さんは不安をもって検査を受けています.検者が患者心理を理解して上手にコミュニケーションをとることがより正確な検査につながっていきます.初版とは少し内容が変更された「臨床心理学」の項をぜひお読みいただきたいと思います.
また,本書の特徴でもある第3部「疾患別検査の進め方」は,臨床で行われている検査を具体的症例により解説することで理解を深められるものです.第2版では今注目されているpachychoroid関連疾患,視神経疾患の抗AQP4抗体陽性視神経炎や抗MOG抗体陽性視神経炎も採り上げました.
2019年冬以降,COVID-19の影響で「安心して生活できる世の中になるのか?」という不安な状態が続いております.長期化する中で感染対策の検討も行われてきておりますが,今回は一般社団法人日本眼科医療機器協会のご協力のもと,眼科機器の感染対策一覧を巻末に掲載しましたので臨床の場で生かしていただければ幸いです.
最後に第2版を出版するにあたり原稿の執筆をご快諾くださいました執筆者の先生方に厚く御礼申し上げます.
2023年2月
編集者一同
目次
開く
第1部 視能検査学を学ぶための基礎知識
序章 視能検査学とは
第1章 視器の解剖学
I 視覚器の発生
II 眼球組織構造
III 眼球の血管系
IV 神経支配
V 視神経,視路
VI 脳の解剖
VII 大脳の機能局在
VIII 視覚情報処理
第2章 臨床心理学
I 患者の心理
II 医療者の心理
第3章 医療コミュニケーション学
I 概論
II 患者─医療者間のコミュニケーション
III 医療者間のコミュニケーション
IV 医療の安全を高めるためのチーム医療
第2部 視能検査学
第4章 視力検査
I 視力
II 視力検査に必要な視覚生理学
III 視力検査の実際
第5章 屈折検査
I 屈折異常
II 他覚的屈折検査
III 調節麻痺薬を用いた屈折検査
第6章 調節検査
I 調節
II 調節検査
III 負荷後調節検査
第7章 コントラスト検査
I コントラスト感度
II コントラスト検査
第8章 グレア検査
I グレア感度
II グレア検査
第9章 収差検査
I 収差
II 収差検査
第10章 視野検査
I 視野
II 視野検査に必要な視覚生理学と心理物理学
III 動的視野検査
IV 静的視野検査
V 特殊視野検査
VI Amslerチャート
VII 両眼視野検査
第11章 臨界融合頻度検査
第12章 瞳孔検査
第13章 暗順応検査
I 光覚と暗順応・明順応
II 暗順応検査に必要な視覚生理学
III 暗順応検査
第14章 色覚検査
I 色覚
II 色覚に必要な視覚生理学
III 色覚検査
第15章 眼圧検査
第16章 電気生理学検査
I 全視野網膜電図(全視野ERG)
II 多局所網膜電図(多局所ERG)
III 視覚誘発電位
IV 眼球電図
V 電気眼振図
VI 筋電図
第17章 角膜内皮検査・角膜知覚検査・角膜厚測定
第18章 フレア検査
第19章 涙液検査
第20章 OCT検査
I 前眼部
II 網膜
III 脈絡膜,強膜
第21章 眼球突出検査
第22章 眼瞼検査
第23章 写真検査
I 外眼部
II 細隙灯顕微鏡写真(スリット写真)
III 眼底写真
IV 蛍光眼底写真
第24章 血流検査
第25章 超音波検査
I 超音波
II Aモード
III Bモード
第26章 光学式眼軸長検査
第27章 画像診断検査
I CT
II MRI
第3部 疾患別検査の進め方
I 屈折・調節の異常
A.弱視①:不同視弱視
B.弱視②:斜視弱視
C.調節障害:老視
II 眼瞼の異常
A.重症筋無力症
B.眼瞼けいれん
III 結膜疾患
A.翼状片
B.輪部デルモイド
IV 涙器疾患
A.鼻涙管閉塞
B.ドライアイ
V 角膜疾患
A.角膜ヘルペス
B.Fuchs角膜内皮ジストロフィ
C.円錐角膜
VI 水晶体の異常・白内障
A.加齢性白内障
VII ぶどう膜・強膜の疾患
A.原田病
B.Behçet病
C.強膜炎
VIII 網膜・脈絡膜疾患
A.加齢黄斑変性
B.加齢黄斑変性(ポリープ状脈絡膜血管症)
C.糖尿病網膜症
D.網膜静脈分枝閉塞症
E.pachychoroid関連疾患
IX 視神経疾患
A.抗アクアポリン4抗体陽性視神経炎
B.抗MOG抗体陽性視神経炎
X 緑内障
A.開放隅角緑内障
B.閉塞隅角緑内障
Ⅺ 眼窩疾患
A.甲状腺眼症
B.眼窩腫瘍
C.内頸動脈海綿静脈洞瘻
Ⅻ 外傷
A.眼窩吹き抜け骨折
XIII 心因性疾患
A.心因性視覚障害
付録:主な眼科機器の感染対策一覧
索引