MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


《標準理学療法学・作業療法学専門基礎分野》
整形外科学
第2版
奈良 勲,鎌倉 矩子 シリーズ監修
立野 勝彦 執筆
《評 者》古川 宏(神戸大教授・身体・精神障害作業療法学)
理学療法士・作業療法士に必須の内容をすべて網羅
 このたび,立野勝彦先生著『標準理学療法学・作業療法学専門基礎分野整形外科学 第2版』が医学書院から刊行された。著者の立野勝彦先生はわが国で最初に理学療法・作業療法の大学教育制度を金沢大学で立ち上げ,その後30年の長きにわたり整形外科・リハビリテーションの専門医として理学療法・作業療法の教育に携わっている第一人者である。豊富な臨床経験に基づいて運動器疾患とリハビリテーション医学との関連性を考慮しながら教授した集大成が,2000年の初版として結集されたものと推測される。今般,著者は第2版の「序」で「(初版から5年間の間の)読者や教科書として使用している先生方の意見を参考にして紛らわしい表現や図をていねいに,わかりやすく改変し,図を新たに追加した」としている。第2版を拝見すると「序」で記述の通り,図,イラスト,写真,表現も一層精選されて本来広範で難解な疾病構造の変遷,細分化された整形外科の診断法や治療法もわかりやすく,スムースに頭に入っていく。これは,著者が初版から「広く整形外科学を系統的に理解することを目的とし,(中略) 運動器障害の基礎的知識を十分に習得し,それを理解応用できるように記述したつもりである。基礎的知識を十分に理解してくれるように特別な解説を加え,国家試験にも対応できるように工夫した」と一貫して述べているように,読者である学生や若い理学療法士,作業療法士への温かい配慮がみられる。
このたび,立野勝彦先生著『標準理学療法学・作業療法学専門基礎分野整形外科学 第2版』が医学書院から刊行された。著者の立野勝彦先生はわが国で最初に理学療法・作業療法の大学教育制度を金沢大学で立ち上げ,その後30年の長きにわたり整形外科・リハビリテーションの専門医として理学療法・作業療法の教育に携わっている第一人者である。豊富な臨床経験に基づいて運動器疾患とリハビリテーション医学との関連性を考慮しながら教授した集大成が,2000年の初版として結集されたものと推測される。今般,著者は第2版の「序」で「(初版から5年間の間の)読者や教科書として使用している先生方の意見を参考にして紛らわしい表現や図をていねいに,わかりやすく改変し,図を新たに追加した」としている。第2版を拝見すると「序」で記述の通り,図,イラスト,写真,表現も一層精選されて本来広範で難解な疾病構造の変遷,細分化された整形外科の診断法や治療法もわかりやすく,スムースに頭に入っていく。これは,著者が初版から「広く整形外科学を系統的に理解することを目的とし,(中略) 運動器障害の基礎的知識を十分に習得し,それを理解応用できるように記述したつもりである。基礎的知識を十分に理解してくれるように特別な解説を加え,国家試験にも対応できるように工夫した」と一貫して述べているように,読者である学生や若い理学療法士,作業療法士への温かい配慮がみられる。
序説でPT・OTと整形外科のかかわりを概説して重要性を簡単に述べた後,第1章の整形外科基礎知識では,骨,関節,骨格筋,神経系の基本構造と病態生理,第2章で運動器の評価および検査法,第3章で整形外科的治療法の総論を簡潔に体系づけてまとめて述べている。第1章から第3章では臨床現場で見られる基本的症状とその原因を解説し疾病論に必要な基本的知識の整理を行っている。重要な用語については,「NOTE」で定義および解説を簡潔に表記している。また,一歩進んで学習しておくべき事柄は「Advanced Studies」で解説している。各章の最初の「学習目標」,各章の最後の項目「理学・作業療法との関連事項」,各章のまとめ「復習のポイント」は,箇条書きで重要事項の総復習,自己学習に大変役立つ。第4章から第7章の整形外科疾病論では,第4章 炎症性疾患,第5章 代謝・内分泌性疾患,退行性疾患,第6章 先天性骨・関節疾患,第7章 循環障害と壊死性疾患,第8章 骨・軟部腫瘍,第9章 神経・筋疾患,第10章脊椎の疾患と疾患別にわかりやすく分類されているので,とかくそれぞれの病名をバラバラに記憶して頭が混乱する愚を防ぎ類似疾患との対比がしやすくなっている。写真やイラストがわかりやすいのは理解の助けになっている。第11章から第18章の外傷性疾患では,第11章 骨折,第12章 脊髄損傷,第13章 関節における外傷性疾患(捻挫,脱臼),第14章 末梢神経における外傷性疾患,第15章 腱・靭帯における外傷性疾患,第16章 スポーツ傷害,第17章 熱傷,第18章 切断および離断,という整形外科の理学療法で最も多い対象となる分野の原因,症状,治療法が簡潔に記述されている。
最後に,セルフアセスメントとして各章から2-3題合計41題の代表的な問題を国家試験形式で出題し,解答と解説で復習と知識の整理をしている。
ベテランの整形外科医,リハビリテーション専門医として理学療法,作業療法の学生に整形外科学を教授してきた立野勝彦先生が理学療法士,作業療法士にとって必須な内容をすべて網羅した本書は学生や経験年数の少ないコメディカルスタッフにお勧めしたい教科書である。


長廻 紘,大井 至,坂本 長逸,星原 芳雄 編
《評 者》名川 弘一(東大教授・腫瘍外科)
編者のこだわりが感じられる内視鏡学の専門書
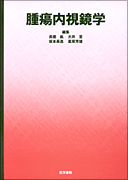 本書は,内視鏡学からみた消化器腫瘍の専門書である。専門書であるから,専門家に読んで欲しい。さらりと読み流すのではなく,一語一句を熟読して欲しい。編者のこだわりが感じられるであろう。本書は,内視鏡を単なる検査,診断,治療の道具としてではなく,内視鏡学として捉えた一冊である。
本書は,内視鏡学からみた消化器腫瘍の専門書である。専門書であるから,専門家に読んで欲しい。さらりと読み流すのではなく,一語一句を熟読して欲しい。編者のこだわりが感じられるであろう。本書は,内視鏡を単なる検査,診断,治療の道具としてではなく,内視鏡学として捉えた一冊である。
流氷は美しい。流氷を見るツアーも組まれている。この流氷を見て,その美しさに感激する人も多いことであろう。一方,流氷の静かな佇まいから水面下に隠されている大きな氷の塊を想像する人もいるであろう。
本書は,食道,胃,大腸などの実際の症例を中心に,海面上の流氷を描くように,豊富で美しい写真を用いて詳細な解説がなされている。これだけで,十分,読み応えのある書物となっている。しかし,編者の狙いは違う。本書をもとに,水面下の氷塊に思いを馳せる人を探している。これが編者のこだわりである。
まず,序論が圧巻である。冒頭に「序」あるいは「序文」と題して,著者あるいは編者の意図などが1-2ページで記載されているのが通常の書籍である。本書は,通常の書籍とは異なる。本書の冒頭に「序論-内視鏡の過去・現在・未来」と題して,内視鏡学の軌跡と編者の思いが10ページ強の紙面で綴られている。この序論によって,本書を作り上げた編者の強烈な思いと力の強さ,そして学問に対する真摯な姿勢を読み取ることができよう。
次に,その編集方針が特徴的である。編者によって執筆項目が厳選されたのであろう。内視鏡と腫瘍にかかわる一般的な知識については,これをすでに習得していることが前提となっているようである。
本書全体で4章の構成である。第1章の食道・咽頭で6項目,第2章の胃・十二指腸で10項目,第3章の大腸・小腸で9項目,第4章の胆・膵で5項目であり,全体で30項目の構成となっている。執筆項目としてとりあげられている疾患は26を数えるのみである。冒頭に「専門家に読んで欲しい」と記載した所以である。
編者の真の狙い,すなわち今後の内視鏡学のブレークスルーのために,各章のはじめに「展望」を置くことによって,そのヒントが与えられている。流氷の美しさに感激しているだけではなく,氷山全体を見て欲しい,そしてその不思議に気付き,さらに謎を解明して発展させて欲しい。編者のこのような思いが伝わってくる一冊である。


本郷 利憲,廣重 力,豊田 順一 監修
小澤 瀞司,福田 康一郎,本間 研一,大森 治紀,大橋 俊夫 編集
《評 者》本間 生夫(昭和大教授・生理学)
学生から臨床医まで使える優れた教科書
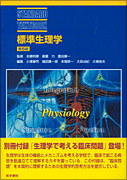 『標準生理学』の改訂版が出版された。1,100ページに及ぶ大作である。日本の生理学の教科書としてはもっとも厚く,各章ともそれぞれの分野での日本の第一人者が執筆されている。
『標準生理学』の改訂版が出版された。1,100ページに及ぶ大作である。日本の生理学の教科書としてはもっとも厚く,各章ともそれぞれの分野での日本の第一人者が執筆されている。
その厚さゆえ,まったく知識のない学生が生理学の教科書として最初に手にするには少し戸惑うかもしれない。しかし,内容はただ単に解説の文章が並んでいるのではなく,随所に勉強しやすくするための工夫がみられる。
本書の初版からの特徴でもあるが,それぞれの章のはじめに「本章を学ぶ意義」が書かれており,まず章の全体像を捉えることができる。特に本書のように内容が豊富な教科書では,詳しく読む前にアウトラインを把握することができ,理解を早めるためにたいへん有効である。そして章の最後には,「学習のためのチェックポイント」が書かれている。
この方式は現在,各大学で取り入れられているコアカリキュラムの方式に則っており,各章の行動目標が達成されたかどうか,自分自身でチェックすることができる。チェックポイントにかかれている設問にすべて答えられれば,その章を完全にマスターできたといえるであろう。それだけ充実している。編者が,教育方法にかなり精通していることがうかがえる。
本文中にはadvanced studyの項が設けられており,その分野における最先端の学問が書かれている。そのため本書は学部学生だけでなく,大学院生にも十分使える教科書にもなっている。基礎的なことを理解できた学生に,さらに突っ込んで勉強したい,と思わせる内容である。
この本を読んだ大学院生に感想を聞いたところ,「最新の知見を踏まえ,各項目が非常にわかりやすく整理されている」,「論文を読んでいてわかりにくい部分や,学部学生時代に学んだことを辞書代わりに調べるのに最適である」という意見が返ってきた。往々にして,何度読んでも理解できない,という教科書が作られやすいが,この本では丹念に解説が加えられている。
序文で編者が,この教科書は臨床で直面する病態生理の理解にも役立つと述べているように,病態生理に関しても詳しく記述されている。したがって生理機能の理解ばかりでなく,疾患の理解にも役立つ。付録としてついている「生理学で考える臨床問題」は,生理学の教科書としては新しい試みである。
本書は生理学の基礎を学ぶ学生,臨床医学を勉強している高学年の学生,さらには現在すでに医師になっている方にも,一冊持っていると役に立つ生理学の教科書である。


泉 孝英,長井 苑子 編集
《評 者》佐藤 睦子(京都学園大 学生相談室ヘルスカウンセラー)
これからの医療者に必携の教本
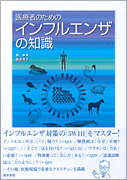 パターナリズムと評される医療者中心のあり方は,さまざまな反省と検討のうちに,医療システムの質改善と再設計をめざして21世紀医療をよりよい方向に導く契機になった。
パターナリズムと評される医療者中心のあり方は,さまざまな反省と検討のうちに,医療システムの質改善と再設計をめざして21世紀医療をよりよい方向に導く契機になった。
医療システムの質改善と再設計には課題や条件が明らかにされているが,中でも患者の価値観に対応する患者中心の医療提供と,最新最善のエビデンスを反映することが特質的な側面としてガイドラインの策定に反映されている。
一方,策定の推進には,医療の主体者を医師に限定することなく,個々の医療従事者が患者との相互的対話を媒介に,優先疾患と症状の説明責任を果たすことが不可欠条件として認識されてもいる。
優先疾患と症状説明をとおして,患者の価値観と最新最善のエビデンスベースを統合する医療ガイドラインは今後の開発に期待される点も大きい。しかし,そのような中にあって,本書『医療者のためのインフルエンザの知識』は,人々に不可避的な健康不安を起こす現代の優先疾患インフルエンザについて説明責任を果たすべく,一定レベルのエビデンスを共有するための教本である。
本書には大学,医学研究機関,医療団体,医薬研究機関など幅広いグループによる最先端,最善のエビデンスが集積されているが,そのコラボレーションは読者のニーズを想定して9つのカテゴリーに整理統合されている。それぞれのカテゴリーはQ&A方式で編集され,その編集形式は読者自身が自らの知識を改めて整理し,取得可能なエビデンスのレベル修正を行いながら患者への説明能力を再構成するためのポイントでもある。
各カテゴリーに設定された質問項目は,医療改革へ向けられた編者の視座と臨床判断から作られているが,最善のエビデンスを,最大多数の人々へ提供しようとする意図が明確に映し出されている。
私のように教育現場で学生や教職員の健康管理に携わる場合でも,健康や疾病の説明責任を意識して,常に自己啓発の必要性と自己能力の不安を痛感している。しかし,本書との出会いによって,自分の身の丈にあったエビデンスベースを活用しながら,日常生活での優先疾患であるインフルエンザを語り,説明するための説明構造をその時々の状況によって創造できる安心感を得ることかできた。
よき医療の発展には説明行為だけでなく,癒しの関係を継続させる相互的対話の交流も大切であるが,本書に掲載されている16のコラムはインフルエンザを取り巻く社会文化の出来事や様子を興味深く紹介して会話に華を添え,本書をインフルエンザと人間の「物語」として彩っている。本書に一貫する編者の眼差しは,21世紀医療の職能者の輪を広やかにして確実に育むであろう。
これからの医療現場,学校教育や産業保健,福祉施設などの官民を合わせた医療職能者にとって,本書は必携の快い教本である。


松田 晋哉 著
《評 者》竹田 秀(財団法人竹田綜合病院理事長)
DPCによる病院マネジメントのための必読書
 現在DPCは,実施病院・試行的適用病院あわせて144病院において導入されている。また調査協力病院として100以上の病院がデータを提出しており,DPCの本格導入にむけて準備を進めている。もちろん2006年度からDPCが本格実施されるかどうかは中医協マターであり,現時点では断言できない。しかし,著者も指摘するようにDPCは支払いへの活用を第一目的とするものではなく,あくまで病院の医療の質と経営のマネジメントのためのツールである。私見ではあるがその科学性と有用性を考えると,DPCの適用は拡大することはあっても,後退することはないであろう。その点本書はこれからDPCについて取り組もうとしている病院関係者にとって必読の入門書と言える。
現在DPCは,実施病院・試行的適用病院あわせて144病院において導入されている。また調査協力病院として100以上の病院がデータを提出しており,DPCの本格導入にむけて準備を進めている。もちろん2006年度からDPCが本格実施されるかどうかは中医協マターであり,現時点では断言できない。しかし,著者も指摘するようにDPCは支払いへの活用を第一目的とするものではなく,あくまで病院の医療の質と経営のマネジメントのためのツールである。私見ではあるがその科学性と有用性を考えると,DPCの適用は拡大することはあっても,後退することはないであろう。その点本書はこれからDPCについて取り組もうとしている病院関係者にとって必読の入門書と言える。
著者の松田晋哉先生は,急性期試行診断群分類を活用した調査研究班の主任研究者としてDPCの開発にあたったリーダーであり,DPCについての執筆者として最もふさわしい方である。本書はDPCの仕組みやその意義をわかりやすく説明するという難しい試みに挑戦したもので,平易な記述ながらDPCの本質を説いており,その目的は成功したと言える。
第1章は「診断群分類とは何か」でDPCのコードの意味や開発経緯などを解説している。この章だけで全体の半分を占めているので,16のMDCそれぞれの診断群分類の事例については別の章にしたほうがよかったかもしれない。個人的には8の「開発の経緯」が先頭にあったほうが流れが自然であったと思うが,実務家を対象に考えたためこのような構成にしたのであろう。
第2章は「DPCを何に使うのか」であり,本書の核心である。病院経営における情報システム,原価管理,医療の質などDPCを活用した病院マネジメントについて簡潔に記述されている。病院幹部・管理職はここの内容を理解していなければ,これからの病院経営はできないであろう。第3章は「今後の課題」,第4章は「諸外国の状況」で全体に端的にまとめられていてコンパクトな仕上がりである。
DPCの導入予定がない病院においても,今後はDPCを活用した病院マネジメントの考え方を理解しておく必要があると思う。その意味で本書を,職種を問わずすべての病院関係者に薦めたい。本書はDPCの基礎についての解説書であるが,2年が経過してDPCのデータは着実に蓄積されており,今後はそれらの分析手法についての続編が書かれることを期待したい。
