MEDICAL LIBRARY 書評特集


泉 孝英 監修
冨岡 洋海 編
《評 者》藤田 次郎(琉球大教授・感染病態制御学)
結核診療に携わる臨床医のバイブル
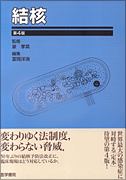 『結核 第4版』を通読し,書評をさせていただく。
『結核 第4版』を通読し,書評をさせていただく。
私自身,第1版からこの本に親しんでいたという点で愛着を持っていたが,第4版の内容は新しい知見が多く盛り込まれ,内容を刷新したという印象である。もともとまず1985年に「結核」の第1版を出版しようと企画された泉孝英先生の先見の明に感銘するのみならず,この書を継続して改版されているエネルギーにも敬意を表したい。
もし本書がなかったと仮定しよう。結核予防会からも多数の優れた医学書が出版されており,それはそれで歴史の息吹に触れることができるものが多く,その当時の研究者の努力に感銘しながら私自身も愛用している本もある。しかしながら内容的には,若干古くなっているものも多いことも事実であり,かつ本書のように,結核病学全体を包括したような書は少ない。
客観的に考えて,日本の結核病学は,患者数の多かったこと,検査法が高いレベルで広く普及していたこと,および結核予防法など公費医療システムの整備されていたこともあり,世界一のレベルにあるといえる。現在の独立行政法人,国立病院機構の多くの病院は結核療養所としてスタートしたものが多く,かつ結核が国民病であった時代には最高の人材が結核の臨床,および研究に従事したと考えられる。その優れた先人達の遺産を引き継ぎ,それを土台にさらに発展させたのが本書といえる。どの章を読んでも,Up―To―Dateの内容が網羅されており,現段階の最高の結核病学を集積したものであると断言できる。
私自身は,結核,および非結核性抗酸菌症の画像所見に特に興味を持って拝読したが,その両者とも優れたものであり,かつ多数の症例が紹介されていることに驚嘆した。また外科領域の記載も歴史的な背景も含め充実しており,内科医の私にはたいへん参考になった。さらに臓器別のとらえ方,年齢,および基礎疾患への配慮,症例呈示,および結核の社会学など,さまざまな配慮を持って編集されている点にも,監修者,および編集者の意気込みを感じることができる。
しかしながら本書の圧巻は付録の部分にある。付録1の「結核の歴史」は,ただいたずらに結核の脅威をあおるのではなく,歴史観からわが国における結核の現状を正確に評価しており,本書をより格調高いものにしている。さらに付録2の「わが国における結核文献」は,わが国における結核研究が歴史的に判断しても世界最高の質・量を誇ることが明らかにされている。このような詳細な資料をどのように調査されたのか,その調査方法にも関心を持った。
本書は,呼吸器内科医のみならず,結核診療に携わる多くの臨床医のバイブルとなりうるし,該当する行政機関,および保健所などでも備えておくべき書であると考える。しかしながら,個人的には,結核について断片的な知識しか有していない若い先生方にぜひ,本書を通読していただき,結核に関する最新情報を学んでもらうことを切望するものである。


米国喘息教育・予防計画委員会 編
泉 孝英 監訳
《評 者》浅井 泰博(湯沢町保健医療センター・地域家庭診療部)
臨床研究エビデンスを一層反映したガイドライン
 米国の喘息ガイドラインである,National Asthma Education and Prevention Program, Expert Panel Report: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma Update on Selected Topics2002の邦訳である。初版はオリジナルが1991年,日本語版は1993年に発行された。日本語版は第3版となっているが,第2版(1991年)の一部のトピックスについて2002年にアップデートされたものである。日本語版が待ち遠しかったがようやく2006年になって発行された。
米国の喘息ガイドラインである,National Asthma Education and Prevention Program, Expert Panel Report: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma Update on Selected Topics2002の邦訳である。初版はオリジナルが1991年,日本語版は1993年に発行された。日本語版は第3版となっているが,第2版(1991年)の一部のトピックスについて2002年にアップデートされたものである。日本語版が待ち遠しかったがようやく2006年になって発行された。
日本語初版が発行されたとき,私はちょうど瀬戸内海に浮かぶ島の町立病院に赴任していた。夜間は定期船が運行していないので時間外患者はすべて受診していた。喘息発作患者も多かったが,普段の治療は気管支拡張薬は十分すぎるほどであったが,吸入ステロイド薬はわずかの患者にしか使われていなかった。病院の内科医師は一丸となって兎にも角にも吸入ステロイドを導入した。効果がないとすぐに止める人もいて,経口ステロイドを数日間は服用してもらいながらであった。1年足らずで徐々に喘息発作の受診が減っていくことが実感できた。喘息治療の流れが変わっていくにちがいないと思った。
その後,喘息治療は吸入ステロイドが中心となり,さらによい喘息コントロールを効率的に得るにはどうすればよいのかについて世界中で研究が進んだ。本ガイドラインの改訂には,臨床研究から得られたより強固なエビデンスを反映するシステムが取られている。第2版から改訂になった点を列挙する。治療においては,小児における喘息の長期管理(吸入ステロイドと他の薬剤の比較,吸入ステロイドの安全性),併用療法(吸入ステロイドに他の薬剤を追加),喘息増悪時の抗菌薬の使用,である。モニターにおいては,書面による行動計画と薬剤のみとの比較,ピークフローを使った行動計画と症状による行動計画との比較である。予防においては,早期治療が喘息の進展に及ぼす影響についてである。どれも興味深いテーマであり,近年の臨床研究の結果が反映されている。
本書の構成は,前半3分の2が第2版とその改訂,後半3分の1が改訂の根拠となった報告書となっている。改訂部分は青色で印字されているので一目瞭然である。前の版をすでに読んだことのある読者は,改訂部分のみなら1時間程度で読めるだろう。しかし改訂部分よりも変わらない部分の方がより大切である。例えば,喘息の鑑別診断には,「小児においても成人においても,繰り返す咳や喘鳴のエピソードのほとんどは喘息によるものである。特に,気道感染のときに喘鳴を示す小児では,喘息の診断が見逃されている」とあり,私はドキッとした記憶がある。喘息患者を診るなら一度は目を通しておきたい(必携度数80%)。


長谷川 敏彦,松本 邦愛 編
《評 者》八代 尚宏(国際基督教大教授・教養学部社会学)
医療という鏡をとおして経済学を理解するための好著
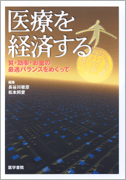 本書はこれまでにない「医療関係者による医師のための経済学入門」という,経済学の立場から見ても興味深いものである。
本書はこれまでにない「医療関係者による医師のための経済学入門」という,経済学の立場から見ても興味深いものである。
しばしば医療と経済学とは正反対の極にあるように言われているが,希少な医療資源や人材を多様な医療需要にどのように配分すべきかという問題は,経済学の基本でもある。
本書では,経済学の基礎的な議論を解説した後で,保健医療,国民医療費,医療保険,医療に関わる規制改革等,幅広い内容について専門的な立場から経済学の理論を用いた解説がなされている。とくに医療技術評価に関する章は興味深かった。これは医療関係者にとって身近な問題を通じて経済学の考え方に触れられるとともに,医学以外の分野の者にとって,医療の制度的な問題についての理解を深めるというメリットが大きい。
他方で,経済学の立場から見ると,残念ながら表面的な議論に終わっている部分もある。まず,経済学の考え方に,「市場メカニズム」を信頼するものと,そうでなく政府の役割を重視するものとの2つがあるという説明は誤解を生みやすい。新古典派経済学の教科書には必ず「市場の失敗」についての章があり,情報の非対称性の大きな医療や教育分野には政府の介入が必要であることが明記されている。問題は政府の介入の仕方であり,情報が非対称だから直ちに医療機関の行動を規制すべきと考えるか,むしろ情報を公開し,第三者評価を受け入れる方向への医療機関のインセンティブを高めるような制度を設け,市場の失敗の補正に重点をおくかという方法論の違いである。また,医療の公共性からすべての疾病を公的保険の対象とすべきという考え方と,公的保険は,医療の専門家が決める基礎的(古典的)な医療範囲に限定し,それを越える部分は,適切な事後評価に基づき,自由診療との多様な組み合わせを容認するかという,政府介入のあり方についての違いである。
経済学の研究対象は「効率性」だけで「公平性」は対象外という説明も誤解である。医療における公平性とは何かという専門的な議論を前提に,それを保障する医療保障制度を,モラル・ハザードを防ぐなど,効率的に運用することは経済学の大きなテーマである。
さらに,営利主体の医療への参入規制の根拠として,「採算性の低い分野からの撤退」を防ぐという論理が紹介されているが,そもそも分野によって採算性が異なる公定価格が設定されていること自体が「政府の失敗」の現れである。また,医療における「公共性」とは,「利益追求を犠牲にして採算性の低い医療を行うこと」に尽きるのだろうか。それならば,現在は形骸化している医師の応召義務等に関わる具体的な基準を整備し,営利・非営利主体の区別なく平等に規制するほうが,より公共性を効率的に確保できるのではないだろうか。
経済学の基本は,抽象的な理論よりも,「事業者間の競争が利用者の利益を守る」ことにある。最近は,患者主体の医療という表現が用いられるが,「患者のためになる参入規制」とは,経済学にはない不思議な論理である。それはむしろ患者の自由な選択肢を妨げ,既存の「いわゆる非営利」の医療機関の利益擁護が目的ではないかという疑いを抱いてしまう。
本書は,医療という鏡をとおして経済学の考え方を理解してもらうためには絶好の教科書であり,医学部等の授業での積極的な活用が期待される。


奥村 雄介,野村 俊明 著
《評 者》松下 正明(東大名誉教授)
本書を読まずして語れない非行精神医学の必読書
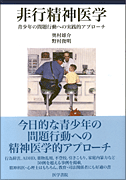 時代や社会の動きはわれわれが想像する以上に早く,旧来の常識がまったく通用しない社会状況がめまぐるしく出現している。特に,青少年の世界,とりわけ彼らの非行や犯罪の世界において目立つ。この書評を執筆している時期をとっても,母親をタリウムで殺害しようとした少女,殺人をしてみたかったからといって写真館主を殺害した高校生,交際相手の女子中学生を殺した高校1年生などマスコミを賑わす事件が相次いでいる。いまや,かつての常識では理解できない殺人が日常茶飯事化してきているのが青少年の世界である。
時代や社会の動きはわれわれが想像する以上に早く,旧来の常識がまったく通用しない社会状況がめまぐるしく出現している。特に,青少年の世界,とりわけ彼らの非行や犯罪の世界において目立つ。この書評を執筆している時期をとっても,母親をタリウムで殺害しようとした少女,殺人をしてみたかったからといって写真館主を殺害した高校生,交際相手の女子中学生を殺した高校1年生などマスコミを賑わす事件が相次いでいる。いまや,かつての常識では理解できない殺人が日常茶飯事化してきているのが青少年の世界である。
そのような,事例そのものがかつての常識では捉えることができない状況になっている現代,その背景にある問題を従来の精神医学の考え方で理解することが一体可能なのかというのが評者の疑問とするところであった。非行や犯罪を行った青少年のための独自の新しい精神医学が樹立される必要があるのではないかとかねがね考えていたのだが,このたび,まさに評者が願っているような非行や犯罪に走る青少年を対象とした精神医学書が刊行された。それが本書『非行精神医学』である。
本書は3部構成からなる。第1部は,「青少年の問題行動と精神医学」として,少年非行や行為障害の理論的分析がなされるが,それと同時に本書全体の理論編ともなっている。第1部はさらに,反社会的行動と非社会的行動・自己破壊的行動の2章に分けられ,前者では,DSM―IIIによって初めて採用された行為障害と少年法による行動分類について,その定義や診断基準,分類などが詳しく説明される。さらに,後者では,不登校,ひきこもり,家庭内暴力,自己破壊的行動についての分析がなされる。
第2部では,現今の精神医学における疾患概念と少年非行との関連が逐一説明される。しかし,従来の精神医学教科書にみるようなステレオタイプの記述ではなく,あくまでも青少年の非行と犯罪との関連で記されている。その内容は,まず心因性精神障害(パーソナリティ障害,衝動制御障害,神経症性障害と適応障害,摂食障害,児童虐待とPTSD,拘禁反応)にもっとも多くの頁数が割り振られ,続いて,内因性精神障害(統合失調症,気分障害),薬物乱用と薬物起因性精神障害,器質性精神障害・症状性精神障害,発達障害と行動障害という順序で構成される。
第3部は,治療と矯正教育の項で,そこでは,まず保護観察制度についての説明がなされ,次いで,触法事例の施設治療,社会での治療・教育の基本,家族への対応について,具体的な方法が語られる。
このような3部からなる本書の構成をみても本書がいかにユニークかつ新しいものであるかがわかるであろう。
本書の最大の特徴は,豊富な事例をもとに非行精神医学が述べられていることにある。事例の総数は54,1例を除きすべて10代の少年,少女の事例であり,それらの事例を通して非行精神医学の実態を明らかにするという著者らの強い姿勢が窺われる。著者らは長年にわたって,関東医療少年院,八王子医療刑務所,八王子少年鑑別所,東京拘置所に勤務し,そこでの経験が本書に集約されており,事例もすべて著者らの自験例であることが,本書の主張を一層説得力あるものとしている。
本書は,200頁足らずの小冊子であるが,事例を中心にして青少年の非行や犯罪と精神医学との関連を包括的に記述し,さらに,「非行精神医学」という現代的な独自の分野を日本で最初に提唱したことをもって,きわめて画期的な著書であるといっていいだろう。
おそらく,今後この分野に携わる医師,看護師,臨床心理士,ケースワーカー,あるいは,学校,警察,裁判所,矯正施設,福祉施設などの関係者たちは,本書を読まずして非行精神医学は語れないのではあるまいか。


カラー図解 臨床でつかえる神経学
大石 実 訳
《評 者》棚橋 紀夫(埼玉医大教授・神経内科学)
神経学のすべてをカラーでわかりやすく解説
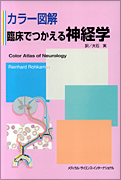 本書はReinhard RohkammによるColor Atlas of Neurologyの訳本である。訳者の大石実先生は,私の慶應義塾大学医学部時代の同級生である。学生時代から医学のみでなく語学に堪能で,英語のみならず,ドイツ語,フランス語などを完全マスターしたmultilingualで,卒業後多くの原著論文を英語,ドイツ語,フランス語で発表している。医学のみでなく語学の天才でもある。神経内科医としても多年にわたる臨床経験,研究歴を有し米国神経内科専門医でもあり,超一流の神経内科医である。英語の神経学教科書Handbook of Neurologyという著書もある。『カラー図解 臨床でつかえる神経学』は,まさに大石先生ならではの訳本である。神経学を学ぶものにとって,解剖,機能解剖,神経症候は最も重要であるが,難解でもある。本書は神経学のすべてをカラーでわかりやすく解説している。特にFrank H. Netter博士の図も引用されており視覚的な面から理解を深めるよう工夫されている。見開きで右のページはカラーの図であり,まさに「カラーアトラス」である。しかし,左ページには簡潔に図の説明があり読みやすい構成となっている。第1章は基礎の解剖,生理で神経学を学ぶものに必須の項目が取り上げられている。第2章の機能と症候は,臨床でしばしば遭遇する課題を取り上げている。わかりやすい図で知らず知らずのうちに難解な神経経路,機能,主要症候,病態生理を学ぶことができる。第3章の疾患も,画像(CT,MRIなど)に加え,図により疾患のエッセンスを簡潔に記載しかつ治療にまで言及している。大石先生ならではの名訳本であり,学生のみでなく,研修医,指導医にいたるまで役立つ内容となっている。また,第5章は,訳者独自の考えで,解剖,症候群,診断基準,鑑別診断,ガイドラインなど,日本の臨床医に必要な表を網羅している。本訳本は,神経疾患を診察する医師が常に身近な場所において閲覧したい最良の書といえる。
本書はReinhard RohkammによるColor Atlas of Neurologyの訳本である。訳者の大石実先生は,私の慶應義塾大学医学部時代の同級生である。学生時代から医学のみでなく語学に堪能で,英語のみならず,ドイツ語,フランス語などを完全マスターしたmultilingualで,卒業後多くの原著論文を英語,ドイツ語,フランス語で発表している。医学のみでなく語学の天才でもある。神経内科医としても多年にわたる臨床経験,研究歴を有し米国神経内科専門医でもあり,超一流の神経内科医である。英語の神経学教科書Handbook of Neurologyという著書もある。『カラー図解 臨床でつかえる神経学』は,まさに大石先生ならではの訳本である。神経学を学ぶものにとって,解剖,機能解剖,神経症候は最も重要であるが,難解でもある。本書は神経学のすべてをカラーでわかりやすく解説している。特にFrank H. Netter博士の図も引用されており視覚的な面から理解を深めるよう工夫されている。見開きで右のページはカラーの図であり,まさに「カラーアトラス」である。しかし,左ページには簡潔に図の説明があり読みやすい構成となっている。第1章は基礎の解剖,生理で神経学を学ぶものに必須の項目が取り上げられている。第2章の機能と症候は,臨床でしばしば遭遇する課題を取り上げている。わかりやすい図で知らず知らずのうちに難解な神経経路,機能,主要症候,病態生理を学ぶことができる。第3章の疾患も,画像(CT,MRIなど)に加え,図により疾患のエッセンスを簡潔に記載しかつ治療にまで言及している。大石先生ならではの名訳本であり,学生のみでなく,研修医,指導医にいたるまで役立つ内容となっている。また,第5章は,訳者独自の考えで,解剖,症候群,診断基準,鑑別診断,ガイドラインなど,日本の臨床医に必要な表を網羅している。本訳本は,神経疾患を診察する医師が常に身近な場所において閲覧したい最良の書といえる。
A5変・頁440 定価7,980円(税5%込)MEDSi
http://www.medsi.co.jp/
