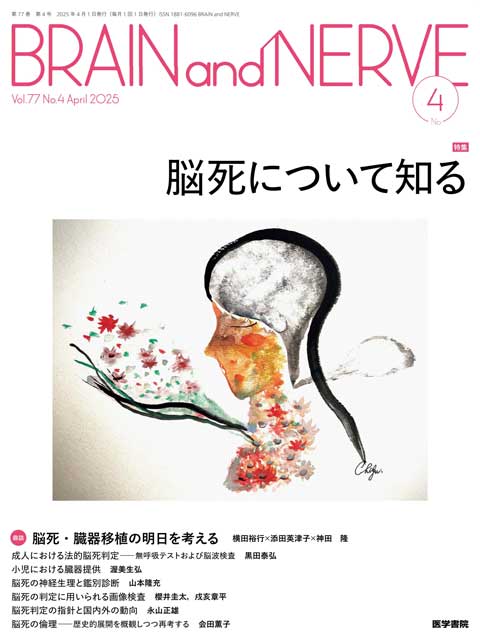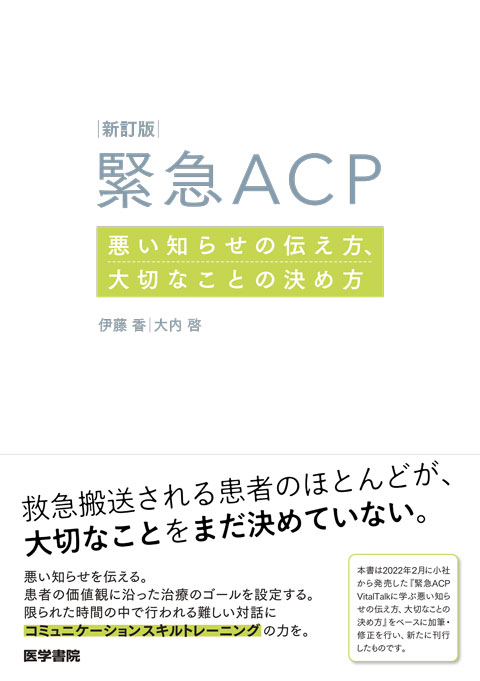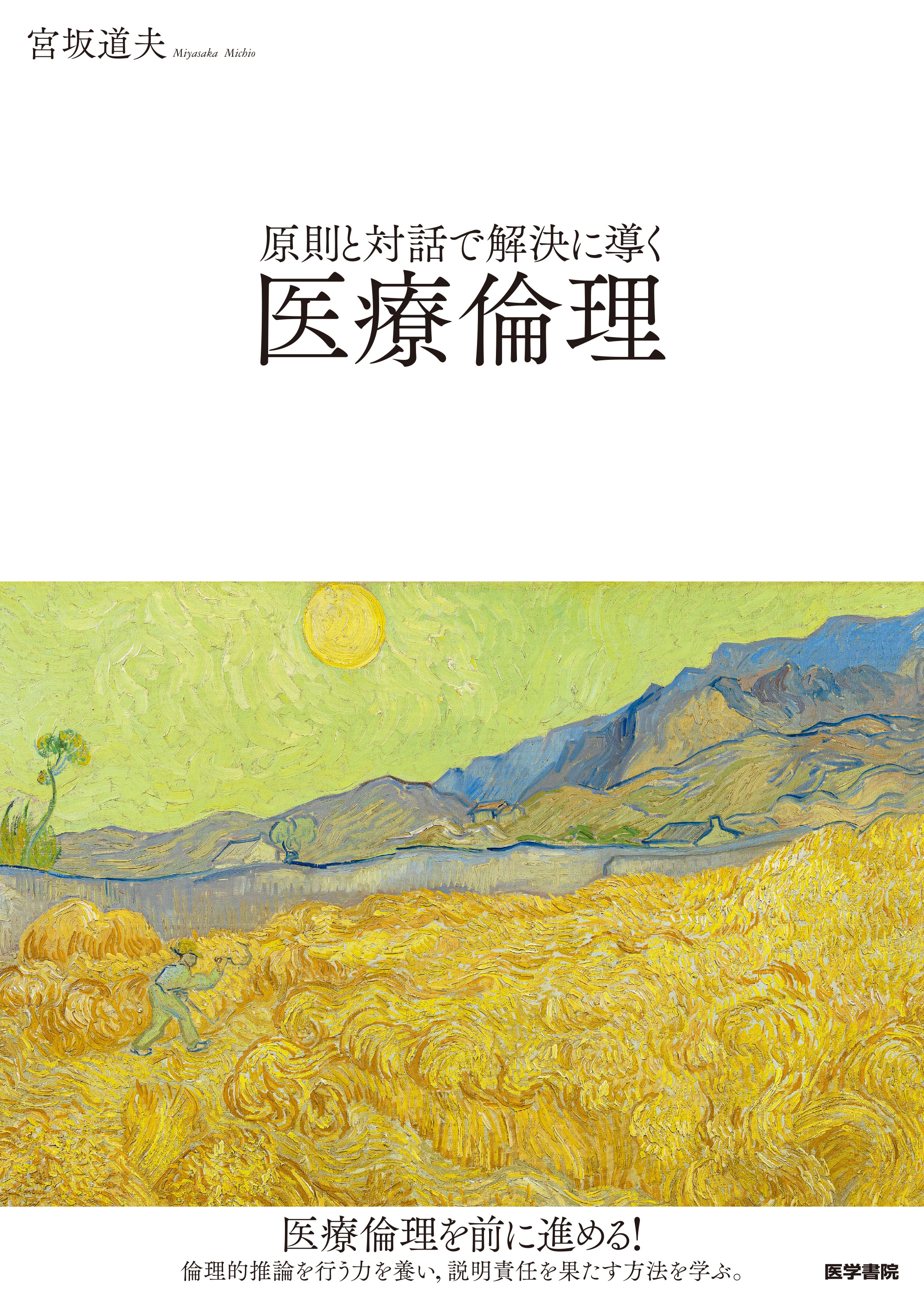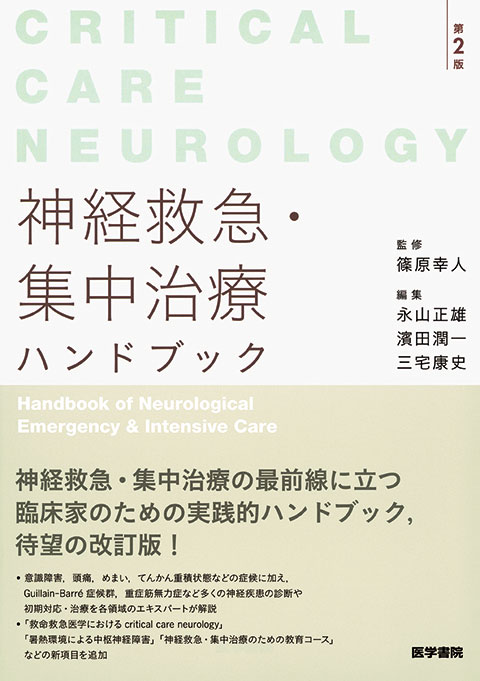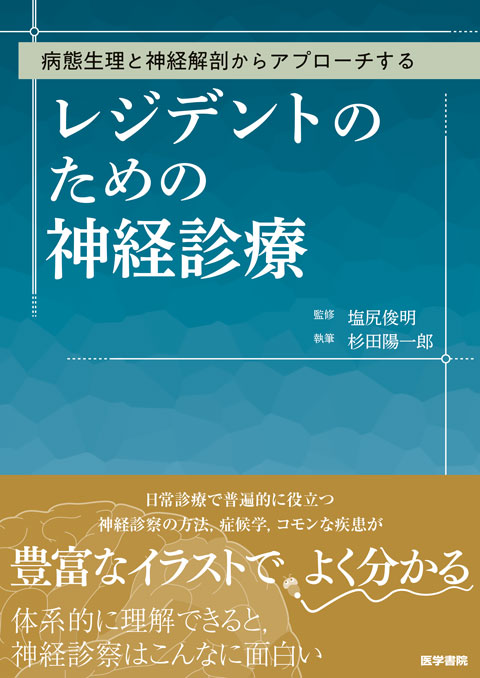- HOME
- 雑誌
- BRAIN and NERVE
- BRAIN and NERVE Vol.77 No.4
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 特集の意図
- 収録内容
特集の意図
開く
本特集は,脳死を神経学というサイエンスの視点から考える意図で企画された。ただし,日本では脳死と臓器移植の問題を切り離すことは難しく,科学的視点と移植医療の視点の双方が重要である。鼎談では本邦での脳死および臓器移植の現状について議論を交わした。各論では法的脳死判定の実際,脳死の神経生理や画像検査,諸外国と比較した日本の現状,そして倫理の問題などを取り上げている。2020年に脳死判定の国際コンセンサスが発表され,標準化に向けた流れが進む一方で,本邦の厳格な基準とは異なる面もみられる。脳死医療に関する知識を整理するとともに,今後の展望,そして医療スタッフの関与のあり方について考えたい。
【鼎談】脳死・臓器移植の明日を考える 横田 裕行 , 添田 英津子 , 神田 隆
本特集では,神経学的なサイエンスの視点から脳死を考えること,そして脳神経内科医のさらなる関与を期待して,脳死に関する知識を広く共有し,この問題への理解を深めてもらうことをねらいとしている。ただし,日本では,臓器移植の問題と切り離して脳死の議論を進めることはとても難しく,脳死を科学的な観点から捉える側面と,移植医療との関連から捉える側面の両方が重要であると私たちは考える。本鼎談では,救急医として脳死の臨床に長く携わり,現在は日本臓器移植ネットワーク理事長を務める横田裕行氏と,同じく日本臓器移植ネットワーク理事であり,レシピエント移植コーディネーター・看護師(教員)の添田英津子氏,そして本誌編集主幹の神田隆氏を交えて,主に移植医療の立場から脳死を議論した。
成人における法的脳死判定—無呼吸テストおよび脳波検査 黒田 泰弘
2020年のBD/DNC(brain death/death by neurologic criteria)は脳死の世界初のコンセンサスで,深昏睡,脳幹反射の消失,自発呼吸消失で定義される脳機能の完全かつ永続的な喪失状態である。無呼吸テストではベースライン時の低血圧,A-aDO2開大,低酸素血症,アシデミア,年齢はリスク因子であり,呼気終末陽圧(PEEP)下で施行することが勧められる。日本では脳死とされうる状態においても脳波をとることが義務づけられている。法的脳死判定における無呼吸テスト(成人)および脳波検査は1回とすることは妥当であり,今後省令改正を要望する。
小児における臓器提供 渥美 生弘
本邦における小児の臓器提供は2009年の臓器移植法改正で年齢制限が撤廃されたことにより始まった。虐待の可能性を除外する手順の明確化,小児急性期医療の整備,医療者間での臓器提供の認知拡大による家族との話し合いの促進により,近年小児の臓器提供数が増えている。臓器移植は費用対効果の観点からも重要である。臓器提供は家族と医療スタッフとが協働し,最良の看取りを行う際の選択肢だと捉えている。
脳死の神経生理と鑑別診断 山本 隆充
脳幹を含む脳全体の機能が廃絶した状態とされる脳死状態では,自発呼吸が消失して人工呼吸管理となり,脳幹反射の消失や瞳孔の散大固定などが認められる。一方,脳幹を含む脳機能がある程度残存して,昏睡状態を脱却しても意思の疎通性がまったく認められない状態を植物状態と呼び,持続的ではないがなんらかの意思の疎通性が認められる状態を最小意識状態と呼んでいる。本論では,電気生理学的な残存脳機能の評価についても解説する。
脳死の判定に用いられる画像検査 櫻井 圭太 , 戌亥 章平
従来,本邦では深昏睡,瞳孔の散大・固定,脳幹反射の消失,平坦脳波,自発呼吸の消失をもって脳死の判定をすることが基本であった。しかしながら,2020年に発表された国際コンセンサスでは本邦では必須の脳波検査をルーチンで用いず,脳死の偽陽性判定を否定するために種々の画像検査を含めた補助検査による脳血流評価を提案している。本論では脳死の判定を行う際に用いられる画像検査に関して解説する。
脳死判定の指針と国内外の動向 永山 正雄
わが国では脳死判定は「臓器の移植に関する法律」(臓器移植法)に基づいており,臓器移植を前提とするときに適用され「法的脳死判定」と呼ぶ。法的脳死判定の方法は,いわゆる竹内基準に基づいて作成された法的脳死判定マニュアルに従って行われる。一方,国際的には2020年8月,脳死判定の標準化の必要性が指摘され,2023年10月に米国神経学会,米国小児科学会,小児神経学会合同による米国の脳死(BD/DNC)判定ガイドライン改訂版が公表されている。本論では,わが国の脳死判定に関する指針,国内外の最新動向を紹介する。
脳死の倫理—歴史的展開を概観しつつ再考する 会田 薫子
1968年に米国のハーバード・メディカルスクール特別委員会が脳死を死とすると報告してから半世紀余が経過した。この間,脳神経学と集中治療技術の進展によって,脳死の概念の科学的な不完全性と定義の不適切さが明らかになった。しかし,脳死の診断は看取り医療の必要性を示す指標として臨床的に意義がある。看取り医療においては,臓器提供の選択を含め本人の意思を尊重するとともに,家族ケアを家族の視点で提供することが求められる。その際,西洋諸国と日本の精神の基層の相違を認識することも重要である。
収録内容
開く
医書.jpにて、収録内容の記事単位で購入することも可能です。
価格については医書.jpをご覧ください。
特集 脳死について知る
【鼎談】脳死・臓器移植の明日を考える
横田裕行×添田英津子×神田 隆
成人における法的脳死判定──無呼吸テストおよび脳波検査
黒田泰弘
小児における臓器提供
渥美生弘
脳死の神経生理と鑑別診断
山本隆充
脳死の判定に用いられる画像検査
櫻井圭太,戌亥章平
脳死判定の指針と国内外の動向
永山正雄
脳死の倫理──歴史的展開を概観しつつ再考する
会田薫子
■総説
経頭蓋静磁場刺激(tSMS)による神経調節のメカニズム
──ホールセルパッチクランプ法を用いた大脳皮質錐体細胞の解析
芝田純也,他
黒質ドーパミン神経細胞投射解析の試み
藤山文乃,苅部冬紀
老化におけるエピゲノム記憶による長期的身体機能の制御
早野元詞
●日本人が貢献した認知症研究の足跡
第1回 認知症モデルマウスの開発と応用
盛戸貴裕,他
●原著・過去の論文から学ぶ
第12回 分離脳
酒井邦嘉