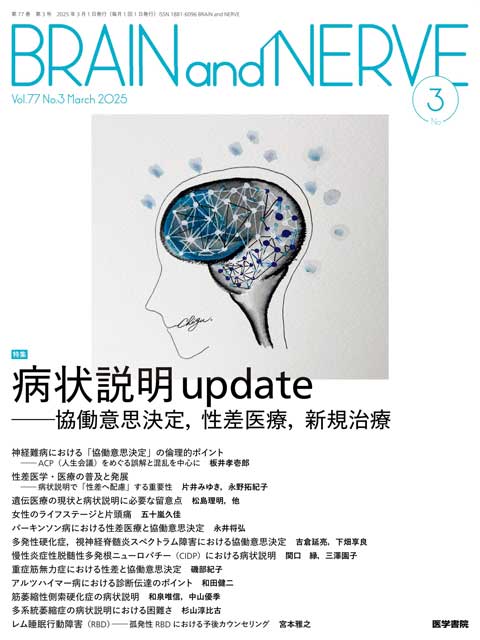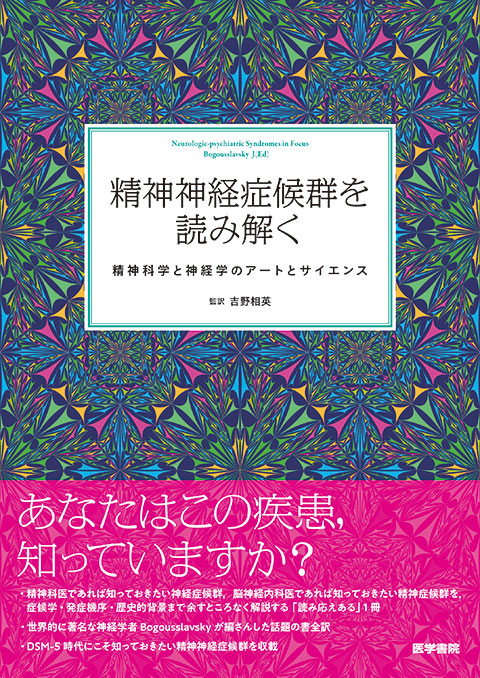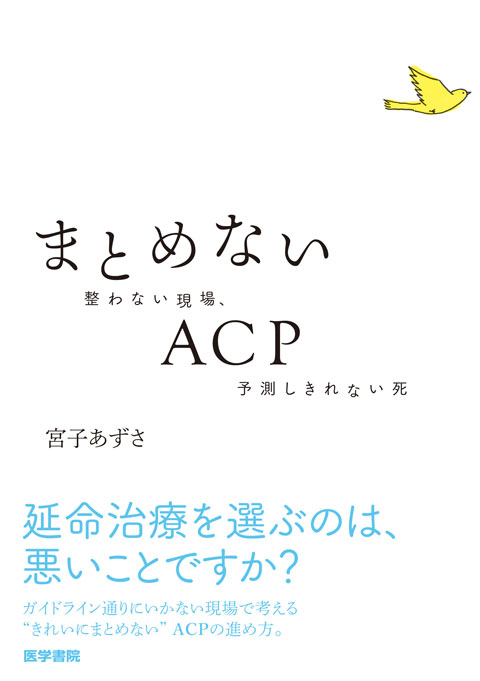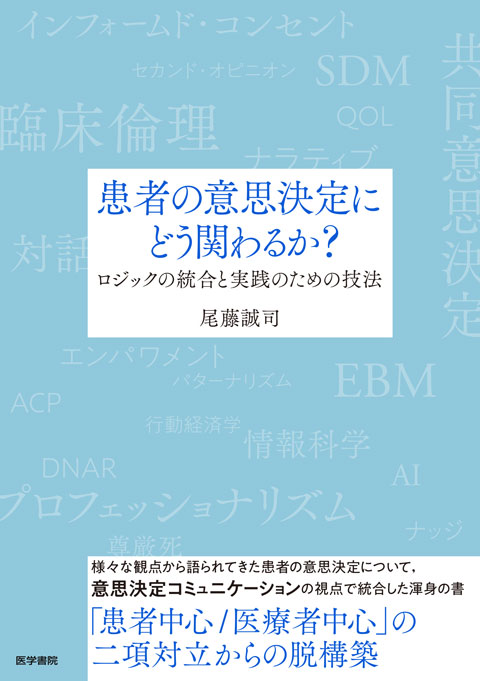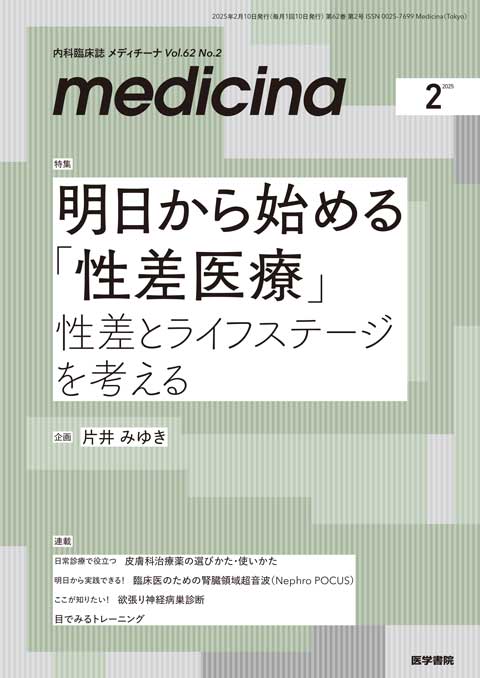- HOME
- 雑誌
- BRAIN and NERVE
- BRAIN and NERVE Vol.77 No.3
特集 病状説明 update 協働意思決定,性差医療,新規治療
| ISSN | 1881-6096 |
|---|---|
| 定価 | 3,080円 (本体2,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 特集の意図
- 収録内容
特集の意図
開く
近年,神経疾患の患者・家族への病状説明が複雑化し,難しい対応を迫られる場面が増えている。この背景には,協働意思決定の重要性が増していることや,性差に基づく個別化医療の進展,さらに疾患修飾薬,遺伝子治療,PGT-M(着床前遺伝学的検査)といった新規治療の導入があると考えられる。こうした変化に伴い,病状説明には新たな臨床倫理的課題も生じている。本特集では,協働意思決定,性差医療,新規治療に関わる新しい臨床倫理を踏まえた病状説明のあり方について考察する。各疾患のどのような点に留意して病状説明を行うべきかを解説するとともに,実践に役立つヒントや具体例を提示する。患者・家族とよりよい関係を構築し,適切な医療提供につなげるための一助となることを願っている。
神経難病における「協働意思決定」の倫理的ポイント—ACP(人生会議)をめぐる誤解と混乱を中心に 板井 孝壱郎
協働意思決定において医療者の果たすべき役割は,ガイドランナーのようなものである。選手よりも速すぎると失格にしてしまう。遅すぎると迷惑以外の何物でもない。コースアウトしそうになれば,しっかりと導きながらも,あくまでも選手が主人公であるのと同じく,医師をはじめ医療者は,患者が「コースアウト」しないように導きながらも,あくまでも主人公である患者自身が,自らの足で歩んでいけるように支えることが重要である。
性差医学・医療の普及と発展—病状説明で「性差へ配慮」する重要性 片井 みゆき , 永野 拓紀子
性差医学は,生物学的性差・社会的文化的性差およびライフステージ(LS)が心身に及ぼす影響を明らかにする。脳神経疾患でも性差とLSに配慮した診療が求められる。性差医療により,前医で不定愁訴とされた女性患者の27%に器質的疾患が診断された。女性は月経や更年期症状によって他の疾患が隠れ,見逃されやすい。医療者が「性差とLSの視点・知識」を持つことで,診断の精度,病状説明,疾患予防や治療の質的向上が期待される。
遺伝医療の現状と病状説明に必要な留意点 松島 理明 , 柴田 有花 , 矢部 一郎
遺伝医療の進歩に伴って,さまざまな疾患で遺伝に関連した説明が求められる場合がある。遺伝情報の特性に配慮した対応が必要となるが,その際に遺伝カウンセリングの手法は参考になる。また,近年は遺伝性神経・筋疾患においても病態修飾療法が登場したり,網羅的遺伝子解析が実施されたりする場面があり,説明のあり方が変化しつつある。さらに,成人発症の神経・筋疾患に対しても着床前遺伝学的検査が慎重な審査の結果として適応ありと判断され得る状況となった。
女性のライフステージと片頭痛 五十嵐 久佳
片頭痛は生活への支障が大きい疾患であり,特に20〜40代の女性での有病率が高い。片頭痛の病態には女性ホルモンの変動が関与していると考えられており,女性のライフステージによってさまざまな影響を受ける。重症度の高い月経時片頭痛の治療,子宮内膜症を合併した場合の治療法,妊娠・授乳中の薬剤選択など,常に患者の優先事項を確認し,患者とともに治療を選択・支援することが重要である。
パーキンソン病における性差医療と協働意思決定 永井 将弘
パーキンソン病において性差が症状やパーキンソン病治療薬の薬物動態や副作用に影響を及ぼすことが報告されているが,日常診療ではこれらの点はあまり考慮されていない。また,高齢者の割合が高いため,妊娠時における薬物治療に関する情報は十分とは言えない。進行期パーキンソン病の運動合併症に対してデバイス補助療法が行われているが,侵襲性が高い治療なので導入には協働意思決定がより大切となってくる。
多発性硬化症,視神経脊髄炎スペクトラム障害における協働意思決定 吉倉 延亮 , 下畑 享良
多発性硬化症や視神経脊髄炎スペクトラム障害では,ここ数年で有効性の高い新規薬剤が複数登場し,患者の予後の改善が認められる。その一方で,診療が複雑化しており,医療者は患者に病状や治療薬を説明するだけではなく,患者の好みや価値観も重視して,協働意思決定(shared decision-making:SDM)を行う必要がある。SDMが患者の転帰に関わるかどうかについては今後の検証が必要である。
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)における病状説明 関口 縁 , 三澤 園子
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)は複数の病態を内包しており,症状や経過も多様である。一方で免疫グロブリン静注療法や皮下注療法などの維持療法が導入され,継続した通院加療が必要である。個々の患者に最適な治療を提供するためには,丁寧に病状説明を行い,患者との協働意思決定を行う必要がある。日常診療における説明のポイントを以下に記載する。
重症筋無力症における性差と協働意思決定 磯部 紀子
重症筋無力症は,神経筋接合部における代表的な自己免疫性疾患である。男女比は同等から女性にわずかに多くみられる。これまでの研究において,女性患者のほうが治療抵抗性で,治療介入後の生活の質が改善されにくいことが指摘されている。昨今,さまざまな新規治療薬が使用可能となり,治療方針について協働意思決定を行う場面が増えている。性差も踏まえた病状説明を行い,各患者にとって最善の治療を選択する必要がある。
アルツハイマー病における診断伝達のポイント 和田 健二
アミロイドPETや脳脊髄液バイオマーカーの導入,抗アミロイドβ抗体薬の登場は,認知症診療に大きな変革をもたらしている。また,血漿バイオマーカーなどの新技術の開発も進展している。こうした状況において,日常診療では,最新かつ適切な情報を正確に伝えることがますます求められる。本論では,アルツハイマー病における最新の診断基準,診断技術の進展,抗アミロイドβ抗体治療について概説し,診断の伝達における重要なポイントを論じる。
筋萎縮性側索硬化症の病状説明 和泉 唯信 , 中山 優季
筋萎縮性側索硬化症(ALS)の説明の場には患者の同意を得て家族,介護者,多職種の同席を促す。病状,患者の性格,家庭環境などによって,患者の受け止め方は相当に異なるので説明の内容も工夫する必要がある。十分な理解や納得が得られていない場合には,繰り返し説明を行う。対象者の理解や受容の状態によっては,段階的に説明を行うことも考慮する。治療方針を決定しても,あらためてその方針を変更してもよいと伝える。多職種が参加した説明では,それぞれの職種が説明するのはもちろんであるが,チームリーダーが患者の受け止めを把握しておくことが大切である。
多系統萎縮症の病状説明における困難さ 杉山 淳比古
多系統萎縮症(multiple system atrophy:MSA)は,進行性の神経変性疾患であり,突然死のリスクを有することや,運動症状以外に自律神経障害や高次脳機能障害による症状など多彩な症状を呈し得るという特徴がある。MSAの告知に関する大規模な調査研究は乏しく,MSA告知指針の基盤となるようなエビデンスが求められている。われわれの行った医師対象の大規模オンライン質問紙調査研究の結果を含め,MSAの病状説明における困難さについて概説する。
収録内容
開く
医書.jpにて、収録内容の記事単位で購入することも可能です。
価格については医書.jpをご覧ください。
特集 病状説明 update──協働意思決定,性差医療,新規治療
神経難病における「協働意思決定」の倫理的ポイント──ACP(人生会議)をめぐる誤解と混乱を中心に
板井孝壱郎
性差医学・医療の普及と発展──病状説明で「性差へ配慮」する重要性
片井みゆき,永野拓紀子
遺伝医療の現状と病状説明に必要な留意点
松島理明,他
女性のライフステージと片頭痛
五十嵐久佳
パーキンソン病における性差医療と協働意思決定
永井将弘
多発性硬化症,視神経脊髄炎スペクトラム障害における協働意思決定
吉倉延亮,下畑享良
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)における病状説明
関口 縁,三澤園子
重症筋無力症における性差と協働意思決定
磯部紀子
アルツハイマー病における診断伝達のポイント
和田健二
筋萎縮性側索硬化症の病状説明
和泉唯信,中山優季
多系統萎縮症の病状説明における困難さ
杉山淳比古
レム睡眠行動障害(RBD)──孤発性RBDにおける予後カウンセリング
宮本雅之
■総説
アレキサンダー病(一次性アストロサイト病)の進行抑制に関与する新たな細胞の発見──ミクログリアの病態監視保護のメカニズム
齋藤光象,小泉修一