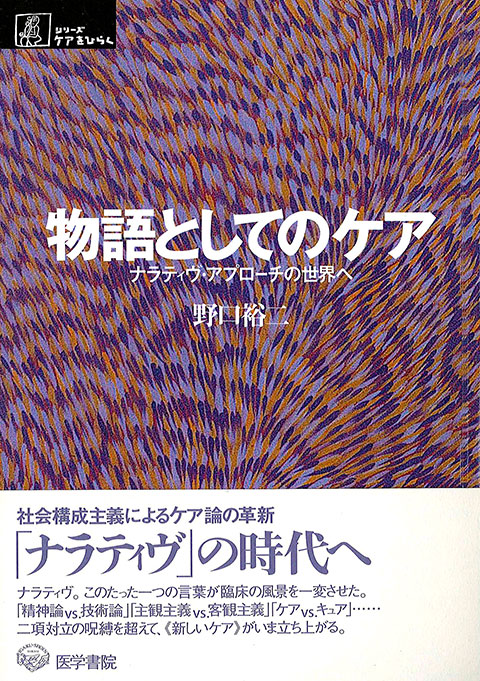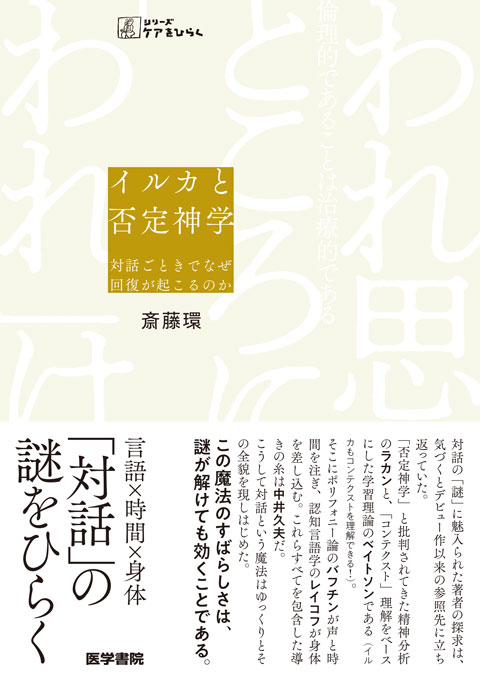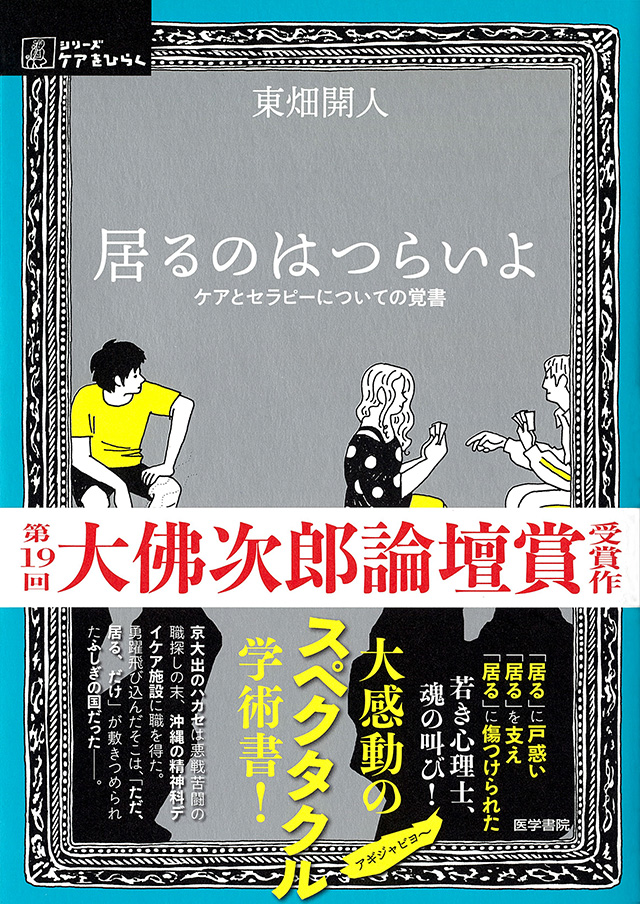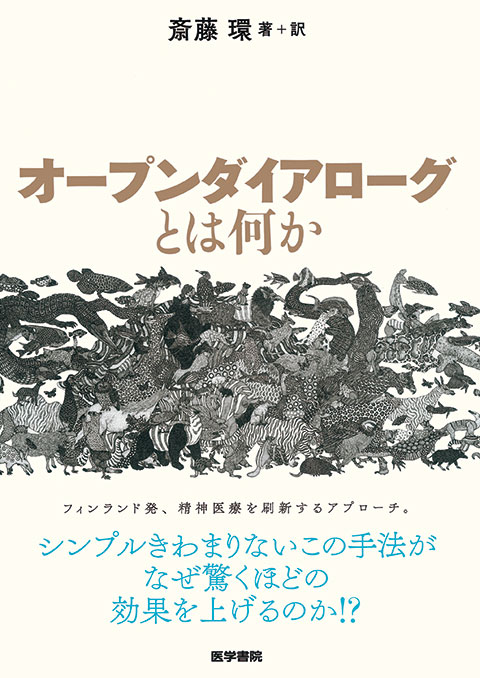物語としてのケア
ナラティヴ・アプローチの世界へ
「ナラティヴ」の時代へ
もっと見る
「語り」や「物語」を意味する<ナラティヴ>。人文諸科学で衝撃を与えつづけているこの言葉は,ついに臨床の風景さえ一変させた。臨床の物語論的転回はどこまで行くのか。「精神論vs.技術論」「主観主義vs.客観主義」「ケアvs.キュア」という二項対立の呪縛を超え,新しいケアがいま立ち上がる。
| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |
|---|---|
| 著 | 野口 裕二 |
| 発行 | 2002年06月判型:A5頁:220 |
| ISBN | 978-4-260-33209-5 |
| 定価 | 2,420円 (本体2,200円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- TOPICS
- 目次
- 書評
TOPICS
開く
●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!
第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。
目次
開く
第1章 言葉・物語・ケア
第2章 物語としての自己
第3章 物語としての病い
II
第4章 外在化とオルタナティブ・ストーリー
第5章 「無知」のアプローチ
第6章 リフレクティング・チーム
III
第7章 三つの方法
第8章 新しい専門性
第9章 ナラティヴ・コミュニティ
IV
第10章 物語としてのケア
書評
開く
自分の拠って立つところを根底からくつがえされる
書評者:中木 高夫(日赤看護大教授)
ナラティヴ・アプローチはおもしろい。いままでの自分の拠って立つところを根底からくつがえされた気分なのだが,それでもなお爽快な後味を残すからだ。これはいったい何なのか?
衝撃的な3つの実践例
ナラティヴ・アプローチを説明するために,本書の中で3つのナラティヴ・セラピーの実践例が紹介されてている。
まず,ホワイトとエプストンの《外在化とオルタナティブ・ストーリー》。問題状況があるとしよう。その原因が自分の中にある(内在化)と考えると,いままでの自分を否定し,自分を変えなければならず,苦しい。原因を外に求める(外在化)と,自分は苦しまなくてもよいが,なんでも他人のせいにすると見られてしまう。そこで,ホワイトたちは〈問題そのもの〉を外在化し,問題の存続に立ち向かったり,問題を無視したり,問題に振り回されないというような,いままでと違った〈ユニークな結果〉を体験するということに着目した。
専門家は,「問題の原因はこれだから,こういうふうにしなければならない」というような専門的知識に裏づけられた〈ドミナント・ストーリー〉を押しつけるが,そうではなく,クライアントがユニークな結果にもとづいて〈オルタナティブ・ストーリー〉を誕生させるのを見守ることが要求されることになる。
2つ目は,グーリシャンとアンダーソンの《「無知」のアプローチ》。専門家というものはクライエントの生きる世界について〈無知not-knowing〉なのだということを自覚するところから始めようというのだ。となると,従来の専門家観にもとづく実践は,専門的知識を駆使して〈クライエントの生きる世界〉を専門家の世界に翻訳することに過ぎないということになる。
3つ目が,アンデルセンの《リフレクティング・チーム》。家族療法ではワンウェイ・ミラーを用いた専門家による観察が定番といってよいほど普及しているが,この〈観察する側〉と〈観察される側〉という構造を逆転させ,専門家をクライアントに観察させるという構造もセラピーの中に組み込もうというのだ。病棟のナース・ステーションの中での会話が,患者さんに筒抜けになるというような状況を考えれば容易に想像がつくだろう。
自分の説明モデルを,限界を含めて理解する
言葉がわれわれの生きる社会をかたちづくるという《社会構成主義》に基礎を置くナラティヴ・セラピーについては,「聴くこと・語ること」というテーマで医学界新聞の座談会(第2391号,6月12日発行,医学書院のホームページで読むことが可能)を行なった時に,本書の著者である野口裕二さんから教わった。
その著者が,専門性に対する従来の考え方を根底からくつがえすアプローチを提案していることは,上述の3つの実践例からも明らかである。
かといって,従来の専門家の仕事を完全に否定されたとも思えない。専門家が専門知識を持たないということは考えられないし,それにもとづいて実践を行なうこともとがめられる筋合いのものではない。問題はアプローチである。
最終的には,クラインマンの《説明モデル》を紹介しているところで著者が述べているように,おたがいの説明モデルの妥協点を探すのではなく,相手の説明モデルに最大の敬意を払い,相手の説明モデルをより深く理解するのと同時に,自分の説明モデルを(その限界をも含めて)より深く理解することから,たがいの了解を生成させることが必要なのであろう。そのためのナラティヴ・アプローチである。
了解不能な「専門性」を打破する試み
看護過程・POS・看護診断の普及に精力を注いできた身としては,専門用語は問題の外在化のよい武器となると思う。また,患者さんのことをもっと深く知りたいという無知のアプローチは,患者さんの生きる世界を共有するための姿勢として,看護過程を実践するうえではなくてはならないものだ。診療情報提供のおどろくほど簡単な実践である《バラマキ型診療記録開示》は,リフレクティング・チームの診療記録版である。名古屋のみなと生協協立総合病院では,1日2-3時間,診療記録を患者さんのベッドの上に配布して,患者さんに自由に閲覧してもらっている。この病院ではまさに専門家の語りを患者さんに受けとめてもらっているのである。
なぜ,爽快なのかわかった。いままで専門性だと信じて閉じこもっていたぼくたちの殻を,このアプローチがいとも簡単に打ち砕いてくれたからだ。