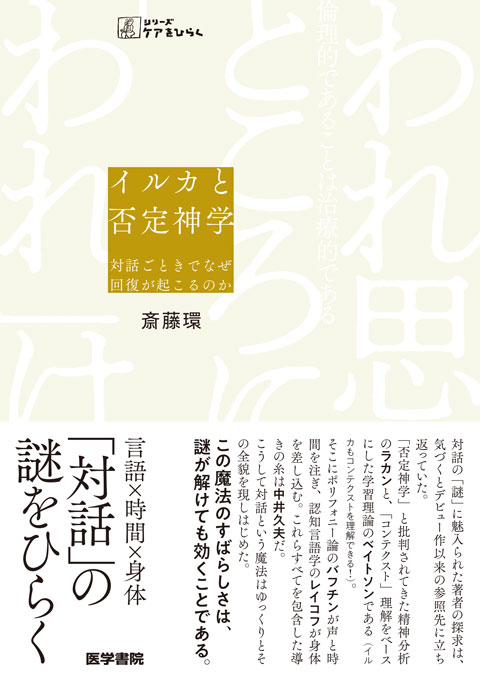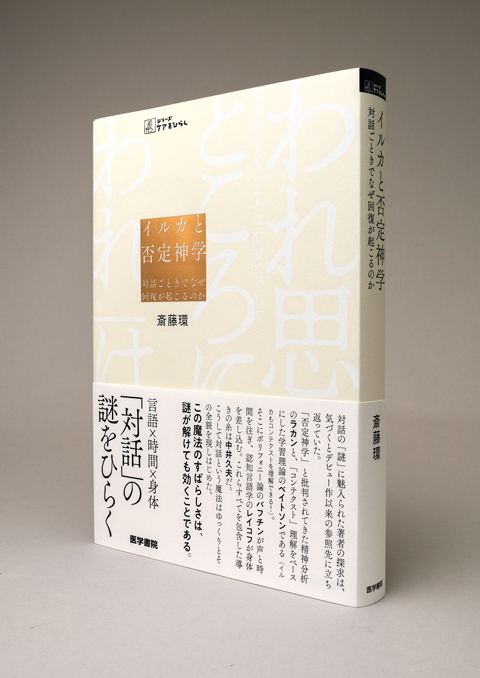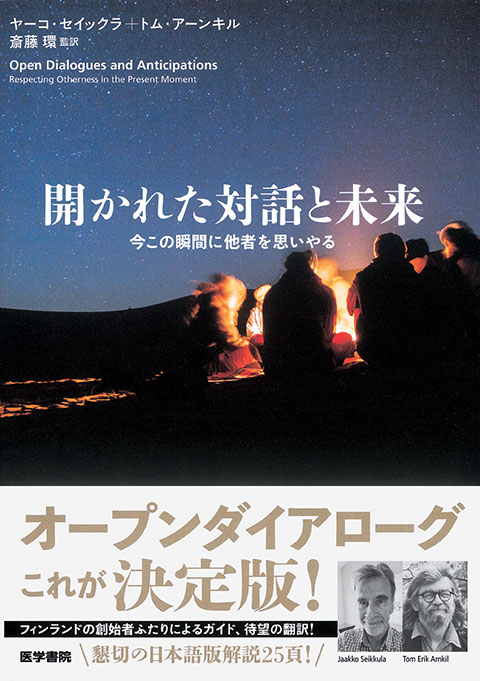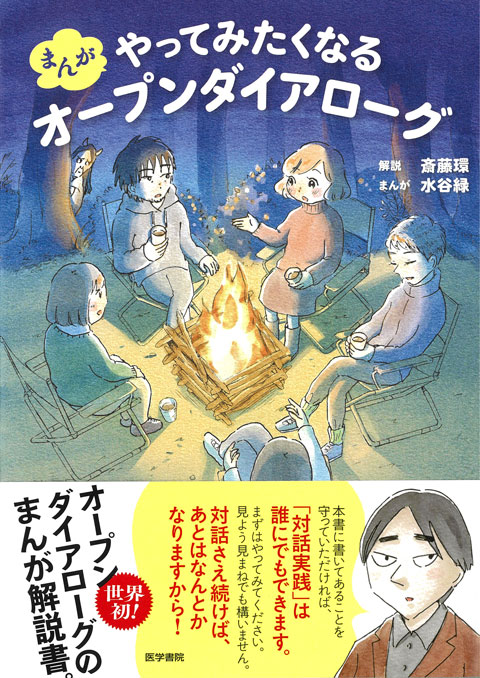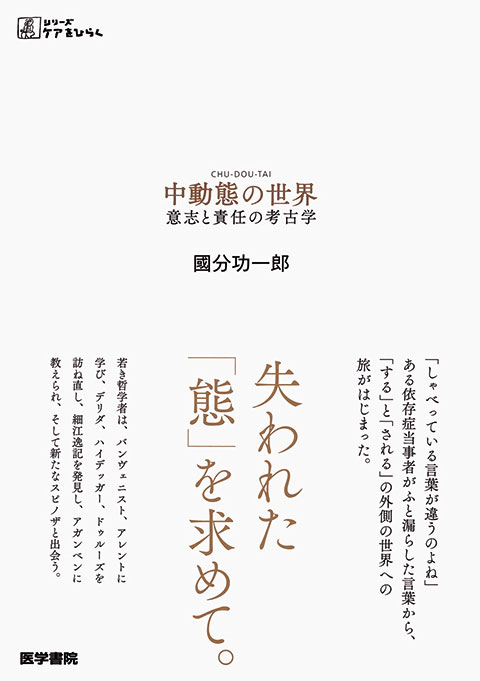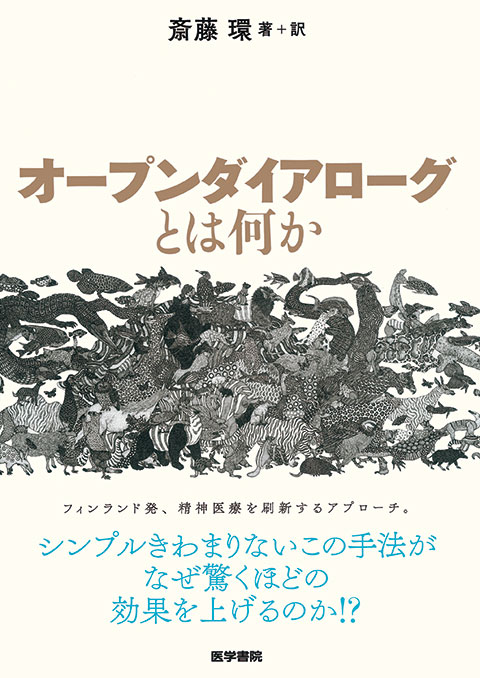イルカと否定神学
対話ごときでなぜ回復が起こるのか
「ゼロ」からはじめるオープンダイアローグ!
もっと見る
――なぜ対話するだけで、これほどの変化が生ずるのだろう。
――なぜこんな「ふつうのこと」で、回復が起きてしまうのだろう。
ラカン、ベイトソン、バフチン、レイコフ、中井久夫……著者の全キャリアを支えてきた思想を総動員して、この哲学的疑問に真正面から答えた渾身の一冊。
こうして対話という魔法はゆっくりとその全貌を現しはじめた。この魔法のすばらしさは、謎が解けても効くことである。
| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |
|---|---|
| 著 | 斎藤 環 |
| 発行 | 2024年10月判型:A5頁:288 |
| ISBN | 978-4-260-05735-6 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 本書の特長
- 序文
- 目次
- 書評
本書の特長
開く
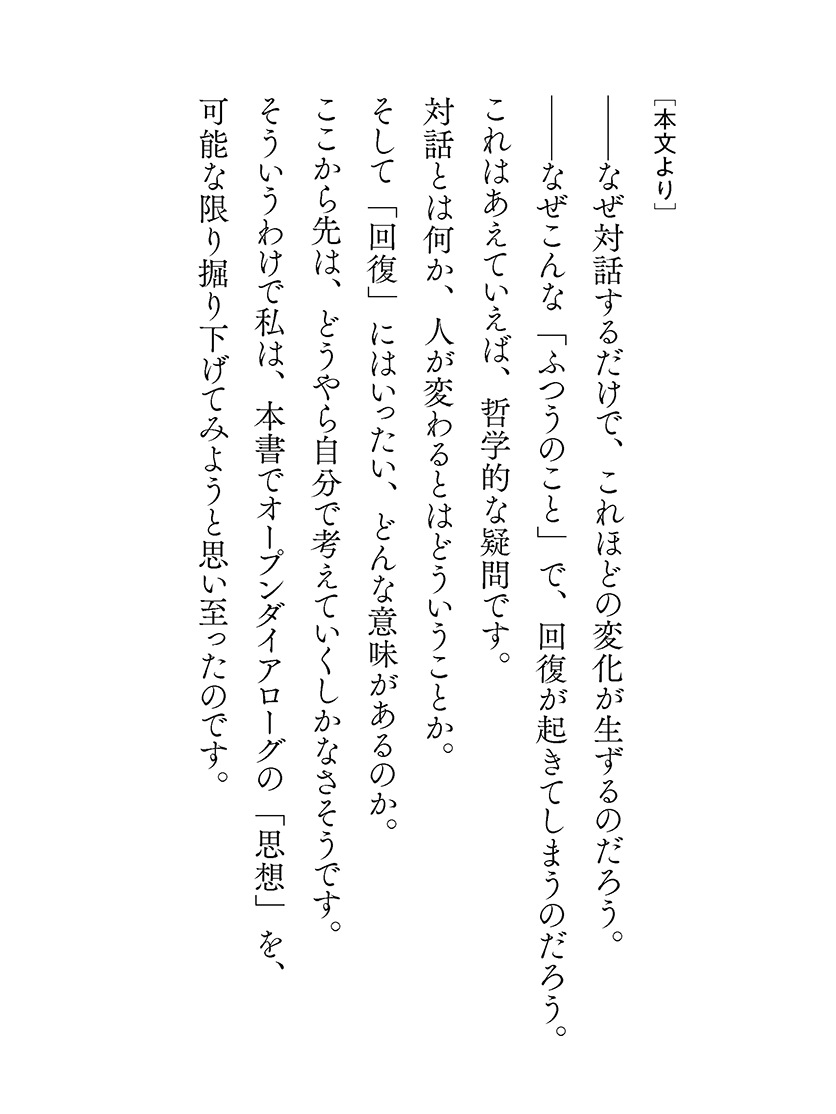
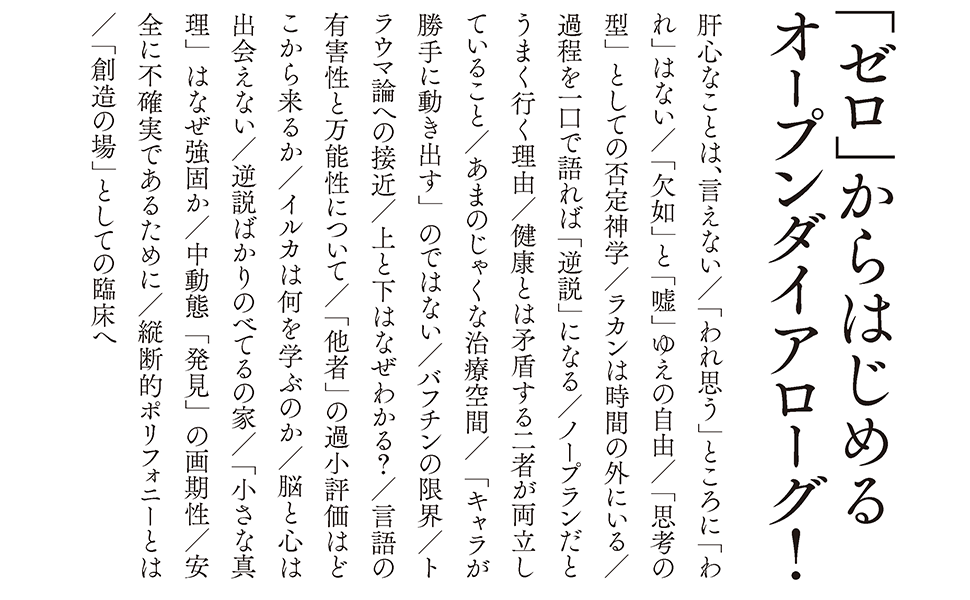
序文
開く
はじめに──哲学的疑問
フィンランド発のケアの手法・システム・思想である「オープンダイアローグ」は、この数年間でかなり広く知られるようになり、支援者からも当事者からも強い関心が寄せられています。国際学会などに参加した印象からも、日本における関心が突出して高いように思われるほどです。初期から普及啓発にかかわってきた者の一人として、この状況には大きな感謝と喜びを禁じえません。
私は臨床家として、オープンダイアローグの実践を八年間以上続けてきました。つねにフェアであろうと努力してきたことを除いては、さして傑出したものを持たない凡庸な精神科医に、オープンダイアローグは超強力なブースター(昇圧器)を与えてくれました。
支離滅裂な妄想を語りつづける精神病の患者、かつての私ならただちに「了解不能」の烙印を押して保護室に隔離していたような患者、そうした人々とも対話を繰り返しながら、薬物の力を借りずにリカバリーの方向へ歩を進めることができるようになりました。そうした治療経験の一部については、患者さんご本人の許諾を得て報告もしてきました。
還暦目前にして臨床技術が突然向上するとは考えにくいので、こうした変化は、明らかに私の所属する治療チームとオープンダイアローグのおかげ、と考えてよいでしょう。少なくとも私たちは、オープンダイアローグの有効性はすでに確立されたものと考えています。十分なエビデンスの確立や保険適用に至るまでの道のりはまだかなり先ですが、おそらく時間の問題でしょう。
目下の私の悩みは、もはやオープンダイアローグの実践と普及の難しさ、ではありません。自分でやっていながら、いまだによくわからないことがあるのです。つまり、「なぜ対話ごときで、精神病が治るのか」という根本的な疑問です。
たしかに私たちは、複数の患者とともに、着実に回復の道を歩んでいます。オープンダイアローグがあれば、それができる。この点についての確信は揺るぎないものです。
しかし、「なぜか」がわからない。なぜ対話するだけで、これほどの変化が生ずるのだろう。なぜこんな「ふつうのこと」で、回復が起きてしまうのだろう。
これはあえていえば、哲学的な疑問です。対話とは何か、人が変わるとはどういうことか、そして「回復」にはいったい、どんな意味があるのか。
私のこうした疑問に対しては、ヤーコ・セイックラの著作やミハイル・バフチンの著作に、ある程度まではヒントや答えが記されています。しかし実際のところ、私はそれらの答えにまだ十分には納得していません。ここから先は、どうやら自分で考えていくしかなさそうです。
そういうわけで私は、本書でオープンダイアローグの「思想」を、可能な限り掘り下げてみようと思い至ったのです。
目次
開く
I 否定神学をサルベージする
1 対話ごときでなぜ回復が起こるのか?
2 「無意識」の協働作業
3 ジャック・ラカンの精神分析
4 こんなに “使える” 否定神学
II 構造からプロセスへ
5 「プロセス」をめぐる逆説
6 逆説・プロセス・システム
7 バフチンにおける対話と「プロセス」
III よみがえる身体
8 対話における身体性
9 隠喩と身体
10 身体が思考する
IV 逆説とコンテクスト
11 「他者」の逆説
12 心は「コンテクスト」にしかない
13 ベイトソンの学習理論
14 対話と逆説
15 コンテクストの転換に向けて
引用・参考文献
あとがき
書評
開く
新聞で紹介されました
《読者は、日々の対話という平凡な事実にこそ、多くの非凡な秘密があることに気づくだろう。本書は医学書の枠を超えて、小さな対話の偉大さを語った思想書である。》──福島亮大(批評家)
(『朝日新聞』2024年11月23日より)
《特定の目的や意味から距離を取った、余白を含む対話だからこそ、個人は主体的に振る舞うことができる。逆説がもたらす回復への過程を知ることは、複雑な人間の心の在りようの一端を理解する道筋でもある》
(『聖教新聞』2024年12月24日より)
《ラカンとオープンダイアローグをつなぐ、著者の総決算ともいえる理論書。》──東畑開人(臨床心理学)
《ただひたすらに対話を重ねていくプロセスで、学習するAIの如く回復の更新が起きている。》──宮尾節子(詩人)
(『図書新聞』12月21日、2024年下半期読書アンケートより)
雑誌で紹介されました
《急性期の統合失調症を含む精神疾患に「よく効く」ことは立証されていても「なぜ効く」のかは分かっていない。その「なぜ」を、診療医であり、現代思想の論客でもある著者が探求していく。これは冒険の書である。》──佐藤良明(翻訳家)
(『世界』2025年2月号より)