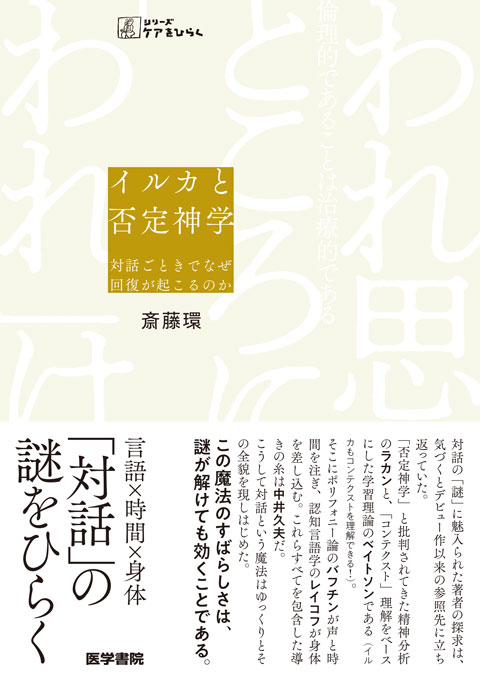オープンダイアローグとは何か
“開かれた対話”が、なぜ驚くほどの効果を上げるのか!?
もっと見る
依頼があったら「専門家チーム」が出向き、患者・家族・関係者をまじえて、状態が改善するまで、ただ「対話」をする———フィンランド発のシンプルきわまりないこの手法に、なぜ世界が注目するのか? オープンダイアローグの第一人者セイックラ氏の論文と、斎藤環氏の熱情溢れる懇切丁寧な解説が融合。生き生きとした事例、具体的なノウハウ、噛み砕いた理論紹介で、オープンダイアローグの全貌がわかる。
| 著+訳 | 斎藤 環 |
|---|---|
| 発行 | 2015年07月判型:A5頁:208 |
| ISBN | 978-4-260-02403-7 |
| 定価 | 1,980円 (本体1,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- TOPICS
- 序文
- 目次
- 書評
TOPICS
開く
●新聞で紹介されました。
《強い提案はモノローグ(独白)的なのに対し、弱い提案が使い手の希望や気付きを引き出し語らせる、その語りで設計者も気付き、さらに語りが設計物として立ち現れる。この積み重ねは、本書のオープンダイアローグに近く、ものが生まれる現場として正しいのだろうなという気がします。》──乾久美子(建築家)
(共同通信配信、河北新報「読書日和」2023年3月19日ほか)
《症状が他者と分かちあわれ人間全体の事象として受け止められたとき、患者のなかに安心感が芽生え、結果として症状が消える。その鍵が言葉にあるという考え方は大きな励ましだ。》――大竹昭子(作家)
(『朝日新聞』2015年8月30日 書評欄・BOOK.asahi.comより)
《斎藤さんは「妄想という強固な建築物が、みんなで共有しようとした瞬間に崩れ去ってしまう。私自身も、そうした例を見てきている」と話す。》
(『毎日新聞』2015年8月30日 東京朝刊 出版:精神科医・斎藤環さん「オープンダイアローグとは何か」 妄想、幻覚 対話で抜け出す)
序文
開く
はじめに それは“本物”だろうか?
対話の力? 薬を使わない? 反精神医学?
フィンランドでは統合失調症に対する画期的な治療がおこなわれているらしい。そんな噂を耳にしたのは、2013年暮れのことでした。『アディクションと家族』という雑誌に掲載するための対談があり、その席上で斎藤学〈さとる〉先生が、何気なくつぶやいたのです。「そういえばフィンランドでは、オープンダイアローグという治療が話題になっているらしいね」と。
その夜帰宅してから、耳慣れないその名前のメモを頼りにネットで検索してみました。日本語のサイトでは情報があまり見当たらなかったのですが、同名映画(DVD)の解説や感想がヒットして、どうやら統合失調症に対する家族療法的なアプローチらしいことまではわかりました。なんでも対話の力で、薬物をほとんど使わずに統合失調症を治すというのです。
正直に言えば、最初は半信半疑でした。医療不信が広がるなかで、「あらゆるワクチンは有害である」とか「抗がん剤は無意味」といったデマゴーグが飛び交っています。精神障害にはいっさい薬物治療をおこなうべきではないと主張する医師さえいます。このオープンダイアローグなる治療にしても、せいぜいマイナスイオンとかEM菌のたぐいのニセ科学か、うさんくさい代替療法なのではないか。そうした疑いがぬぐえませんでした。
どれほど精神療法 〔注〕 志向の医師でも、統合失調症だけは薬物療法が必須であると考えています。かつて反精神医学運動のなかで、薬物投与や行動制限をしない治療の試みが何度かなされ、ことごとく挫折に終わっているという苦い記憶もあります。統合失調症だけは薬を用いなければ治らない。それどころか、かつて早発性痴呆と呼ばれたように、放置すれば進行して荒廃状態に陥ってしまう。これは精神医学において専門家なら誰もが合意する数少ないハード・ファクトのひとつです。少なくとも、そう信じられています。
十分な薬物治療をせずに、もし患者が事件を起こしたり自殺したりした場合、担当医は確実に法的責任を問われるでしょう。繰り返しますが、ほとんどの精神科医にとって、統合失調症とはそのような病気です。さらに言えば、かつて多くの精神科医が、統合失調症の診断と治療に、みずからの存在意義を賭けてきたという歴史的経緯もあります。それが薬物を使わずに治ると言われても、にわかには信じられません。
しかし矛盾するようですが、「統合失調症が治る」と言われなければ、私はオープンダイアローグにさしたる関心を持たなかったと思います。うつ病が治る、ひきこもりがよくなると言われても、「ふーんそれは素晴らしいですね」という感想を持つだけで、すぐ忘れてしまったと思います。
注……「精神療法」だろうが「心理療法」だろうがどうでもいいのですが、いちおう私は精神科医だし、雑誌『精神療法』へもたびたび寄稿はしているしというとても些末な事情から、本書では「精神療法」で統一しました。
衝撃の治療成績
ともあれ私は、現地で治療過程を記録したという、そのドキュメンタリー映画をさっそく注文してみました(ダニエル・マックラー監督の“Open Dialogue:An Alternative, Finnish Approach to Healing Psychosis”.現在はYouTubeで、日本語字幕付きで見ることができる)。
映画の舞台は西ラップランド、トルニオ市の精神科病院であるケロプダス病院。家族療法を専門とする臨床心理士であり、ユバスキュラ大学教授のヤーコ・セイックラ氏が治療の中心人物です。映画は治療スタッフのインタビュー(英語)が中心で、治療場面らしきものは少ししか出てきません。しかし、映画に登場する病院スタッフたちが語る内容は、実に驚くべきものでした。
この治療法を導入した結果、西ラップランド地方において、統合失調症の入院治療期間は平均19日間短縮されました。薬物を含む通常の治療を受けた統合失調症患者群との比較において、この治療では、服薬を必要とした患者は全体の35%、2年間の予後調査で82%は症状の再発がないか、ごく軽微なものにとどまり(対照群では50%)、障害者手当を受給していたのは23%(対照群では57%)、再発率は24%(対照群では71%)に抑えられていたというのです。そう、なんとこの治療法には、すでにかなりのエビデンス(医学的根拠)の蓄積があったのです。
くどいようですが繰り返します。私自身もそうですが、入院と薬物治療によって統合失調症にかかわってきた医師ほど、この治療成績に衝撃を受けるでしょう。これらの数字が事実なら、それはほとんど“魔法のような治療”と呼んでも差し支えありません。しかし、すでにこの治療は1980年代から着実に成果を上げつつあり、フィンランドでは公的な医療サービスに組み込まれて、希望するものは無料で治療が受けられるというのです。
そして論文の説得力
まだ半信半疑のまま、セイックラ教授の論文を検索してみました。彼の主要な論文は、家族療法分野では一流誌とされるFamily Processに掲載されており、さいわいそのほとんどはインターネット上で読むことが可能です。著作もすでに共著が2冊刊行されており、そのうち1冊はAmazonで注文できます。さっそく取り寄せて読んでみました。
結論から言いましょう。いまや私は、すっかりオープンダイアローグに魅了されてしまっています。ここには確実に、精神医療の新しい可能性があります。すでに私は、ふたつの計画を構想中です。ひとつは、セイックラ教授の主著を翻訳出版すること。これはすでに現在進行中です。そしてもうひとつは、彼の治療実践を日本にも導入し、臨床場面での検証と応用を試みることです。
こうした反応は、なにも私だけではありません。看護師やPSW、臨床心理士や家族療法家など、いまや多くの専門家がオープンダイアローグに注目しています。
2015年3月に元ケロプダス病院のスタッフだった精神科医カリ・バルターネン氏が来日しておこなった講演会には、ほとんど広報しなかったにもかかわらず、50名以上の専門家が集まりました。翌4月に台湾の家族療法家が主催したセイックラ教授の有料のワークショップにも、100名以上の学生や専門家が参加しました。
「いちばん開いているときだからね」
専門家の反応といえば、私には忘れがたいエピソードがあります。
神田橋條治先生といえば、さまざまな意味でカリスマ的な名人芸を誇る精神科医として有名ですが、氏の名声を高からしめた業績のひとつに「自閉の利用」というものがあります。
これは簡単にいえば、こういうことです。統合失調症患者が他者との交流を絶って自分の世界に閉じこもる「自閉」的な態度を性急に批判したり治療しようとするべきではない。むしろそうした態度を尊重する姿勢のほうが、精神療法的な態度である。このような氏の主張は、当時の精神医学界に大きな衝撃をもって迎えられました。
しかし、「自閉」と「開かれた対話」とでは、ほとんど目指す方向が真逆です。はたして神田橋先生ならどうお考えだろう。そんなおり、たまたまある学会で幸運にも先生と立ち話をする機会があり、さっそく聞いてみました。「オープンダイアローグという治療法があって、手法はこれこれ、先生はどう思われますか?」と。
先生の答えはきわめて明快でした。
「ああ、それは効くだろうね。いちばん“開いて”いるときだからね」
即答でした。これには「さすがは名人」と感服したものです。ちょっと解説しておきましょう。
“開いている”とはどういう意味なのか。統合失調症という疾患は、その病理を簡単に説明するのはきわめて難しいのですが、あえてひとことで言えば、「自分と他者の境界があいまいになる病気」と考えられます。自分の考えたことが“だだ漏れ”になったり、他人の考えがどんどん入り込んでくるような感覚を訴えることがよくあります(思考伝播、思考吹入)。某有名漫画の影響で、これを「サトラレ」と呼ぶ人もいます。心の声が外から聞こえてくれば、「幻聴」という症状になります。
この状態は、ふだんは自分を守るためにある他者とのあいだの壁が壊れてしまい、外からのノイズを含むさまざまな刺激が、心の中にどんどん入り込んでくるような状態にたとえることができます。神田橋先生は、この状態を“開いている”と表現されたわけです。
開いているからこそ、有害なノイズを避けるための「自閉」は尊重されるべきです。しかし、開いているからこそ、治療的な刺激としての「開かれた対話」が効力を発揮するとも考えられるのです。ここに矛盾はありません。
よいたとえかどうかわかりませんが、身体のバリアとしての免疫力を低下させると、感染症の危険が高まりますが、臓器移植はしやすくなります。他者に向けて開かれた状態においては、「有害な」他者の被害を受けやすくなるぶん、「有益な」他者の受け入れも容易になる。その意味でオープンダイアローグとは、有益な他者の受け入れを容易にするための技術なのかもしれません。
経験を積んだ専門家ほど納得する
こうした反応は、神田橋先生に限ったことではありません。むしろ私が尊敬している優れた臨床家の多くが、この治療法に強い関心を示しています。それはある意味当然のことで、オープンダイアローグとは、これまで長い歴史のなかで蓄積されてきた、家族療法、精神療法、グループセラピー、ケースワークといった多領域にわたる知見や奥義を統合したような治療法なのです。
経験を積んだ専門家ほど、その手法と思想を聞いて「これは効かないほうがおかしい」と感じてしまうのは無理もありません。私自身が文献を読んだだけで、これほど入れあげてしまったのもおわかりいただけるでしょう。それほどこの「開かれた対話」には確たる手応えがあったのです。
オープンダイアローグの発想は、何もないところから急に出現したわけではありません。あとで述べるとおり、思想的には社会構成主義やポストモダン思想、治療法としてはシステム論的家族療法やナラティブ・セラピー、リフレクティング・プロセスといった複数の技法から大きな影響を受けています。
また、オープンダイアローグとの影響関係は定かではありませんが、薬物療法に依存しないコミュニティケアの試みは、D.クーパーの「ヴィラ21」やR.D.レインの「キングズレイ・ホール」がよく知られています。こうした反精神医学の文脈とは別に、L.モッシャーらによって創始された「ソテリア・プロジェクト」も、世界各国で試みられています。
このほか私がオープンダイアローグに近い治療実践として思い浮かべたのは、フランスのラ・ボルド精神病院における「制度を使った精神療法」です。精神分析家で思想家のフェリックス・ガタリは、この病院に1950年代半ばから1992年の死まで勤務していたことでも知られています。
ここでの治療は見方によってはオープンダイアローグよりもラディカルで、患者とスタッフの区別すらも撤廃してしまうようなものでした。患者とスタッフが協働しつつ、治療システムのあり方そのものを書き換え続けていくというもので、診断・治療といった硬直的な枠組みを拒絶するところや、専門家も患者もシステムの一部としてとらえるところなどは、オープンダイアローグによく似ています。
ただトレーニングや専門性までも排除してしまうとなると、ちょっと行きすぎの気もします。オープンダイアローグのように、必要最低限の専門性を維持しつつ、治療システムを構築するほうが現実的であるようにも思えるのです。
フィンランドでは公費医療の対象
ラ・ボルドの実践についてはともかく、オープンダイアローグによる治療成績は、ここにあげたコミュニティケアのそれをはるかに上回ります。比較的うまく行っているソテリア・プロジェクトですら、薬物治療とほぼ同等という評価ですから、ほかは推して知るべしでしょう。
もちろん、セイックラ教授らが示している統計データはエビデンスとしては弱い、という批判も出されています。私もこうした、オープンダイアローグについて懐疑的な姿勢まで排除しようとは思いません。たとえフィンランドでは有効であっても、日本の臨床にそのまま導入することができるかどうか。精神疾患への偏見がまだまだ根強いこの国で、家族や関係者の前で、精神的問題を自己開示してもらうことは可能かどうか。オープンダイアローグに関して、今ものすごく前のめりになっている私にすら、すでに多くの課題が見えています。
ただエビデンスについてちょっとだけ弁明しておくなら、何のエビデンスもない「治療プログラム」が、フィンランドにおいて公費負担医療の支援を受けられるとは考えにくいように思います。
ケロプダス病院では、後述するとおり、電話によるすべての相談依頼に24時間以内に治療チームが対応する方針をとっています。限られたスタッフでこの体制をパンクせずに回すことができている事実もまた、オープンダイアローグの有効性の傍証となりうるのではないでしょうか。有効性の低い治療法が、むしろ治療対象の患者を増やす結果につながることは、SSRIが導入された各国において軒並み、うつ病患者が増加していることからも明らかです。
「有効かどうか」ではなく「なぜ有効か」
しかし繰り返しますが、本音を言えば、エビデンス以上に説得的だったのは、セイックラ教授らによる理論構築の手堅さです。彼らはもはや「オープンダイアローグが有効かどうか」を問題にしていません。彼らの調査研究はすでに「なぜオープンダイアローグがこれほど有効なのか」という立場からなされています。
インチキな代替医療の提唱者の宣伝文は、しばしばコピペと見まがうような同じ主張の繰り返しで、創造性のかけらも見当たりません。しかしセイックラ教授らの理論展開は、「オープンダイアローグの有効性」をさまざまな角度から検討しており、失敗事例の検討も含め、その姿勢はきわめてフェアでオープンです。
もう一点付け加えるなら、オープンダイアローグはあくまでも複数の専門家が協働で発展させてきたものであり、セイックラ教授はそのスポークスマンのひとりという立場を貫いています。原著論文を数多く執筆しながらも、いまだに単著については禁欲的です。
何が言いたいのかといえば、オープンダイアローグの理論は、ひとりのカリスマ的な理論家のナルシシズムに奉仕するためのものではない、ということです。
ラカン派をはじめとする精神分析理論は、多かれ少なかれカルト化や教祖の絶対視を免れませんでした。特にラカン派の一部に顕著な傾向として、患者の言葉以上に原典教義の解釈が優先され、難解なジャーゴン(業界用語)が飛び交う秘教的空間をつくり上げることがよくあります。理論的な正当性はともかくとして、これでは臨床場面では使いものになりません。
ここにはとんでもない鉱脈が……
私がオープンダイアローグに惚れ込んだ理由は他にもありますが、実は、それらはすべて後づけです。シンプルに言い切ってしまえば、要は私の臨床家としての直感です。「オープンダイアローグ」という単語を聞いた瞬間から、直感がずっと囁いているのです。「ここにはとんでもない鉱脈がある」と。比較するのもおこがましいですが、はじめてフロイトの著作に接したときの古澤平作氏も、精神分析に対して同じ予感を抱いたのではないでしょうか。
できるだけ読みやすくなるように、部分的には“超訳”したところもありますが、なにせ専門誌に掲載された原著論文なので、それでも難しく感じる人もいるでしょう。手っ取り早くわかってもらうべく、この章では私なりの解説を試みることにしました。
妙にハイテンションな感想文の域を出ないかもしれませんが、オープンダイアローグという“冴えたやり方”をはじめて日本に紹介する著作にかかわったものの高揚感として、ご寛恕ねがえれば幸いです。
以下、オープンダイアローグについて私なりの解説を試みていきます。まずはオープンダイアローグの概略を示し、続いて実践の背景にある考え方、思想を解説します。そして、症例などを引用しながら、具体的な手法について解説をしていく予定です。概略→思想→マニュアルという、やや変則的な流れですが、おそらくオープンダイアローグに関しては、この順番のほうが頭に入りやすいのではないかと判断しました。
対話の力? 薬を使わない? 反精神医学?
フィンランドでは統合失調症に対する画期的な治療がおこなわれているらしい。そんな噂を耳にしたのは、2013年暮れのことでした。『アディクションと家族』という雑誌に掲載するための対談があり、その席上で斎藤学〈さとる〉先生が、何気なくつぶやいたのです。「そういえばフィンランドでは、オープンダイアローグという治療が話題になっているらしいね」と。
その夜帰宅してから、耳慣れないその名前のメモを頼りにネットで検索してみました。日本語のサイトでは情報があまり見当たらなかったのですが、同名映画(DVD)の解説や感想がヒットして、どうやら統合失調症に対する家族療法的なアプローチらしいことまではわかりました。なんでも対話の力で、薬物をほとんど使わずに統合失調症を治すというのです。
正直に言えば、最初は半信半疑でした。医療不信が広がるなかで、「あらゆるワクチンは有害である」とか「抗がん剤は無意味」といったデマゴーグが飛び交っています。精神障害にはいっさい薬物治療をおこなうべきではないと主張する医師さえいます。このオープンダイアローグなる治療にしても、せいぜいマイナスイオンとかEM菌のたぐいのニセ科学か、うさんくさい代替療法なのではないか。そうした疑いがぬぐえませんでした。
どれほど精神療法 〔注〕 志向の医師でも、統合失調症だけは薬物療法が必須であると考えています。かつて反精神医学運動のなかで、薬物投与や行動制限をしない治療の試みが何度かなされ、ことごとく挫折に終わっているという苦い記憶もあります。統合失調症だけは薬を用いなければ治らない。それどころか、かつて早発性痴呆と呼ばれたように、放置すれば進行して荒廃状態に陥ってしまう。これは精神医学において専門家なら誰もが合意する数少ないハード・ファクトのひとつです。少なくとも、そう信じられています。
十分な薬物治療をせずに、もし患者が事件を起こしたり自殺したりした場合、担当医は確実に法的責任を問われるでしょう。繰り返しますが、ほとんどの精神科医にとって、統合失調症とはそのような病気です。さらに言えば、かつて多くの精神科医が、統合失調症の診断と治療に、みずからの存在意義を賭けてきたという歴史的経緯もあります。それが薬物を使わずに治ると言われても、にわかには信じられません。
しかし矛盾するようですが、「統合失調症が治る」と言われなければ、私はオープンダイアローグにさしたる関心を持たなかったと思います。うつ病が治る、ひきこもりがよくなると言われても、「ふーんそれは素晴らしいですね」という感想を持つだけで、すぐ忘れてしまったと思います。
注……「精神療法」だろうが「心理療法」だろうがどうでもいいのですが、いちおう私は精神科医だし、雑誌『精神療法』へもたびたび寄稿はしているしというとても些末な事情から、本書では「精神療法」で統一しました。
衝撃の治療成績
ともあれ私は、現地で治療過程を記録したという、そのドキュメンタリー映画をさっそく注文してみました(ダニエル・マックラー監督の“Open Dialogue:An Alternative, Finnish Approach to Healing Psychosis”.現在はYouTubeで、日本語字幕付きで見ることができる)。
映画の舞台は西ラップランド、トルニオ市の精神科病院であるケロプダス病院。家族療法を専門とする臨床心理士であり、ユバスキュラ大学教授のヤーコ・セイックラ氏が治療の中心人物です。映画は治療スタッフのインタビュー(英語)が中心で、治療場面らしきものは少ししか出てきません。しかし、映画に登場する病院スタッフたちが語る内容は、実に驚くべきものでした。
この治療法を導入した結果、西ラップランド地方において、統合失調症の入院治療期間は平均19日間短縮されました。薬物を含む通常の治療を受けた統合失調症患者群との比較において、この治療では、服薬を必要とした患者は全体の35%、2年間の予後調査で82%は症状の再発がないか、ごく軽微なものにとどまり(対照群では50%)、障害者手当を受給していたのは23%(対照群では57%)、再発率は24%(対照群では71%)に抑えられていたというのです。そう、なんとこの治療法には、すでにかなりのエビデンス(医学的根拠)の蓄積があったのです。
くどいようですが繰り返します。私自身もそうですが、入院と薬物治療によって統合失調症にかかわってきた医師ほど、この治療成績に衝撃を受けるでしょう。これらの数字が事実なら、それはほとんど“魔法のような治療”と呼んでも差し支えありません。しかし、すでにこの治療は1980年代から着実に成果を上げつつあり、フィンランドでは公的な医療サービスに組み込まれて、希望するものは無料で治療が受けられるというのです。
そして論文の説得力
まだ半信半疑のまま、セイックラ教授の論文を検索してみました。彼の主要な論文は、家族療法分野では一流誌とされるFamily Processに掲載されており、さいわいそのほとんどはインターネット上で読むことが可能です。著作もすでに共著が2冊刊行されており、そのうち1冊はAmazonで注文できます。さっそく取り寄せて読んでみました。
結論から言いましょう。いまや私は、すっかりオープンダイアローグに魅了されてしまっています。ここには確実に、精神医療の新しい可能性があります。すでに私は、ふたつの計画を構想中です。ひとつは、セイックラ教授の主著を翻訳出版すること。これはすでに現在進行中です。そしてもうひとつは、彼の治療実践を日本にも導入し、臨床場面での検証と応用を試みることです。
こうした反応は、なにも私だけではありません。看護師やPSW、臨床心理士や家族療法家など、いまや多くの専門家がオープンダイアローグに注目しています。
2015年3月に元ケロプダス病院のスタッフだった精神科医カリ・バルターネン氏が来日しておこなった講演会には、ほとんど広報しなかったにもかかわらず、50名以上の専門家が集まりました。翌4月に台湾の家族療法家が主催したセイックラ教授の有料のワークショップにも、100名以上の学生や専門家が参加しました。
「いちばん開いているときだからね」
専門家の反応といえば、私には忘れがたいエピソードがあります。
神田橋條治先生といえば、さまざまな意味でカリスマ的な名人芸を誇る精神科医として有名ですが、氏の名声を高からしめた業績のひとつに「自閉の利用」というものがあります。
これは簡単にいえば、こういうことです。統合失調症患者が他者との交流を絶って自分の世界に閉じこもる「自閉」的な態度を性急に批判したり治療しようとするべきではない。むしろそうした態度を尊重する姿勢のほうが、精神療法的な態度である。このような氏の主張は、当時の精神医学界に大きな衝撃をもって迎えられました。
しかし、「自閉」と「開かれた対話」とでは、ほとんど目指す方向が真逆です。はたして神田橋先生ならどうお考えだろう。そんなおり、たまたまある学会で幸運にも先生と立ち話をする機会があり、さっそく聞いてみました。「オープンダイアローグという治療法があって、手法はこれこれ、先生はどう思われますか?」と。
先生の答えはきわめて明快でした。
「ああ、それは効くだろうね。いちばん“開いて”いるときだからね」
即答でした。これには「さすがは名人」と感服したものです。ちょっと解説しておきましょう。
“開いている”とはどういう意味なのか。統合失調症という疾患は、その病理を簡単に説明するのはきわめて難しいのですが、あえてひとことで言えば、「自分と他者の境界があいまいになる病気」と考えられます。自分の考えたことが“だだ漏れ”になったり、他人の考えがどんどん入り込んでくるような感覚を訴えることがよくあります(思考伝播、思考吹入)。某有名漫画の影響で、これを「サトラレ」と呼ぶ人もいます。心の声が外から聞こえてくれば、「幻聴」という症状になります。
この状態は、ふだんは自分を守るためにある他者とのあいだの壁が壊れてしまい、外からのノイズを含むさまざまな刺激が、心の中にどんどん入り込んでくるような状態にたとえることができます。神田橋先生は、この状態を“開いている”と表現されたわけです。
開いているからこそ、有害なノイズを避けるための「自閉」は尊重されるべきです。しかし、開いているからこそ、治療的な刺激としての「開かれた対話」が効力を発揮するとも考えられるのです。ここに矛盾はありません。
よいたとえかどうかわかりませんが、身体のバリアとしての免疫力を低下させると、感染症の危険が高まりますが、臓器移植はしやすくなります。他者に向けて開かれた状態においては、「有害な」他者の被害を受けやすくなるぶん、「有益な」他者の受け入れも容易になる。その意味でオープンダイアローグとは、有益な他者の受け入れを容易にするための技術なのかもしれません。
経験を積んだ専門家ほど納得する
こうした反応は、神田橋先生に限ったことではありません。むしろ私が尊敬している優れた臨床家の多くが、この治療法に強い関心を示しています。それはある意味当然のことで、オープンダイアローグとは、これまで長い歴史のなかで蓄積されてきた、家族療法、精神療法、グループセラピー、ケースワークといった多領域にわたる知見や奥義を統合したような治療法なのです。
経験を積んだ専門家ほど、その手法と思想を聞いて「これは効かないほうがおかしい」と感じてしまうのは無理もありません。私自身が文献を読んだだけで、これほど入れあげてしまったのもおわかりいただけるでしょう。それほどこの「開かれた対話」には確たる手応えがあったのです。
オープンダイアローグの発想は、何もないところから急に出現したわけではありません。あとで述べるとおり、思想的には社会構成主義やポストモダン思想、治療法としてはシステム論的家族療法やナラティブ・セラピー、リフレクティング・プロセスといった複数の技法から大きな影響を受けています。
また、オープンダイアローグとの影響関係は定かではありませんが、薬物療法に依存しないコミュニティケアの試みは、D.クーパーの「ヴィラ21」やR.D.レインの「キングズレイ・ホール」がよく知られています。こうした反精神医学の文脈とは別に、L.モッシャーらによって創始された「ソテリア・プロジェクト」も、世界各国で試みられています。
このほか私がオープンダイアローグに近い治療実践として思い浮かべたのは、フランスのラ・ボルド精神病院における「制度を使った精神療法」です。精神分析家で思想家のフェリックス・ガタリは、この病院に1950年代半ばから1992年の死まで勤務していたことでも知られています。
ここでの治療は見方によってはオープンダイアローグよりもラディカルで、患者とスタッフの区別すらも撤廃してしまうようなものでした。患者とスタッフが協働しつつ、治療システムのあり方そのものを書き換え続けていくというもので、診断・治療といった硬直的な枠組みを拒絶するところや、専門家も患者もシステムの一部としてとらえるところなどは、オープンダイアローグによく似ています。
ただトレーニングや専門性までも排除してしまうとなると、ちょっと行きすぎの気もします。オープンダイアローグのように、必要最低限の専門性を維持しつつ、治療システムを構築するほうが現実的であるようにも思えるのです。
フィンランドでは公費医療の対象
ラ・ボルドの実践についてはともかく、オープンダイアローグによる治療成績は、ここにあげたコミュニティケアのそれをはるかに上回ります。比較的うまく行っているソテリア・プロジェクトですら、薬物治療とほぼ同等という評価ですから、ほかは推して知るべしでしょう。
もちろん、セイックラ教授らが示している統計データはエビデンスとしては弱い、という批判も出されています。私もこうした、オープンダイアローグについて懐疑的な姿勢まで排除しようとは思いません。たとえフィンランドでは有効であっても、日本の臨床にそのまま導入することができるかどうか。精神疾患への偏見がまだまだ根強いこの国で、家族や関係者の前で、精神的問題を自己開示してもらうことは可能かどうか。オープンダイアローグに関して、今ものすごく前のめりになっている私にすら、すでに多くの課題が見えています。
ただエビデンスについてちょっとだけ弁明しておくなら、何のエビデンスもない「治療プログラム」が、フィンランドにおいて公費負担医療の支援を受けられるとは考えにくいように思います。
ケロプダス病院では、後述するとおり、電話によるすべての相談依頼に24時間以内に治療チームが対応する方針をとっています。限られたスタッフでこの体制をパンクせずに回すことができている事実もまた、オープンダイアローグの有効性の傍証となりうるのではないでしょうか。有効性の低い治療法が、むしろ治療対象の患者を増やす結果につながることは、SSRIが導入された各国において軒並み、うつ病患者が増加していることからも明らかです。
「有効かどうか」ではなく「なぜ有効か」
しかし繰り返しますが、本音を言えば、エビデンス以上に説得的だったのは、セイックラ教授らによる理論構築の手堅さです。彼らはもはや「オープンダイアローグが有効かどうか」を問題にしていません。彼らの調査研究はすでに「なぜオープンダイアローグがこれほど有効なのか」という立場からなされています。
インチキな代替医療の提唱者の宣伝文は、しばしばコピペと見まがうような同じ主張の繰り返しで、創造性のかけらも見当たりません。しかしセイックラ教授らの理論展開は、「オープンダイアローグの有効性」をさまざまな角度から検討しており、失敗事例の検討も含め、その姿勢はきわめてフェアでオープンです。
もう一点付け加えるなら、オープンダイアローグはあくまでも複数の専門家が協働で発展させてきたものであり、セイックラ教授はそのスポークスマンのひとりという立場を貫いています。原著論文を数多く執筆しながらも、いまだに単著については禁欲的です。
何が言いたいのかといえば、オープンダイアローグの理論は、ひとりのカリスマ的な理論家のナルシシズムに奉仕するためのものではない、ということです。
ラカン派をはじめとする精神分析理論は、多かれ少なかれカルト化や教祖の絶対視を免れませんでした。特にラカン派の一部に顕著な傾向として、患者の言葉以上に原典教義の解釈が優先され、難解なジャーゴン(業界用語)が飛び交う秘教的空間をつくり上げることがよくあります。理論的な正当性はともかくとして、これでは臨床場面では使いものになりません。
ここにはとんでもない鉱脈が……
私がオープンダイアローグに惚れ込んだ理由は他にもありますが、実は、それらはすべて後づけです。シンプルに言い切ってしまえば、要は私の臨床家としての直感です。「オープンダイアローグ」という単語を聞いた瞬間から、直感がずっと囁いているのです。「ここにはとんでもない鉱脈がある」と。比較するのもおこがましいですが、はじめてフロイトの著作に接したときの古澤平作氏も、精神分析に対して同じ予感を抱いたのではないでしょうか。
*
だいぶ前置きが長くなってしまいました。本書のメインは、オープンダイアローグの発展と普及に寄与してきたユバスキュラ大学のヤーコ・セイックラ教授による論文3本の翻訳です。オープンダイアローグの全体的な解説と、よい治療成果を上げるための工夫、改善をもたらしてくれる要因の分析がそれぞれのテーマです。できるだけ読みやすくなるように、部分的には“超訳”したところもありますが、なにせ専門誌に掲載された原著論文なので、それでも難しく感じる人もいるでしょう。手っ取り早くわかってもらうべく、この章では私なりの解説を試みることにしました。
妙にハイテンションな感想文の域を出ないかもしれませんが、オープンダイアローグという“冴えたやり方”をはじめて日本に紹介する著作にかかわったものの高揚感として、ご寛恕ねがえれば幸いです。
以下、オープンダイアローグについて私なりの解説を試みていきます。まずはオープンダイアローグの概略を示し、続いて実践の背景にある考え方、思想を解説します。そして、症例などを引用しながら、具体的な手法について解説をしていく予定です。概略→思想→マニュアルという、やや変則的な流れですが、おそらくオープンダイアローグに関しては、この順番のほうが頭に入りやすいのではないかと判断しました。
目次
開く
第1部 解説 オープンダイアローグとは何か (斎藤環)
はじめに それは“本物”だろうか?
1 オープンダイアローグの概略
全体をざっくりつかんでみよう
どんなルールで進められるのか
リフレクティングとは何か
2 オープンダイアローグの理論
ミクロポリティクス
詩学1 不確実性への耐性
詩学2 対話主義
詩学3 社会ネットワークのポリフォニー
3 オープンダイアローグの臨床
それはどんな経験だったのか
ミーティングの実際
実践のための12項目
4 オープンダイアローグとその周辺
ポストモダン
オートポイエーシス
精神分析
ケロプダス病院の実情
「べてるの家」との類似性
5 本書に収録した論文について
おわりに 私たちに「不確かさへの耐性」はあるか
第2部 実践者たちによる厳選論文 オープンダイアローグの実際
1 精神病急性期へのオープンダイアローグによるアプローチ
———その詩学とミクロポリティクス
The Open Dialogue Approach to Acute Psychosis:
Its Poetics and Micropolitics.
(Jaakko Seikkula & Mary E. Olson)
2 精神病的な危機においてオープンダイアローグの成否を分けるもの
———家庭内暴力の事例から
Open Dialogues with Good and Poor Outcomes for Psychotic Crises:
Examples from Families with Violence.
(Jaakko Seikkula)
3 治療的な会話においては、何が癒やす要素となるのだろうか
———愛を体現するものとしての対話
Healing Elements of Therapeutic Conversation:
Dialogue as an Embodiment of Love
(Jaakko Seikkula & David Trimble)
用語解説
索引
著訳者紹介
あとがき
はじめに それは“本物”だろうか?
1 オープンダイアローグの概略
全体をざっくりつかんでみよう
どんなルールで進められるのか
リフレクティングとは何か
2 オープンダイアローグの理論
ミクロポリティクス
詩学1 不確実性への耐性
詩学2 対話主義
詩学3 社会ネットワークのポリフォニー
3 オープンダイアローグの臨床
それはどんな経験だったのか
ミーティングの実際
実践のための12項目
4 オープンダイアローグとその周辺
ポストモダン
オートポイエーシス
精神分析
ケロプダス病院の実情
「べてるの家」との類似性
5 本書に収録した論文について
おわりに 私たちに「不確かさへの耐性」はあるか
第2部 実践者たちによる厳選論文 オープンダイアローグの実際
1 精神病急性期へのオープンダイアローグによるアプローチ
———その詩学とミクロポリティクス
The Open Dialogue Approach to Acute Psychosis:
Its Poetics and Micropolitics.
(Jaakko Seikkula & Mary E. Olson)
2 精神病的な危機においてオープンダイアローグの成否を分けるもの
———家庭内暴力の事例から
Open Dialogues with Good and Poor Outcomes for Psychotic Crises:
Examples from Families with Violence.
(Jaakko Seikkula)
3 治療的な会話においては、何が癒やす要素となるのだろうか
———愛を体現するものとしての対話
Healing Elements of Therapeutic Conversation:
Dialogue as an Embodiment of Love
(Jaakko Seikkula & David Trimble)
用語解説
索引
著訳者紹介
あとがき
書評
開く
非構成的エンカウンターグループの豊かさ (雑誌『看護教育』より)
書評者: 橋本 久仁彦 (「きくみるはなす縁坐舞台」坐・フェンスの座長)
私は30年ほど前に非構成的エンカウンターグループに出会った。我と汝という実存的な在り方を志向し,メンバーのどんな発言にもていねいに耳を傾け,互いに深く出会っていくというグループイメージはとても魅力的だった。組織に人間中心の雰囲気をもたらす革新的なアプローチとして,「静かなる革命」とか「20世紀最大の社会的発明」といった評価が寄せられ,教育,医療,福祉などに携わる多くの人々がこの方法に触れた。
しかし,今,非構成的エンカウンターグループを行う人や場所は少ない。実践家の多くは,構成的グループに移行していった。あらかじめグループのねらいや目的を明確化し,アイスブレークやウォームアップ,出会いや気づきのワークなど多数の心理テクニックを用いて,決められた時間内に所定の効果をあげるやり方のほうが,学校や企業などでは歓迎される。
人生や生き方に決定的な影響をもたらす本当の何事かが起こるまで,非構成的なグループのプロセスのなかで,誠実に,待つという態度を堅持することは,難しいことなのだろうか。オープン・ダイアローグの理論を整備したセイックラ教授は,エンカウンターグループにはなかった3つの観点を繰り返し強調している。
まず「不確実性への耐性」という概念によって,たとえやりとりが非生産的に見えようともよく耐え,専門性を使って安易に操作せず,生々しい対話や関係性のあいまいさのなかに,果敢に存在し続けることのしんどさを“価値”として可視化してみせた。「対話主義」は,どんな不思議な発話,幻聴や幻覚であっても敬意をもって真剣に聴き,医学用語ではなく,患者や家族と心から共有理解できる新しい言葉を協力して生み出すこと。「ポリフォニー」とは,“ミーティング”と呼ばれる対話の場において,まったく異なる複数の主張も,その語られるままに聞き取り,あたかも一つの民族文化のようにみなして互いに存在し合い,治療目標や問題解決へ向かって導かないこと。これは従来の自他の区別や個人の尊厳といった視点より,全体的,関係存在的な視界である。
かつて,大学の人事課主催で,全学の課長クラスの職員を集めて,ありのままの対話を重視するグループを行ったとき,人事課長が「このグループは何を話してもいいんですか? たとえ上司や大学の悪口でも?」と不安げな表情で確かめに来たことを思い出す。オープン・ダイアローグを知った今なら,このように返事するだろう。「全員が同じ空間にいるということ,それぞれの話し方や仕草などに触れること,お互いに人間として関係をもつということが,何かを決めたり問題を解決することより大事なこともあります」と。教育現場で,つい忘れがちな視点ではないだろうか。
(『看護教育』2016年2月号掲載)
反-主体としてのオープンダイアローグ (雑誌『精神看護』より)
書評者: 松本 卓也 (自治医科大学精神医学教室)
オープンダイアローグの登場は、統合失調症に対する治療法の大きなパラダイムシフトを引き起こすのみならず、現代の精神医療における大きなパラダイムシフトを引き起こすかもしれない。
それは、この治療法が統合失調症患者の入院治療期間を大幅に短縮し、症状の再発を防ぎ、障害者手当の受給率を大幅に抑えることができるからだけではない。この治療法は、現代の精神医学が前提としてきた「主体」についての考えを根底から変えてしまうようなものであるがゆえに、大きなパラダイムシフトを喚起する起爆力をもっているのである。
◆毎日繰り返される「開かれた対話」
そのことを説明する前に、オープンダイアローグがどのような治療法なのかを確認しておこう。まず、患者か家族のどちらかから病院のオフィスに電話相談が入る。すると、すぐさま治療チームが組織され、相談から24時間以内に初回ミーティングが開かれる。
特徴的なのは、このミーティングのやり方である。ミーティングには、患者本人とその家族、親戚、医師、看護師、心理士など、本人にかかわる重要な人物であれば誰でも参加できるのである。これらの人々が共に集まって、車座になって座り、そこで開かれた対話(オープンダイアローグ)がなされる。
では、「開かれた対話」というのはどういうものか。
薬物療法や入院の必要性など、治療に関するあらゆる決定は本人を含む全員が出席したミーティングで行われる。そして、ミーティングではすべての参加者に平等に発言の機会と権利が与えられ、医師などの専門家の発言に患者や家族が従わなければならないということは一切ない。また、患者は幻覚や妄想などの病的体験について話すことになるが、その病的体験は他の参加者によって頭ごなしに否定されることはなく、むしろそこに他の参加者が新たな語りを付け加えていくことになる。
こうして、ミーティングの語りは、患者の独語や専門家の指導が一方的に語られるモノフォニーではなく、多数の声が響き合うポリフォニーになる。このようなミーティングを、病気が改善するまで、毎日繰り返すのである。
1 現代の精神医療 vs. オープンダイアローグ
◆オープンダイアローグの「非常識」さ
この「非常識」な治療法を、私たちが馴染んでいる現在の精神医療システムと対比させてみよう。現代の精神医療システムは、徹底して反オープンダイアローグ的である。
統合失調症の急性期治療の決定は、医師などの専門家が主導権を握り、患者本人は方針の決定の場にはかかわることができないことがほとんどである。現代の精神医療システムは、措置入院や医療保護入院といった強制入院の制度の存在が示すように、急性期の統合失調症の患者を意思決定の主体として認めていないのだ。
また、通常、病的体験を語らせて肯定的なフィードバックを与えることは、病的体験をさらに賦活してしまうと考えられているし、幻覚や妄想などは語るものであるよりは、薬物療法などによって除去されるべきものであると考えられている。これは、患者を意思決定の主体としてのみならず、語る主体としても認めていないということにほかならない。
◆奪還から溶解へ
では、オープンダイアローグは、専門家だけが意思決定の主体として機能している現代の精神医療システムを逆転させて、患者を意思決定の主体の座につかせるものなのだろうか。
断じてそうではない。もしオープンダイアローグがそのような反動的なものであれば、それはかつての反精神医学に非常に近いものになってしまうだろう。そこには、権力をもつ者ともたざる者のあいだの終わりなき綱引き合戦がつづくだけである。
また、オープンダイアローグは、これまで無視されてきた語る主体としての患者をそのまま肯定するものでもない。オープンダイアローグは、意思決定の主体や語る主体という座を、専門家の側から患者の側に奪い返すようなものではないのだ。この治療法はむしろ、専門家や患者といった単一の声(モノフォニー)をもつ人物が主体の座を占めることに反対し、多数的な声(ポリフォニー)が鳴り響く空間へと主体を溶解させることを企図するという意味で、反-主体的な実践なのである。
2 参照点としての精神病理学
◆「主体化の失敗」としての統合失調症
精神病理学という、精神医学のなかでも特に「文系」的な学問領域がある。この領域におけるこれまでの研究は、主体の問題が統合失調症の発病と治癒に大きく関係していることを繰り返し指摘してきた。
例えば、統合失調症は、進学・就職・結婚といった状況においてしばしば発症することが知られている。これらの状況は、ひとが「1人の主体として出立する」契機であるといえる。
誤解を恐れずに言えば、統合失調症の発病は、それまで他者の庇護のもとで人生を送ってきた人物が、誰の力も借りずに一人前の主体となり、自立しようとするときの失敗の地点に位置付けられるのである(もちろんこれは、統合失調症が心因性の疾患であるという意味ではないが、紙幅の都合上、ここでは詳論できない)。
つまり、「文系」的な言い方をするなら、統合失調症とは、主体化の失敗によって、他者に対して主体の座を明け渡してしまった結果として生じる病なのである。
◆主体をめぐる闘争の場
よりミクロな、日常の会話のなかでも、主体の座をめぐる抗争は統合失調症の発症と関係している。奇妙な心気体感症状のために私たちの病院に入院したある患者さんの例をあげておこう。
この患者さんは、入院して数日たったころ、大部屋の他の患者さんたちが談笑している姿をみて、病棟スタッフにいきなり「あれは、俺のことを話しているんですよね」と訴えた。この後、この患者さんは本格的な統合失調症を発病させたのである。「自分が語る主体にはなりえない場所で、むしろ他者が主体となり、他者が自分のことを話している」という状況は、それまでなんとか発病を回避してきた統合失調症の患者さんにとって、決定的な発病契機ないし症状増悪の契機となりうるのである。
精神分析家ジャック・ラカンは、そのことを「妄想は、主導権が他者の側からやってくるようになったときに始まる」と述べた。誰かが主体の座につく空間においては、必然的に、誰かがその主体に従属する座につかなければならない。統合失調症は、主体の座をめぐる争いの結果として生じる。この病にしばしばみられる自我障害は、自我が1人の主体であることを守りきれず、自我のなかに他者が浸透してきてしまった結果である。
◆「精神病理学の苦闘」を無化する方向
それゆえ、多くの精神病理学者たちは、統合失調症の患者さんに対して、主体を再生するような精神療法的かかわりを推奨してきた。そのひとつが、「精神科医が狂者の秘書になること」、すなわち妄想する患者さんと一体化するのではなく、あくまでも患者さんの語りを聞き届ける役目を果たす、という考え方である。
統合失調症の患者さんは、一方では他者の世界(すなわち妄想の世界)に否応なしに引き寄せられてはいるが、他方では妄想を自ら主体的に語りなおすことによって、現実の世界ともかかわりをもつこともできる。このような分裂的なあり方を利用し、妄想を否定せずに現実とも折り合いをつけていけるような構造的な二重見当識を獲得させることが、しばしば統合失調症に対する精神療法の指針とされてきたのである。
このように、精神病理学は、統合失調症が主体化の要請において発病する病でありながらも、その治癒には主体化が不可欠であるという逆説のなかで苦闘してきた。そして、統合失調症の精神病理学における倫理性は、この困難な逆説との向き合い方によって担保されてきたと言っても過言ではない。
しかし、オープンダイアローグはよりエレガントな解答を提供してくれる。統合失調症が主体化の逆説をめぐる病であるとすれば、主体を多数的な声(ポリフォニー)が鳴り響く空間へと溶解させ、消滅させてしまえばよいではないか、と。
3 第三の道へ
◆精神医療自体が回復を阻害していた?
私は本書を読んで、中井久夫が次のように述べていたことを思い出した——「ひょっとすると分裂病〔=統合失調症〕は本来なおりやすいものであるけれども、それを妨害する要因が時には非常にたくさんあるので、結果としては遷延することが少なくないという考えもありうるのではないか」。
オープンダイアローグが私たちに突きつけているのは、現代の精神医療の枠組みそれ自体が、治癒阻害的だったのではないかという気付きである。統合失調症の患者さんにとって、自分の知らないところで自分に関する重大事が決まってしまうという権力の非対称性や、自分がかかわっていないところで自分のことが話されているという「知」の非対称性は、容易に妄想を賦活してしまうのである。
◆薬物療法でもなく精神分析でもなく
現代の精神医療は岐路に立っている。一方には、細分化され精緻化された薬物療法によって患者さんのあらゆる逸脱や叫び(主体の発露)を抑えこんでしまうような実践がある。他方には、精神分析(とりわけラカン派)のように、患者の主体をあくまでも尊重する立場をとる実践があり、前者の実践に大いに抵抗している。オープンダイアローグという主体を溶解させる実践は、そこに新たに登場した第三の道である。
中井久夫は、先の言葉に続けて、次のように述べている——「おそらく、分裂病が治癒しやすい病気と裏表なしに表現される時がもし来るならば、その時には精神病理学的魅力は消失しているかもしれない」。
中井の予言が正しいとすれば、オープンダイアローグが世界を席巻する未来は、精神病理学者をいささか寂しい気持ちにさせてしまうだろう。しかしそれはずっと先の未来のことであろうし、薬物療法によってあらゆる人間の逸脱や叫びが消滅させられる未来よりは受け入れやすい未来なのかもしれない。
(『精神看護』2015年9月号掲載)
「言語」への深い理解にもとづいた驚くほど平明な実践知
書評者: 上野 千鶴子 (社会学者)
◆なぜ「ダイアローグ」なのか
かねてより自助グループのコミュニケーション作法である「言いっぱなし,聞きっぱなし」に疑問を持っていた。ことばというのは,何より伝わることを求める。そしてかならず相手からの応答を求めるものだと思っていたからだ。
ラカンに俟〈ま〉つまでもなく,ことばとはつねにすでに他者のものだから。他者に属する言語を用いたとたん,どんなひとでもいやおうなく社会的存在になる。急性期発作のさなかにあって叫んだりわめいたりするほかなかった統合失調症の患者ですら,あとになってそのときの経験を言語化することを通じて,かれは理解を求め,応答を求める,社会的な存在として自らをさしだすことになる。
構造言語学が前世紀にわたしたちに教えてくれたのはそのことだ。そして構造言語学にもっともふかく影響を受けた精神科医であるラカンの,日本における最良の理解者である斎藤環が,本書の紹介者となった。
もちろん「言いっぱなし,聞きっぱなし」という,コミュニケーションともいえない「モノローグ」のようなコミュニケーション作法が定着したのは,自助グループに属する当事者たちがそれほど他者の反応に怯え,傷ついてきたからだとも言えよう。なら安全な聞き手の集団なら,応答があって当然ではないだろうか。だから「ダイアローグ」なのである。
◆謎もなければ秘技もない
急性期の精神症状を示す患者と家族のもとへ,複数の支援者がただちに出向く。必要なかぎり,何度でも,毎日でも出向く。そして患者と家族とともに,何が問題かを徹底的に語りあう。たったこれだけのことで,精神症状が治まる……ウソのようなマコトだが,ここには何の謎も,とくべつの秘技もない。条件はオープンダイアローグ,すなわち(1)ダイアローグであること,(2)ポリフォニーであること,このふたつである。
解のない状況に対して,ノイズを含む複数の応答が提示される。支援者も家族も本人も対等である。支援者のあいだで本人についてメタダイアローグが行われることもあるが,それも本人の目の前で行われる。自分が他人にどう見えるか,自己相対化のよい機会だろう。本人のいない場で意思決定がされることはない。安心できる聞き手の範囲は最初はコントロールされているが,この幅が拡がっていけば,当事者はやがて予期せぬ敵対的なノイズにも対応ができるようになっていくだろう。
◆言語コミュニティへ招き入れる実践知
このフィンランド生まれの統合失調症治療法は,おどろくほど平明で,秘教的なところは何もない。この技法をコミュニティ・アプローチと呼ぶのは理にかなっている。自我の危機を迎えた患者を言語コミュニティへと招き入れ,そこにしっかりとつなぎとめる。言語とは自我の檻でもあり,繋留〈けいりゅう〉点でもある。だが同時にそれは終わりのないオープンエンドのプロセスなのだ。ハバーマスの熟議民主主義をここで想起してもよい。
精神療法の理論家であるより治療者であろうとする斎藤が惚れこんだ実践知。解説も周到でわかりやすい。
書評者: 橋本 久仁彦 (「きくみるはなす縁坐舞台」坐・フェンスの座長)
私は30年ほど前に非構成的エンカウンターグループに出会った。我と汝という実存的な在り方を志向し,メンバーのどんな発言にもていねいに耳を傾け,互いに深く出会っていくというグループイメージはとても魅力的だった。組織に人間中心の雰囲気をもたらす革新的なアプローチとして,「静かなる革命」とか「20世紀最大の社会的発明」といった評価が寄せられ,教育,医療,福祉などに携わる多くの人々がこの方法に触れた。
しかし,今,非構成的エンカウンターグループを行う人や場所は少ない。実践家の多くは,構成的グループに移行していった。あらかじめグループのねらいや目的を明確化し,アイスブレークやウォームアップ,出会いや気づきのワークなど多数の心理テクニックを用いて,決められた時間内に所定の効果をあげるやり方のほうが,学校や企業などでは歓迎される。
人生や生き方に決定的な影響をもたらす本当の何事かが起こるまで,非構成的なグループのプロセスのなかで,誠実に,待つという態度を堅持することは,難しいことなのだろうか。オープン・ダイアローグの理論を整備したセイックラ教授は,エンカウンターグループにはなかった3つの観点を繰り返し強調している。
まず「不確実性への耐性」という概念によって,たとえやりとりが非生産的に見えようともよく耐え,専門性を使って安易に操作せず,生々しい対話や関係性のあいまいさのなかに,果敢に存在し続けることのしんどさを“価値”として可視化してみせた。「対話主義」は,どんな不思議な発話,幻聴や幻覚であっても敬意をもって真剣に聴き,医学用語ではなく,患者や家族と心から共有理解できる新しい言葉を協力して生み出すこと。「ポリフォニー」とは,“ミーティング”と呼ばれる対話の場において,まったく異なる複数の主張も,その語られるままに聞き取り,あたかも一つの民族文化のようにみなして互いに存在し合い,治療目標や問題解決へ向かって導かないこと。これは従来の自他の区別や個人の尊厳といった視点より,全体的,関係存在的な視界である。
かつて,大学の人事課主催で,全学の課長クラスの職員を集めて,ありのままの対話を重視するグループを行ったとき,人事課長が「このグループは何を話してもいいんですか? たとえ上司や大学の悪口でも?」と不安げな表情で確かめに来たことを思い出す。オープン・ダイアローグを知った今なら,このように返事するだろう。「全員が同じ空間にいるということ,それぞれの話し方や仕草などに触れること,お互いに人間として関係をもつということが,何かを決めたり問題を解決することより大事なこともあります」と。教育現場で,つい忘れがちな視点ではないだろうか。
(『看護教育』2016年2月号掲載)
反-主体としてのオープンダイアローグ (雑誌『精神看護』より)
書評者: 松本 卓也 (自治医科大学精神医学教室)
オープンダイアローグの登場は、統合失調症に対する治療法の大きなパラダイムシフトを引き起こすのみならず、現代の精神医療における大きなパラダイムシフトを引き起こすかもしれない。
それは、この治療法が統合失調症患者の入院治療期間を大幅に短縮し、症状の再発を防ぎ、障害者手当の受給率を大幅に抑えることができるからだけではない。この治療法は、現代の精神医学が前提としてきた「主体」についての考えを根底から変えてしまうようなものであるがゆえに、大きなパラダイムシフトを喚起する起爆力をもっているのである。
◆毎日繰り返される「開かれた対話」
そのことを説明する前に、オープンダイアローグがどのような治療法なのかを確認しておこう。まず、患者か家族のどちらかから病院のオフィスに電話相談が入る。すると、すぐさま治療チームが組織され、相談から24時間以内に初回ミーティングが開かれる。
特徴的なのは、このミーティングのやり方である。ミーティングには、患者本人とその家族、親戚、医師、看護師、心理士など、本人にかかわる重要な人物であれば誰でも参加できるのである。これらの人々が共に集まって、車座になって座り、そこで開かれた対話(オープンダイアローグ)がなされる。
では、「開かれた対話」というのはどういうものか。
薬物療法や入院の必要性など、治療に関するあらゆる決定は本人を含む全員が出席したミーティングで行われる。そして、ミーティングではすべての参加者に平等に発言の機会と権利が与えられ、医師などの専門家の発言に患者や家族が従わなければならないということは一切ない。また、患者は幻覚や妄想などの病的体験について話すことになるが、その病的体験は他の参加者によって頭ごなしに否定されることはなく、むしろそこに他の参加者が新たな語りを付け加えていくことになる。
こうして、ミーティングの語りは、患者の独語や専門家の指導が一方的に語られるモノフォニーではなく、多数の声が響き合うポリフォニーになる。このようなミーティングを、病気が改善するまで、毎日繰り返すのである。
1 現代の精神医療 vs. オープンダイアローグ
◆オープンダイアローグの「非常識」さ
この「非常識」な治療法を、私たちが馴染んでいる現在の精神医療システムと対比させてみよう。現代の精神医療システムは、徹底して反オープンダイアローグ的である。
統合失調症の急性期治療の決定は、医師などの専門家が主導権を握り、患者本人は方針の決定の場にはかかわることができないことがほとんどである。現代の精神医療システムは、措置入院や医療保護入院といった強制入院の制度の存在が示すように、急性期の統合失調症の患者を意思決定の主体として認めていないのだ。
また、通常、病的体験を語らせて肯定的なフィードバックを与えることは、病的体験をさらに賦活してしまうと考えられているし、幻覚や妄想などは語るものであるよりは、薬物療法などによって除去されるべきものであると考えられている。これは、患者を意思決定の主体としてのみならず、語る主体としても認めていないということにほかならない。
◆奪還から溶解へ
では、オープンダイアローグは、専門家だけが意思決定の主体として機能している現代の精神医療システムを逆転させて、患者を意思決定の主体の座につかせるものなのだろうか。
断じてそうではない。もしオープンダイアローグがそのような反動的なものであれば、それはかつての反精神医学に非常に近いものになってしまうだろう。そこには、権力をもつ者ともたざる者のあいだの終わりなき綱引き合戦がつづくだけである。
また、オープンダイアローグは、これまで無視されてきた語る主体としての患者をそのまま肯定するものでもない。オープンダイアローグは、意思決定の主体や語る主体という座を、専門家の側から患者の側に奪い返すようなものではないのだ。この治療法はむしろ、専門家や患者といった単一の声(モノフォニー)をもつ人物が主体の座を占めることに反対し、多数的な声(ポリフォニー)が鳴り響く空間へと主体を溶解させることを企図するという意味で、反-主体的な実践なのである。
2 参照点としての精神病理学
◆「主体化の失敗」としての統合失調症
精神病理学という、精神医学のなかでも特に「文系」的な学問領域がある。この領域におけるこれまでの研究は、主体の問題が統合失調症の発病と治癒に大きく関係していることを繰り返し指摘してきた。
例えば、統合失調症は、進学・就職・結婚といった状況においてしばしば発症することが知られている。これらの状況は、ひとが「1人の主体として出立する」契機であるといえる。
誤解を恐れずに言えば、統合失調症の発病は、それまで他者の庇護のもとで人生を送ってきた人物が、誰の力も借りずに一人前の主体となり、自立しようとするときの失敗の地点に位置付けられるのである(もちろんこれは、統合失調症が心因性の疾患であるという意味ではないが、紙幅の都合上、ここでは詳論できない)。
つまり、「文系」的な言い方をするなら、統合失調症とは、主体化の失敗によって、他者に対して主体の座を明け渡してしまった結果として生じる病なのである。
◆主体をめぐる闘争の場
よりミクロな、日常の会話のなかでも、主体の座をめぐる抗争は統合失調症の発症と関係している。奇妙な心気体感症状のために私たちの病院に入院したある患者さんの例をあげておこう。
この患者さんは、入院して数日たったころ、大部屋の他の患者さんたちが談笑している姿をみて、病棟スタッフにいきなり「あれは、俺のことを話しているんですよね」と訴えた。この後、この患者さんは本格的な統合失調症を発病させたのである。「自分が語る主体にはなりえない場所で、むしろ他者が主体となり、他者が自分のことを話している」という状況は、それまでなんとか発病を回避してきた統合失調症の患者さんにとって、決定的な発病契機ないし症状増悪の契機となりうるのである。
精神分析家ジャック・ラカンは、そのことを「妄想は、主導権が他者の側からやってくるようになったときに始まる」と述べた。誰かが主体の座につく空間においては、必然的に、誰かがその主体に従属する座につかなければならない。統合失調症は、主体の座をめぐる争いの結果として生じる。この病にしばしばみられる自我障害は、自我が1人の主体であることを守りきれず、自我のなかに他者が浸透してきてしまった結果である。
◆「精神病理学の苦闘」を無化する方向
それゆえ、多くの精神病理学者たちは、統合失調症の患者さんに対して、主体を再生するような精神療法的かかわりを推奨してきた。そのひとつが、「精神科医が狂者の秘書になること」、すなわち妄想する患者さんと一体化するのではなく、あくまでも患者さんの語りを聞き届ける役目を果たす、という考え方である。
統合失調症の患者さんは、一方では他者の世界(すなわち妄想の世界)に否応なしに引き寄せられてはいるが、他方では妄想を自ら主体的に語りなおすことによって、現実の世界ともかかわりをもつこともできる。このような分裂的なあり方を利用し、妄想を否定せずに現実とも折り合いをつけていけるような構造的な二重見当識を獲得させることが、しばしば統合失調症に対する精神療法の指針とされてきたのである。
このように、精神病理学は、統合失調症が主体化の要請において発病する病でありながらも、その治癒には主体化が不可欠であるという逆説のなかで苦闘してきた。そして、統合失調症の精神病理学における倫理性は、この困難な逆説との向き合い方によって担保されてきたと言っても過言ではない。
しかし、オープンダイアローグはよりエレガントな解答を提供してくれる。統合失調症が主体化の逆説をめぐる病であるとすれば、主体を多数的な声(ポリフォニー)が鳴り響く空間へと溶解させ、消滅させてしまえばよいではないか、と。
3 第三の道へ
◆精神医療自体が回復を阻害していた?
私は本書を読んで、中井久夫が次のように述べていたことを思い出した——「ひょっとすると分裂病〔=統合失調症〕は本来なおりやすいものであるけれども、それを妨害する要因が時には非常にたくさんあるので、結果としては遷延することが少なくないという考えもありうるのではないか」。
オープンダイアローグが私たちに突きつけているのは、現代の精神医療の枠組みそれ自体が、治癒阻害的だったのではないかという気付きである。統合失調症の患者さんにとって、自分の知らないところで自分に関する重大事が決まってしまうという権力の非対称性や、自分がかかわっていないところで自分のことが話されているという「知」の非対称性は、容易に妄想を賦活してしまうのである。
◆薬物療法でもなく精神分析でもなく
現代の精神医療は岐路に立っている。一方には、細分化され精緻化された薬物療法によって患者さんのあらゆる逸脱や叫び(主体の発露)を抑えこんでしまうような実践がある。他方には、精神分析(とりわけラカン派)のように、患者の主体をあくまでも尊重する立場をとる実践があり、前者の実践に大いに抵抗している。オープンダイアローグという主体を溶解させる実践は、そこに新たに登場した第三の道である。
中井久夫は、先の言葉に続けて、次のように述べている——「おそらく、分裂病が治癒しやすい病気と裏表なしに表現される時がもし来るならば、その時には精神病理学的魅力は消失しているかもしれない」。
中井の予言が正しいとすれば、オープンダイアローグが世界を席巻する未来は、精神病理学者をいささか寂しい気持ちにさせてしまうだろう。しかしそれはずっと先の未来のことであろうし、薬物療法によってあらゆる人間の逸脱や叫びが消滅させられる未来よりは受け入れやすい未来なのかもしれない。
(『精神看護』2015年9月号掲載)
「言語」への深い理解にもとづいた驚くほど平明な実践知
書評者: 上野 千鶴子 (社会学者)
◆なぜ「ダイアローグ」なのか
かねてより自助グループのコミュニケーション作法である「言いっぱなし,聞きっぱなし」に疑問を持っていた。ことばというのは,何より伝わることを求める。そしてかならず相手からの応答を求めるものだと思っていたからだ。
ラカンに俟〈ま〉つまでもなく,ことばとはつねにすでに他者のものだから。他者に属する言語を用いたとたん,どんなひとでもいやおうなく社会的存在になる。急性期発作のさなかにあって叫んだりわめいたりするほかなかった統合失調症の患者ですら,あとになってそのときの経験を言語化することを通じて,かれは理解を求め,応答を求める,社会的な存在として自らをさしだすことになる。
構造言語学が前世紀にわたしたちに教えてくれたのはそのことだ。そして構造言語学にもっともふかく影響を受けた精神科医であるラカンの,日本における最良の理解者である斎藤環が,本書の紹介者となった。
もちろん「言いっぱなし,聞きっぱなし」という,コミュニケーションともいえない「モノローグ」のようなコミュニケーション作法が定着したのは,自助グループに属する当事者たちがそれほど他者の反応に怯え,傷ついてきたからだとも言えよう。なら安全な聞き手の集団なら,応答があって当然ではないだろうか。だから「ダイアローグ」なのである。
◆謎もなければ秘技もない
急性期の精神症状を示す患者と家族のもとへ,複数の支援者がただちに出向く。必要なかぎり,何度でも,毎日でも出向く。そして患者と家族とともに,何が問題かを徹底的に語りあう。たったこれだけのことで,精神症状が治まる……ウソのようなマコトだが,ここには何の謎も,とくべつの秘技もない。条件はオープンダイアローグ,すなわち(1)ダイアローグであること,(2)ポリフォニーであること,このふたつである。
解のない状況に対して,ノイズを含む複数の応答が提示される。支援者も家族も本人も対等である。支援者のあいだで本人についてメタダイアローグが行われることもあるが,それも本人の目の前で行われる。自分が他人にどう見えるか,自己相対化のよい機会だろう。本人のいない場で意思決定がされることはない。安心できる聞き手の範囲は最初はコントロールされているが,この幅が拡がっていけば,当事者はやがて予期せぬ敵対的なノイズにも対応ができるようになっていくだろう。
◆言語コミュニティへ招き入れる実践知
このフィンランド生まれの統合失調症治療法は,おどろくほど平明で,秘教的なところは何もない。この技法をコミュニティ・アプローチと呼ぶのは理にかなっている。自我の危機を迎えた患者を言語コミュニティへと招き入れ,そこにしっかりとつなぎとめる。言語とは自我の檻でもあり,繋留〈けいりゅう〉点でもある。だが同時にそれは終わりのないオープンエンドのプロセスなのだ。ハバーマスの熟議民主主義をここで想起してもよい。
精神療法の理論家であるより治療者であろうとする斎藤が惚れこんだ実践知。解説も周到でわかりやすい。