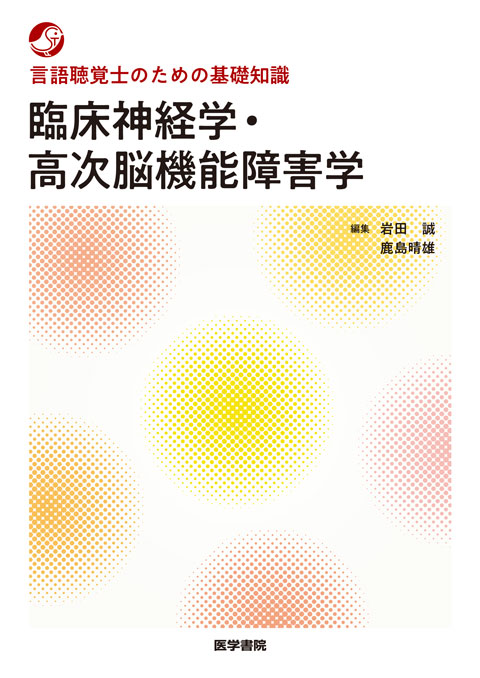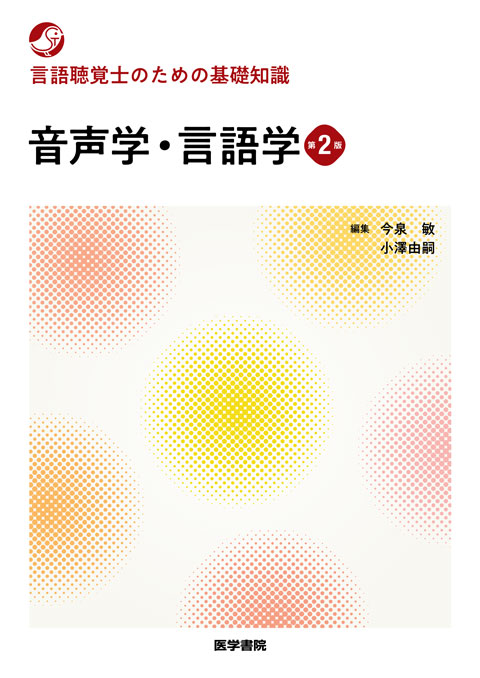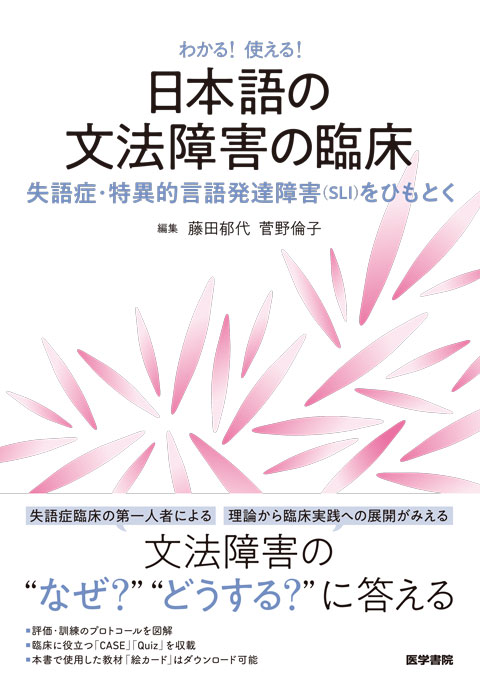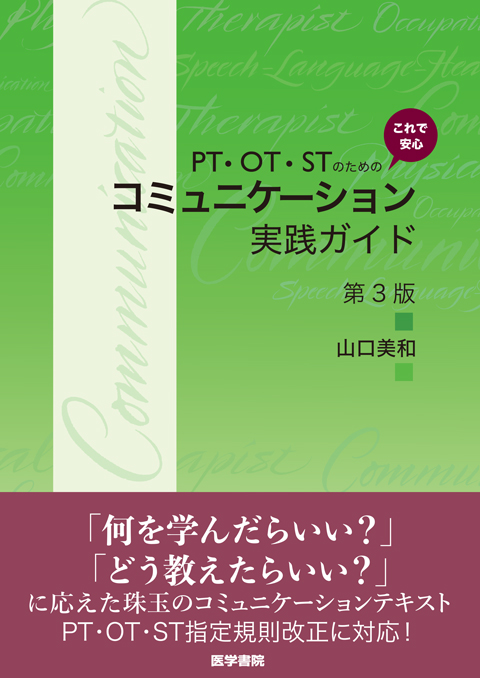失語症学 第4版
言語聴覚士をめざす学生が失語症を学ぶ最初の教科書。指定規則改正にならい改訂
もっと見る
令和6年「言語聴覚士学校養成所指定規則」改正を踏まえ改訂。失語症臨床の理論・技術を網羅かつ体系化した標準的な教科書という大前提を堅持しつつ、今版では新たな知見を盛り込み、学生が通読できるボリュームとレベルにも心を砕き構成を刷新した。臨床実習や卒後の臨床現場の橋渡しになる事例も充実している。
*「標準言語聴覚障害学」は株式会社医学書院の登録商標です。
更新情報
-
正誤表を掲載しました
2026.01.30
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
第4版の序
標準言語聴覚障害学『失語症学』第3版が出版されてから4年が経過した.この間の学問および臨床技術の進歩は著しく,失語症臨床を取り巻く環境は大きく変化しつつある.
今回の改訂では,2024年に行われた言語聴覚士学校養成所指定規則の初めての改正を踏まえ,構成および内容を刷新・整理し,失語症言語治療の全体像がより伝わりやすくなるよう努めた.
近年の学問の進歩や失語症を取り巻く環境の変化をみると,画像解析技術の進歩に伴う言語の神経ネットワークや回復メカニズムに関する知見の増加,クライエント中心およびエビデンスに基づく臨床の定着,国際生活機能分類(ICF)の視点から機能,活動,参加,背景要因のすべてを支援する包括的介入の浸透などがあげられる.また,失語症の言語治療技術について,標準となる認知神経心理学的アプローチを中心にさまざまな治療方法が工夫され,言語治療効果の測定によるエビデンスの蓄積が進んでいる.非侵襲的脳刺激法の利用や本人の活動や参加を支援する社会的アプローチの発展もみられる.そのほか地域包括ケアシステムの推進により,失語症の言語治療におけるサービス提供のあり方について,多様な試みがなされている.
第4版では,これらの学問の進歩と環境の変化をふまえたうえで,構成および内容を刷新した.具体的には,第1章,第2章で失語症の言語治療の基礎となる知識や基本概念を説明し,第3章,第4章にて,失語症への理解を深めるために,その症状と症候群についてくわしく解説している.第5章でまず失語症言語治療の全体像を示したのちに,第6章から第8章にかけて評価・診断から訓練・指導・支援までの言語治療の展開方法について,理論的根拠を示しながら具体的かつ実践的に解説している.
本書は,言語聴覚士を志す学生のテキストとなることを念頭に作成しており,失語症言語治療の基本となる普遍的な理論・技術について,体系的にわかりやすく解説している.また,最先端の内容まで網羅的に含んでおり,学生の知的関心を引き出すとともに,失語症言語治療に携わる方や,各分野の専門家の関心にも応えうると思われる.
学修を効果的に進められるように,第3版に引き続き「言語聴覚士養成教育ガイドライン」(日本言語聴覚士協会,2018年)を参照し,各章に「学修の到達目標」を設定した.さらに,今版では章末に「Point」として内容を復習できる「問い」を記載し,学びのポイントを明確にした.事例も豊富に記載し,本書の内容が実際の臨床と関連づけて学べるように工夫している.
本書の作成においては,臨床・研究ともに十分な経験と実績のある執筆者を幅広く迎え,標準テキストとして内容に偏りがないよう,基本的な理論・技法を網羅することに努めた.今版から初めて参加された執筆者の方も多い.失語症臨床への科学的視点と熱意をもって,真摯にご執筆いただいた方々に心から感謝を申し上げる.同時に,本書の完成に御尽力いただいた医学書院編集部のみなさまに深謝申し上げる.
2025年10月
編集
菅野倫子
津田哲也
目次
開く
失語症の言語聴覚療法の基礎
第1章 失語症の言語聴覚療法
1 失語症とそれに伴う問題
2 失語症の言語聴覚療法と言語聴覚士の役割
第2章 言語とその神経学的基盤
1 脳の構造
2 認知機能と関連する脳領域
3 言語に関与する脳領域
4 失語症の原因疾患
5 失語症と脳画像,脳機能イメージング
失語症を理解する
第3章 失語症の臨床症状
1 失語症の発見と理論の進歩
2 言語症状
3 失語症の近縁症状
4 失語症に随伴しやすい障害
第4章 失語症候群 失語症のタイプ
1 ブローカ失語
2 ウェルニッケ失語
3 伝導失語
4 健忘失語(失名辞失語)
5 超皮質性失語
6 全失語
7 交叉性失語
8 皮質下性失語
9 純粋型
10 原発性進行性失語
失語症の言語聴覚療法の展開
第5章 失語症の言語聴覚療法の全体像
1 失語症者とのコミュニケーションのとり方
2 失語症の言語治療のプロセス
3 失語症の回復プロセス
4 言語聴覚療法の提供体制
5 失語症の言語聴覚療法における連携とリスク管理
第6章 失語症の評価・診断
1 評価・診断の目的
2 情報収集
3 情報の統合と鑑別診断
第7章 失語症の言語治療計画の立て方
1 言語治療の理論と技法
2 伝統的治療
3 認知神経心理学的アプローチ
4 語用論的アプローチ
5 社会的アプローチ
6 CI言語療法
7 メロディックイントネーションセラピー(MIT)
8 非侵襲的脳刺激
第8章 失語症の言語治療の実際
1 語彙
2 構文
3 文字・音韻
4 発語失行(失構音)
5 実用的コミュニケーション
6 社会的アプローチ
7 報告
・ Pointの答え
・ 参考図書
・ 失語症学の授業プラン
・ 『標準言語聴覚障害学』全10巻の特長と構成
・ 索引
Note 一覧
① 失語のベストプラクティス提言
② EBPとエビデンスマップ
③ 失語症における発話の流暢性
④ 陰性症状と陽性症状
⑤ 日本語の文字表記
⑥ 滞続言語
⑦ 閉じ込め症候群
⑧ 残語
⑨ 文産生と動詞産生
⑩「置換」の成因に迷うとき
⑪ 発語失行と運動障害性構音障害の鑑別
⑫ 口部顔面失行
⑬ 新造語の有無
⑭ 語聾の分類
⑮ ウェルニッケ失語の回復傾向
⑯ 治療と仕事の両立支援
⑰ 失名辞(詞)失語の分類
⑱ 超皮質性運動失語のサブタイプ
⑲ 語義失語
⑳ 行政サービス
㉑ 非右利き(左利き,両手利き)の失語症
㉒ 非一貫性
㉓ 異書体性失書
㉔ 非流暢/失文法型PPAのさまざまな病型
㉕ PPAの病理学的背景
㉖ 大声で話しかける必要はない
㉗ 廃用症候群
㉘ 通所リハビリテーション
㉙ 訪問リハビリテーション
㉚ A-FROM(Living with Aphasia:Framework for Outcome Measurement)
㉛ 単一的事例研究法の例
㉜ 機能再編成法の例
㉝ 局所表象モデルと分散表象モデル
㉞ 意味のコントロール障害(semantic aphasia)
㉟ 認知神経心理学的な失読分類の補足
㊱ タイピングによる「書字」
㊲ 認知神経心理学的な失書分類の補足
㊳ 書字・読字モダリティの訓練効果のエビデンス
㊴ キーワード法の訓練効果機序
㊵ パソコン入力・スマートフォン入力
㊶ 発語失行に関する先行研究の紹介
㊷ ISAAC(アイザック)
㊸ SGD
㊹ 障害のある人を取り巻く法制度
㊺ 失語症会話パートナー
㊻ 失語症友の会
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。