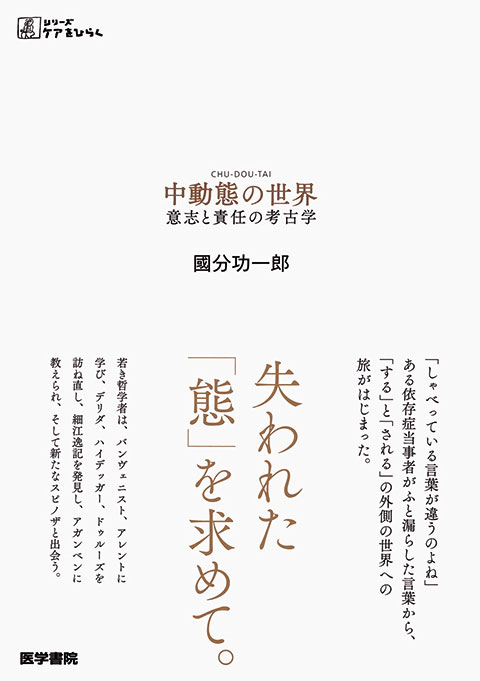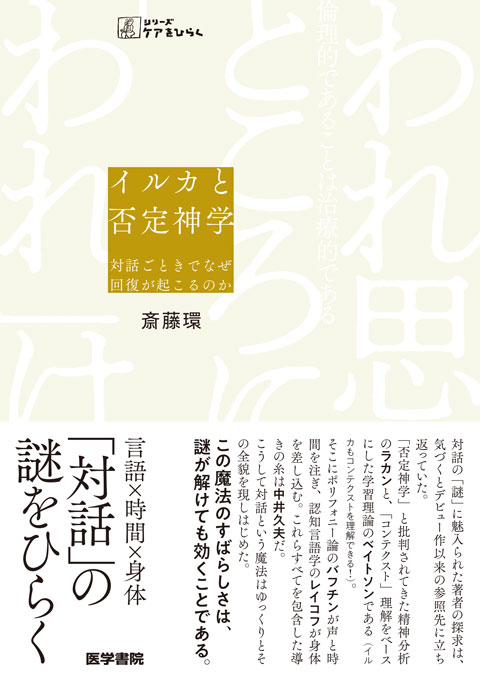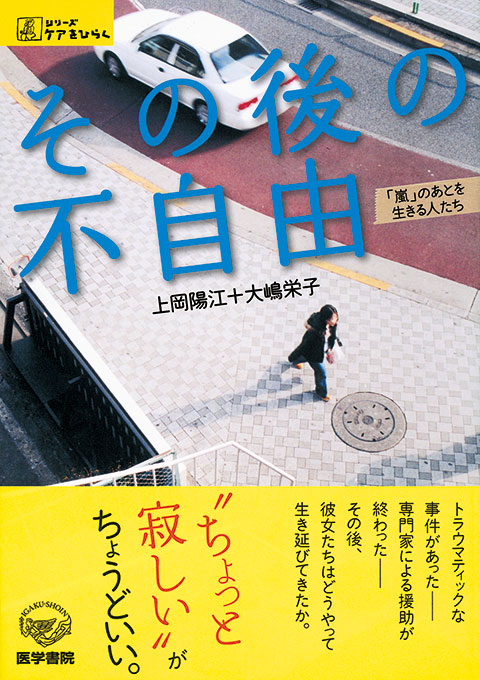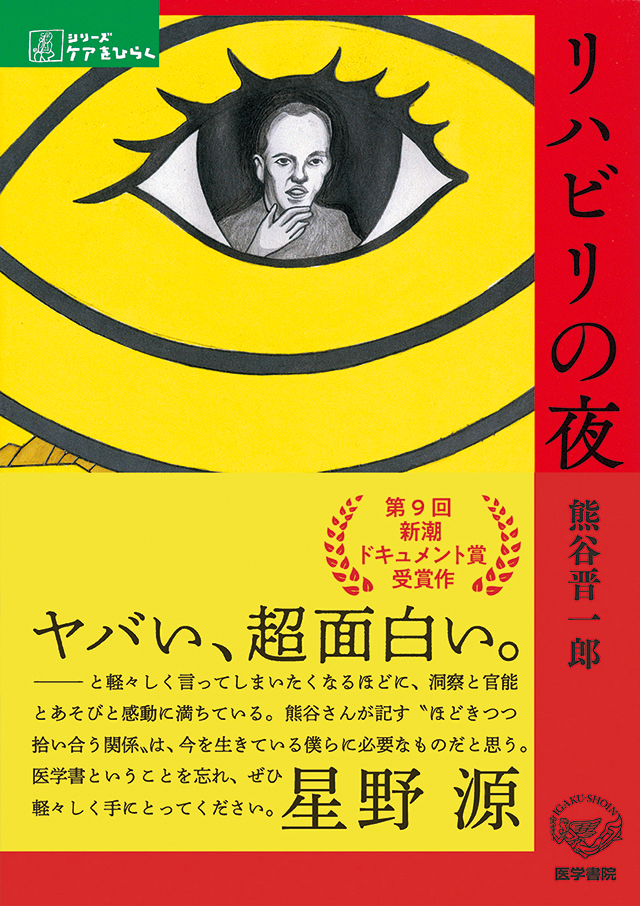中動態の世界
意志と責任の考古学
失われた「態」を求めて――《する》と《される》の外側へ
もっと見る
自傷患者は言った。「切ったのか、切らされたのかわからない。気づいたら切れていた」依存症当事者はため息をついた。「世間の人とはしゃべっている言葉が違うのよね」-当事者の切実な思いはなぜうまく語れないのか? 語る言葉がないのか?それ以前に、私たちの思考を条件づけている「文法」の問題なのか? 若き哲学者による《する》と《される》の外側の世界への旅はこうして始まった。ケア論に新たな地平を切り開く画期的論考。
| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |
|---|---|
| 著 | 國分 功一郎 |
| 発行 | 2017年04月判型:A5頁:344 |
| ISBN | 978-4-260-03157-8 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- TOPICS
- 序文
- 目次
- 書評
TOPICS
開く
●本書が小林秀雄賞を受賞!
第16回小林秀雄賞(主催:財団法人新潮文芸振興会)が2017年8月18日に発表となり,本書が選出されました。同賞は,自由な精神と柔軟な知性に基づいて新しい世界像を呈示した作品に授与されるものです。
・同賞の詳細情報はこちら(新潮社ホームページ:「小林秀雄賞」のページへ)。
・《Parce que j'aime la philosophie !(だって私は哲学が好きなんだ!)》――新潮社ホームページにて,國分先生の受賞スピーチもご覧いただけます(新潮社ホームページ:「第16回 小林秀雄賞」のページへ)。
●本書が紀伊國屋じんぶん大賞2018 第1位を受賞!
「紀伊國屋じんぶん大賞2018」が2017年12月26日に発表され,本書が大賞に選ばれました。同賞は紀伊國屋書店が主催し,読者の投票や出版社,書店員の推薦などによって,2016年12月~2017年11月に刊行された人文書のベスト30を選出するものです。
・同賞の詳細情報はこちら(紀伊國屋書店ホームページ:「発表!!紀伊國屋じんぶん大賞2018 読者と選ぶ人文書ベスト30」のページへ)。
●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!
第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。
●著者からのメッセージです。
《中動態が失われたというのは何を意味するかというと、意志を強く問う言語、尋問する言語が登場したということだと思います。ではなぜ意志にフォーカスする言語が出てきたのか?》
(『週刊読書人』2017年6月23日 講演「失われた『態』を求めて」より)
《能動態でも受動態でもない「中動態」を知ると少し生きやすくなる|著者は語る 國分功一郎『中動態の世界――意志と責任の考古学』》――「週刊文春」編集部
(「文春オンライン」文藝春秋社、2017年5月14日より)。
《私たちがこれまで決して知ることのなかった「中動態の世界」――「する」と「される」の外側へ》――國分 功一郎(哲学者・高崎経済大学准教授)
(「現代ビジネス」講談社、2017年4月2日より)。
《『中動態の世界』の謎に迫る!》
(「かんかん!――看護師のためのwebマガジン」医学書院、2017年3月28日より)。
序文
開く
-ちょっと寂しい。それぐらいの人間関係を続けられるのが大切って言ってましたよね。
「そうそう、でも、私たちってそもそも自分がすごく寂しいんだってことも分かってないのね」
-ああ、それはちょっと分かるかもしれないです。
「だから健康な人と出会うと、寂しいって感じちゃう」
-それは「この人は自分とは違う……」って感じるということですか?
「そういうのもあるかもしれないけど、人とのほどよい距離に耐えられない」
-多かれ少なかれ、そういう気持ちは誰にでもあるような気もしますけど。
「でも、私たちの場合、人との安全な距離というのがよく分かってない。だから、たとえば相手から聞かれれば、実家の住所から電話番号、携帯のアドレスも全部教えちゃう」
-自分でうまく相手を選べない、と。
「というか、そもそも人間関係を選んでいいなんて知らないんです」
-ああ。
「ちょっと親しくなると、『全部分かってほしい』ってなる。相手と自分がピッタリ重なりあって、〈二個で一つ〉の関係になろうとしてしまう。自分以外は見ないでほしい。自分以外としゃべってほしくない。そういうふうに思っちゃうわけ」
-その相手に一〇〇パーセント依存しようとするというか……。
「だから私が話を聞いて『大変だったね』って言うよね。そうすると次のときにクスリを使ってきたりする。『こんなでも受け入れてくれる?』って彼女たちはそう思ってしまう」
-それは分からないことはないけど、うまく想像ができない感じもあります。いちおう理解できるけれど、目の前で本当にそれをやられたらショックというか、自分はうまく対応できない気がする。
「そう、援助する人も傷つくんだよね」
-そういう話を聞くと、どうしても「しっかりとした自己を確立することが大切だ」と思ってしまう自分がいるんですが……。
「まあ私たちっていつも、『無責任だ』『甘えるな』『アルコールもクスリも自分の意志でやめられないのか』って言われてるからね」
-そういう言葉についてはどう思いますか?
「アルコール依存症、薬物依存症は本人の意志や、やる気ではどうにもできない病気なんだってことが日本では理解されてないからね」
-そういう言葉を発したくなるという気持ちは正直分かるんですよね。病気だってことは知ってます。でも、やっぱりまずは自分で「絶対にもうやらないぞ」と思うことが出発点じゃないのかって思ってしまう。
「むしろそう思うとダメなのね」
-そうなんですか。
「しっかりとした意志をもって、努力して、『もう二度とクスリはやらないようにする』って思ってるとやめられない」
-そこがとても理解が難しいです。アルコールをやめる、クスリをやめるというのは、やはり自分がそれをやめるってことだから、やめようって思わないとダメなんじゃないですか?
「本人がやめたいって気持ちをもつことは大切だけど、たとえば、刑務所なんかの講習会とかに呼ばれるじゃない? クスリで捕まった女性の前で話すんだけど、話が終わった後で、刑務官の女の人が『みなさん、分かりましたか。一生懸命に努力すれば薬やアルコールはやめられます。あなたたちもしっかり努力しなさい』なんてまとめをされて、『ああ、私が一時間話したことは何だったの』とかなる」
-僕の友人でも、「回復とは回復し続けること」って言葉の意味が全然分からなかったという人がいるんですよ。彼は「ずうっと毎日、回復の努力をし続けなければならないなんて大変だなぁ」って思っていたと言う。
「こうやって話していると何となく分かってくるんだけど、しゃべってる言葉が違うのよね」
-と、言いますと?
「いろいろがんばって説明しても、ことごとく、そういう意味じゃないって意味で理解されてしまう」
-ああ、たしかにいまは日本語で話をしているわけだけれど、実はまったく別の意味体系が衝突している、と。僕なんかはその二つの狭間にいるという感じかな。
「そうやって理解しようとしてくれる人は、時間はかかっても分かってくれる。けれども、まったく別の言葉を話していて、理解する気もない人に分かってもらうのは本当に大変なのよね……」
-僕なんかはお話をうかがっていると、むしろふだん見ないようにしている自分が見えてくる感じがしますけどね。だから、別世界の話とは思えない。けれどもそれが別世界の話じゃないと理解するのを妨げる何かがあって、僕のなかにもその何かがまだ作用している気がする。
「やっぱり言葉だと思う」
-そうですね。この相容れない二つの言葉って何なんでしょうね……。
目次
開く
第1章 能動と受動をめぐる諸問題
第2章 中動態という古名
第3章 中動態の意味論
第4章 言語と思考
第5章 意志と選択
第6章 言語の歴史
第7章 中動態、放下、出来事-ハイデッガー、ドゥルーズ
第8章 中動態と自由の哲学-スピノザ
第9章 ビリーたちの物語
註
あとがき
書評
開く
●新聞で紹介されました。
■毎日新聞「2017この3冊」
《動詞に「おもいつかれた」人がものした、詩篇である。》――堀江敏幸(作家)
《とにかく面白い。今年最も刺激を受けた一冊だ。》――中島岳志(東工大教授・政治学)
《哲学者による言語的な検討は、思いがけず治療論にも通じていた。》――斎藤環(筑波大教授・精神科医)
(『毎日新聞』2017年12月10日・17日 読書欄より)
■週刊読書人「二〇一七年の収穫!」
《最後はとんでもなく大きな発見と興奮とに導かれる。》――角幡唯介(作家・探検家)
《内容自体の面白さに加え考察の手順が鮮やか》――江南亜美子(書評家)
《『ヘブライ語文法綱要』の内容がくわしく紹介されているのがありがたかった。》――上村忠男(東外大名誉教授・思想史)
(『週刊読書人』2017年12月15日より)
《國分さんは自ら哲学してるという感じがすごくあって、そういう仕事を出来る人は同じ時代に日本にたくさんはいないんです。しかも、母語でない言語だから一番難しい、それをやってしかもこれだけの結果を出すのは凄いことだなと思いましたね。》――大澤真幸(社会学者)
(『週刊読書人』2017年6月23日 対談「中動態と自由」大澤真幸×國分功一郎より)
《あたかも、地下迷宮に潜り込み、いにしえの名剣を手に入れた冒険家が、地上に戻り戦いに向かっていくかのようだ。》――野矢茂樹(東京大教授・哲学)
(『朝日新聞』2017年5月21日 読書欄より)
《たとえばアルコール依存症の人々は、自由に飲酒する喜びを喪失した人々、自身の「外」にある病によって飲酒を強制された人々、と言えるだろう。……彼らの「本質」と「自由」の回復を支援する臨床家にとっても、「中動態」から見える風景は、新たな希望の糧となるだろう。》――斎藤環(筑波大教授・精神科医)
(『毎日新聞』2017年5月28日 読書欄より)
《充実した哲学書であるとともに、きわめて臨床的な書物である。……精神病理学/精神分析の思考を刺激する本書が、医学書院の「シリーズ・ケアをひらく」で出た意味は大きいと言わざるをえない。》――松本卓也(京都大准教授・精神科医)
(『図書新聞』第3305号 2017年6月3日より)
《シリーズ「ケアをひらく」の一冊に入った本書で、看護が正面から論じられる場面はほとんどない。だが、私たちが生きる現場を根底から見据える視点を、哲学から与えてくれる。》――納富信留(東京大教授・哲学)
(『読売新聞』2017年5月7日 読書欄より)
《これまで人は行動をどう捉えてきたか。これが本書のテーマだ。〔…〕読み終えて現実だと思い込んでいた夢から醒めるような感覚にくらくらする。》――山本貴光(文筆業・ゲーム作家)
(『日本経済新聞』2017年4月29日 読書欄より)
《「思い出」とは、思い出すことではない。身体に宿った「思い」が、ふと出てくることをいう。……そこには能動も受動もない。》――安田登(能楽師)
(共同通信社配信、『山陰新聞』2017年6月4日 書評欄、ほか)
《本書は、「私が何ごとかをするというのはどういうことか」という問いを解明しようとするものである。》――宇波彰(評論家)
(『公明新聞』2017年8月21日 読書欄より)
●webで紹介されました。
《「まさにそこを質問したかった」と読み手の気持ちを先取りする、「そんな大事な論点が残っていたか」と蒙を啓かせる、「そんな細かいところまで詰めるのか」と感心させられる、本書では、そんな驚きの問いが次から次へと繰り広げられる。》――小木田順子(編集者)
(『三省堂書店×WEBRONZA 神保町の匠』2017年04月20日より)
《この論点を「ケアをひらく」というシリーズ内に収めたことも秀逸な視点だと思う。アルコール依存症や薬物依存症の問題は、本人の意志だけではどうにも解決できないのだが、周囲に正しく理解されないことも多い。これを回避するための術が、この中動態という概念の中に眠っているかもしれないというのだ。》――内藤順(書評家)
(『HONZ』おすすめ本レビュー 2017年04月11日より)
演劇における中動態の世界――演じるという態
書評者:松村 武(劇作家・演出家)
書評を見る閉じる
國分功一郎著『中動態の世界―意志と責任の考古学』は,当たり前のようでいて新鮮かつ奥深い論考がスリリングに展開していく大変面白い本だった。自分が携わっている演劇というジャンルに反映させても,「中動態」に関して考えることは,何かきっと,見落とされていた新たな視点の在りかを発見させてくれるような気がする。そういう直観から,この書論を書き始めてみたい。
「役になりきる」考
俳優が役柄を演じる方法について,「役になりきる」という言い方がある。いわゆる名優の優れた演技を指して,この言葉で称賛する場合が多い。舞台上で俳優としてどう歩き,どうしゃべり,どう振る舞うのかを,俳優が彼(もしくは彼女)本人として演技を“構成する”“計算する”というよりも,本人が身体ごと作品世界における役柄そのものと化して,いわば演技を“生み出す”というような演技概念を指す。一つの見方においては,これが自在にできるほど,優れた俳優であるというコンセンサスになっている。
極端な例を出すと,ある健康な俳優が,例えば貧困の時代に生きる,食うや食わずのやせ細った病人を演じなければならないときに,彼(もしくは彼女)は実際に断食し,ガリガリにやせ細り,役と同じように生活し,時には本当に病気になったりする。これは「役になりきる」ために,わざと似た生活環境をつくることで,自分を役に寄せて誘導していく作戦である。歯を抜いたり,ひげを伸ばしたり,住む場所を変えたりするのも同じことだ。また,わざと「役になりきる」場合でなくても,俳優が「役になりきって」,恋する相手役に本当に恋してしまう場合もある。普段はおとなしい俳優が,乱暴者の役を演じているせいで,日常での喋り方や服装が変化する場合もある。
しかしだからといって,俳優が「役になりきる」状態のまま,目覚めてから寝るまで,自宅であろうが,劇場であろうが,電車の中であろうが,飲み屋であろうが,役柄として現実世界をさまようなんてことは当然起こり得ない。その俳優は,本人の俳優としての能動的な意志を持って劇場へやってきて,開幕のベルとともに作品世界の「役になりきる」だけだ。
能動から受動へ――早すぎる結論
ところで私の経験的な印象だが,演技を始めたばかりの未熟な俳優は,せりふを積極的に言いたがるところがある。そして積極的に動きたがる。せりふをいかにうまく喋り,いかにうまく動き回るか。それこそが演技の実力なのだと思いがちである。言い換えれば,演技というものを極めて能動的なものだと考えがちである。
彼らは指導者や先輩たちにまずそこを注意されるだろう。その際に,受動的に演技を考えるという視点を初めて教えられる。私自身もそういう段階を経て演技というものを学んでいった実感があるので思うのだが,この受動的な視点での芝居の捉え方というものを一度体感すると,演技観が大きく変わるのだ。これは演技力を深めていく経路として必要な発見段階なのかもしれない。つまり相手の演技に応じて自分の演技が発生する。あるいは,観客の反応に即して自分の演技が発生するという考え方である。
これはうまくいったと感じると目からうろこが落ちるような体験である。その瞬間に自分の外部,他人との「つながり」というものを実感する。これが演劇なのだと感激し,演じるということの何らかの結論にたどり着いたかのように思える。
受動し続ける先
そうなると,次はどこまで舞台上で受動的でいられるかということが演技力の指標となる。周りで起こっていることにどこまで純粋に影響を受けることができるか。「芝居は相手役から発する」あるいは「芝居は観客から発する」。いかにもベテランの俳優が若手にアドバイスしそうな言葉である。
この考え方は一見,楽なように思えるかもしれない。確かに基本的に俳優は,自分の外で何かが起こるのを「待つ」だけのようにも思えるからだ。あとはでき得る限り純粋な形で受動的に影響さえ受ければ,勝手に自分の演技が発動し,自ずと芝居が進行していく。
しかしこれは,ただ能動的に演技することよりよっぽど難しい。なぜなら,演技という現象が催眠術にかかった人みたいにどこか得体のしれない場所から都合よく発生してくるわけではない。あるいはベルトコンベアみたいに,電力か何かで勝手に芝居が動いていくわけではない。つまり受動的になる度合いには限度がある。芝居には段取りがあり,せりふがある。どんなに「役になりきる」状態でいようが,いかなるタイミングで登場し,どこに立ち,どちらに顔を向け,誰に向かって何をしゃべるかということは基本的には台本・演出によって決まっており,その道をたどらなければならない。
極端な例として,たとえそれが即興演劇だったとしても,即興的に振る舞うことができる範囲というものは,時間や空間,置かれている状況によって制限されるという意味で同じことである。無制限に何でもありの状況なんてものはあり得ない。つまり無制限に受動的でいることはできない。作品世界の中で演技をするためには,能動的に段取りや約束事をたどらなければいけない。しかも効果的に,つまり上手にそれをたどるということが,俳優には必ず課されるのである。
それでいて,同時に受動的でなくては良い演劇はできない。誰の影響も受けず誰ともつながることができない一人だけの密室演劇は演劇と言い難い。
心地良さの正体
ここまで考えてきて明らかなように,そもそもこの演劇の分析においてズレを生じている原因があるとすれば,演技の中身を能動/受動の区別を使って説明しようとすることである。まさに本書にさまざまな例を使って書かれている事態である。そしてここに中動態の概念を持ち込むことで,俳優の演技という行為は比較的簡単に説明される。「演じる」という行為は中動態の範疇にある。
演じているとき,俳優は自分の意志やプランの力のみで,自分の演技を進行させているのではない。また何かの力,例えば台本や演出,相手役の演技,観客の期待,反応などによって人形のように操られているというわけでもない。そのどちらでもあり,また同時にどちらでもないような状態が,演じている時間には流れる。
例えて言うなら,流れている川に,その流れに乗りたくて飛び込み,身体は流れに任せて,それでいて同時にその流れの中を何かに向かって泳いでいるような状態である。その格別な心地良さの正体は,川の流れとの一体感,その流れの力が加わることで体感する自分だけでは得られない推進力,その推進力がもたらす解放感,日常重力からのしなやかな逸脱……。能動でも受動でもない,中動態で表され得る,この演じているという状態は,一般にイメージされるよりもずっと“自由”を感じ得るものだ。
観る態について
さて,ではもう一方の極にある観客にとって,演劇を観るという行為はどうか。
観客が能動的に観る芝居を選んで,劇場に足を運んで,チケットを買って舞台を観る。面白くなければ途中で席を立っても誰にも文句は言われない。なぜならそれはその観客が自分の意志で能動的に選んだ舞台だから。自分に責任があるのだから,その行動は他人(舞台側の立場の人間)に問われることはないし,観客側から舞台に対して文句を言う筋合いもない。その芝居がつまらなければ,その芝居を選んだ自分が悪いのだ。
しかし現実には,つまらない芝居に対して「金を返せ」なんて声がしばしば飛んでくる。最近は「時間を返せ」という声も多い。こういう声が出るときの観客の,舞台側への捉え方はきわめて受動的である。金と時間を払ったのだから,当然面白いものを見せられるべきであるというのが彼らの考え方である。自らの意志で作品を見世物興行にしている舞台側にはそういう責任がある,というように。
しかし,面白さなんてものは当然,定まったものではない。ここが電化製品や食べ物とは違うところだ。便利度合いや味といったものと比べて,面白さという価値観の幅は広い。したがって当然舞台側は,金も時間も返さない。能動的な責任は観客にあるのだからと彼らは考える。ここに芸能芸術の経済的難しさがある。
しかしここでもまた,能動と受動という区別の議論の立て方に問題がある。演劇を観るという行為,演技を観られるという行為は,その区別自体が能動/受動の図式に合わせて当てはめられているだけで,実のところは一つの「演劇」という中動態の範疇の行為なのである。それは観る,観られるという区別を越えて,同じ場所で両者自他一体に影響し合いながら進んでいく中動態的な現象なのだ。だからこそ責任の所在が曖昧になる。先に述べた経済上の難しさはここから発生するのだろう。
面倒くささと自由の実感
このご時世,経済的な難しさを孕んだ中動態的現象―演劇すなわち舞台芸術―は,より責任の所在がはっきりとしたその他の娯楽に比して,勢いとしては押されるばかりである。大量消費に乗るかどうかという価値観に資本も人も集中する度合いが高まるばかりのこの国において,それは時代遅れとばかりに取り残され,その能動/受動的な意志と責任の在りかの曖昧さという特徴ゆえに,面倒くさがられる傾向にあるのは間違いない。これはまるで,昔の言語から中動態的な考え方が失われていき,能動と受動の色分けが世界を覆っていくという,本書に書かれた歴史そのもののようである。
しかし,それでもこの舞台芸術の魅力に取り憑かれて,経済的成功や日常的幸福とやらを犠牲にしても,この分野にこだわる人が今でも後を絶たない。それは,この「演劇」という行為の本質が中動態的な範疇に含まれる行為であることと少なからず関係しているのではないかと思われる。
中動態的な認識の仕方が世界から失われつつあるという状況に対して,すなわち,何から何まで能動/受動の図式の中で責任の所在をクリアにすべきだという考え方がほぼ常識となっている事態に対して,直観的に危機感を持っている人が少なからずいるということだ。そこにおいて,一見責任を裏付けるものとして,よりクリアに整理されているように見える意志は,かりそめの図式が見せる幻影にすぎない。実は中動態的な認識の内側においてのみ,初めて意識され,初めて立ち昇る,本物の意志というものがある。そして,その存在を実感として感じ取っている人が少なからずいるということだ。その中動態の内における意志こそ,「自由」と感じる人々が。
自由の奪還
能動とも受動ともつき難い因果のつながりの内側で,ままならぬ流動に身を任せる私たちが,その前提において,瞬間瞬間に下し続ける決断。大きな受動的状況の中で,その状況だからこそ不断に生起する能動的な選択。その同時進行,両論併記的な中動態状況の中でしか生まれ得ない,人間能力の常識的限界からの解放感。自由の実感。大げさを承知で言うならば,演劇への憧れを絶ち難い人々というのは,この,自由の実感への渇望を絶ち難い人々なのである。
私は演劇に携わる一人の人間として,優れた演劇を観る行為が,その実感を取り戻す契機になり得ると信じている。そして本書を繰り返し読み,中動態という人間がそもそも持っていた,いわば“謙虚”な世界認識を自分なりにイメージし,身体の中に取り込むことが,この自由の実感の奪還戦において心強い稽古になるとこれまた強く信じている。
「能動的な学び」の価値観に一石を投じる(雑誌『看護教育』より)
書評者:大谷 則子(和洋女子大学看護学部設置準備室)
書評を見る閉じる
能動的な学習者を育てる,という言葉が盛んにいわれている昨今,私は,能動と受動といった二項対立の枠組みとは異なる,もう少し自由な学習者のとらえ方があるのではないか,というジレンマに陥っていたことがある。なぜ,安易に学習者を二項対立の図式にあてはめようとするのか。
能動と受動の対立,つまり「する」か「される」かの対立には意志と責任の概念が存在し,これが善か悪かの二項対立の判断基準になるという。学習においては,能動的な学習者が意志と責任を担う善で,受動的な学習者が悪とされる。
しかし,この本はそこに疑問を投じる。「強制ではないが自発的でもなく,自発的ではないが同意している」という事態は,看護基礎教育の現場にも,臨床の現場にも,ありふれている。「それが見えなくなっているのは強制か自発かという対立で,すなわち,能動か受動かという対立で物事を眺めているからである。そして能動と中動の対立を用いれば,そうした事態は実にたやすく記述できるのだ」と著者は語りかける。
では,中動態とは何か。著者は中動態の起源から歴史的な背景と変遷を紐解き,迫っていく。言語学者バンヴェニストによると,能動と受動の対立においては,するかされるかが問題になるのであるが,能動と中動の対立においては,主語が過程の外にあるか内にあるかが問題となる。
この考え方をもとに臨地実習における学生とのかかわりを例に挙げてみると,学生は,対象者との間でさまざまに揺れ動く相互作用プロセスの内に存在しているため,臨地における学生は中動的に存在しているとも考えられる。つまり,臨床の現実に圧倒され,自分からは手も足も出ないように見える学生であっても,まちがいなく看護という相互作用のプロセスのなかにいるのだ。中動的な存在である学生というとらえ方は,プロセスの外側から学生に能動的であることを強いる教員に疑問を投げかける。一見すると教員の答えを待っているだけの受動的に見える学生ではあっても,中動的にそのときその場に存在するなかで学びを得ているのだ。こうした新たな学習者観をもつことは,形式だけの能動を強制せず,ゆるやかに学び続けることを可能にするのでないだろうか。
これは,自らの看護実践における対象者との相互作用や,日常の学生とのかかわり,学習者のとらえ方などにも通じるであろう。私自身が生きるあらゆる過程の内において,中動態の世界はとても自然だ。この世界を知ることは,自由に近づき,自分自身を解き放つ素敵な発見であると私は感じている。
(『看護教育』2017年7月号掲載)
中動態の歌(雑誌『精神看護』より)
書評者:伊藤 亜紗(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授)
書評を見る閉じる
1 世界に対してできる作用
15年ほど前に、初めてバリ島のウブドという村を訪れた時のこと。薄靄の中で目が覚めた私は一瞬、国立競技場のピッチのど真ん中、しかもサッカーW杯の決勝戦がまさに行われているピッチのど真ん中に自分が横たわっているのではないかと錯覚した。満員の観客席から湧き上がる歓声にも似た、地鳴りのような生き物たちの大合唱が、夜明けのウブドを包んでいたのである。ホテルといっても壁のない部屋で私は、天井から吊られた蚊帳の中でじっと横になったまま、ジャングルのあらゆる葉の陰、あらゆる石の下、あらゆる水の辺に生き物がいて、それら一匹一匹が自分に可能な方法で音を出し、満足し、また沈黙に帰っていく様子に、じっと耳を澄ませていた。
虫もいたし鳥もいたしトッケイという鳴くヤモリもいた。面白いのは、この大合唱には時間的に移ろう「模様」のようなもの、パターンの変化のようなものがあったことだ。もちろん楽譜はないが、かといってただのカオスでもない。右の藪からある種類の虫の声がわーっと聞こえてきたかと思えば、今度は奥の田んぼから別の種類の虫が一斉に声をあげ、その音の層に穴を開けるようにトッケイが鳴き始め、その違和を埋めるようにして樹冠で鳥たちが鳴き出す。そんな具合に、ゆるやかな構造が生まれては消え、消えてはまた生まれながら、生き物たちの大合唱は日が昇るまで続いたのである。
「あいつが声を出したからオレも返事しよう」とか、「隣の田んぼの住人には負けたくない」とか、生き物たちが思っていたかどうかは知らない。知らないが、明らかに同調する動きや、逆に打ち消そうとする動きがあり、その「模様」に聴き入りながら、人間の営みと言われているものも、じつは同じようなものなんだろうな、と思っていた。
私たちが世界に対してできる作用はただ2つ、「同調(YES)」と「違和(NO)」だけだ。生起しつつある運動の流れに、身を任せるないし加速させるか、それとも異質なものを付け加えるか。コマンドはこの2つしかないけれど、エージェントの数が多いからきわめて複雑な、相互に干渉しあうネットワークが生まれる。それが社会なのではないか、と。
2 いつも“意志”して行動してる?
◆「能動か受動か」では分けられないこと
國分功一郎『中動態の世界』は、「中動態」というインド=ヨーロッパ語族の失われた文法カテゴリーを発掘しながらも、いわゆる言語学の領域を超えて、世界の新しい見方、つまり「中動態的な見方」を教えてくれる哲学の本である。文法カテゴリーとしての中動態は、「意志」概念の誕生と共に衰退した。だから「中動態的な見方」とは、一言でいえば、「意志」の枠組みを外すことによって見えてくる行為や出来事のありようを捉える、ということである。
もとになっているのは本誌『精神看護』に2014年1月号から11月号まで連載されていた論考だ。主題的に論じられることはないが、発端になったのは、依存症患者とのかかわりだったという。アルコールや薬物に依存してしまう人は、まさに「やめようという意志が弱いからやめられないのだ」といった「意志」の枠組みで責任を追及されがちだ。ところが彼らの実感としては、「依存したくないのに依存させられている」だったり、「やめようとすればするほどやめられない」だったり、意志や責任といった概念ではスパッと割り切れないものを抱えている。むしろ、概念のほうに、私たちの心の動きや行為の構造には合わない、不具合があるのではないか。そのあわいをすくい取るために本書は、そうした概念を支えている言語の仕組みにまで遡り、「中動態」という失われた態を召喚するのである。
中動態は、能動態でも受動態でもない、はたまたその中間でもない、全く別の態である。インド=ヨーロッパ語はある時代まであまねくこの態を持っていたことがわかっており、古典ギリシャ語にもサンスクリット語にも、中動態はふつうに存在する。しかしラテン語では失われている。いまでは能動態と受動態が対のように考えられているが、かつては能動態と中動態の対立があった。受動態は、中動態から派生してその地位を奪い、ついでに相方となる能動態の意味をも書き換えたのである。
能動態と受動態は、行為や出来事を「する」と「される」に二分するシステムである。「する」というと、意志して自発的にやっているようだが、実際の行為や出来事を観察してみれば、話はそんなに単純ではない。「やらざるを得ないからやっている」行為や、「やらされたわけじゃないけど、すすんでやっているわけでもない」行為のような、どっちつかずの例がたくさん存在する。というか、そんな行為が日常にはむしろありふれている。例えば私が本を拾う時、それは落ちたから仕方なく拾うのであって、どう見ても意志的な行為とは言えない。かといって、拾わないという選択肢もないわけではないのだから、強制とも言えない。そんな「能動か受動か」では割り切れない事態も、中動態ならうまく語れる、というわけだ。
◆「意志」があやしい
そもそも「意志」という概念がそうとうあやしい。意志は、〈私〉が〈意志して〉〈行為する〉という形で、行為の起点を「私」の中に置こうとする。しかしそもそも、100%自分発進で始まる行為など存在するだろうか。
私が本を拾う時、その前にまず「本が落ちる」という出来事があったはずだ。本が落ちる手前には「本を机の上に積み上げる」という習慣があったはずで、さらにその前には「読み切れないほどの大量の本を買い込む」という衝動が、その前には「講演会で面白そうな本をたくさん紹介される」という出会いが、さらには「その講演会に行こうと友達に誘われる」という人間関係があったかもしれない。その講演会に行くにしても、たまたまその日に「上司に仕事を褒められて気分がよかった」から何となく行ったのかもしれないし、「同姓同名の小説家が講師だと勘違いして」行ってしまったのかもしれない。要するにすべての行為は、過去に起こったさまざまな出来事との関係でなされているのであって、決して「私」を絶対的な開始地点として起こっているわけではない。「意志」という仕方で強引に開始地点を確定することは、「無からの創造」と同じくらい無謀なことなのだ。
◆意志とは、「過去の切断」である
著者は、哲学者ハンナ・アレントにならって、意志を「過去の切断」と定義する。「責任を問うためには、この選択の開始地点を確定しなければならない。その確定のために呼び出されるのが意志という概念である。この概念は、私の選択の脇に来て、選択と過去のつながりを切り裂き、選択の開始地点を私の中に置こうとする」(132頁)。
確かに、仮にあの本が、「前を歩いている女性のカバンから落ちたもの」であったとしたら、それを拾うことは「女性のもとに返す」という責任を生む。どうも声がかけづらくて、あるいはただ信号が赤になったせいで、その責任が果たせなかったとしたらどうだろう。場合によっては窃盗罪に問われるかもしれない。私は「意志して」その本を拾った人になってしまうのだ。「常に不純である他ない選択が、過去から切断された始まりと見なされる純粋な意志に取り違えられてしまう」(133頁)。
意志をこのように時間的な視点からとらえる発想は、とても面白い。過去とのつながりを断ち切ってしまうのだから、意志とはいわば連続性に対する不敬行為ということになる。となると、意志の概念が生まれるより前に使われていたカテゴリー、すなわち中動態が語っていたのは、断ち切られていない時間の感覚、さまざまな出来事が起こり、作用しあい、積み重なって行く、その連続的な流れの中にいる感覚ということになろう。私が今何かの行為をしているとすれば、それは過去のさまざまな出来事のうちに、すでにきっかけや萌芽が埋め込まれていたのだ。同じように未来に対しても、自分の行為は別の出来事や別の行為、思いもよらない結末の可能性を秘めている。「中動態的な時間感覚」というものがあるとすれば、それはこのような過去から未来へと続く連続性の中にある感覚だ。
◆主語が、過程の内にあるか外にあるか
著者の言葉を借りて整理してみよう。
中動態が指し示していたのは、「主語が過程の内部にある」状態だと著者は言う(88頁)。中動態のみをとっていた動詞、たとえば「できあがる」「惚れ込む」「希望する」などはどれも、生成の過程、感情に突き動かされている過程、未来に期待している過程を表している。逆に能動態のみをとっていた動詞、たとえば「行く」や「食べる」は、「行ってしまう」や「平らげる」といったニュアンスを持ち、主語が完結した過程の外部にいる状態を表していた(88-89頁)。「中動態と能動態」という対で語られる時、問題になるのは「過程の内か外か」なのだ。このような「過程の内部」にある連続的な視点に立つ時、初めて「する」という単純な意志の枠組みでは割り切れない行為を表せるようになる。「流れでやることになったけど楽しい行為」や「気づけばやっていたけど狙ったわけじゃない行為」。そんな日常生活にありふれた行為のあり方について、中動態ならば生き生きと語ることができるのだ。
3 日常は、中動態にあふれている
さいごに著者の議論を離れて、この中動態的時間感覚にぐーっと身を沈めてみたい。すると私には、冒頭で述べたあのウブドの夜明けの大合唱が聞こえてくるのだ。いつからともなく始まった大音量の歌ならぬ歌に、あらゆる生き物がその声でもって「同調(YES)」あるいは「違和(NO)」の入力をし続ける時間。その相互作用によって、歌の「模様」が少しずつ変化していき、つんざくような鳥の甲高い一声さえ、ひとつの違和的応答として飲み込まれていく。もちろん私はあの時は大合唱の外に、つまり中動態ではなく能動態の側に立っていたわけだが、それでも蚊帳の底に横たわって動けないほど、あの分厚いポリフォニーに圧倒されていたことは確かだ。それは、私がふだん東京という大都会で生活していること、つまり仮設された「意志」の世界に生きていることと、おそらく無関係ではあるまい。
◆回転寿司のポリフォニー
ふだんは「意志」の言語で生きているとしても、おそらく本質的には、人間の営みもまたあの大合唱のようなものだと思う。「人間の営み」と言うと何だか大げさなのだが、そんな歌は、耳をすませばいたるところに聞き取ることができそうだ。例えば、回転寿司店の店内。
いきなり卑近な例で恐縮だが、回転寿司店の内部は、さまざまな行為や出来事が、飲食店としては異常なほどに可視化された空間だ。それゆえ、相互作用がきわめて「聞き取りやすい」のである。ポイントはあの同心円状の構造である。中心から順番に、料理人(板前)、コンベア上を回る寿司、客、店員、という多数のエージェントが、帯状に円を成している。全員が中心を向き合う格好になるため、他の客の食事のペースや料理人の忙しさ、やってくる寿司ネタの順番などを、誰もがお互いに察することができるのだ。通常の飲食店では客同士の目線がぶつからないように席の配置が工夫されていることを思えば、これはまさに異例の空間デザインである。
料理人にネタを注文することは、能動/受動式の発想からすれば、まさに「意志」のカタマリのような行為だ。何しろここは回転寿司店で、黙ってコンベアの寿司を取って済ませることもできるのだから。
しかしこの注文行為は、「意志」の様相に反して、実際にはさまざまな出来事の干渉の産物である。料理人に確実に聞き入れてもらうためには、体がこちらに向くのを待ったり、「まぐろ1枚!」の前に「すいません」を付けて注意を引き付ける必要がある。直前に別の客が同じネタを頼んでしまったら、続けて注文するのは何だか気まずい。そうこうしているうちに、コンベア上の惹句につられて「まぐろ」ではなく「ホタテ」が食べたくなることもあるだろう。料理人は料理人で寿司を握る手をリズミカルに動かしつつ客の注文を聞き、担当でないネタの注文にも復唱で応え、シャリの残り具合を勘案してホールのスタッフに指示を出したりする。まるですべてのエージェントが、協力するわけでもなく、ただ黙々と相互に干渉しあいながら、ひとつの「中動態ポリフォニー」を歌っているかのようだ。
個人的に以前から気になっていたのは、「おあいそ!」のタイミングである。私がよく行く近所の回転寿司店は繁盛店で、週末に行くとたいてい待たされる。壁伝いの列に並びながら、客が去って行くタイミングをぼんやりと観察するはめになるのだが、そこには明らかに「波」のようなものがある。一組の客が「おあいそ!」と叫んで席を立つと、それにつられるかのように別の客も「おあいそ!」となり、あれよあれよと言うまに店内は歯の欠けたようになって行列が一気に解消される。パチンコで言うなら「確変」のような時間帯だ。逆に、待てど暮らせど「おあいそ!」がかからない我慢比べのような時間帯もある。
「おあいそ!」とは、いわば回転寿司的な「中動態の歌」から降りるという離脱宣言である。そのような大きな「決断の一手」こそ、私たちは流れの中で歌うように下すのかもしれない。
(『精神看護』2017年7月号掲載)