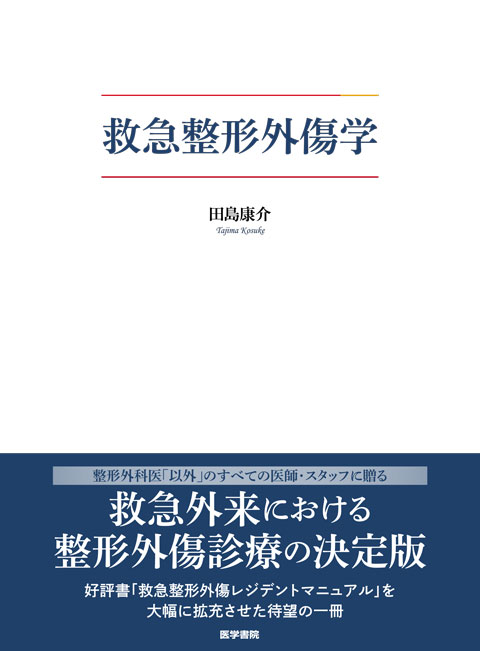クリニカル・クエスチョンで考える外傷整形外科ケーススタディ
外傷整形外科の最適解を症例と文献から読み解く
もっと見る
外傷整形外科に必要なスキルと質の高い治療戦略を学ぶ1冊。実際の症例とエビデンスをベースに、若手医師が臨床現場で悩むこと・困ることをクリニカル・クエスチョンで整理し、豊富な文献を読み解き治療の最適解を模索する。読者はハイレベルな外傷治療を疑似体験できる。「臨床家の視点」では、エキスパートの目と経験を通して臨床的センスのさらなるレベルアップを促す。整形外科医必携。
| 編集 | 土田 芳彦 |
|---|---|
| 発行 | 2024年03月判型:B5頁:368 |
| ISBN | 978-4-260-05321-1 |
| 定価 | 11,000円 (本体10,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
始まりはWebカンファレンス
2021年1月から約1年間,北海道大学整形外科の後期レジデントを対象に外傷整形外科のWebカンファレンスを開始しました.これは症例を通して日頃の疑問に答えるというものでしたが,回を重ねていくうちに,湘南鎌倉総合病院と札幌東徳洲会病院の医師が「レジデント提示症例」に対して解説プレゼンテーションを行うようになり,これがとても秀逸で高い評判を得ました.
そこで,Webセミナーとして,もう一度このプレゼンテーションを再現し,さらにその内容を書籍化することを計画しました.
外傷整形外科医療はいかにして学ぶか?
さて,医療を学ぶうえで重要なのは,症例ベースで考えることであるのは異論のないところですが,四肢外傷のように個別性の高いものは「現場主義」,「経験主義」に頼らざるをえない側面があります.もちろん,治療法の選択には「根拠」が必要です.それが文献であり,エビデンスベースと言われるものです.
しかし,外科手術の成績には技術の巧拙が大きく影響を与えることを考えると,「外科的臨床文献」には適切な技術を有する臨床医の知見と経験に基づいた解釈が必要です.平たく言えば,ある一定レベル以上の高い技術がなければ,その文献を正確に理解して臨床に応用することは難しいということです.
そこで本書では,症例に応じた臨床的疑問に対して文献的背景を述べた後に「臨床家の視点」で,文献と実践との溝を埋めるような内容を加えています.これらの症例提示とクリニカル・クエスチョン,文献考察は佐藤和生,佐藤 亮,髙田大輔,伊澤雄太の4名の先生方が担当し,「臨床家の視点」とコラムを筆者が担当しています.
外傷整形外科医療教育における問題
筆者自身も他の整形外科医と同様に,レジデントの頃には主に外傷手術に従事していましたが,将来的には外傷を専門とするつもりはなく,マイクロサージャリーと手外科を主体としてキャリアを積むことを考えていました.
それが,救急部に勤務するようになり,マイクロサージャリーがいかに重度な四肢外傷症例を救うことができるか身をもって感じ,外傷整形外科を専門にしようと思い立ったわけです.
幸いにして救急部での整形外科外傷治療の成績は比較的良好だったため,自分が会得した外傷治療のノウハウを後進に伝えようと考えるようになりましたが,大学医局での教育はなかなか進まないのが現実でした.
そこで,自ら研究会を立ち上げ,セミナーを開催したりしました.その後,新型コロナウイルス感染症の流行により一般化してきたWebセミナーを多く開催しました.しかし,外傷整形外科における「討論」はいまだ不十分であり,多くの整形外科医は真の理解に至っているとは言えないと考えています.
この分野を担う医師たちへ
医療はそれを享受する人の最大効果を目的としなければなりません.整形外科外傷の手術数は整形外科手術全体の約半数を占めるほど多いものですが,外傷整形外科をサブスペシャルティとする医師は少なく,外傷整形外科手術の多くは後期レジデントによって行われています.
外傷整形外科手術は決して容易なものではありません.困難な事例がたくさんあり,稚拙な治療の犠牲者も多く存在しています.ぜひともこの分野に真剣に向き合い,外傷整形外科をサブスペシャルティとする医師が多く現れることを願っています.
最後に,本文を執筆された4名はいま成長目覚ましい外傷整形外科医たちで,驚くほど高いレベルで本文をまとめてくれました.今後も切磋琢磨し,日本の外傷整形外科を牽引していってほしいと思っています.また,本書を刊行するにあたりご協力いただいた医学書院の石井美香氏ほか各位にも心より御礼申し上げます.
この書籍を多くの若手医師にご活用いただき,外傷整形外科治療のレベル向上に寄与できればこの上ない幸いです.
2024年2月
土田芳彦
目次
開く
1章 肩
鎖骨骨幹部骨折
T's Column 昔,ほとんどの鎖骨骨折は保存的に治療していた
鎖骨遠位端骨折
肩鎖関節脱臼
T's Column 知らない罪/鎖骨遠位部のフックプレート
肩峰骨折
T's Column 未発達な肩甲骨骨折治療
上腕骨近位部骨折valgus impacted fracture
T's Column 至適アプローチは変化する
2章 上腕・肘
上腕骨近位部骨折に対する髄内釘固定
鉤状突起基部骨折を合併した尺骨肘頭骨折
T's Column なぜ肘関節前方アプローチを嫌がるのか?
不安定性を伴う肘関節脱臼骨折terrible triad injury
T's Column 巨人の肩の上に立つ/守・破・離
橈骨頭頚部骨折
T's Column やはりできれば骨接合術を
上腕骨近位部骨折に対する人工関節置換術
T's Column RSA規制のよい面と悪い面
上腕骨遠位骨幹部骨折
T's Column MIUT法を開始した頃
Galeazzi骨折
T's Column Galeazzi骨折の苦い思い出
3章 手・手関節
Bennett骨折
PIP関節背側脱臼骨折
T's Column PIP関節背側脱臼骨折は手外科専門医の登竜門?/Beak ligamentの重要性
手指基節骨骨折
T's Column 基節骨粉砕骨折治療の悩み!
橈尺骨遠位端開放骨折
T's Column 開放骨折のデブリドマンで思うこと
橈骨遠位端関節面粉砕骨折
T's Column 橈骨遠位端関節面粉砕骨折はこだわりの世界
手指末節骨開放骨折
T's Column たかが末節骨,されど末節骨
第5中手骨頚部骨折
T's Column 拳がなくなった?
4章 小児
小児Monteggia 骨折
T's Column Monteggia骨折が肘内障になる
小児上腕骨顆上骨折
T's Column 有用なall at one time reduction法
小児上腕骨内側上顆骨折
T's Column 小児上腕骨内側上顆骨折の保存治療
小児大腿骨近位部骨折
T's Column 小児大腿骨近位部骨折はまれ!
小児脛骨骨幹部骨折
T's Column 見直されるエンダー釘
5章 大腿骨・股関節
転位型大腿骨頚部骨折
大腿骨頚基部骨折
T's Column 頚部骨折インプラントの変遷/秀逸な前額面剪断型骨折という概念
外弯を伴う大腿骨転子下骨折
T's Column 最終手段としての髄内骨切り
大腿骨遠位端骨折に対するダブルプレート固定
T's Column 常に髄内釘固定が第一選択
大腿骨逆行性髄内釘後インプラント周囲骨折
T's Column 二次骨折を強く意識する
大腿骨順行性髄内釘後インプラント周囲骨折
T's Column アルゴリズムに従って治療する危険性
不安定型大腿骨転子部骨折
T's Column 大腿骨転子部骨折における中野分類
髄腔の狭い大腿骨骨幹部骨折
T's Column 髄内釘挿入時のスタック/日本の救命救急センター事情
大腿骨骨幹部骨折に対するdamage control orthopedics
人工骨頭術後ステム周囲骨折
T's Column 骨折専門医と人工関節専門医
前額面剪断型大腿骨頚部骨折
T's Column Cement augmentationの威力
6章 膝関節・脛骨
ステム付きTKA 周囲大腿骨骨折
T's Column プレートの適応外使用?
膝蓋骨骨折
T's Column 実力の差が表れるTBW固定法
脛骨骨幹部骨折における髄内釘治療
T's Column 辛かったinfrapatellarアプローチ
脛骨遠位骨幹部骨折
T's Column 固定インプラント選択の変遷!/これは本当にコンパートメント症候群?
コンパートメント症候群と脛骨骨幹部開放骨折
脛骨プラトー両顆骨折bicondylar fracture
T's Column ジョセフ・シャッカー先生の『骨折』
後内側・後外側骨片を伴う脛骨近位部骨折
T's Column 何を選択するのか? 臨床のセンスが問われている/感染症治療に王道なし
脛骨感染性偽関節
7章 足部・足関節
踵骨骨折
T's Column ロジックによる治療
踵骨開放骨折
T's Column 砂のような踵骨
両側踵骨骨折
T's Column 踵骨骨折全例に「大本法」を施行するべきである
第5中足骨骨幹部骨折
T's Column アジア人にはフット用プレートはサイズが大きい
Pilon骨折①
T's Column Pilon骨折治療は軟部組織損傷との戦い
Pilon 骨折②
T's Column 関節面整復には「基準」が必要である
母趾末節骨骨折
T's Column 治療は類似部位のものを応用する
足関節骨折 TypeC
T's Column 後果固定の意味
8章 骨盤
脆弱性骨盤骨折
T's Column FFPは急に増えた?
索引
書評
開く
本書を熟読し,これからの診療に臨んでほしい
書評者:最上 敦彦(順天堂大静岡病院先任准教授・整形外科学)
編者の土田芳彦先生は,小生の旧来の友人であり,ともに還暦を過ぎた同級生であり,そしてともに外傷整形外科の分野で戦ってきた戦友である。「土田芳彦」といえば,言わずと知れた日本を代表する外傷整形外科医である。とりわけマイクロサージェリーを駆使した重度四肢外傷治療の先駆者で,その知的戦略は『重度四肢外傷の標準的治療―Japan Strategy』(南江堂)として2017年に出版され,今や日本の重度四肢外傷治療のバイブルとして多くの外傷整形外科医の手元に置かれていることであろう。
今回,この重度四肢外傷とは別に,一般整形外科外傷を対象にした本書『クリニカル・クエスチョンで考える外傷整形外科ケーススタディ』が刊行された。本書は新型コロナウイルス感染症が広がる2022年初頭の3ヶ月間,土田先生のコーディネートで開催されたwebセミナー「症例と文献に学ぶ外傷整形外科」の内容を基に構成されている。上・下肢全般52項目にわたる外傷を,4人の新進気鋭の整形外科外傷医 佐藤和生先生,佐藤亮先生,髙田大輔先生,伊澤雄太先生が分担執筆している。いずれも土田先生がセンター長を務める湘南鎌倉総合病院・札幌東徳洲会病院の外傷センターで直接指導を受けた,まさに「愛弟子」である。
本書では,まず代表的症例が提示され,次いでその症例に応じた臨床的疑問(Clinical Question)が列挙され,執筆者はこれに対する文献的考察(Evidence)から読み解いた治療戦略を解説する。最後に臨床家(土田先生)の視点から文献と実践との溝を埋めるような内容を加えることで,必要なスキルを各ケースから手に入れられる構成となっている。随所に散りばめられたコラム(T’s Column)には,土田先生の本音が見え隠れして一興である。
ちなみに本書の元ネタとなるwebセミナー「症例と文献に学ぶ外傷整形外科」は,土田先生が主催するホームページ「湘南・札幌外傷整形外科研究所」(http://sotc.kenkyuukai.jp/,または「湘南・札幌外傷整形外科研究所」で検索)にアーカイブ動画が収録されている(http://syoreitobunkennimanabu.kenkyuukai.jp/member/society_entry.asp)。試しに本書を開きながら,アーカイブ動画を見てみた。すると,テキストを手にweb講義を視聴している気分になるのと同時に,本文には収まりきらない情報や土田先生と演者のやり取りの中に考えるヒントが隠れていて,極めて有効な利用法と思われた。読者の皆さんもぜひ試してみていただきたい。
本書に取り上げられた整形外科外傷はいずれも一般整形外科医が日々の診療で遭遇する頻度の高い外傷であり,本書の内容はこれを治療する医師にとって必須の知識である。日本の整形外科手術の約半分を整形外科外傷が占めると言われて久しい。よって,本書が出版された以上,もはや「知らぬ存ぜぬ」は通用しない。本書を熟読し,これからの診療に臨むことが,日本の整形外科医に求められている。
治療の最適解へのアプローチ指南書
書評者:野坂 光司(秋田大大学院准教授・整形外科学)
史上最高の外傷整形外科テキストでした。全368ページでしたが,飽きのこない小説のようで,あっという間に読み終えました。
さすがは「日本の外傷整形外科の巨人」土田芳彦先生の作品です(テキストというよりは作品と呼んだほうがしっくりくる内容です)。共同執筆は土田先生の薫陶を受けた4人の若き外傷整形外科医(若武者)たちです。本書は,若武者が整形外科外傷に立ち向かう際,さまざまに抱かれる疑問,戦い方(治療方針)と考察が提示されます。それに対して一つひとつ,百戦錬磨の軍師(指導医)が丁寧にその戦い方を説き,そして熱くディスカッションしているかのように進んでいく様が小気味よかったです。
全体を通して,質の高い症例報告であり,手術手技書であり,エビデンスに基づいたレビューであり,最新の治療アルゴリズムも取り上げてくれています。そして医学書であると同時に深い哲学書であり,エッセイです。さらに全体として入門編であり,応用編であり,要点と盲点までが見事にぎっしりと詰め込まれていました。
四肢外傷から小児,骨盤骨折の8つの大項目があり,各項目は細分化され,症例提示,クリニカル・クエスチョン,文献考察と,臨床家の視点という土田先生の解説が詳しく書かれています。そして,小項目には土田先生により計45個のコラムが書かれています(これが実に面白く,秀逸です)。
本書の特長として,手術中の展開時の外観写真や整復操作の透視画像などがふんだんに盛り込まれていて,視覚的にもわかりやすいことが挙げられます。どんなに綿密に術前計画を立てても,うまくイメージできないことがあり,論文やテキストを見ても詳しいところまでは書かれていないことが少なくありません。本書は「見たかったそのイメージ」がこれでもか,これでもかと散りばめられています。
トップナイフの手術見学をし,こういうやり方があるのか!と目からうろこが落ちることがあります。難治症例に悩み,苦しいとき,症例報告の一枚のX線によって道が開けることがあります。本書はその連続でした。
コラムの一つに「アルゴリズムに従って治療する危険性」というものがありました。「アルゴリズムは基本的に二者択一で進んでいくが,この選択が曖昧である。また,アルゴリズムに当てはめようとして,思考が停止している医師に遭遇することは多い。原則に立ち帰らなければならない」という内容です。これにはハッとさせられ,難治症例ほど患者さんへの愛と,治療者のしっかりとした哲学の大切さを改めて感じました。
治療の最適解へのアプローチ指南書として,私を含め,整形外科外傷に携わる第一線の外傷医には必携本ですが,コールドサージェリーしかやらなくなった先生,外来しかやらなくなった先生にもぜひ手にしていただきたい一冊です。忘れかけていた熱い魂を呼び起こされると思います。読み物としても読み応えがあります。「百聞は一見に如かず」です。
重度四肢外傷を治すプロフェッショナルである土田先生の生き様を見せられた気がしました。常に歩みを止めず,より良い方法と環境づくりを探求し,進化し続ける大切さが溢れていました。
文献と実践の溝を埋めてくれる書
書評者:善家 雄吉(産業医大病院外傷再建センター部長)
著者の土田芳彦先生は整形外傷界で知らない人はいない著名な先生です。私自身は15年以上前より数多くのセミナーや学会で教えを乞うてきました。実際に一緒に働いたことはありませんが,尊敬する先生の代表格です。先生の知的好奇心は際限なく,常に最良の医療を行うために尽力されてこられました。近年はオンラインセミナーの開催に注力され,数多くの会を自ら主催し,事前・事後検討を重要視した「教育」を展開されています。
2021年1月から1年間,北大整形外科後期レジデントを対象にした外傷整形外科のウェブカンファレンスが行われました。これは症例を通して若手の疑問に答えるという形式でしたが,私も時間が許せばオンラインで聴講していました。好評だったことにより,その後「症例と文献に学ぶ外傷整形外科」というオンラインセミナーとして再編されました。このセミナーは,本書の執筆者である佐藤和生,佐藤亮,髙田大輔,伊澤雄太の4人の先生たちが「提示症例」に対して解説プレゼンを行い,土田先生がコメントするというとても教育効果の高い素晴らしい企画でした。その内容はオンラインサロンでも討論され,多くの先生が勉強されたことと思います。
本書はその企画の書籍化であり,外傷整形外科の各領域(8章)で構成されています。それぞれの部位で代表的な症例がほぼ網羅されており,それぞれの「臨床的疑問」に対して文献的考察を述べた後に,臨床家の視点やコラムで語られます。若手のうちは経験が少ないため,教科書や論文から知識を蓄えます。治療の選択に当たっては「根拠」が必要になってきますので,文献は重要な情報源です。一方で,四肢外傷のように多様性に富むものに関しては「現場主義」や「経験主義」に頼らざるを得ない側面も多々あります。
本書は,文献と実践の溝を埋めるようによく考えて作成されている点が斬新であり,内容も素晴らしく洗練されています。それぞれの外傷ごとに,多くの臨床画像やイラスト,文献から引用されたデータやグラフも掲載されているため,ビジュアル的にとても見やすく,容易に理解できるようになっています。また,さらに理解を深めたい場合には,多くの引用文献を掲載してくれている点も志のある者にとっては非常にありがたいことです。随所に土田先生の「臨床家の視点」と「コラム」が散りばめられており,肩肘張らずに読み進めて行くことができる点もうれしいです。
本書は,外傷整形外科が専門の先生のみならず,最近の外傷整形外科をアップデートしたい多くの先生にもぜひ一読をお薦めしたいと思います。
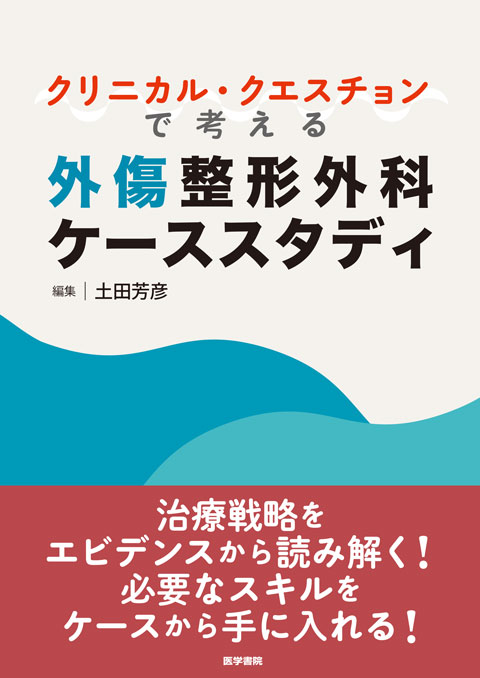
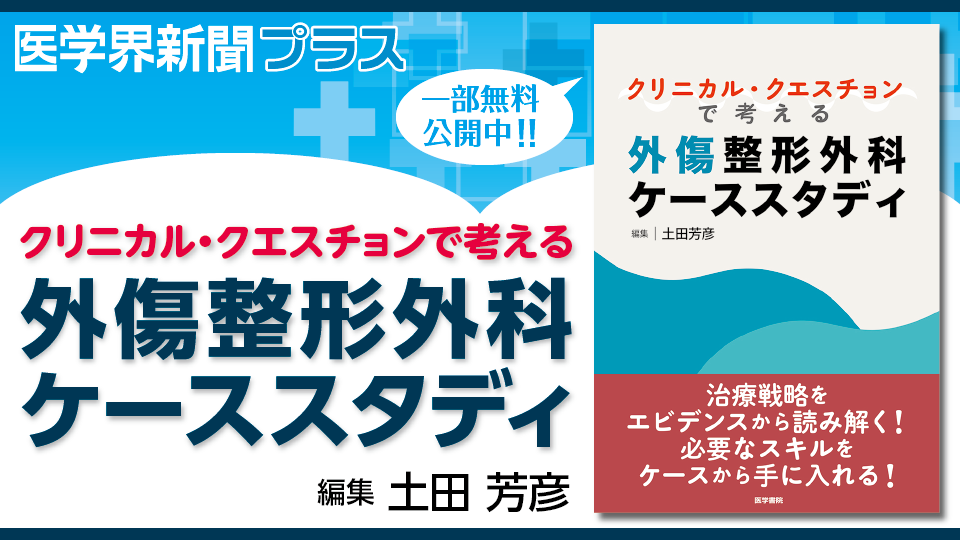
![AO法骨折治療[英語版Web付録付] 第3版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/2016/0672/1800/106445.jpg)
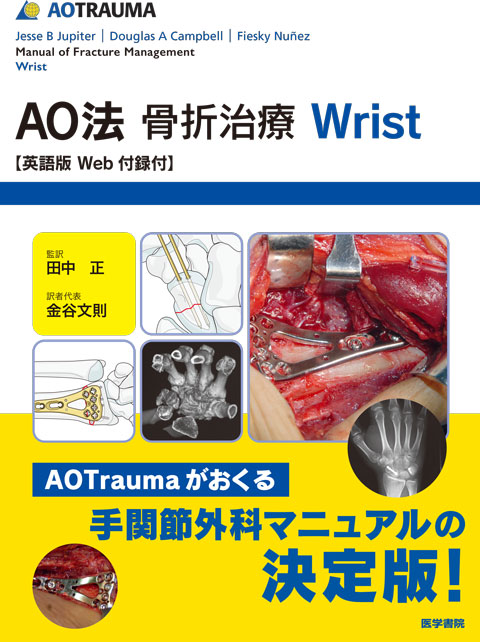
![AO法骨折治療 Foot and Ankle [英語版Web付録付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/5616/8248/3611/110660.jpg)