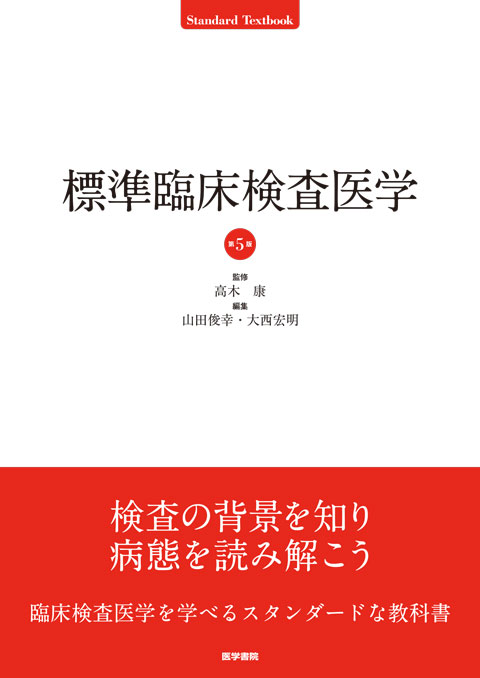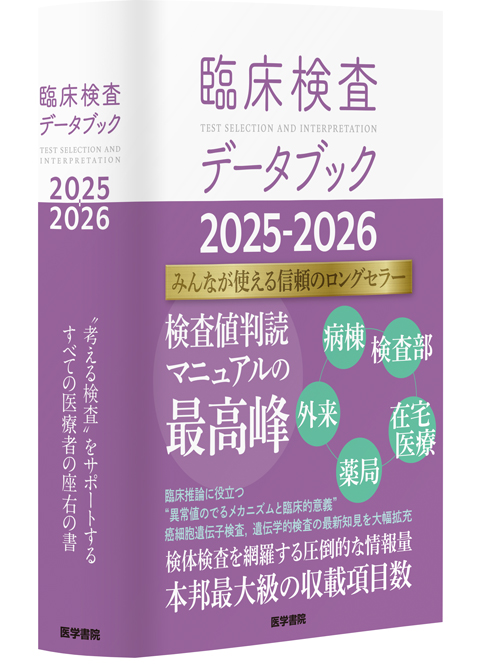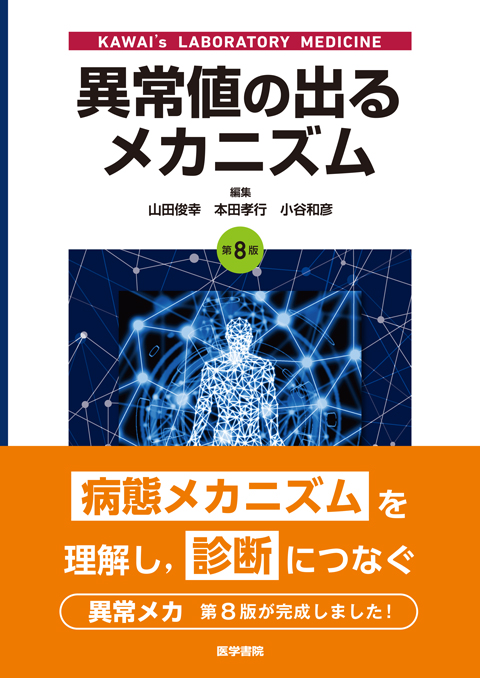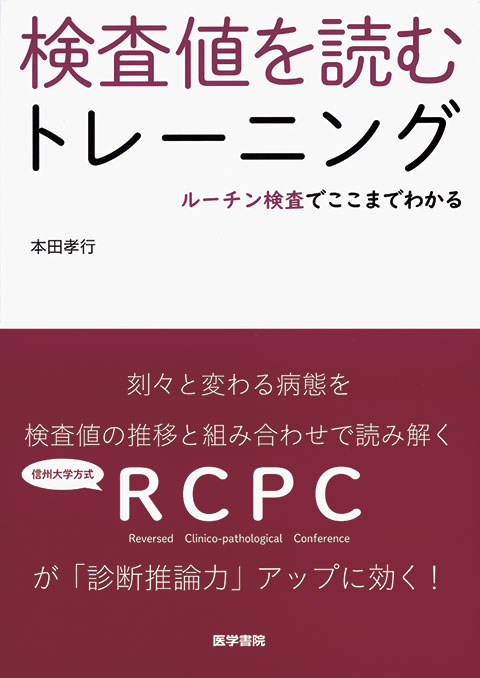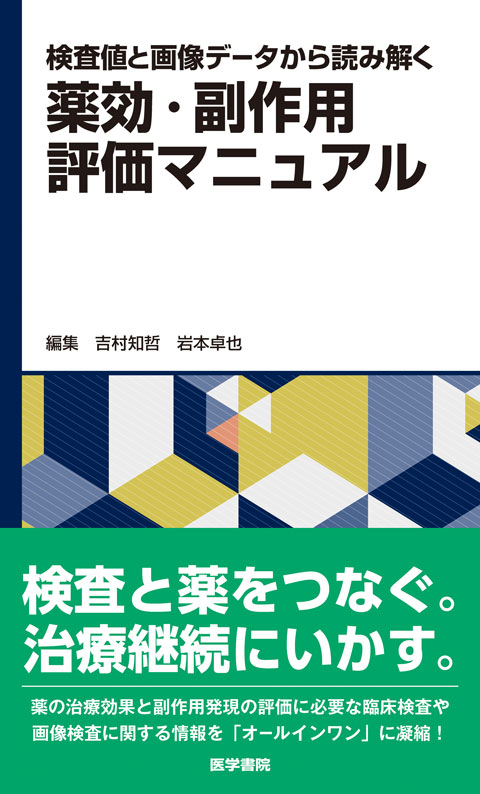標準臨床検査医学 第5版
基本的な検査項目をバランスよく学べる教科書
もっと見る
臨床検査医学は臨床医学の基本であり、すべての医師の必須知識である。その範囲は広く、深い。本書は臨床検査医学総論、検体検査と生理検査の基礎医学的背景、異常値のもつ意義を解説する。現在の臨床で“いつでもどこでも”使われる基本的な検査を扱い、「全体の理解を助けるために」の項により学習内容を俯瞰したうえで、検査の選択と判断、異常値の出る病態と機序を示す。臨床検査医学をバランスよく学べる唯一無二の教科書。
| ● | 『標準医学シリーズ 医学書院eテキスト版』は「基礎セット」「臨床セット」「基礎+臨床セット」のいずれかをお選びいただくセット商品です。 |
| ● | 各セットは、該当する領域のタイトルをセットにしたもので、すべての標準シリーズがセットになっているわけではございません。 |
更新情報
-
2025.04.23
-
正誤表を掲載しました。
2023.08.21
- 序文
- 目次
- 書評
- 正誤表
序文
開く
第5版 序
本書は1987年に初版が上梓され,長く臨床検査医学の代表的な教科書の一つとして活用されてきた.2013年に第4版として改訂され10年が経過した.医学・医療の進歩は領域を問わず目覚ましいものがあり,臨床検査医学においても,新しく登場した検査,グローバル化にあわせた検査法・検査値の変更,有用性の低下により実施されなくなった検査など検査項目の変遷以外にも,基準範囲と臨床判断値の用語をめぐる混乱,共用基準範囲の勧奨など臨床検査医学の総論的な部分が社会的に注目された.そして何と言っても新型コロナウイルス感染症における臨床検査の重要性が毎日のように語られるようになり,PCR検査,抗原検査,抗体検査,偽陰性,偽陽性などの用語が一般に浸透するようになった.以上のような流れに鑑み,第5版として改訂することとなった.
本書は,「基本的な検査項目への理解を深める」,つまり,いつでもどこでも行われる基本的検査につき,その基礎医学的な背景と異常な成績のもつ意義の学修を重要視している.『病態から検査』ではなく『検査から病態を読む』ことで,例えば予想外の検査成績に遭遇した場合に対応可能になるであろう.
第5版の構成は,若干の章立てを変更した以外は第4版を踏襲した.前版改訂時から大きく変化が生じた部分については,躊躇なく新知見を読者の学修の利便に供した.基本事項の羅列では理解が不十分であった部分について,詳細な解説を読むことでより理解が深まることが期待される.一人ひとり異なる背景をもつ患者に奉仕する医療人として,臨床上の疑問に対し自ら考え最善の対応策を導き出すことは,人工知能が隆盛する時代となっても変わらず備えるべき医療者の矜持であり,それを支えることが教科書の最大の役割であろう.また,診療ガイドラインにおいて臨床検査が主要項目となることが増えており,それと齟齬のないよう各種ガイドラインをふんだんに取り入れるとともに,勿論,医師国家試験出題基準も重要視した.
執筆は原則として全国の大学において臨床検査医学の卒前教育を担当している臨床検査専門医にお願いした.多くの章で新たな執筆者を迎えることができた.
本書の主たる対象は医学生であるが,それ以外にも,研修医,検査を専門としない医師,臨床検査技師・薬剤師・看護師ほか医療スタッフの方々にも役立てていただけるように,平易過ぎず,難解過ぎずの教科書を目指した.多くの方に活用いただけたら幸いである.
2022年12月
編者ら
目次
開く
第I編 臨床検査医学の基礎
“臨床検査医学の基礎”の構成マップ
第1章 臨床検査の基礎
A 検査の意義と目的
B 検査の種類と特性
C 検査の有用性と効率性
D 基準値と臨床判断値(病態判別値)
E 検査の誤差と精度管理
F 検査結果の解釈
G 検査における医療安全
第2章 検体の採取と保存
A 検査値の生理的変動
B 採血手技による検査値への影響
C 各種検体の採取
D 採血管および添加物の特徴と使用法
E 検体の保存・運搬と安全性
第II編 検体検査
“検体検査”の構成マップ
第3章 血液学的検査
A 血球検査
B 血栓・止血関連検査
第4章 生化学検査
A 蛋白
B 非蛋白窒素
C 色素
D 酵素
E 心筋マーカー/心筋ストレスマーカー
F 脂質・リポ蛋白
G 糖尿病関連検査
H 内分泌
I 電解質
J 重金属ならびに関連蛋白
K ビタミン
L 腫瘍マーカー
M 血中薬物・毒物と代謝産物
第5章 免疫血清学検査
A アレルギー
B 細胞性免疫・サイトカイン
C 自己抗体
D 補体
第6章 微生物学検査
A 微生物学検査の位置付けと現状
B 検体の採取法
C 検査法の実際
D 各病原体による感染症と検査方法
第7章 一般検査
A 尿検査
B 糞便検査
C 脳脊髄液検査
D 穿刺液(胸水・腹水)検査
E 喀痰検査
F その他の穿刺液,分泌液検査
第8章 細胞診
A 細胞診の意義
B 細胞診標本の作製
C 細胞診の判定
第9章 輸血・移植関連検査
A 献血に際して行われる検査
B 血液型検査
C 不規則抗体スクリーニング
D 交差適合試験
E Coombs(クームス)試験(抗グロブリン試験)
F 輸血副反応と診断のための検査
G 輸血準備の実際
H HLA検査
第10章 染色体検査・遺伝子検査
A 染色体検査
B 遺伝子検査
第III編 生理検査
“生理検査”の構成マップ
第11章 呼吸機能検査
A 換気機能に関する検査
B ガス交換機能に関する検査
第12章 循環機能検査
A 心電図検査
B 心音図検査
C 脈波検査
D 心臓超音波検査
第13章 腹部と体表臓器の超音波検査
A 腹部超音波検査
B 体表臓器超音波検査
第14章 神経系の電気生理学的検査
A 脳波
B 筋電図
C 末梢神経伝導検査
D その他の神経系電気生理学的検査
付録1 主要症候・検査による鑑別チャート
付録2 図解 検査手技
付録3 JCCLS 共用基準範囲
付録4 医学教育モデル・コア・カリキュラムとの対照表
付録5 医師臨床研修の到達目標との対照表
付録6 MCQ(multiple choice question)
和文索引
欧文索引
書評
開く
臨床検査医学を学ぶ人のための教科書の決定版
書評者:村上 正巳(群馬大名誉教授)
臨床検査医学は,全ての診療科に関連した医療の根幹をなす学問分野で,医療のどのような専門領域においてもその知識と素養は不可欠である。診療においては通常,医療面接と身体診察を行い,必要な検査を実施し,診断,治療が行われ,治療後の経過観察においても検査が実施される。臨床検査は,画像検査とともに診療に必要・不可欠なツールである。
『標準臨床検査医学』の初版は1987年に上梓され,臨床検査医学の代表的な教科書として版を重ねてきた。2013年に第4版が刊行されてから10年が経過し,今回版を新たにしたことは大きな意義がある。この10年の間にわが国の臨床検査を取り巻く環境にさまざまな変化がみられた。2018年に検体検査の品質・精度の確保に関連した医療法等の一部を改正する法律が施行され,臨床検査の品質・精度を確保するための施設基準や方法が明確化されるとともに,遺伝子関連検査・染色体検査が一次分類に位置付けられた。また,2019年に初めて報告された新型コロナウイルス感染症はパンデミックとなり,わが国においても医療提供体制の逼迫を招くなど未曾有の事態となった。新型コロナウイルス感染症の対策において,核酸検査や抗原検査などの検査法の開発と普及,検体採取の方法,検査精度の確保,検査試薬と機器の供給体制,臨床検査に携わる人材の育成など,臨床検査の課題と役割が広く一般に理解されるようになったものと思われる。
本書では読者の理解を助けるためのさまざまな工夫がみられ,今回の第5版からオールカラーとなり,ビジュアル面での充実が図られている。
第I編「臨床検査医学の基礎」では,臨床検査医学の総論として,臨床検査の基礎と検体の採取と保存に関して記述され,臨床検査全体を的確に過不足なく把握できる内容となっている。
第II編「検体検査」では,まず,“全体の理解を助けるために”として検査項目の基本的な事項が述べられ,検査項目の概要,基準範囲(基準値),異常値を示す疾患・病態とそのメカニズム,関連検査について理解を促すカラーの図表をふんだんに用いて説明されている。新型コロナウイルス検査など最新の情報も随所に盛り込まれ,近年のゲノム医療の進歩を反映して,染色体検査・遺伝子検査が全面改訂され,内容の充実が図られている。
第III編「生理検査」では,腹部と体表臓器の超音波検査の章が新設され,循環機能検査に脈波検査が加わり,神経系の電気生理学的検査に聴性脳幹反応,体性感覚誘発電位,視覚誘発電位が追加されるなど全面改訂されている。
付録では,主要症候・検査による鑑別チャート,図解検査手技やMCQ(multiple choice question)に加えて,新たに日本臨床検査標準協議会(JCCLS)共用基準範囲や医学教育モデル・コア・カリキュラムとの対照表が掲載され,読者の理解を助ける構成となっている。
本書は,医学生に最適の教科書であるのはもちろん,研修医をはじめとする医師,臨床検査技師,薬剤師,看護師ほかメディカルスタッフの方々に広く利用していただける内容となっている。本書を熟読することにより,臨床検査医学の近年の進歩とその奥深さを実感していただけるものと確信する。本書を活用し,臨床検査医学の基本的な知識と素養を身につけていただくことを切に願うものである。
ぜいたくな改良と増量が加えられた良書
書評者:前川 真人(浜松医大教授・臨床検査医学)
本書は1987年に初版が上梓されて以来,検査方法から結果の判読,そして異常値のメカニズム・病態との関連性にまで言及した内容が盛り込まれ,長きにわたり臨床検査医学の教科書として使用されてきた良書である。昨今の臨床検査医学は技術の進歩も相まって,新しい検査法や検査項目が生まれ臨床応用されてきたため,新しいコンテンツも含めて第5版が作成された。
「臨床検査医学の基礎」,「検体検査」,「生理検査」の3つに大別され,旧版と同様に,最初に構成マップとして概略が述べられているが,内容はより詳細にカラフルでエッセンスが抜き出され,これから新章に入る前だけでなく復習にも使いやすいと思われた。また,旧版では巻頭にカラーグラフなどがまとめられており使いにくさを感じていたが,新版では説明のある本文中適所に掲載されており,教える側も学習する側もストレスなく使用でき,改善されたと評価できる。
新版で追加された情報を少し紹介したい。第1章ではパニック値に関する説明がされている。パニック値が臨床に適切に伝えられなければ医療過誤の危険性が高くなる重要な案件である。第2章では採血(使用する採血管)の順番についても理由を含めて詳細に説明されていた。第3章から始まる検体検査では,検体の採取から検査結果に影響することを教えるのは重要である。第6章ではSARS-CoV-2の検査が加えられた。ウィルス抗体価の評価と予防接種との関係性も加えられ,職業感染防止に有用な情報となる。第10章では遺伝子関連検査に関する記述が大幅に増えた。がんゲノムプロファイル検査やリキッドバイオプシーについても言及されている。昨今のゲノム医療への期待からはこれでも物足りないかもしれないが,全体のバランスから考えるとやむをえないだろう。生理検査の中では,第13章として腹部と体表臓器の超音波検査が新しく取り上げられた。超音波検査機器も大きく進歩したので,待たれていた新章であろう。第11章の呼吸機能検査ではPOCTなど簡易検査機器についてもカラー写真付きで例示されていた。検体検査系でもPOCT機器は多く活用されているので,それらの紹介や注意点などについてももっと増やしてもよいかと思われた。また,小さな章立てか付録としてとりまとめてもよいかもしれない。付録は,検査結果による病態の鑑別チャートや検査手技に,JCCLS共用基準範囲などが新しく追加され,さらに充実がみられる。Advanced Studiesの記載も増え,この内容からも10年間の臨床検査の進歩と変革が窺えて,旧版と読み比べるとおもしろかった。
このようにぜいたくな改良と増量が加えられた本書,医学生のみならず,いろいろな医療スタッフの方にも手元に置いてもらいたい一冊として,強くお薦めしたい。
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。