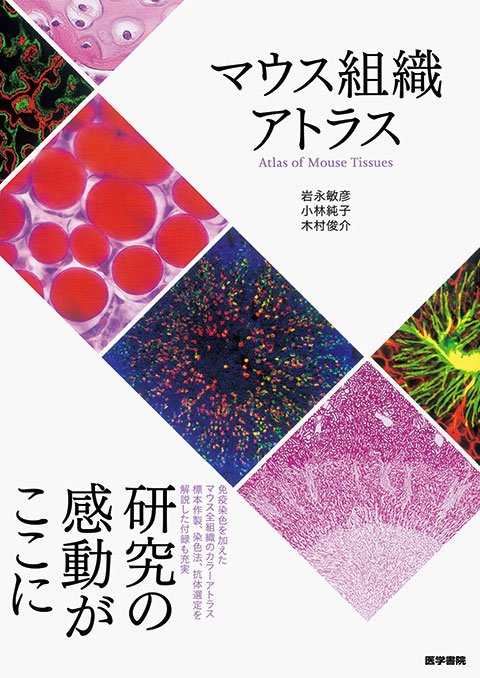標準組織学 総論 第6版
美しい写真の数々で読者を圧倒する組織学の最高峰テキスト総論編,待望の改訂第6版
もっと見る
読んで面白く、わかりやすい教科書として絶大な支持を獲得している『標準組織学』。本書は、細胞と組織の概念から神経組織までを収載した「総論」編の改訂第6版。読者を圧倒する高いクオリティの組織写真やイラストは、今改訂でも健在。実習に役立つHE染色などの光顕写真も多数追加した。科学史に残る研究者たちの発見の物語も随所で紹介。時代の要請に応え、分子レベル、遺伝子レベルの新知見もカバーした最高峰のテキスト。
| ● | 『標準医学シリーズ 医学書院eテキスト版』は「基礎セット」「臨床セット」「基礎+臨床セット」のいずれかをお選びいただくセット商品です。 |
| ● | 各セットは、該当する領域のタイトルをセットにしたもので、すべての標準シリーズがセットになっているわけではございません。 |
更新情報
-
2025.04.23
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
第6版 序
自国の教科書をもつことの意義やメリットは大きい。少なくとも翻訳に伴う表現のぎこちなさは避けられる。また,日本人の業績を顕彰し,日本人の高い研究レベルを示すことができれば,医学生に勇気を与えるであろう。この第6版の改訂においても,どなたかが言っておられた「『標準組織学』は組織学のバイブル」という言葉が確固たるものになるよう努力したつもりである。
研究の話になるが,論文を「mechanistic(メカニズムを解明するもの)vs. descriptive(記述的,説明的なもの)」と区別することがある。後者のほうは,現象や形態像を単に述べるだけで本質に迫っていないと,低くみられる傾向にある。組織学,形態学はこの記述的な要素が強い学問分野である。しかし,現象や形態像を正確に記述することこそが医学の基本になるのである。新しい研究分野や考え方は,まさに記述的な研究から始まり,その後物質や遺伝子を中心にしたメカニズムの解明に発展してきた。そうはいっても,本書を改訂するにあたりメカニズム的要素を視野に入れることは重要であり,免疫組織化学やin situ hybridization法,時には遺伝子改変動物により得られた最新の知見も取り入れるよう努力をした──十分ではないかもしれないが。一方で,これらは平易な記述となるように努めた。分子や遺伝子はつぎつぎと新しいものが見つかり,メカニズムの解釈も複雑化したが,厳選して紹介することにした。
他書にはあまり見かけない点として,サイズの小さな文字で記された小活字の部分が本文の随所に混在していることがある。通常サイズの部分よりは重要ではなく,補足的要素を含んでいると理解してほしい。また,以前より本書で使われていた「つけはなし(漢字や平仮名が続く場合など,意味がとりやすいように文字の間に狭い空きスペースをもうけること。この文の後半を参照)」は,読みやすくする工夫であるが,一般に なじみが薄いこともあり,今版では できるかぎり減らした。
この『標準組織学』は,当初から総論と各論の2分冊を維持してきた。しかし,過去をふり返ると,ボリュームのある2冊を同時に出版することは難しく,実現していなかった。購入する際に,同時に入手することが望まれることは十分想像できたので,今回の第6版ではそれを実現すべく苦労した。大人数で分担執筆すればその苦労は軽減するのであるが,できるかぎり少人数で作業するという初版以来の定めに従った。
今回の改訂でも,貴重な写真を多数提供していただき,また的確なアドバイスをいただいた。ここに改訂者一同深く御礼を申し上げる。とくに,かなりのボリューム,時には章単位でご協力いただいた方々のお名前をあげさせていただく(敬称略)。
染色体(広田 亨),軟骨・骨(中村浩彰),神経系(寺島俊雄,榎原智美)
また,前版と同様に,医学書院 医学書籍編集部の中 嘉子氏と制作部の富岡信貴氏にこの第6版改訂を担当してもらったことは,大きな安心につながった。こころから感謝したい。
2022年1月
改訂者ら
目次
開く
序章 細胞と組織の概念
虫めがねから電顕に至るまで
電子顕微鏡の登場
1 透過(型)電子顕微鏡
2 走査(型)電子顕微鏡
細胞の概念
組織の概念
1章 細胞の化学的性状
1 蛋白質とアミノ酸
2 糖質(炭水化物)
3 核酸
4 脂質
5 原形質の物理化学的性状
2章 細胞の構造と機能
細胞の概要
細胞膜
細胞小器官
1 リボソーム
2 小胞体
3 ゴルジ装置
4 ミトコンドリア
5 水解小体(リソソーム)
6 ペルオキシソーム
7 細胞骨格
8 中心体
鞭毛と線毛,微絨毛
基底陥入
封入体
細胞核
1 核膜
2 染色質
3 核小体
4 核基質
細胞の分裂
1 体細胞の細胞周期
2 分裂期と染色体
3 生殖細胞にみられる減数分裂
増殖と分化
1 増殖因子
2 細胞の分化
3 細胞の死
細胞の運動
細胞のとりこみ
1 のみこみ(パイノサイトーシス)
2 カベオラ
3 たべこみ
3章 上皮組織
上皮組織の分類
上皮細胞間の特殊分化
1 接着装置
2 ギャップ結合
3 細胞間のかみあい
腺
1 外分泌腺と内分泌腺
2 外分泌腺の分泌物による分類
3 外分泌腺の形態による分類
4 外分泌腺の終末部
5 外分泌腺の導管系
6 内分泌腺の形態による分類
7 内分泌細胞の分泌物による分類
8 腺細胞における分泌物の放出機序
4章 結合組織
支持組織の概要
結合組織の線維成分
1 膠原線維
2 細網線維
3 弾性線維
線維成分以外の細胞間質
1 グリコサミノグリカン
2 プロテオグリカン
3 基底膜
4 フィブロネクチンとインテグリン
結合組織の細胞成分
1 線維芽細胞
2 脂肪細胞
3 マクロファージ
4 樹状細胞
5 リンパ球
6 形質細胞
7 肥満細胞
8 好酸球(酸好性白血球)
9 色素細胞
さまざまな結合組織
1 疎性結合組織
2 密性結合組織(強靱結合組織)
3 膠様組織
4 細網組織
5 脂肪組織
6 弾性組織
5章 軟骨組織
ガラス軟骨
線維軟骨
弾性軟骨
軟骨の形成から老化まで
1 軟骨の発生,成長,再生
2 軟骨の老年性変化
6章 骨組織
器官としての 骨の構造
1 緻密骨の管系
2 ハヴァース系
3 層板の力学的構築
4 海綿骨の構築
5 骨膜と骨の再生,シャーピー線維
骨の細胞性要素
1 骨細胞
2 骨芽細胞
3 破骨細胞
細胞間質
1 コラゲン(膠原)細線維
2 線維間の物質すなわち基質
骨の発生
1 膜内骨化
2 軟骨内骨化
骨の成長と維持──リモデリング
1 長骨の成長
2 短骨の成長
3 頭蓋冠の扁平骨の成長
4 ハヴァース系の改築
骨の血管と神経
1 血管
2 神経
関節腔とその周辺
1 関節軟骨
2 関節円板と関節半月
3 滑膜
4 関節液
5 滑液包(滑液鞘)
7章 血液,リンパおよび組織液
血液
1 赤血球
2 白血球
3 血小板
4 血漿
リンパ
組織液
血球の発生
1 造血の場
2 血球発生の過程
8章 筋組織
平滑筋
1 平滑筋線維=平滑筋細胞
2 平滑筋の結合組織
3 平滑筋の神経
4 平滑筋の発生と再生
骨格筋
1 骨格筋線維=骨格筋細胞
2 器官としての骨格筋
3 骨格筋の神経終末
4 骨格筋の発生,成長,再生
心筋
1 心筋線維=心筋細胞
2 心房筋の内分泌
3 心筋の結合組織,血管,神経
4 刺激伝導系
5 心筋の発生,成長,肥大,再生
9章 神経組織
神経細胞
1 神経細胞の形態
2 神経細胞の構造
3 神経線維の さや
4 神経終末の形態
神経膠細胞
1 上衣細胞
2 星状膠細胞
3 希突起膠細胞
4 小膠細胞
5 衛星細胞
6 シュワン細胞
血液脳関門
神経組織の発生
神経組織の再生
付録 組織学の研究法
組織切片標本の作製
染色法
特殊な観察法
組織化学
物質と細胞の追跡法
電顕用試料の作製
新しい顕微鏡
組織培養
和文索引
欧文索引
人名索引
書評
開く
美しい形態像から始める組織学学習の第一歩
書評者:内山 安男(順大老人性疾患病態・治療研究センターセンター長)
藤田・藤田の『標準組織学』は,総論と各論からなる大冊です。教科書は,その時点で科学的に事実と認められている事象を基に書き上げることが必要です。これを徹底すると,教科書ほどつまらない読み物はありません。しかし,個人で書き上げる教科書は,事実に基づく記載に独自の味付けをすることで面白くなると考えられます。今や故人となられた藤田恒夫先生と藤田尚男先生の手による『標準組織学』は,その典型であると思います。
藤田恒夫先生が本書第4版の執筆時,岩永敏彦先生に多くを依頼されていたことを記憶しています。版を重ねるごとに,岩永先生の免疫組織細胞化学の技が随所にちりばめられるようになりました。岩永先生は,藤田恒夫先生の下で,免疫染色を武器に消化管をはじめさまざまな領域のペプチドホルモン産生細胞(脳腸ペプチドホルモン)の研究を進めてきました。その後,独立して北大に移り,獣医学部,医学部と経験され,第5版で『標準組織学』の改訂者になられています。本書はフォローしている論文の数だけでも膨大です。この5~7年間で,新たに加える事項と切り捨てる事項を調べるだけでも大変な作業です。藤田恒夫先生は科学者であるとともに文筆家でもあり,非常にたくさんの本を世に出されました。岩永先生も形態関連の本を出版されていますが,筆まめな先生でないと,この大著を仕上げるのは至難の業かもしれません。
第6版の改訂では章構成はほぼ変わりませんが,内容は,かなり踏み込んで手を入れられています。岩永先生は総論の序で,「形態を主にした研究はdescriptive(記述的)で物事の本質に迫ることができず,mechanistic(メカニズムを解明するもの)な研究より低くみられる傾向にある。しかし,現象や形態像を正確に記述することこそが医学の基本である」という趣旨のことを述べられています。本書の電子顕微鏡像,光学顕微鏡像,免疫組織細胞化学的染色像は,どれをとっても美しい像ばかりです。これは科学的な思考力を要求される若き学徒にとって,重要な刷り込みになります。美しい形態を見ると,細胞の中の小器官が何かを語りかけてくれるような,そんな感覚にとらわれます。これが組織学学習の第一歩であると思います。
第6版では,共著者の方々の特徴も十分に反映されています。読みやすい,わかりやすい,さらに高度な内容も含む教科書を一人で作り上げることは,不可能に近い話です。本書も,総論では岩永ひろみ先生,小林純子先生が,各論では渡部剛先生が共に改訂者となっています。そして諸所で素晴らしい仲間の手による章もあり,内容をより豊かにしています。
本書は,組織形態学に分子細胞生物学的要素を随所に取り込んだ教科書です。若い学生が本書を読み込むことで,形態科学の歴史的な背景を知ることができ,読み物としても一級品です。学部学生のみならず,院生や若き研究者にとっても手元に置いておきたい教科書の一つです。
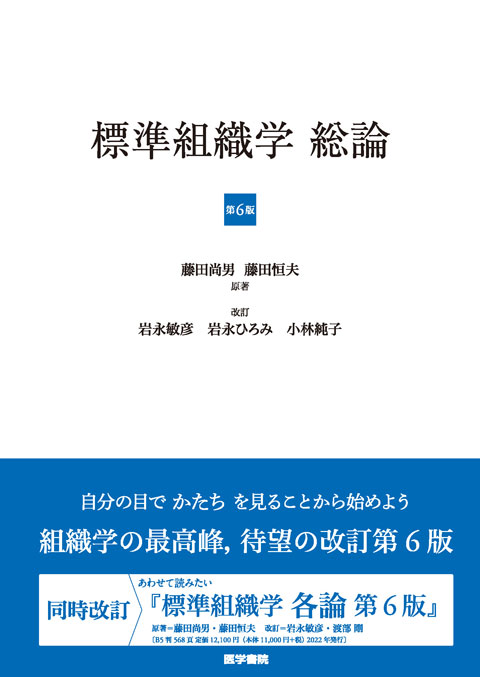

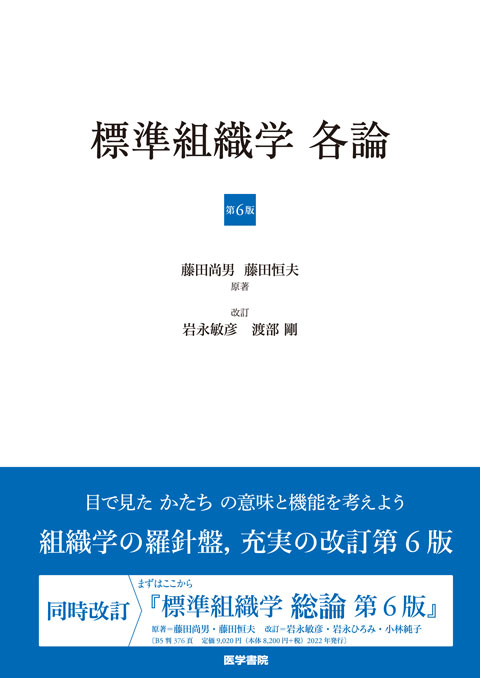
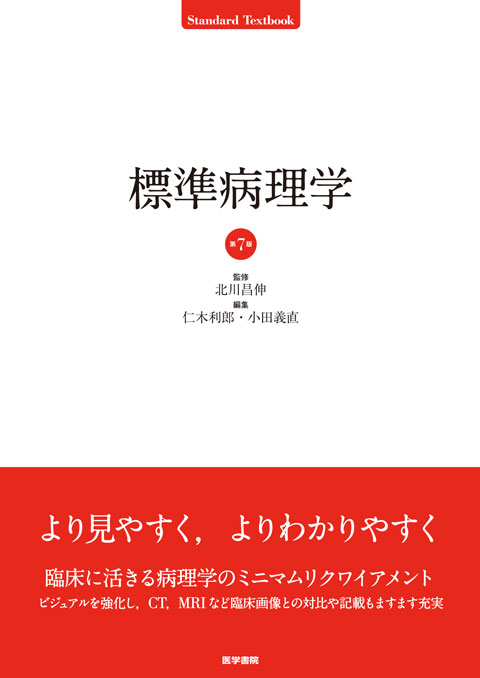
![組織病理カラーアトラス[Web付録付] 第3版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/8816/1881/2522/108972.jpg)