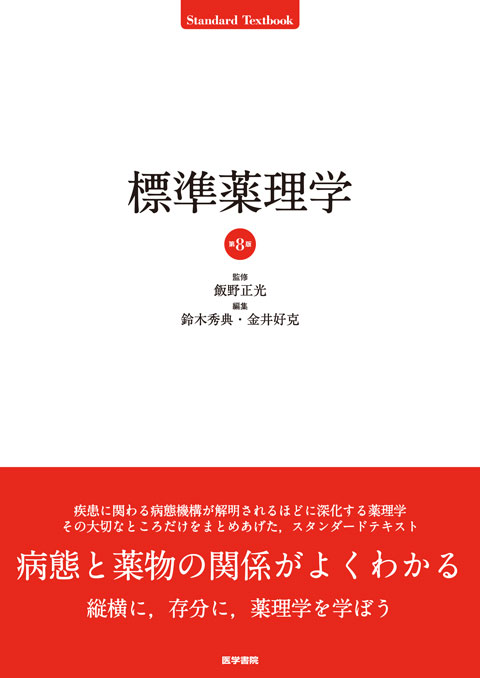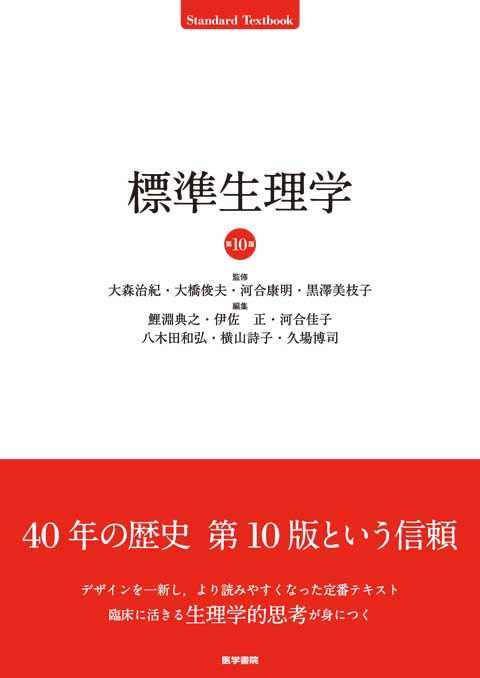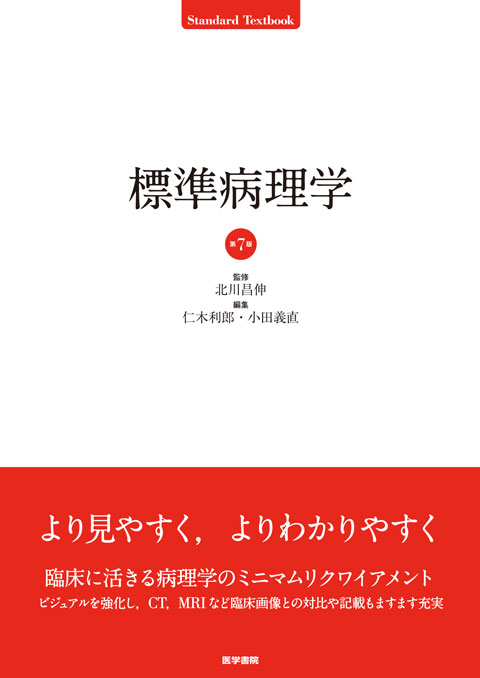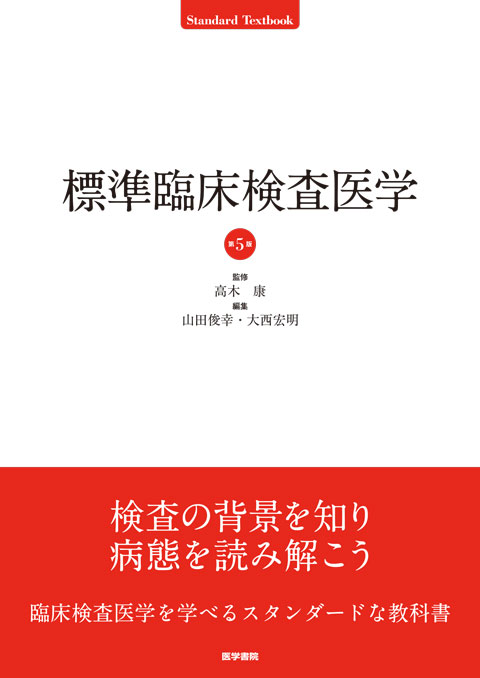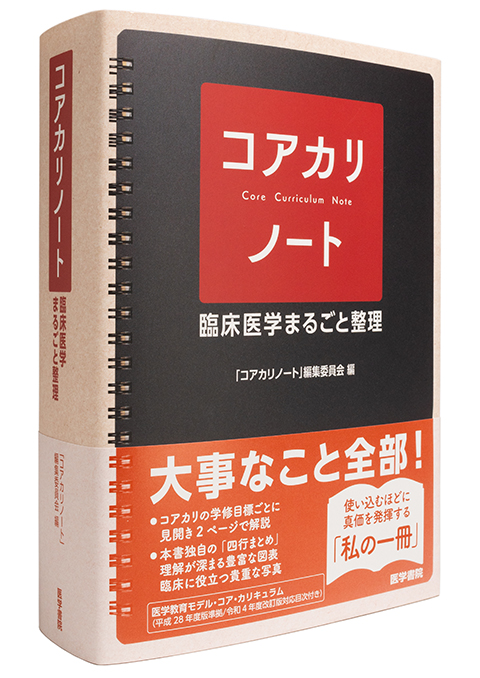標準薬理学 第8版
病態と薬物の関係がわかる、医学生向けテキスト。この1冊で縦横に、薬理学を学ぼう!
もっと見る
薬物治療の基本概念を学ぶ薬理学は、疾患に関わる病態機構が解明されるにつれて深化・複雑化するようにみえる。本書は医学生を対象にその大切なところをまとめあげたスタンダードテキスト。基礎的な内容と合わせ、薬物を臨床応用する際に必要な概念も解説。病態と薬物の関係がよくわかる。改訂第8版では新章「内因性情報伝達物質」において生理活性物質を化学構造に基づいて整理した。この1冊で縦横に、存分に、薬理学を学ぼう!
| ● | 『標準医学シリーズ 医学書院eテキスト版』は「基礎セット」「臨床セット」「基礎+臨床セット」のいずれかをお選びいただくセット商品です。 |
| ● | 各セットは、該当する領域のタイトルをセットにしたもので、すべての標準シリーズがセットになっているわけではございません。 |
更新情報
-
2025.04.23
- 序文
- 目次
序文
開く
第8版 序
今回の標準薬理学第8版は大幅改訂であった第7版を土台にその方針を引継ぎ,若手の執筆者も加わり内容を刷新するとともに,新たな視点に立つ章を設けた.
本書の特徴である3編構成は堅持している.第I編では,薬理学の基本となる概念とともに薬理学を学ぶことの意義を解説した.第II編は,薬理作用を理解するうえで重要となる細胞機能制御メカニズムを整理して概説した.これら2編の基盤に立って,第III編では主要な治療薬について解説した.また,各章の記述に関連がある場合,可能な限り互いを参照できるようガイドを挿入した.第I,II編の冒頭と第III編の各章の冒頭に構成マップを設け,何を学ぶのかについて視覚的にも把握できるようにすることは第7版から継続して行った.
従来,薬理学の教科書では,薬理作用や受容体を中心にして解説することが主流で,神経伝達物質やホルモンなどの生理活性物質を,化学構造の視点からまとめることはあまり行われてこなかったと思う.生理活性物質(内因性受容体アゴニスト)は,発見の経緯などから特定の機能的側面やその受容体から分類されてきたものの,個々の生理活性物質に複数の機能があることが次々に明らかにされるようになってきて,知識の整理を難しくしている.また,各生理活性物質の化学構造について整理しておくことは,薬物動態の理解に必須となる.このような観点から新たに設けた第13章「内因性情報伝達物質」では,生理活性物質を化学構造に基づいて分類し整理した.すなわち,他の章が機能ごとに生理活性物質を扱う縦串だとすると,新章は横串の役割を果たすと位置づけられる.
薬物治療の基本概念を学ぶ薬理学は,疾患に関わる病態機構が解明されるにつれて深化する.医学に関連する情報は日々蓄積され複雑化しているようにみえるが,それは新たな知識に立脚してこれまでブラックボックスであったことを整理し直す機会でもある.そうした変化を常に取り込むべく編んだ本書が,薬理学を学ぶ読者の役に立つことを切に望むものである.
2021年1月
監修・編集者ら
目次
開く
第I編 総論
構成マップ(第1~3章)
第1章 薬理学とは
A なぜ薬理学を学ぶのか
B 受容体――概念から実体へ
C 薬理学の歴史と展望
D どのように薬理学を学ぶか
第2章 薬理学総論
A 分子・細胞レベルでの薬理作用
B 個体・集団レベルでの薬理作用
C 薬物の生体内動態
第3章 臨床薬理学
A 臨床薬理学総論
B 臨床薬物動態学
C 薬理遺伝学
D 薬物相互作用
E 高齢者の薬物療法
F 妊産婦・小児における薬物動態
G 病態時における薬物動態
H 処方と調剤
第II編 薬物と生体機能制御系
構成マップ(第4~13章)
第4章 Gタンパク質共役型受容体
A GPCRとGタンパク質
B GPCRの分類と構造の特徴
C GPCRに結合するリガンド
D GPCRの調節メカニズム
E バイアス型シグナリング
F 主要なGPCR
G GPCRに対する自己抗体と疾患
第5章 サイクリックヌクレオチド
A cAMP
B cGMP
C サイクリックヌクレオチド分解系
第6章 イオンチャネル型受容体
A 構造と機能
B 代表的な受容体
第7章 チャネル
A イオンチャネル
B 水チャネル
第8章 トランスポーター
A 輸送と拡散
B イオンポンプ
C ABCトランスポーター
D SLCトランスポーター
E トランスポーターの生体内での機能と病態への関与
第9章 Ca2+シグナル機構
A Ca2+シグナルの薬理学的意義
B Ca2+シグナル機構の概要
C 細胞内Ca2+濃度調節機構の概要
D 細胞膜を介したCa2+流入経路
E 小胞体のCa2+放出チャネル
F ミトコンドリアのCa2+輸送
G Ca2+の能動輸送
H Ca2+結合タンパク質
第10章 酵素型受容体とシグナル伝達
A 酵素型受容体
B チロシンキナーゼ型受容体
C セリン・スレオニンキナーゼ型受容体
D サイトカイン受容体
E グアニル酸シクラーゼ型受容体
F その他の受容体
第11章 細胞内受容体
A 一酸化窒素と可溶性グアニル酸シクラーゼ
B ホスホジエステラーゼ
C 核内受容体
第12章 神経系の化学伝達
第13章 内因性情報伝達物質
A アミノ酸およびその代謝物
B エステル
C ポリペプチド:ペプチド,タンパク質
D 脂質
E プリン化合物
第III編 薬物と器官病態制御
第14章 末梢神経系
本章の構成マップ
A 末梢神経系の薬理学
B 交感神経系に作用する薬物
C 副交感神経系に作用する薬物
D 自律神経節に作用する薬物
E 神経筋接合部遮断薬
F 局所麻酔薬
第15章 循環系
本章の構成マップ
A 心不全治療薬
B 虚血性心疾患治療薬
C 高血圧治療薬
D 抗不整脈薬
第16章 体液
本章の構成マップ
A 利尿薬
B 輸液
第17章 中枢神経系
本章の構成マップ
A 統合失調症治療薬(抗精神病薬)
B 抑うつ障害および双極性障害治療薬
C 不安症・強迫症治療薬
D 睡眠-覚醒障害治療薬
E 抗てんかん薬
F パーキンソン病治療薬
G アルツハイマー型認知症治療薬
H アルコール
I 鎮痛薬
J 薬物依存
K 全身麻酔薬
第18章 内分泌・代謝系
本章の構成マップ
A 内分泌
B 代謝
第19章 抗感染症薬
本章の構成マップ
A 感染症治療の原則
B 抗菌薬とその原理
C ペプチドグリカン生合成過程に作用する抗菌薬
D タンパク質合成阻害薬
E 葉酸代謝阻害薬
F DNA,RNAに関与する薬物
G その他の抗菌薬
H 抗酸菌症治療薬
I 抗真菌薬
J 原虫・蠕虫治療薬
K 抗ウイルス薬
L ワクチン
M 消毒薬
N 多剤耐性菌とその治療薬
O 小児,妊婦への抗菌薬投与と安全性
第20章 抗悪性腫瘍薬
本章の構成マップ
A 細胞障害性抗癌薬
B 分子標的薬
C ホルモン薬とホルモン拮抗薬
D その他の抗癌薬
E 抗癌薬に対する耐性
第21章 血液系
本章の構成マップ
A 造血
B 赤血球系疾患
C 白血球系疾患
D 巨核球系疾患
E 血栓性疾患/出血性疾患
第22章 呼吸器系
本章の構成マップ
A 生理と薬理
B 呼吸器系疾患の病態と薬物治療
第23章 消化器系
本章の構成マップ
A 消化性潰瘍の治療薬
B 機能性消化管障害の治療薬
C 止瀉薬と瀉下薬
D 炎症性腸疾患の治療薬
E 制吐薬と催吐薬
F 肝臓疾患の治療薬
G 胆道系疾患の治療薬
H 膵臓疾患の治療薬
第24章 免疫・炎症系
本章の構成マップ
A 抗炎症作用を発揮する薬物
B 免疫機能を調節する薬物
C アレルギー疾患治療薬
D 抗リウマチ作用を発揮する薬物
E サイトカイン,ケモカインを標的とする薬物
本書で用いた略語一覧
和文索引
欧文索引