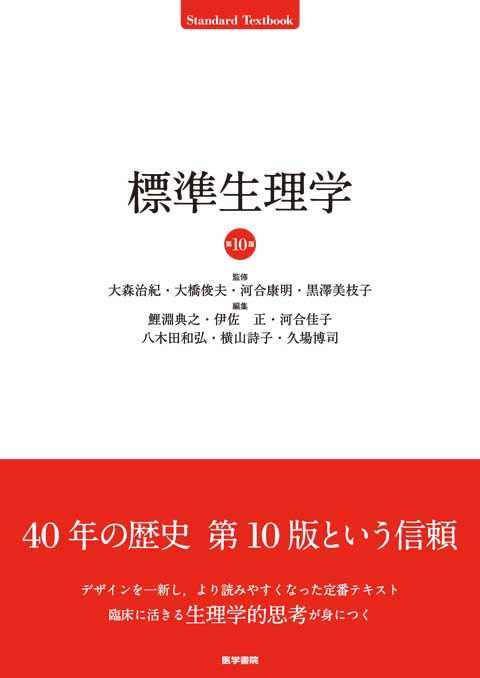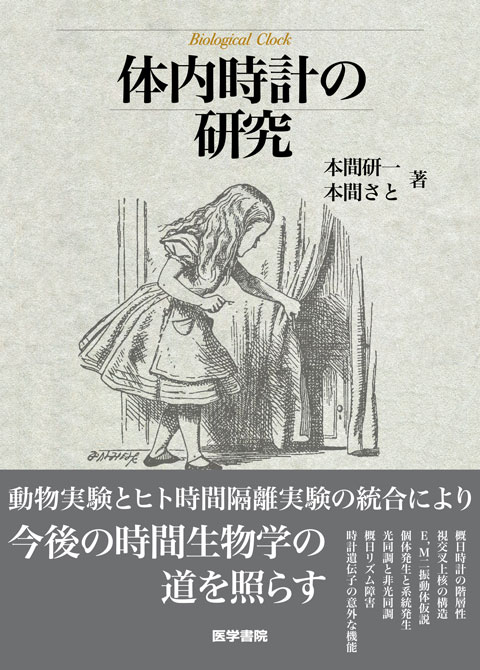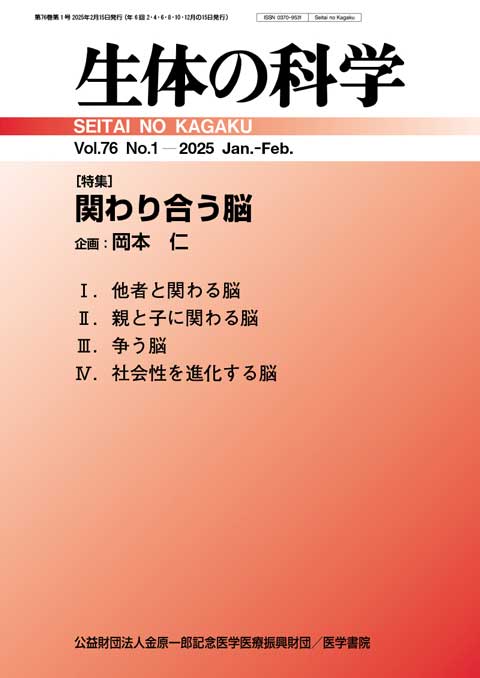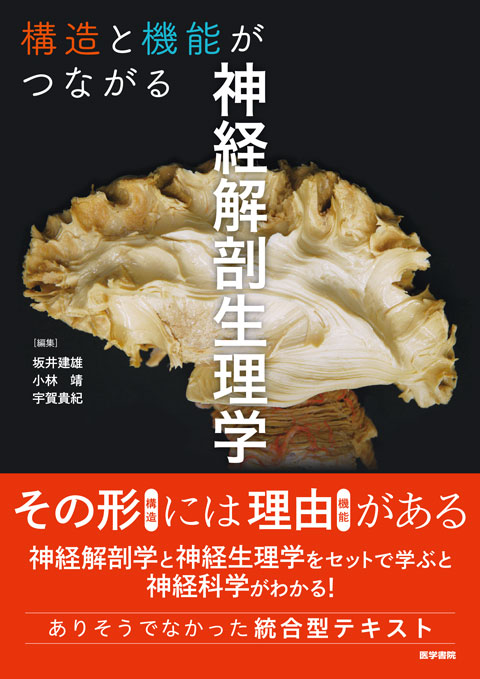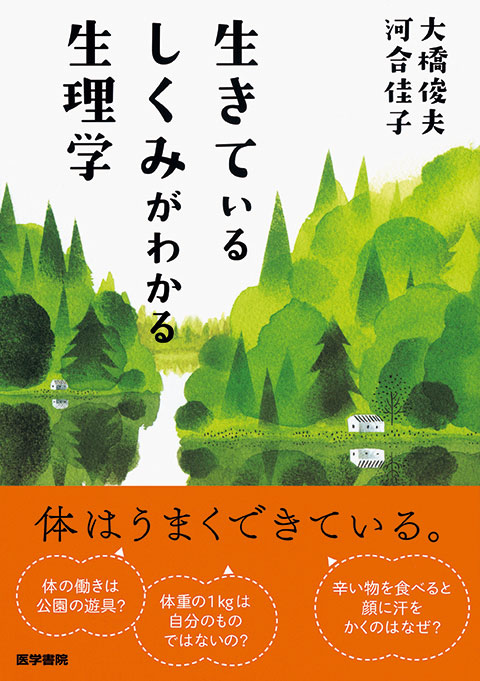標準生理学 第10版
40年の歴史ある生理学の定番テキストが、デザインを一新し、より読みやすく改訂!
もっと見る
高い網羅性と深い記述内容を誇る日本語オリジナルの生理学教科書。10版の節目に誌面デザインをリニューアル。多くの読者モニターにご協力いただき、よりわかりやすい記述を目指して全文の見直しも実施した。基礎的な解説を増やしながらも、サイエンスとしての生理学研究の魅力も紹介。巻末の「生理学で考える臨床問題」では、生理学の知識を臨床に活かす発想を学べる。学生時代から始まる生涯学習の、良きパートナーとなる一冊。
| ● | 『標準医学シリーズ 医学書院eテキスト版』は「基礎セット」「臨床セット」「基礎+臨床セット」のいずれかをお選びいただくセット商品です。 |
| ● | 各セットは、該当する領域のタイトルをセットにしたもので、すべての標準シリーズがセットになっているわけではございません。 |
更新情報
-
2025.04.23
- 序文
- 目次
序文
開く
第10版 序
標準生理学は,1985年に初版が刊行され,今回で第10版の出版を迎える.40年にわたり世の中に受け入れられたのは,読者の理解とこれまで執筆を分担された諸先生の意気込みの成果でもある.
初版の序でも述べられているように,本書は「生理学的なものの見方,考え方」の習得に主眼を置いた教科書である.このため本書は,生命機能の重要性,あるいは生理学上の結論に至る過程を論理的に記述することを目指している.生理学は医学,そして生命科学領域の学問である.しかし,ほかの生命科学分野に比べても物理学,化学そして物理化学に根ざした学問である.そして,ほかの生命科学分野では使われていない独特の用語が多数使われている.初めて生理学を学ぶ人たちは,多くの新しい用語に戸惑いを感じるかもしれない.そこで,本書では生理学上の用語の意味,あるいは定義を記述する過程で可能な範囲で関連した現象を例示し,生理学の論理と結論を丹念に書き込んでいる.その結果として,ある意味では大部の書物となっている.
本書の第1章では細胞の生理学を概説し,本書全編の基礎でもある細胞の微細構造と情報伝達機能を解説している.第2章~第22章は動物生理学を記述し,機能的に第2編~第7編に類別されている.第23章~第75章は植物生理学を記述し,第8編~第16編に機能的にまとめられている.それぞれの編の冒頭には構成マップとして各章の解説を図示し,それぞれの編を学ぶことの意義を記述した.さらに付録として,生理学で考える臨床問題が掲載されている.学習の道程を把握するために活用してほしい.臨床所見および病態生理学に関する解説は,本書の随所に記載されている.臨床問題と相互に対照することで,読者が生理学の学習を効率よく進めてくれることを期待する.
終わりに,執筆を分担された諸先生に深く感謝を表するとともに,医学書院の編集および制作の関係者に心から御礼申し上げたい.
2025年2月
編集者一同
目次
開く
序章
第1編 細胞の一般生理
第1章 細胞の一般生理
第2編 神経と筋
本編の構成マップ
第2章 膜興奮性とイオンチャネル
第3章 筋肉とその収縮
第4章 興奮の伝達
第3編 神経系の形態と機能/概説
本編の構成マップ
第5章 神経細胞学/総論
第6章 神経回路機能/総論
第4編 感覚機能
本編の構成マップ
第7章 感覚機能/総論
第8章 体性感覚
第9章 聴覚
第10章 平衡感覚
第11章 視覚
第12章 味覚と嗅覚
第5編 運動機能
本編の構成マップ
第13章 筋と運動ニューロン
第14章 脊髄
第15章 脳幹
第16章 大脳皮質運動野と大脳基底核
第17章 小脳
第18章 発声と構音
第6編 自律機能と本能行動
本編の構成マップ
第19章 自律神経系
第20章 本能的欲求に基づく動機づけ行動
第7編 高次神経機能
本編の構成マップ
第21章 大脳皮質の機能局在
第22章 統合機能
第8編 体液
本編の構成マップ
第23章 水分子の特性と浸透圧
第24章 体液の調節
第25章 酸・塩基平衡の基本概念
第9編 血液
本編の構成マップ
第26章 血液
第27章 血液細胞の産生
第28章 赤血球
第29章 鉄の代謝
第30章 白血球
第31章 免疫反応と炎症
第32章 止血血栓形成機構とその制御機構
第33章 血液型
第10編 循環
本編の構成マップ
第34章 循環系の基本的性質
第35章 血液循環
第36章 心臓の働き
第37章 循環系の調節
第38章 局所循環
第11編 呼吸
本編の構成マップ
第39章 呼吸生理学の基礎
第40章 肺の換気
第41章 肺循環とガス交換
第42章 血液ガスの運搬
第43章 呼吸の調節
第44章 呼吸の適応と病態
第12編 腎機能と排尿
本編の構成マップ
第45章 腎生理学の基礎
第46章 腎循環と糸球体濾過
第47章 尿細管の機能
第48章 下部尿路機能とその調節
第49章 体液とその成分の調節
第50章 腎臓における酸塩基輸送と調節
第13編 消化と吸収
本編の構成マップ
第51章 消化と吸収の一般原理
第52章 食物の摂取と輸送
第53章 胃
第54章 肝・胆および膵外分泌系
第55章 小腸
第56章 大腸の機能と排便
第57章 栄養素などの消化吸収
第14編 環境と生体
本編の構成マップ
第58章 エネルギー代謝
第59章 体温とその調節
第60章 概日リズム
第61章 運動と体力
第62章 発達と老化
第63章 極限環境下の生理学
第15編 内分泌
本編の構成マップ
第64章 内分泌総論
第65章 視床下部と下垂体のホルモン
第66章 副腎の機能と分泌調節
第67章 ゴナドトロピンと性腺ホルモン
第68章 甲状腺刺激ホルモンと甲状腺ホルモン
第69章 カルシウム代謝の内分泌制御
第70章 消化管ホルモンの機能と分泌制御
第71章 糖代謝の内分泌制御
第16編 生殖
本編の構成マップ
第72章 生殖腺の性分化・発達
第73章 男性の生殖機能
第74章 女性の生殖機能
第75章 妊娠と分娩
付録 生理学で考える臨床問題
1 周期性四肢麻痺
2 悪性高熱症
3 神経筋接合部の障害
4 多発性硬化症
5 水頭症
6 関連痛
7 脊髄病変と感覚障害
8 めまいを伴う突発性難聴
9 夜盲症と色覚の障害
10 視野欠損
11 痙性麻痺
12 運動ニューロン疾患
13 MLF症候群
14 大脳基底核疾患
15 錐体路障害
16 小脳による運動制御異常
17 Horner症候群
18 自律神経反射異常
19 摂食症
20 失語症
21 半側空間無視
22 ナルコレプシー
23 記憶障害
24 脱水症
25 血漿タンパク質異常
26 貧血または立ちくらみ(起立性低血圧)
27 鉄の吸収と輸送
28 黄疸
29 感染と炎症性マーカー
30 血管雑音
31 狭心症
32 期外収縮
33 大動脈弁閉鎖不全症
34 心不全
35 ショック
36 動脈硬化症
37 エコノミークラス症候群
38 高血圧症
39 先天性QT延長症候群
40 心筋活動電位の異常
41 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
42 肺高血圧症
43 呼吸性アルカローシス(過換気症候群)
44 拘束性肺疾患(間質性肺線維症)
45 低酸素環境(高山病)
46 低酸素症
47 前立腺肥大症──尿路閉塞,排尿障害
48 下部尿路機能とその調節
49 Fanconi症候群
50 尿毒症──高窒素血症,意識障害
51 高カリウム血症
52 尿崩症
53 低アルブミン血症(ネフローゼ症候群)と浮腫
54 門脈圧亢進症
55 逆流性食道炎──胸やけ
56 胆石症
57 乳糖不耐症──下痢
58 ダンピング症候群
59 肥満症
60 高体温症
61 非24時間睡眠覚醒症候群
62 オーバートレーニング症候群
63 低血糖症
64 先端巨大症
65 中心性肥満(Cushing症候群)
66 原発性無月経(Kallmann症候群)
67 甲状腺機能低下症(橋本病)
68 骨粗鬆症
69 代謝性アシドーシス(糖尿病性ケトアシドーシス)
70 Turner症候群
71 更年期障害
和文索引
欧文索引
人名索引