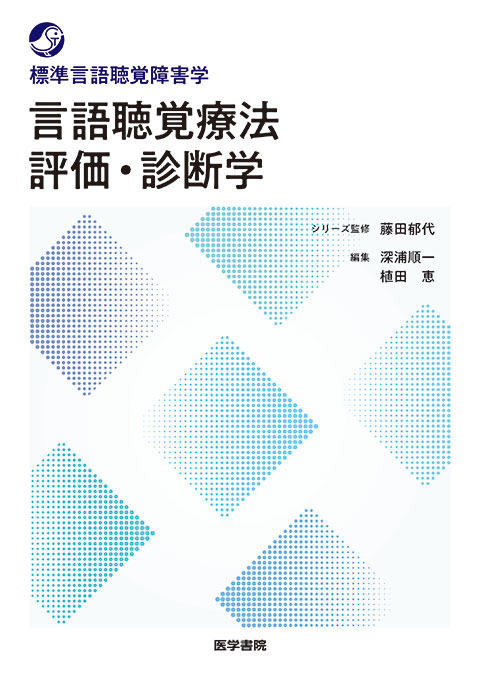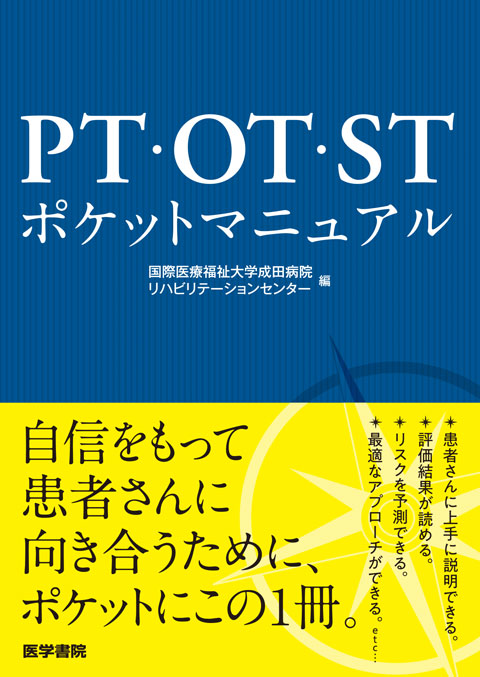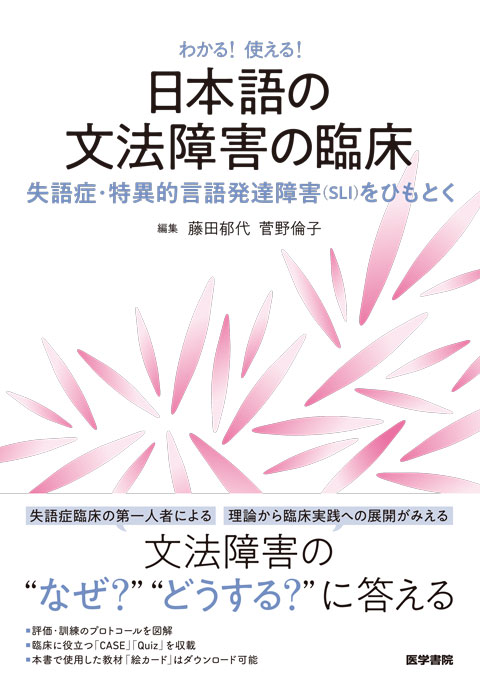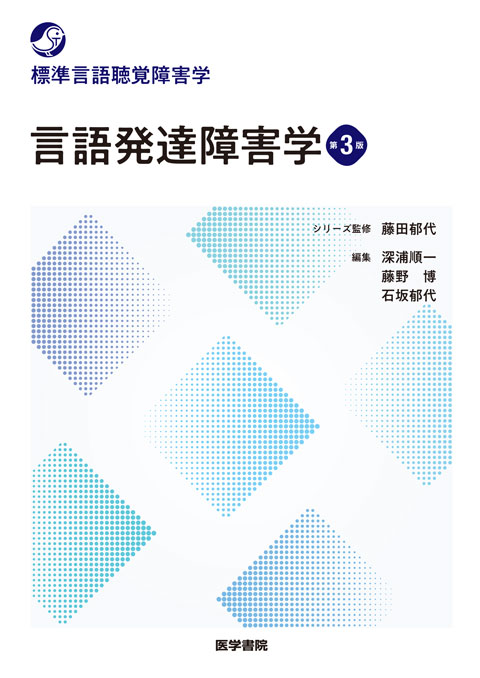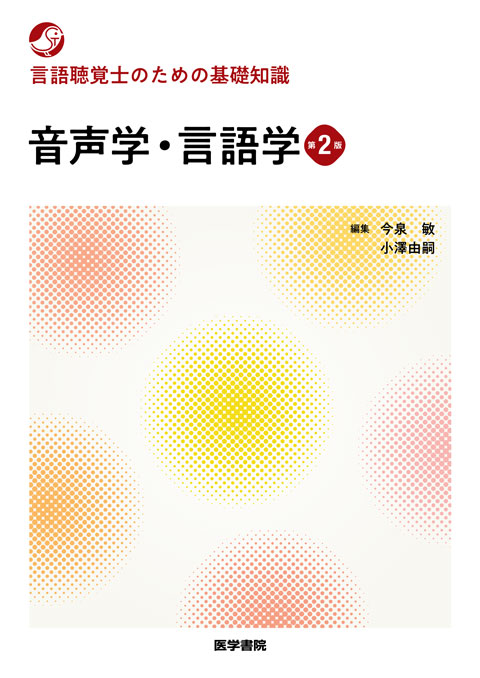言語聴覚療法 評価・診断学
言語聴覚障害の診断・評価の基本概念の体系的に学ぶ
もっと見る
言語聴覚障害の診断・評価の基本概念の体系的に学び、その上で評価・診断のプロセスと思考過程の領域横断的な理解を深めます。・言語聴覚士養成教育モデル・コア・カリキュラムの内容を網羅しています。・教育的な典型事例を介して、現場で直面する問題を俯瞰で見る力を養います。
*「標準言語聴覚障害学」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 標準言語聴覚障害学 |
|---|---|
| シリーズ監修 | 藤田 郁代 |
| 編集 | 深浦 順一 / 植田 恵 |
| 発行 | 2020年11月判型:B5頁:308 |
| ISBN | 978-4-260-04148-5 |
| 定価 | 5,280円 (本体4,800円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
正誤表を更新しました。
2022.12.02
-
正誤表を追加しました。
2022.06.07
- 編集者からのコメント
- 序文
- 目次
- 正誤表
編集者からのコメント
開く
2020年秋,シリーズに新しく加わったタイトルです。言語聴覚療法のスタートである評価・診断を行うにあたっては,言語聴覚障害の特徴の理解,必要な検査の選択とその解釈,全体像の統合など,基本的知識の理解と臨床推論の力を十分身に着ける必要があります。 言語聴覚療法の学修の初期段階で評価・診断の基本的過程について学び,また研究法の基礎について身につけておくことが,確かな臨床能力の獲得につながっていくものと考えています。
序文
開く
今回,標準言語聴覚障害学のシリーズで新たに『言語聴覚療法 評価・診断学』を刊行することとなった.言語聴覚障害や摂食嚥下障害のある方に言語聴覚療法を実施するにあたり,そのスタートとなるのは評価・診断である.評価・診断は,情報収集,スクリーニング検査,総合的(鑑別診断)検査,特定(掘り下げ)検査によって対象者の全体像を把握し,その結果を根拠に訓練・指導・助言の方針を立案するという過程である.言語聴覚療法は,言語聴覚障害がある方の心身機能の回復と生活機能の回復を通して自立生活を支援すると同時に,評価・診断による障害の発現機序と回復に関する仮説の設定と,訓練等を通した仮説の検証を行うという過程である.
評価・診断を行う際には,言語聴覚障害の特徴の理解,必要な検査の選択とその解釈,全体像の統合など,基本的知識の理解と臨床推論の力を十分身に着けることが必要である.評価・診断能力は,最終的には臨床的経験の中で高められるが,養成校で学ぶ段階から評価・診断の基本的な過程を学ぶことが重要であり,本書がその援助となることを願っている.
したがって,本書では1章で言語聴覚障害の種類と特徴,評価・診断の基本概念と評価の技法,臨床データの解釈,2章で評価・診断の過程,3章で評価・診断に用いる検査という内容とし,評価・診断の基本を学修できるようにした.続く4章では,各言語聴覚障害領域における評価・診断の実際を学修してもらうために評価・診断の各過程を詳述している.評価・診断の結果は報告書として文書化するが,5章でその実際を身に着けていただきたい.最後の6章では研究法を取り上げた.研究法を学ぶことは対象者から得られたデータを解釈するうえで基本となる知識を与えてくれる.さらに,近年は言語聴覚療法のエビデンスを構築する重要性が増しているが,研究法の理解は適切なデータの収集と処理に基づくエビデンスレベルの高い報告を提供するための基礎を与えてくれるものと考えている.
本書の執筆者は,言語聴覚障害の各領域において臨床・研究の第一人者として活躍している言語聴覚士の方々である.新しい企画のもとで執筆には苦労されたと思うが,言語聴覚士を目指す学生や若き言語聴覚士にとって理解しやすく,実際的な内容となったと考えている.
最後に,このように熱意をこめてご執筆くださった先生方に心から感謝申し上げたい.また,本書の出版にあたり,忍耐強い励ましとご尽力をいただいた医学書院編集部の皆様に深謝申し上げる.
2020年8月
編集
深浦順一
植田 恵
目次
開く
1 言語聴覚障害の種類と特徴
A 聴覚障害
B 言語発達障害
C 失語症
D 構音障害
E 吃音・流暢性障害
F 音声障害
G 高次脳機能障害に伴う認知・コミュニケーション障害
H 摂食嚥下障害
2 評価・診断の基本概念
A 言語聴覚障害を診るとは
B 評価・診断における臨床推論
C 言語聴覚療法における測定,評価,診断
D 評価・診断の目的
E 科学的根拠に基づく言語聴覚療法(EBP)
F ICFと言語聴覚療法
G 評価・診断の倫理
H 障害特性に対応した評価・診断
3 評価の技法
A 面接法
B 観察法
C 質問紙法
D 検査法
E 機器を用いた測定
4 臨床データの解釈
A 妥当性と信頼性
B 数値化と尺度水準
C データの特性
D 測定値の解釈(正常値と異常値の見方)
E 検査実施時および結果の解釈における留意点
第2章 評価・診断の過程
1 評価・診断の流れ
2 評価・診断の枠組み
A 評価プランの立て方
B スクリーニング
C 総合的(鑑別診断)検査
D 特定(掘り下げ)検査
E 評価のまとめと言語病理学的診断
F 全体像の整理
G 適応の判定と予後予測
H 訓練・指導方針の決定
I 再評価
第3章 評価・診断に用いる検査
1 スクリーニング
A 成人の言語聴覚障害のスクリーニング
B 小児の言語聴覚障害のスクリーニング
2 各領域において必要とされる検査
[1 言語・認知系(成人)]
A 言語機能
B 高次脳機能
[2 言語・認知系(小児)]
A 言語発達障害の検査
B 学習・認知の検査
C コミュニケーションの検査
[3 発声・発語系]
A 呼吸に関する評価
B 発声に関する評価
C 共鳴に関する評価
D 構音に関する評価
E プロソディに関する評価
F 発話の検査
G 総合的評価
[4 摂食嚥下系]
A スクリーニング
B 総合的検査
C 詳細な検査
D その他の検査
E 摂食場面の観察
F 重症度分類
[5 聴覚系]
A 聴覚障害の評価・診断に必要な検査
B 聴覚補償機器装用効果の評価に必要な検査
C 全体発達・言語発達の評価に必要な検査
[6 その他]
A 運動機能・日常生活活動
B パーソナリティ・精神症状
C 健康関連QOL,精神健康度
D 運動機能と日常生活活動
第4章 各領域の評価・診断の実際
1 言語・認知系
[1 成人]
A 総論
B 面接
C 観察
D 検査・質問紙
E 各種情報の統合と解釈
[2 小児]
A 臨床の流れと留意点
B 面接と質問紙
C 行動観察
D 検査
E 各種情報の総合と解釈(典型事例)
2 発声・発語系
[1 音声障害]
A 総論
B 面接
C 観察
D 質問紙
E 検査
F 各種情報の統合と解釈
[2 構音障害(成人)]
A 総論
B 面接
C 他部門・関係機関からの情報
D 観察・スクリーニング検査
E 質問紙
F 検査
G 各種情報の統合と解釈
[3 構音障害(小児)]
A 総論
B 面接
C 観察
D 検査
E 各種情報の統合と解釈
[4 流暢性障害]
A 総論
B 面接
C 観察
D 検査
E 各種情報の統合と解釈(典型事例)
3 摂食嚥下系
[1 成人]
A 総論
B 面接
C 観察
D 質問紙
E 検査
F 各種情報の統合と解釈
[2 小児]
A 総論
B 面接
C 質問紙
D 観察
E 検査
F 各種情報の統合と解釈
4 聴覚障害
[1 成人]
A 総論
B 面接とそれに際した行動観察
C 質問紙
D 検査
E 各種情報の統合と解釈
[2 小児]
A 総論
B 面接
C 行動観察
D 質問紙
E 検査
F 各種情報の統合と解釈(典型事例)
5 障害が重複した事例の評価・診断
A 失語・高次脳機能障害
B 摂食嚥下障害と認知症
C 発達障害・聴覚障害
D 脳性麻痺・重複障害
第5章 評価・診断結果の報告
1 報告書の書き方
A 報告書作成の目的
B 作成時の注意事項
C 評価報告書の具体例
2 情報提供
A 情報提供の目的
B 多職種カンファレンス
C 情報提供書の作成
D 情報提供書の一例(他院の言語聴覚士宛)
E 情報提供書の一例(リハビリテーション関連職種以外宛)
F まとめ
第6章 研究法
1 言語聴覚障害学における研究
A 言語聴覚研究とは
B 臨床における研究の重要性
C 根拠に基づく言語聴覚療法
D 言語聴覚研究の特徴
2 研究の種類
A 量的研究(quantitative research)
B 質的研究(qualitative research)
3 研究における実証の方法
A 変数の操作
B 測定における妥当性と信頼性
C サンプリング
D バイアス
E データの尺度
F 統計的分析
G 統計的検定
4 研究の倫理的配慮
5 研究の進め方
A 研究テーマを設定する
B 研究計画を立案する
C 研究を実施する
D 研究成果を報告する
6 論文の読み方
7 論文の書き方
8 学会発表の仕方
Note 一覧
1.ラポール(rapport)
2.主訴
3.HOPE
4.補充現象(リクルートメント現象)
5.音場検査
6.遺伝子診断
7.自己発話認識力
8.sucklingとsucking
9.munchingとchewing(咀嚼)
10.インフォームド・コンセント
11.個人情報
12.利益相反
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。
更新情報
-
正誤表を更新しました。
2022.12.02
-
正誤表を追加しました。
2022.06.07