新春随想2017(吉村博邦,武田俊彦,松本紘,大曲貴夫,岡野栄之,大澤真木子,山田不二子,志真泰夫,山本則子,丸光惠,小山珠美,石本淳也,村井説人,田中牧郎)
2017.01.02
2017年
新春随想
新専門医制度の実現に向けて
吉村 博邦(一般社団法人日本専門医機構理事長) 新年明けましておめでとうございます。皆さまには,健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
新年明けましておめでとうございます。皆さまには,健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
さて,わが国の新たな専門医制度については,プロフェッショナル・オートノミーを基盤とする,第三者機関としての日本専門医機構が3年前に設立され,新たな仕組み作りがスタートしました。しかしながら,地域医療への影響等のご意見を考慮し,いったん立ち止まってその見直しを図っていることはご承知の通りです。
かつては,多様な学会が独自に学会専門医制度を立ち上げ,専門医の質の向上,社会的認知の普及等をめざして50年近く活動がなされてきました。新たな機構の役割は,乱立している多様な専門医制度を標準化し,社会から質の高い資格として認知されるように認証し,国民にとってわかりやすく,患者さんの受診に当たって良い指標となるような制度に再構築することです。また,専門医をめざす若い医師にとっては,専門技量を確実に身につけられる仕組み,意欲と誇りをもって専門研修を続けることができる仕組みを作る必要があります。
新たな制度による研修は,基本的には3~4年間の研修プログラムに則り,研修施設は,大学病院や地域の中核病院などの基幹病院と地域の協力病院(診療所を含む)が病院群を形成して行うこととなっています。現理事会では,この仕組みについて,制度をより柔軟に運用する方針を決定しています。また,専門医としての質を十分に確保しつつ,地域医療への影響をできるだけ少なくして,2018年4月には,基本19領域の専門医制度について,一斉にスタートできるよう準備を進めています。皆さまのご理解を,何卒よろしくお願い申し上げます。
日米関係の歴史を映すホテル――医薬品行政のさらなる進化へ
武田 俊彦(厚生労働省医薬・生活衛生局長) アメリカに新大統領が誕生する。日米関係がどう変化するのか,多くの人が固唾を飲んで見守っている。日米関係の変化を懸念する声も多いが,そもそも日米の関係は常に一定だったわけではない。
アメリカに新大統領が誕生する。日米関係がどう変化するのか,多くの人が固唾を飲んで見守っている。日米関係の変化を懸念する声も多いが,そもそも日米の関係は常に一定だったわけではない。
箱根に有名なクラシックホテルがある。昨夏の終わりに訪れたが,明治以後日米関係と共に歩んだこのホテルには,歴史が凝縮されていた。たどってきた歴史を誇るホテル内ツアーもある。和洋折衷の部屋の造り,柱の彫刻や美術品等,きらびやかな最新のホテルにはない味わい深さがそこにはある。
明治時代,一気に日本人の目が海外に開かれた。岩倉具視使節団の訪米・訪欧の記録を見ても,最初にサンフランシスコに着いたときにホテルの豪華さに感嘆する一行の様子が描かれている。明治期に渡米した人々が,海外から日本に来る旅行者のために,海外のホテルの水準を取り入れつつ日本らしさも持つ宿泊施設を,日本に作ろうと思ったことは想像に難くない。
まだ観光開発される前の日本が誇るものは自然だっただろう。外国人を迎えるに選ばれた土地が,富士山に近い,箱根の温泉地だったのは十分な理由があると感じられる。手元に『日本風景美観』という1929年の本があるが,日英併記で解説が付された写真集で,わが国の名所を紹介している。人も建物も映り込まず自然が広がる風景は,現代から見ると不思議に思える。ホテルの館内ツアーのハイライトであるメインダイニングルームが竣工したのはこの1年後で,「自然の中に世界に引けを取らない施設を」という当時の日本人の心意気が感じられる名建築だ。
戦後,連合国軍に接収され,その後米軍貸与を経て一般営業を開始したのは1954年。その後,もう一度日本人は世界を追いかけ,今に至る。外国人専用ホテルは,今は日本人夫婦や家族で宿泊できる憩いのホテルになっている。
戦後のアメリカは輝いていて,多くの人が夢を持って海を渡った。私が一家でアメリカに住むことになったのは1990年。湾岸戦争が及ぼす暗い影もあったが,それでも夢と希望の土地だと感じられた。そのアメリカは昨年の選挙で変わってしまったのだろうか。
時代は変わり,世界は変わる。わが国は今,世界をリードする役割を持つ。医薬品の審査は速度も質も世界水準になった。しかし昔も今も変わらないのは人の心。人の心を大事にし,さらに時代に沿って進化する行政でありたい。そう考えている。
理研創立100周年,新しい100年へ
松本 紘(国立研究開発法人理化学研究所理事長) 理化学研究所(理研)は,本年,創立100周年を迎えます。
理化学研究所(理研)は,本年,創立100周年を迎えます。
理研は大正時代の1917年に,学問の力によってわが国の産業発展を図り,国運の発展を期する使命を果たさんとする目的で財団法人として設立されました。以来,研究者の自由な発想に基づく基礎研究を進め,さらにその成果を産業の発展へつなげるため,理研自ら企業を立ち上げ,1939年ごろには会社数63,工場数121に発展し,理研コンツェルンと呼ばれました。まさしく基礎研究の成果を社会実装し,産業の発展に貢献したと言えるものです。
昨年10月,理研は特定国立研究開発法人となりました。特定国立研究開発法人とは,世界最高水準の研究開発成果の創出を特に期待される国立研究開発法人を「特定」として位置付け,国家戦略としてイノベーション創出を強力に推進するものです。そのため,豊かで活力ある社会の実現や地球規模の課題の解決に貢献することが求められます。
しかし,激動する社会が抱える課題や地球規模の課題を解決するためには,もはや一つの企業のみ,あるいは一つの研究機関のみの取り組みでは困難となってきています。解決のためには,互いに連携し,総力を結集して取り組む必要があります。そのため理研は,大学,研究機関,病院,産業界それぞれの力を結集して,連携するための連結役(科学技術ハブ)を担おうと考えています。
さらに,未来社会をどのようにしたいのか,何を変えたいのかというビジョンを,研究を行う一人ひとりが考える必要があると考えます。その結果として,創出される研究成果が実社会にイノベーションをもたらすのです。理研は,科学技術を通じて豊かで活力ある,あるべき未来社会像をデザインできる専門家(イノベーションデザイナー)を育て未来に貢献したいと考えています。
次なる新しい100年においても,理研は,研究者の自由な発想に基づく科学技術の基礎研究を進め,その成果によって産業の発展を図る“理研精神”を受け継ぎ,社会から信頼される,かけがえのない研究所であり続けたいと思います。
薬剤耐性対策に,大規模データベースの活用を
大曲 貴夫(国立国際医療研究センター国際感染症センター長)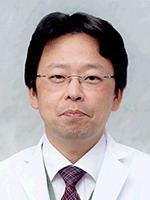 世界的に多剤耐性菌は大きな問題である。その問題は顕在化する一方で,多剤耐性菌に対抗できる新規抗菌薬の開発は鈍っている。
世界的に多剤耐性菌は大きな問題である。その問題は顕在化する一方で,多剤耐性菌に対抗できる新規抗菌薬の開発は鈍っている。
薬剤耐性(Antimicrobial Resistance;AMR)を世界的な健康危機と認識して対策を打つための活動が,WHOを中心として展開されている。2015年5月の世界保健総会では,AMRに関するグローバル・アクション・プランが採択され,加盟各国は2年以内に薬剤耐性に関する国家行動計画を策定することを求められた。これを受けて日本においても,政府により2016年4月に「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」が策定され,2020年までの5年間にわたり「適切な薬剤」を「必要な場合に限り」,「適切な量と期間」使用することを徹底するための国民運動が展開される。
本アクションプランについてはその数値目標に対して大きな関心が寄せられている。しかし他にも重要な点がある。その一つは感染対策に必要な指標の可視化である。感染対策に関するサーベイランスでは,抗菌薬の使用量のサーベイランスが求められる。これについては医療機関等から直接データを受け取るだけでなく,政府のレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)を使った統計化が必要である。加えて抗菌薬の適正使用の推進のためには感染症診療の質を改善しなければならない。これには医療現場での診断・治療と行った診療の内容について情報を収集し,統計化して評価することが必要である。この実現のためにはNDBの活用,DPC情報の活用など,日本の医療機関における診療データを集計し適切に解析して診療の質を見えるようにする必要がある。同様の取り組みはすでに英国などで始まっており,そのデータをウェブサイトで閲覧することも可能である。日本は各国と比較しても診療情報の電子化が進んでおり,しかもその情報が生かしやすい国である。壮大な取り組みだが,これは未来に向けた持続可能な医療環境の構築に大きく貢献するに違いない。
慶應義塾大学医学部200周年に向けたイノベーション戦略
岡野 栄之(慶應義塾大学医学部長) 初代医学部長の北里柴三郎博士が,慶大に医学部を創立したのは1917年であります。まさに今年2017年に,私たち慶大医学部は創立100周年を迎えます。北里初代医学部長は創立時に「基礎医学と臨床医学の連携を緊密にし,学内は融合して一家族の如く」という基本理念を示しました。この志が現在まで継承されたことで,慶大医学部・医学研究科は,基礎教室と臨床教室の連携が進んだ日本でも有数の大学として認知されています。
初代医学部長の北里柴三郎博士が,慶大に医学部を創立したのは1917年であります。まさに今年2017年に,私たち慶大医学部は創立100周年を迎えます。北里初代医学部長は創立時に「基礎医学と臨床医学の連携を緊密にし,学内は融合して一家族の如く」という基本理念を示しました。この志が現在まで継承されたことで,慶大医学部・医学研究科は,基礎教室と臨床教室の連携が進んだ日本でも有数の大学として認知されています。
そしてこのたび私たちは,創立100周年を迎えるに当たり,「大学とは,学問をする所である」と新たに決意を固めております。慶大医学部にとって,学問とは,「教育」「研究」「診療」の実践であります。すなわち,「教育」が「研究」と「診療」を培い,「研究」が「教育」と「診療」を牽引し,「診療」が「教育」と「研究」を開花させる。現在はこの実践ために,病棟建築を含むハードの整備,そして「仏に魂を入れる」ためのソフトの整備を進めております。ソフト面では,慶大病院は2016年に臨床研究中核病院として認定されました。基礎研究の成果を臨床に応用するシームレスなサポート体制を構築し,科学に十分に裏打ちされた新しい医療の構築をめざしております。
また,総合大学として22世紀の創立200周年をめざした長期的プランに基づいて,薬学部・看護医療学部・理工学部など医療と関連の深い学内の英知を結集し,世界に冠たる医学府を構築していきたいと思っております。皆さま,今後ともご指導,ご鞭撻のほど,よろしくお願い申し上げます。
より良いてんかん医療の推進をめざして
大澤 真木子(一般社団法人日本てんかん学会理事長/東京女子医科大学名誉教授) 故・秋元波留夫氏が創立した日本てんかん学会は,精神科,神経内科,小児科,脳外科などの会員からなる学際的なものである。研究会から公開の学会となり,昨年50回学術集会を迎えた。
故・秋元波留夫氏が創立した日本てんかん学会は,精神科,神経内科,小児科,脳外科などの会員からなる学際的なものである。研究会から公開の学会となり,昨年50回学術集会を迎えた。
イタリアのラファエロ・サンティの絵画「キリストの変容」の一部にてんかん発作が描写されているように,特に西洋では,てんかんは悪霊に取りつかれていることが原因だという考え方が根強かった。しかし1900年代に入ってから,「てんかん」という疾患はその概念をはじめ,基礎的にも臨床的にも飛躍的な進歩を遂げた。脳の冠状断をモチーフとする日本てんかん学会のロゴマークは,てんかんは脳の病気であることを表している。
2005年に国際抗てんかん連盟と国際てんかん協会がてんかんの定義を再検討し,「てんかん発作をひき起こす永続的な素因と,この状態に基づく神経生物学的,認知的,心理的,社会的帰結に特徴づけられる脳障害である」という患者さんの日常生活の状態を加味した“包括的”定義へ発展した。また,国際的に心を一つにすることを目的として,2015年に国際てんかんデーが2月の第2月曜日と定められた。これは,発作に悩む人たちが,フランスのベネディクト修道院にまつられているてんかんの守護神の一人,イタリアの聖バレンタインを2月14日に詣でたという歴史にさかのぼる。
2015年のWHO総会でてんかん医療が最重要課題として採択され,てんかん患者の権利を促進・保護する政策や法律を,各国政府が策定・強化・導入する必要性が強調された。これを受け日本では,てんかん地域診療連携体制整備事業が国との連携で,8つの自治体事業として始まった。またビデオ脳波などに診療報酬の増額が認められ,医政と診療報酬制度が連動している。近年科学的根拠に基づき,新規抗てんかん薬が登場し,ドラッグラグも少しずつ解消し,さらに外科治療,ケトン食療法など治療も進歩している。しかし,日常生活での発作の突然性,激越性,意外性にてんかん患者や家族は現在も悩まされており,他疾患に比し,偏見などの社会的側面が大きい。てんかん患者の病状は多彩であり,社会生活にほぼ問題のない方も多いにもかかわらず,診断開示により社会的制約を受ける場合もまだ多い。てんかんの治療目標は,その方の最大限の能力を生かし,生き生きと普通の生活・社会貢献ができるようにすることである。次の50年に向け,本学会はてんかん研究・医療の促進に加え,患者の権利擁護・QOL向上をめざした国民への啓発,てんかん予防の推進などに効果的な活動が必須である。一日も早く,患者さんがてんかんという病名を明るく受け入れ,生き生きと生活できる社会になることを願っている。
虐待・ネグレクトを受けた子どもたちのために
山田 不二子(NPO法人チャイルドファーストジャパン理事長/医療法人社団三彦会山田内科胃腸科クリニック副院長) 「チャイルドファーストジャパン」は,一昨年まで「子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク」という法人名で活動していました。1998年に民間団体を設立して以来の悲願だった「子どもの権利擁護センターかながわ」を開所して子どもたちが来るようになったため,その子どもたちが法人名を見て居心地悪く感じないで済むようにと考え,名称変更しました。
「チャイルドファーストジャパン」は,一昨年まで「子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク」という法人名で活動していました。1998年に民間団体を設立して以来の悲願だった「子どもの権利擁護センターかながわ」を開所して子どもたちが来るようになったため,その子どもたちが法人名を見て居心地悪く感じないで済むようにと考え,名称変更しました。
「子どもの権利擁護センターかながわ」は,日本で最初の「子どもの権利擁護センター(Children’s Advocacy Center;CAC)」で,子どもの発達段階に応じて中立的かつ非誘導的に被害事実を聞き取る「司法面接」と,子どもの身体をくまなく診察する「系統的全身診察」を1つの施設で提供するワン・ストップ・センターです。子どもが児童相談所や医療機関・警察署・検察庁をたらい回しされて,そのたびに同じことを何度も聞かれるという現状を解決できます。施設には観察室があり,児童相談所の職員・警察官・検察官がビデオモニターを通して「司法面接」を観察し,マイクを通した音声により「系統的全身診察」をモニターします。司法面接者は児童相談所・警察・検察のニーズをわきまえた上で子どもから聞き取りをします。児童相談所職員・警察官・検察官が追加して聞き取ってほしい内容は観察室から司法面接者に内線電話でオーダーできるのです。
このようなワン・ストップ・センターの構想は,民間団体を立ち上げたばかりのころに出会った性虐待被害児に,私が何もして...
この記事はログインすると全文を読むことができます。
医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。
いま話題の記事
-
医学界新聞プラス
[第1回]心エコーレポートの見方をざっくり教えてください
『循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.04.26
-
医学界新聞プラス
[第3回]冠動脈造影でLADとLCX の区別がつきません……
『医学界新聞プラス 循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.05.10
-
医学界新聞プラス
[第1回]ビタミンB1は救急外来でいつ,誰に,どれだけ投与するのか?
『救急外来,ここだけの話』より連載 2021.06.25
-
医学界新聞プラス
[第2回]アセトアミノフェン経口製剤(カロナールⓇ)は 空腹時に服薬することが可能か?
『医薬品情報のひきだし』より連載 2022.08.05
-
対談・座談会 2025.03.11
最新の記事
-
対談・座談会 2025.04.08
-
対談・座談会 2025.04.08
-
腹痛診療アップデート
「急性腹症診療ガイドライン2025」をひもとく対談・座談会 2025.04.08
-
野木真将氏に聞く
国際水準の医師育成をめざす認証評価
ACGME-I認証を取得した亀田総合病院の歩みインタビュー 2025.04.08
-
能登半島地震による被災者の口腔への影響と,地域で連携した「食べる」支援の継続
寄稿 2025.04.08
開く
医学書院IDの登録設定により、
更新通知をメールで受け取れます。


