MEDICAL LIBRARY 書評特集


神経救急・集中治療ハンドブック
Critical Care Neurology
篠原 幸人 監修
永山 正雄,濱田 潤一 編
《評 者》太田 富雄(医誠会病院・脳機能研究所長)
国際的にも類例のない神経救急・集中治療の良書
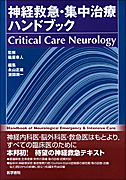 監修の序で篠原教授が指摘されているように,最近,疾患の画像診断の進歩は著しく,その結果,第一線医療施設で疾患の診断が可能になった。このため,従来,疾患診断に苦慮し,大学病院へ転送されていた疾患の多くが,第一線医療施設で治療を開始できるようになった。
監修の序で篠原教授が指摘されているように,最近,疾患の画像診断の進歩は著しく,その結果,第一線医療施設で疾患の診断が可能になった。このため,従来,疾患診断に苦慮し,大学病院へ転送されていた疾患の多くが,第一線医療施設で治療を開始できるようになった。
しかし,篠原教授が,変性疾患の診療研究を「静の神経学」,そして脳血管障害などの診療研究を「動の神経学」と表現されているが,この静と動の神経学を,満遍なく取り扱える医師は,神経内科医または脳神経外科医,救命救急医といえども,そうはいないだろう。さらに最近では,脳卒中のみならず,神経感染症,重症筋無力症,Guillain-Barre症候群などの急性期ないし急性増悪期の救急治療法が確立されており,治療法のみならず急性期の病態の適切なモニタリングも可能になるなど,急激に変化してきている。
このような事情によるものと思われるが,本邦では神経救急を取り上げたマニュアル書としては,本書の共同執筆者の一人,有賀教授の『脳神経救急マニュアル・救急から一週間のマネージメント』(三輪書店,2001)があるが,本格的な教科書はない。先ず,この点からも本書の出版は,この方面の医療に貢献するところ大であり,神経系専門医の立場からも本書出版に対し感謝の意を表したい。
内容に関しては,第一章において,「なぜ,今Critical Care Neurologyか」,「Critical Care Neurology・Emergency Neurologyの現状と課題」について触れているが,この方面のオリエンテーションとしては,きわめて適切な導入部である。第2章では「重症神経症候とその管理」,そして第3章では「重症神経疾患とその管理」に関し,ほとんど同じ様式で記載されており,きわめて読みやすく理解しやすい。
第4章では「全身的合併症とその管理」,そして最後の第5章では,「重症神経症候・疾患管理の方法」,そして最後に,神経疾患におけるDo-Not-Resuscitate(DNR)と脳死について言及している。
神経系の広範かつ十分な神経学の知識の必要性,重症神経疾患の的確な診断能力の養成,そして何よりも重症化する以前に早期に鑑別し,重症化や生命の危機から離脱させるため,リアルタイムの鑑別診断と的確なdecision-makingが必須である。本書を手に取り一瞥して明瞭なように,鑑別表,図,シェーマ,フローチャートを豊富に取り入れ,しかも救急・集中治療に関係するコメディカルスタッフまで念頭に,簡潔を旨として記載されている。
しかも従来の知識が網羅されており,国際的にも類例のない,神経救急・集中治療の優れた学際的教科書であることは間違いない。ぜひ座右のバイブルとして日常診療に役立てていただきたい。


日本フットケア学会 編
《評 者》吉原 広和(埼玉県立がんセンター・理学療法士)
足病変のケアに悩む医療者必携の書
 「人間の生活において『歩く』ことは単なる日常生活動作の範疇ではなく,より高度な文化的活動の維持・向上に不可欠な身体活動である」。このように考えると歩行を支える足機能の維持・ケアはないがしろにはできず,足病変のアプローチがいかに人の営みに影響を与えるかが窺える。
「人間の生活において『歩く』ことは単なる日常生活動作の範疇ではなく,より高度な文化的活動の維持・向上に不可欠な身体活動である」。このように考えると歩行を支える足機能の維持・ケアはないがしろにはできず,足病変のアプローチがいかに人の営みに影響を与えるかが窺える。
フットケアの分野は特に欧米において進歩・発展してきた診療分野ではあるが,日本ではやっと取り組みが始まった段階でしかない。欧米とは違った文化を持つわが国では「フットケア」技術の発展にも生活習慣の違いが影を落とす状況にあったことは否めないが,今後足病変に対する集学的治療分野としての「フットケア」が日本でも確立されることを望む医療者は多いのではないだろうか。
足の異常を招く多くの病因は,閉塞性動脈硬化症(ASO),糖尿病性末梢神経炎,下肢静脈血栓症,リンパ浮腫,がん,リウマチ,皮膚疾患,スポーツ障害,加齢変化など多岐にわたる。近い将来,血管外科・整形外科・内科・皮膚科・形成外科など各専門医や,看護師・理学療法士・義肢装具士・介護福祉士などの多くの職種が連携し,専門的な足病変のケア・治療が当然のように行われる時代が訪れるに違いない。
日本フットケア学会は2003年に発足した足病変に関する多職種による専門学会である。本書は本学会が編集したわが国唯一の体系的な「フットケア教科書」である。内容も各病変における基礎知識から専門的なケア・治療技術が学べる構成となっている。足病変のケアに悩む医療者には,必携の書籍といえよう。日本フットケア学会の意気込みが感じられる一冊である。


奥村 雄介,野村 俊明 著
《評 者》藤縄 昭(京大名誉教授)
新分野「非行精神医学」を開拓する意欲的な書
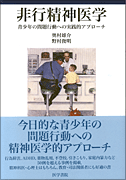 近年,「医療少年院」という施設のあることが,日常的に知られるようになったのは,青少年の思いがけない了解困難な,つまり『病的』と思われる犯罪(非行)が新聞紙上を賑わせるようになったことと無縁ではない。もちろん医療を必要と判断される青少年が,皆がみな世間を騒がせた人達でないことは確かである。犯罪の精神病理を扱う学問としては,古くから司法精神医学の研究分野があり,そこでは主として被疑者の責任能力の精神鑑定をめぐって議論され,医療,教育などが主題になることは少なかった。著者たちがあえて『非行精神医学』という造語を必要としたのは,今日まであまり注目されなかった非行少年たちの「あえて行動症状に着目し,(中略)犯罪・非行など社会規範からの明らかな逸脱から,家庭,学校,職場などで不適応に至るような問題行動まで視野に入れ」て,臨床精神医学的視点からの展望を試みることであった。そういう意味で,新分野を開拓する意欲的な著作である。
近年,「医療少年院」という施設のあることが,日常的に知られるようになったのは,青少年の思いがけない了解困難な,つまり『病的』と思われる犯罪(非行)が新聞紙上を賑わせるようになったことと無縁ではない。もちろん医療を必要と判断される青少年が,皆がみな世間を騒がせた人達でないことは確かである。犯罪の精神病理を扱う学問としては,古くから司法精神医学の研究分野があり,そこでは主として被疑者の責任能力の精神鑑定をめぐって議論され,医療,教育などが主題になることは少なかった。著者たちがあえて『非行精神医学』という造語を必要としたのは,今日まであまり注目されなかった非行少年たちの「あえて行動症状に着目し,(中略)犯罪・非行など社会規範からの明らかな逸脱から,家庭,学校,職場などで不適応に至るような問題行動まで視野に入れ」て,臨床精神医学的視点からの展望を試みることであった。そういう意味で,新分野を開拓する意欲的な著作である。
本書は3部から成り立ち,第1部は「青少年の問題行動と精神医学」,第2部は「精神障害と少年非行」,そして第3部は「治療と矯正教育」となっている。54の事例が詳しく記述されており,具体的に理解できるよう配慮されている。第1部ではDSM-IIIによってはじめて導入された『行為障害』というカテゴリーの検討がなされ,議論の多いこの概念に著者らの考え方を示し,事例を挙げて説明してある。行為障害の診断基準に従うと,行為障害は疾患単位ではなく,客観的に捉えられる問題行動によって診断されるが,基礎疾患(例えば統合失調症)のある場合には,精神病理学的な鑑別診断の必要を重視する。第2部では内因精神病から発達障害に至るまで,あらゆる精神障害のすべてを順次説明し,それぞれの事例を丁寧に提示してある。教科書的な構成であるが,文体はやわらかく流暢で読みやすい。第3部は医療少年院の紹介から,保護観察制度と社会復帰,そのための少年に対する心理的アプローチ,また家族への対応まで細やかに解説してある。
精神障害の分類などはDSM-IVに準拠しながら,著者達の姿勢にはドイツの基礎的な精神病理学の教養が貫かれ,また臨床心理学的配慮も底辺には読み取られて,著者達の経歴をみても納得できるところである。今日,精神病理学研究の低迷がいわれているとき,非行少年の精神病理が新しい分野を提供しているように思われる。本書は教科書の体裁をとり,議論,考察を深めることができなかった点は残念であったが,事例記述を読みながら精神病理学的空想をはせる楽しみがあった。多くの読者を得ることを願いたい。


岡本 保 訳
山鳥 重,彦坂 興秀,河村 満,田邉 敬貴 シリーズ編集
《評 者》長野 敬(自治医大名誉教授)
『手』と「設計」――ベル『手』の解題的な紹介
 脳は文字通り神経系の中枢であるとしても,周辺,末梢がなければ何もできない。切り取られた脳だけがいろいろ考えるというのは,手塚治虫の漫画にもあるし,陰気くさい小説もある(ヤシルド『生きている脳』)が,どちらでも筋書きは受動的に進むことしかできない。眼は,口と同じくらい「ものを言」ったりするかもしれないが,物理的な表出手段として,人間の場合に「手」より以上のものはない。単に物理的どころか,精神的なものも,手には反映する。
脳は文字通り神経系の中枢であるとしても,周辺,末梢がなければ何もできない。切り取られた脳だけがいろいろ考えるというのは,手塚治虫の漫画にもあるし,陰気くさい小説もある(ヤシルド『生きている脳』)が,どちらでも筋書きは受動的に進むことしかできない。眼は,口と同じくらい「ものを言」ったりするかもしれないが,物理的な表出手段として,人間の場合に「手」より以上のものはない。単に物理的どころか,精神的なものも,手には反映する。
チャールズ・ベルの『手』は,「ブリッジウォーター叢書」の一冊として刊行された(Sir Charles Bell: The Hand, Its Mechanism and Vital Endowments, as Evidencing Design. 1833)。叢書の呼称に,わざわざ「創造に示される神の英知と善を説くための」と書いてあることからもその趣旨は明らかだ。信心深いブリッジウォーター伯爵,フランシス・エジャートンが遺産から8000ポンドを宛てて,王立協会会長が8人の著者を選定して執筆してもらうようにと依頼したことから,「叢書」は成立した。いずれも自然科学の眼を通して見た「神の栄光」を説くことを目指している。地質学とか無機化学とか,包括的なものが多いなかで,この第6巻『手』は,ごく具体的な題名をもっている。依頼者としては,ベルがこの限られた入口から広大な思想的景観に導いてくれることを期待したのだろう。ベルはすでに神経系研究の大家であるとともに,以前に刊行した『表情論』のなかで,叢書の趣旨にふさわしい議論も展開していた。(表情論は1806年に前身というべき本が出て,その後1824年に本格的な第2版となった。ただし《神経心理学コレクション》に収められている『表情を解剖する』は最終の第4版によっていて,この版自体の刊行は1847年,つまり『手』よりかなり後で,ベルの没後でもあった)。
王立協会会長からの執筆依頼は名誉なことだし,1000ポンドずつの印税もわるくないが,ベルはこうした不純な動機から書くのでないことを,冒頭でまわりくどく弁明している。「ある主張をしなければならない場合,それが偏見によるものではなく,自然な感情の表明であると知っていれば,人はその意見にいっそう容易に耳を傾けるだろう」つまり,ここに展開する議論は以前からあたため,発展させていた立場からのもので,自分の「自然な感情の表明」であり,「叢書」に賛同して提灯もちをしているのではないから,ぜひ「容易に耳を傾け」てもらいたいというのだ。その立場は,副題の最後の「設計(デザイン)を証拠立てるものとしての」という一句に集約されている。
ベルが序文でも言及しているペイリー(William Paley, 1743-1805)の自然神学は,当時のイギリスで「創造主による行為」を説く際の範例となっていた。大学でも必習カリキュラムに含まれ,進化論のダーウィンも,学生のときに教えられた。『種の起原』(1859)が,それへの反発を引き金にしているという見方は,生物学思想史のなかでひろく定着している。ペイリーの所論のうち「ヒースの野原の時計」の比喩は,とりわけわかりやすくて普及した。時計が野原に落ちているのを拾った人は,その巧妙な設計(デザイン)から,設計者が必ずいることを確信する。時計よりも比較を絶して見事な設計産物である生物体,ことに人間が現にここにいるのだから,その設計者がいないはずがあるだろうか。
解剖学者・医学者だったベルは,人体の解剖構造,また調節などの生理機能の見事さなどの知識を総動員して,横の方向では動物と人間の比較解剖学,そして縦の方向では(第2章「地球の変化と生物の適応」)「岩石が形成される以前に生存していた動物の骨格」まで考察範囲に含めて,基本的には「設計」の理念に立ちながら,具体的な議論を展開する。ただし縦の時間軸に深入りすると,それは必ずや生物の起原(「生命の起原」とまでは言わない)の問題にぶつかり,設計主=創造主の議論がむし返されるはずだ。このあたりではベルの論旨は解剖構造の比較などの明快さと違って,しばしば曖昧になる。化石で発見される動物は,まだ粗削りの地球環境下で創造され,完成した環境のもとで人類は「最後に創造」されたと言うのだが,いつごろ,合計何回(?)の創造があったなど,具体的なことは何も言われているわけではない。
それにしてもこういう変遷観は,ある部分だけ切り取ってくると,ダーウィン以後に急展開した進化の見方と違和感なく重なったりする。「器官の変化がどれほど目をひくものでも,それは同一の偉大な創造的設計の一部分として原型と常にある一定の関係を保つ」(頁17)。これなど,「偉大な創造的設計」という一句を除いてしまえば,いまの高校教科書でいつも出てくる「コウモリとモグラと人の手の相同性」の図説明として,そのまま使えるせりふだ。
ただ,ベルの知識と考察の範囲がひろくて深く,それに真剣に向き合うからこそ,こうした曖昧さが露呈してくるのであり,現代の原理主義の創造論に見られる不誠実なごまかしは,ベルの思想・文章とは無縁のものである。第一級の研究者だったベルは進化論前夜の背景のもとで,動物の構造と機能の合目的性などをどう捉えていたか。『手』は,それを興味ふかく知ることのできる貴重な原資料だ。ジャン・ブラン『手と精神』(中村文郎訳,叢書ウニベルタシス原書1963,訳書1990)はこの本に触れて論じている。フランク・ウィルソン『手の五〇〇万年史』(藤野邦夫・古賀祥子訳,新評論,訳書2005)でも補遺のなかでベルのこの本に対して,短いが濃縮された賛辞を捧げている。


平野 朝雄 編著
《評 者》柳下 三郎(神奈川リハビリテーションセンター・病理)
病変の特徴を美しい写真と的確なコメントで明示
 平野朝雄先生の不朽の名著『神経病理を学ぶ人のために』の第4版「実相観入」のサイン入り書を手にしたのは,2003年5月30日と記載されています。この書を読み返す度に私は胸が熱くなり興奮が今も醒めません。つい先日発刊された思いで,数年前とは想像もできませんでした。
平野朝雄先生の不朽の名著『神経病理を学ぶ人のために』の第4版「実相観入」のサイン入り書を手にしたのは,2003年5月30日と記載されています。この書を読み返す度に私は胸が熱くなり興奮が今も醒めません。つい先日発刊された思いで,数年前とは想像もできませんでした。
今年,姉妹編としての『カラーアトラス神経病理』第3版が発刊されました。第2版が出版されてから,18年余が経過したとのことです。初版と第2版の間が約10年ですから,第3版は約2倍の間隔をおいて再版されたことになり,間隔があきすぎた感がありますが,脳腫瘍のWHOのブルーブックやGreenfieldのNeuropathologyなどが相次いで数年前に改版出版されたことを考えるとタイムリーであります。このアトラスには新たに多数のカラー写真が追加されており,執筆された諸先生方のご努力にも敬意を表します。
このカラーアトラスを3回ほど拝読し,美しい写真を見つめていると,木下利玄の「牡丹花 咲き定まりて静かなり花の占めたる位置のたしかさ」が脳裏に浮かんできました。表現方法はきわめて平凡ですが,花の占める正確な位置とその重厚さが遺憾なく表現されています。先生の写真説明の言葉は簡明で無駄など一語もなく,長年の研究活動を通して磨き上げられた鋭い洞察力をベースに表現されたもので,一語一語の重さとその位置の確かさは,小生などには評者としての資格がまったくないことを悟らされます。忌憚のない感想を述べて書評に換えさせていただきます。
「病理学は肉眼で見,顕微鏡で確認した像が基本となって学問が成立している」と先生が言われているように,写真の3分の1以上が肉眼写真であります。神経科学の進んだ現在ではもう見られない貴重な写真も多数掲載されています。図160の橋中心性髄鞘崩壊の説明でも,「橋の中心部に……一見梗塞のように見えるが……細胞体や軸索はよく保たれているのが本症の特徴である」と説明されています。「よく見ると」や,「一見」などの言葉がよく使われています。丁寧にかつ十分病変を観察し,正確に病変の特徴を見抜いてくださいという先生の声が聞こえてきます。加えて,的確で簡明なコメントも付記されておりますが,一語の無駄もありません。これを念頭において所見や説明のコメントを読んでいただきたい。
ミクロの世界でも,病変を理解するために,適材適所に正常のミクロ像が挿入されており,病変を理解するために大変役立つように考慮されています。終わりの約10ページには最近提唱された疾患概念と新しい染色方法による所見が掲載されています。今までの染色法では見出せなかった所見もあり,方法論の重要性にも言及されています。
最後に,このカラーアトラスの写真はすべて厳選されたすばらしいものばかりですが,写真の説明を読んで写真を眺めるのではなく,先生の長年の真摯な研究活動がこれらの写真に凝縮されていることを思い,拝読すれば,得るものが倍加されることは間違いないと信じています。
幸運にも,平野朝雄先生の母国が私と同じ日本であることで,世界に先駆けてこの名著をいち早く座右に置けることの幸せを噛みしめつつ,感想文(書評)とさせていただきます。
A4・頁264 定価18,900円(税5%込)医学書院
