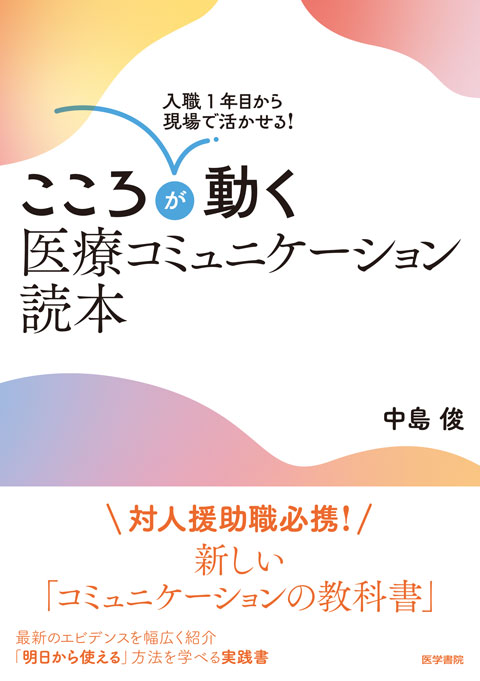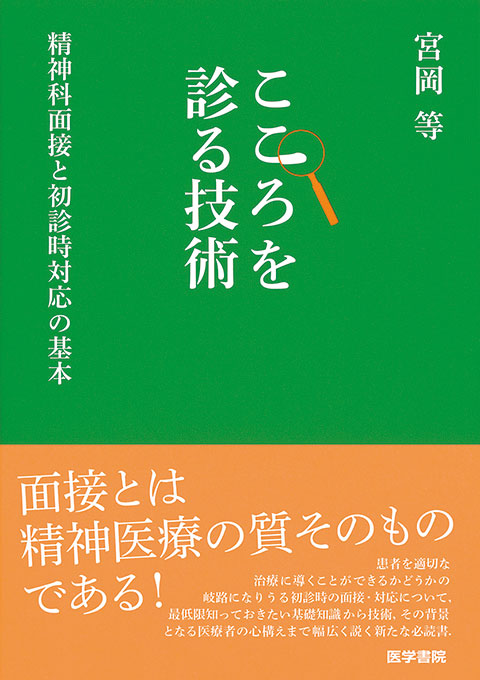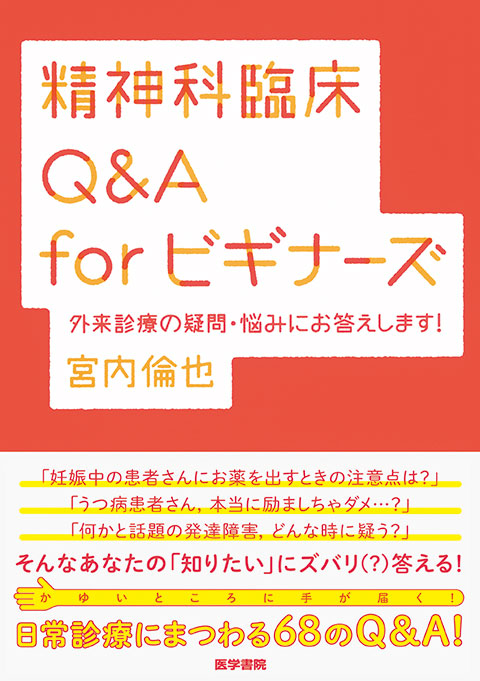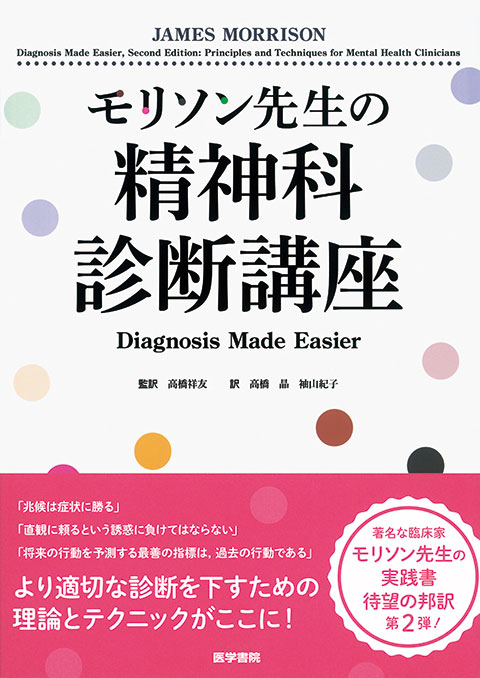こころの病を診るということ
私の伝えたい精神科診療の基本
臨床家は何を見て、どう考えているか
もっと見る
臨床家として名高い著者が、自身の臨床哲学および具体的な診療の仕方についてまとめた実践書。待合室での様子や問診票から読み取れること、問診の進め方、生活史のとらえ方、診断、そして治療と、実際の診療の流れをひと通り網羅。約40年にわたる臨床経験で蓄積された理論と技術を、次世代の精神医療関係者に余すところなく伝授する。
| 著 | 青木 省三 |
|---|---|
| 発行 | 2017年04月判型:A5頁:296 |
| ISBN | 978-4-260-03020-5 |
| 定価 | 3,300円 (本体3,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
新人の精神科医にとって、患者さんを担当し診察を行うことは、最初はとても緊張し不安なものである。診察室にやって来る患者さんは、しばしば自分よりも年上で人生経験も豊かである。話を聞いていても、精神症状なのか人生の悩みなのかよくわからない。病気の診断としては、いくつかの精神症状を認め、○○病かな、とも思うが、いまひとつ自信がない。精神療法をしようとしても何を話したらよいのかわからない。薬を処方しようとしても、何をどのくらいの量から始めるのが妥当なのか、そして作用・副作用を含めて、どのように説明したらよいのかなど、診察の1つひとつが不安になる。
そのようなとき、現症と現病歴をたずね、精神症状を把握し、操作的診断基準を用いて診断し、治療ガイドラインや薬物アルゴリズムに従って治療していくという診療スタイルは明確であり、心強い。わが国にも諸外国にも優れたガイドラインがあり、それらはこれまでの研究のエビデンスに基づいており、地域や国を越えて、一定のレベルの診断と治療を提供し、有意義である。
だが、臨床はそれだけで十分というものではない。精神症状の背景にある、患者さんの生きてきた人生と生きている毎日、これからの生活、そしてその苦労や喜びを聞きながら、その人の生きている日々が少しでもよいものとなるように支援することが求められる。それは症状を改善・消失させることを目標にはするが、仮に症状がなくならなくても、その人が楽しみや潤いのある人生を送れるようにする、すなわち人生の質を少しでもよいものとするということである。これは先達・先輩たちから受け継がれてきた、経験的・伝統的な治療といってもよいかもしれない。
病気を治す治療と、より質のよい人生と生活を目指す治療は、相反するものではなく、一方の限界をもう一方が補うというような相補的なものである。両者が対となって、初めて臨床は生きたものとなると筆者は考える。
また、これからの成人の臨床においては、発達やトラウマ反応を視野に入れるという発達精神医学的視点が、これまで以上に求められる。その人を理解するためには、現在の症状を横断的に切りとるのでは不十分である。人の基盤である、もって生まれたものとその後の発達過程、生活史を加味しながら精神症状について考えていこうとするのである。もって生まれたものと、環境からの影響と、そして本人の意思や考えが影響し合う発達歴・生活史のなかに、現在の症状を置いて考えたとき、初めてその人の症状がより深く理解でき、より遠くまでを見る治療や支援を考えることができる。
本書は、これから精神科医療の道に進もうとしている先生方と、それだけでなく経験を積んだ先生方にも、筆者が、これまでに学び、迷いながら考えたことなどを伝えたいという思いで記した。筆者自身が考えたこともあるが、先達や先輩、同僚から学んだことも記している。臨床においては、エビデンスが重要であると同時に、経験を蓄積し伝えていくことも重要である。読者の先生方には、自分の経験を通して本書を改変し、バージョンアップしていただきたい。精神科診療は、誰か一人の優れた臨床家が生まれればよいというものではない。誰もがその人らしい味のある優れた臨床家になるというのが目指す道である。
本書が今後の精神医療を担う人たちになんらかの示唆を与えるものとなることを心より願ってやまない。
2017年2月
青木省三
新人の精神科医にとって、患者さんを担当し診察を行うことは、最初はとても緊張し不安なものである。診察室にやって来る患者さんは、しばしば自分よりも年上で人生経験も豊かである。話を聞いていても、精神症状なのか人生の悩みなのかよくわからない。病気の診断としては、いくつかの精神症状を認め、○○病かな、とも思うが、いまひとつ自信がない。精神療法をしようとしても何を話したらよいのかわからない。薬を処方しようとしても、何をどのくらいの量から始めるのが妥当なのか、そして作用・副作用を含めて、どのように説明したらよいのかなど、診察の1つひとつが不安になる。
そのようなとき、現症と現病歴をたずね、精神症状を把握し、操作的診断基準を用いて診断し、治療ガイドラインや薬物アルゴリズムに従って治療していくという診療スタイルは明確であり、心強い。わが国にも諸外国にも優れたガイドラインがあり、それらはこれまでの研究のエビデンスに基づいており、地域や国を越えて、一定のレベルの診断と治療を提供し、有意義である。
だが、臨床はそれだけで十分というものではない。精神症状の背景にある、患者さんの生きてきた人生と生きている毎日、これからの生活、そしてその苦労や喜びを聞きながら、その人の生きている日々が少しでもよいものとなるように支援することが求められる。それは症状を改善・消失させることを目標にはするが、仮に症状がなくならなくても、その人が楽しみや潤いのある人生を送れるようにする、すなわち人生の質を少しでもよいものとするということである。これは先達・先輩たちから受け継がれてきた、経験的・伝統的な治療といってもよいかもしれない。
病気を治す治療と、より質のよい人生と生活を目指す治療は、相反するものではなく、一方の限界をもう一方が補うというような相補的なものである。両者が対となって、初めて臨床は生きたものとなると筆者は考える。
また、これからの成人の臨床においては、発達やトラウマ反応を視野に入れるという発達精神医学的視点が、これまで以上に求められる。その人を理解するためには、現在の症状を横断的に切りとるのでは不十分である。人の基盤である、もって生まれたものとその後の発達過程、生活史を加味しながら精神症状について考えていこうとするのである。もって生まれたものと、環境からの影響と、そして本人の意思や考えが影響し合う発達歴・生活史のなかに、現在の症状を置いて考えたとき、初めてその人の症状がより深く理解でき、より遠くまでを見る治療や支援を考えることができる。
本書は、これから精神科医療の道に進もうとしている先生方と、それだけでなく経験を積んだ先生方にも、筆者が、これまでに学び、迷いながら考えたことなどを伝えたいという思いで記した。筆者自身が考えたこともあるが、先達や先輩、同僚から学んだことも記している。臨床においては、エビデンスが重要であると同時に、経験を蓄積し伝えていくことも重要である。読者の先生方には、自分の経験を通して本書を改変し、バージョンアップしていただきたい。精神科診療は、誰か一人の優れた臨床家が生まれればよいというものではない。誰もがその人らしい味のある優れた臨床家になるというのが目指す道である。
本書が今後の精神医療を担う人たちになんらかの示唆を与えるものとなることを心より願ってやまない。
2017年2月
青木省三
目次
開く
1 診察前に考える
受診時の様子はどうか
緊急性をアセスメントする
住んでいるところから見えてくるもの
問診表から何が読みとれるか
紹介状を意識しすぎない
2 診察を始める
患者さんは治療者を映す鏡である
「挨拶」の基本
出会いは柔らかく、穏やかに
「一人の人間」として出会う
表情から読みとれること
受診の経緯をどうたずねるか
誰が、何を問題視し、どんな目的で受診したのか
単身での受診の場合は家族の来院を求める
家族や付き添いの人の話をどう聞くか
患者さんのつらさを代弁する
器質的なものが背景にないか
3 主訴をたずねる
「開かれた質問」から「閉じられた質問」へ
話せることだけを話してもらう
「こころを読みとられる不安」を和らげる
本人と家族の主訴は区別して聞く
主訴を明確にする-異物化、対象化、外在化
話されない主訴に気づく
異物化させるのが難しい症状もある
サラッとたずねたほうがよい主訴もある
きちんとたずねたほうがよい主訴もある
わかろうとし、わかってもらおうとする
閉じられた質問を効果的に用いる
4 生活歴、既往歴、家族歴をたずねる
生活歴をたずねる
既往歴をたずねる
家族歴をたずねる
家族について考える
5 主観的な体験を理解し、客観的に観察する
主観的な体験を理解する
客観的に観察する
理解と観察のバランスをどうとるか
主観的な体験が現実から乖離している場合もある
病歴・生活歴は主観に修飾されている
主観的体験と客観的表出のズレ
6 診察の途中で考える
性格と発達特性をどうたずねるか
病気か、それとも性格か
スムーズに問診を進められない場合
楽なとき、ほっとするときをたずねる
好きなこと、得意なこと、趣味をたずねる
心理検査をより有用なものにするために
1~2度の受診で来なくなる患者さん
質問によって理解を深め、気持ちを汲む
7 言葉のやりとりを確かなものとする
患者さんにとってのコミュニケーション-筆者の体験から
うなずく、相槌を打つ、語尾を継ぐ、まとめて返す
言葉のキャッチボールの流れ
言葉でのコミュニケーションと共有する文化
精神科臨床におけるコミュニケーションの難しさ
8 複数の情報を総合する
診察室の外の患者さんを知る
場面によって異なった姿が現れる
回復の兆候はどこで現れるか
よい情報を共有する
9 生活を理解する
日常生活で、何にどのように困っているか
エピソードから生活を想像する
10 生活史を理解する
人生の大きな流れを知り、仮説を立てて考える
人生の負荷の増加と精神症状の出現
ケース(1):経済的困窮から抑うつ状態となった例
ケース(2):介護負担の増加でうつ病が遷延した例
ケース(3):人付き合いの減少で精神症状が出現した例
ケース(4):友人が少なく不登校となった例
ケース(5):脳梗塞後に妄想が出現した例
ケース(6):転地・転職を繰り返す例
ケース(7):生活への不安の軽減により症状が軽快した例
ケース(8):外傷体験の影響か判断に迷う例
11 診断する
診断・評価するというプロセス
外来受診の流れのなかで診断する
入院生活の広がりのなかで評価する
診断基準で見えるもの・見えないもの
非定型・非典型な病像や経過から考える
すべての人は非定型・非典型である
グレーゾーン診断の意義
診断を保留することもある
状態像診断からスタートする
了解可能と了解不能-内的体験を理解する
反応性と考えてみる
12 病気の経過(形)を知る
病気はどこへ向かっているか
統合失調症の発病過程と回復過程
うつ病の発病過程と回復過程
発達障害の反応性精神症状の増悪と回復
13 発達を視野に入れる
なぜ発達を視野に入れる必要があるのか?
発達障害を考えるときの前提
成人の発達障害の診断
社会性やコミュニケーションの障害
こだわり
ADHDについても考える
統合失調症との鑑別
保護を失うと破綻しやすい
苦手なことを任されると破綻しやすい
何が高度で、何が軽度か
その人なりの生き方を模索する
14 トラウマの影響を視野に入れる
体験の強度や内容に関係なくトラウマ反応は起こる
精神症状の基盤にあるトラウマ反応は気づきにくい
トラウマ反応は危機や負荷が強まったときに顕著となる
人に対する信頼の乏しさに目を向ける
現在のトラウマ反応に気づいていない場合もある
15 治療と支援の基本
精神科治療の目指すもの-人生と生活
個々の治療アプローチの総和として力を発揮する
人のこころを治せるのは“人”である
「保存的」「支持的」治療アプローチを基本とする
治療による外傷を最小限にする
生物学的な要因と心理学的な要因に対する働きかけ
本人が合わせるか、本人に合わせるか
生活へのアプローチ
16 薬物療法
薬物療法の位置づけ
治療全体のなかでの薬物療法の役割を考える
薬物療法からスタートする場合
処方を迷う場合は2~3回の診察を経て考える
どのように処方するかによって薬の効果は大きく異なる
「薬が効く感じがする」ときほど注意を要する
処方の変更や中止の際は時間をかけて説明する
症状に対して薬を処方していると多剤併用となりやすい
服薬感を伝えて不安や恐怖を和らげる
「こころの痛み止め」として服薬する
よい人生を生きるために服薬する
服薬をお願いするときもある
17 精神療法
限られた時間を精神療法的にする
人柄精神療法-理論や技法以前に大切なもの
身体治療の小切開や外傷処置のイメージで行う
支持する
「これでよい」と肯定する
リフレーミング
小さなよい変化に気づき、大切にする
疲労に気づく
出会いと別れ
現実的な助言と配慮をていねいに
助言のバリエーションを増やす
「頑張りましょう」と助言する
日常生活に焦点を当てる-根源的な問題を日常生活の問題におきかえる
よい瞬間はないか
雑談をする
患者さんの治療意欲と希望を引き出す
穏やかで平和な雰囲気を提供する
18 治療者の姿勢・態度
「人のこころはわからない」というスタンス
医師という存在のもつ力
病気・障害の同質性と異質性
“中立的な態度”とはどういうものか
患者さんとの距離のとり方-近くか、遠くか
患者さんとの距離の調整の仕方-近くから、遠くへ
治療者は「冷静で親身な第三者」であるべき
治療者が自身のコンディションを自覚する
治療者に必要なのは仲間である-孤立を防ぐ
おわりに
索引
受診時の様子はどうか
緊急性をアセスメントする
住んでいるところから見えてくるもの
問診表から何が読みとれるか
紹介状を意識しすぎない
2 診察を始める
患者さんは治療者を映す鏡である
「挨拶」の基本
出会いは柔らかく、穏やかに
「一人の人間」として出会う
表情から読みとれること
受診の経緯をどうたずねるか
誰が、何を問題視し、どんな目的で受診したのか
単身での受診の場合は家族の来院を求める
家族や付き添いの人の話をどう聞くか
患者さんのつらさを代弁する
器質的なものが背景にないか
3 主訴をたずねる
「開かれた質問」から「閉じられた質問」へ
話せることだけを話してもらう
「こころを読みとられる不安」を和らげる
本人と家族の主訴は区別して聞く
主訴を明確にする-異物化、対象化、外在化
話されない主訴に気づく
異物化させるのが難しい症状もある
サラッとたずねたほうがよい主訴もある
きちんとたずねたほうがよい主訴もある
わかろうとし、わかってもらおうとする
閉じられた質問を効果的に用いる
4 生活歴、既往歴、家族歴をたずねる
生活歴をたずねる
既往歴をたずねる
家族歴をたずねる
家族について考える
5 主観的な体験を理解し、客観的に観察する
主観的な体験を理解する
客観的に観察する
理解と観察のバランスをどうとるか
主観的な体験が現実から乖離している場合もある
病歴・生活歴は主観に修飾されている
主観的体験と客観的表出のズレ
6 診察の途中で考える
性格と発達特性をどうたずねるか
病気か、それとも性格か
スムーズに問診を進められない場合
楽なとき、ほっとするときをたずねる
好きなこと、得意なこと、趣味をたずねる
心理検査をより有用なものにするために
1~2度の受診で来なくなる患者さん
質問によって理解を深め、気持ちを汲む
7 言葉のやりとりを確かなものとする
患者さんにとってのコミュニケーション-筆者の体験から
うなずく、相槌を打つ、語尾を継ぐ、まとめて返す
言葉のキャッチボールの流れ
言葉でのコミュニケーションと共有する文化
精神科臨床におけるコミュニケーションの難しさ
8 複数の情報を総合する
診察室の外の患者さんを知る
場面によって異なった姿が現れる
回復の兆候はどこで現れるか
よい情報を共有する
9 生活を理解する
日常生活で、何にどのように困っているか
エピソードから生活を想像する
10 生活史を理解する
人生の大きな流れを知り、仮説を立てて考える
人生の負荷の増加と精神症状の出現
ケース(1):経済的困窮から抑うつ状態となった例
ケース(2):介護負担の増加でうつ病が遷延した例
ケース(3):人付き合いの減少で精神症状が出現した例
ケース(4):友人が少なく不登校となった例
ケース(5):脳梗塞後に妄想が出現した例
ケース(6):転地・転職を繰り返す例
ケース(7):生活への不安の軽減により症状が軽快した例
ケース(8):外傷体験の影響か判断に迷う例
11 診断する
診断・評価するというプロセス
外来受診の流れのなかで診断する
入院生活の広がりのなかで評価する
診断基準で見えるもの・見えないもの
非定型・非典型な病像や経過から考える
すべての人は非定型・非典型である
グレーゾーン診断の意義
診断を保留することもある
状態像診断からスタートする
了解可能と了解不能-内的体験を理解する
反応性と考えてみる
12 病気の経過(形)を知る
病気はどこへ向かっているか
統合失調症の発病過程と回復過程
うつ病の発病過程と回復過程
発達障害の反応性精神症状の増悪と回復
13 発達を視野に入れる
なぜ発達を視野に入れる必要があるのか?
発達障害を考えるときの前提
成人の発達障害の診断
社会性やコミュニケーションの障害
こだわり
ADHDについても考える
統合失調症との鑑別
保護を失うと破綻しやすい
苦手なことを任されると破綻しやすい
何が高度で、何が軽度か
その人なりの生き方を模索する
14 トラウマの影響を視野に入れる
体験の強度や内容に関係なくトラウマ反応は起こる
精神症状の基盤にあるトラウマ反応は気づきにくい
トラウマ反応は危機や負荷が強まったときに顕著となる
人に対する信頼の乏しさに目を向ける
現在のトラウマ反応に気づいていない場合もある
15 治療と支援の基本
精神科治療の目指すもの-人生と生活
個々の治療アプローチの総和として力を発揮する
人のこころを治せるのは“人”である
「保存的」「支持的」治療アプローチを基本とする
治療による外傷を最小限にする
生物学的な要因と心理学的な要因に対する働きかけ
本人が合わせるか、本人に合わせるか
生活へのアプローチ
16 薬物療法
薬物療法の位置づけ
治療全体のなかでの薬物療法の役割を考える
薬物療法からスタートする場合
処方を迷う場合は2~3回の診察を経て考える
どのように処方するかによって薬の効果は大きく異なる
「薬が効く感じがする」ときほど注意を要する
処方の変更や中止の際は時間をかけて説明する
症状に対して薬を処方していると多剤併用となりやすい
服薬感を伝えて不安や恐怖を和らげる
「こころの痛み止め」として服薬する
よい人生を生きるために服薬する
服薬をお願いするときもある
17 精神療法
限られた時間を精神療法的にする
人柄精神療法-理論や技法以前に大切なもの
身体治療の小切開や外傷処置のイメージで行う
支持する
「これでよい」と肯定する
リフレーミング
小さなよい変化に気づき、大切にする
疲労に気づく
出会いと別れ
現実的な助言と配慮をていねいに
助言のバリエーションを増やす
「頑張りましょう」と助言する
日常生活に焦点を当てる-根源的な問題を日常生活の問題におきかえる
よい瞬間はないか
雑談をする
患者さんの治療意欲と希望を引き出す
穏やかで平和な雰囲気を提供する
18 治療者の姿勢・態度
「人のこころはわからない」というスタンス
医師という存在のもつ力
病気・障害の同質性と異質性
“中立的な態度”とはどういうものか
患者さんとの距離のとり方-近くか、遠くか
患者さんとの距離の調整の仕方-近くから、遠くへ
治療者は「冷静で親身な第三者」であるべき
治療者が自身のコンディションを自覚する
治療者に必要なのは仲間である-孤立を防ぐ
おわりに
索引
書評
開く
著者の診療に陪席したような味わいのある一冊
書評者: 加藤 忠史 (理化学研究所精神疾患動態研究チーム・シニアチームリーダー)
評者が研修医だった頃,精神科診療の基本は『精神科診断面接のコツ』(神田橋條治,岩崎学術出版社)や『予診・初診・初期治療』(笠原 嘉,診療新社),『精神療法の実際』(成田善弘編著,新興医学出版社)などの本で勉強した。その後,精神疾患啓発が進んで受診のハードルが低下したこと,事例化が早くなったこと,統合失調症の軽症化などの変化に加え,発達障害の考え方など精神医学自体も変化してきた。上記の名著が伝える精神科診療の基本に変化はないが,現代の研修医が基本を学ぶのに適した本とは何だろうか。
まさにその答えがこの本である。タイトルは系統的な原則論との印象だが,実際には,豊富な実例が紹介され,青木省三教授の診療に何か月か陪席して,治療経過を見届けたかのような味わいがある。患者さんの待合室での様子の観察や呼び込み方など,隅々まで気配りされた丁寧な診察の様子を垣間見ることができる。
症状を対象化させることについては,症状をくっきりとさせる,患者さんの“困り感”を育む,医師―患者関係は,“患者さんの症状は実は治療者の表情を映し出す鏡かもしれない”など,精神科診療の基本がわかりやすい言葉で語られている。
また,精神科治療が外傷的となりうるという重要な点について,多くのページを割いて述べ,紹介状記載による先入観で患者さんからパーソナリティ障害的言動を引き出してしまう危険性への警告や,「内容は話さなくてよいけれど,何か困っていることがありますか?」「私の話したことで,後になって心配になっていることはないですか?」といった具体的な言葉のかけ方,“患者さんの体験と自身の体験が連続的なものであるという認識こそが,外傷的な治療となることへのブレーキとなる”といった心構えも大変有意義である。
そして,期待通り,発達障害圏の人の診療やトラウマという視点など,現代的な課題についての記載は特に充実している。近年,「悪口を言われている」などと受診する人の多くは発達障害の反応性の状態であることや,かろうじて生きてきた発達障害の人が,自分を守ってくれる存在を失い,社会性を求められて抑うつ状態になるといった事例を紹介し,発達障害圏の人の診療のコツを示している。
発達障害の特性は初診で際立ちやすく,代診は診断や治療方針の見直しのためにも意義深い,といった指摘や,「あなたの趣味や考えは,今はあまり理解してくれる人がいないかもしれないけど,(中略)これからは少しずつ楽なほうにむかっていく」(p.132)という声掛けなど,さりげない診療の工夫が満載である。
以前は患者さんと距離を置くことが重視されたが,最初からあっさりしている現代の若者に対しては,むしろ親身になることを勧めているというのも,医師のメンタリティーの変化も考慮が必要なのか,と納得した。
豊富な症例を読むたびに,自らが経験したケースが思い起こされ,あのとき,こういうアプローチもできたかな,などといろいろ考えさせられる。研修医が初期に読む本として最適であることはもちろん,シニアな精神科医でも,必ず何かの発見がある本だと思う。
精神医学の不明確な点をどう理解すべきかが語られた一冊
書評者: 松﨑 朝樹 (筑波大講師・精神神経科)
こころに問題を抱える者を前にして,われわれはどのように診療に当たっているだろうか。明確な項目や基準が挙げられた診断基準の使用が普及しつつあり,さまざまな精神障害に対する治療のガイドラインも作成されていることからすれば,すべきことは明確になったように見える。しかし,精神科の医療の全てが明確になったわけではない。精神医学で扱われるものが人のこころや人生である以上,そこには人間的な理解や関わりが必要とされ,アルゴリズムやガイドラインに書かれている事などは実際に必要となる精神科の臨床の一部でしかない。では,精神科に関わる医療者の正しいあり方とはどのようなものだろうか……そんな精神医学における不明確な点をどう理解し,どう対応すべきか,それが語られたのがこの本である。
解説は実際の臨床に沿って始められる。初めて精神科の病院を訪れた者に対してどのように話を始めるべきか,診療情報提供書や問診票を手に何を思うべきか,患者の様子から何を知ることができるのかなど,情報をどう拾い上げ,その精神障害や人物,人生をどう理解し,どう診断を下し,その診断とどう向き合うべきだろうか。診断を下した後,患者と関係を作り,維持し,治療的に関わる中,さまざまな言葉や薬を手に,どのように寄り添い,回復へと導き,その方向を見定めるべきだろうか。さらには患者の中には怒る人もいれば,自殺を試みる人もいれば,話が止まらない人もいるが,どのように対処すべきだろうか。そのような実臨床におけるさまざまな物事につき,ときに極めて細やかに,ときに大局的な視点から理解を助けるよう,あるときには非常に理論的に,あるときには非常に具体的に語られている。
精神医療の正しいあり方につき語られる上で,個人的な考えが語られるだけであったり,学問ばかりで血の通わぬものだったりするようではいけない。先輩の背中を見ながら時間をかけて独自に体得してきた者も多いとは思われるが,正しい理論に基づいた事を学ぶ機会は限られる。そんな中,豊富な臨床経験を積みながら,同時に精神医学に学問として向き合ってきた著者だからこそ書けたこの本は大きな助けとなるであろう。さまざまな状態や障害,さまざまな局面の症例が挙げられる中,丁寧に書かれた解説は,まるで青木先生の外来に陪席し,病棟での診察に同行しながら解説を受けているかのようである。そこから臨床に生かせるアイデアや考え方について学べる事は多く,迷ったとき,困ったとき,臨床家としてさらに一歩前へと進みたいときに何らかの答えを与えてくれることだろう。
新しく精神科医として学び始めた者にとっては良い教科書となり,もう既に精神科医として経験を積んできた人にとっても改めて患者との関わり方を今一度見直す良い機会が得られる一冊といえよう。
患者の日常・生活に絶えず目を注ぐ精神科臨床の極意
書評者: 滝川 一廣 (学習院大教授・心理学)
著者,青木省三先生の日々の診療の姿が目に浮かぶ本である。さまざまな知恵や工夫が語られているけれども,それを知識として覚えるよりも,その姿を思い浮かべながら,つまり,診療に陪席しているつもりで読んでいくとよい。陪席しているかのように読み進められる希有な診療の書である。
症例が数多く出てきて,その多くが「症例→仮説→対応→ポイント」というかたちで語られている。「症例」を読んだところでいったん本を置いて,自分ならどんな仮説を持ちどう対応するだろうかと考えてから(できればメモしておいて)先を読むことをお薦めしたい。臨床家として力を伸ばすのに役立つし,著者青木先生の診療への理解も深まるだろう。陪席とは“見学”することではなく“参加”することである。これはそのように参加的に読むべき(それができる)本であり,著者の読者への願いもそこにあると思う。参加的に読めば,ここにあるのはマニュアル的なノウハウではなく,個々の患者や状況へのその都度の理解から生み出される配慮や工夫であることがよくわかる。
本書の診療に特定の技法やプログラムは出てこない。治療理論が説かれるわけでもない。では無手勝流や行き当たりばったりかといえば,もちろん違う。診療の基底に流れているのものは何だろうか。ぴたっと言い当てる言葉がみつからなくもどかしいが,あえて“日常性”と呼んでみたい。
「次の方,どうぞ」,患者を診察室に招じ入れて話を聴く。5分で済むことも,20分,30分のときもある。いつも真剣に耳を傾ける。話が終わって診察室を出る姿を見送りながら,その患者に思いを馳せる。そうした毎日を5年,10年,15年と重ね,それはすっかり日常の営みとなって治療者のこころの底に根付いている。そうした日常の連なりと重なりから生み出されるある感覚や居ずまいのようなものが,青木先生の臨床を貫く一本のしなやかな筋金になっている。何らかの高度な(ある意味で“非日常的”な)専門技術の駆使によってプロフェッショナルたらんとするのも一つの方向だけれども,青木先生はそれとは別の方向に自身の臨床を鍛えてこられたと思う(もちろん,専門技術を持っておられないという意味ではない)。
この“日常性”は,“生活性”と言い換えてもよいかもしれない。青木先生が絶えず目を注ぐのは,患者の「日常」,すなわち“生活”である。患者がどんな生活体験をしてきて,今どう生活しているのか? そこで何にぶつかっているのか? その生活を少しでもよきものとするにはどうしたら? その患者にとってよき生活とは? そして人間の“生活”とはひとりで成り立つものではない。そこまで視野に入れた手助けとは? 暮らし向きのありよう(実生活)から日々の哀歓のありよう(精神生活)まで,患者の生活を深くまなざそうとする姿勢が臨床の基本線となっている。
また,“常識性”という言い方もできるかもしれない。捻りに捻った解釈も,入り組んだ晦渋(かいじゅう)な説明付けも,あっと驚くパラドックス的アプローチも出てこず,理解の仕方も働き掛けも,とても常識的なものである。“常識”とは“ありきたりの表面的理解”や“流布されわたった一般通念”を意味するのではなく,私たちの生活意識や日常感覚に照らして無理のない,確かな納得を持って共有できる理解(common sence)のことを指す。日常性と生活性とに裏打ちされた深い“常識性”が,患者の生活やこころをより広がりを持つもの,より自由なものへと開き得るのである。
ワクワクしながら読む小説のように(雑誌『精神看護』より)
書評者: 村本 好孝 (精神看護専門看護師/精神科認定看護師/認定看護管理者/フリーランス看護師(株式会社ここから))
初めて手にして読み始めた時に一番に感じたのは「読みやすさ」である。まるで楽しい小説を読み進める時のように、ワクワクしながらもスムーズに入っていけた。
患者や家族が最初に出会うのは「受付のスタッフ」であると著者は書く。いかに一緒に働くスタッフを大事に考えているか、スタッフの専門性を大切にしているかがわかる。
自分自身は看護師であるが、本書を読みながら、自分が支援していることや考えていることが間違っていないと感じることができた。その時に、少し「ほっ」とする自分がいた。日々の臨床では、どうしても自分たちのやっていることが「本当にいいのか……」と思う機会が少なからずあるからだ。
本書には、著者が日々の臨床で患者や家族にかかわる時に考えていること、聞いていること、また、診るためにどのような工夫をしているのか、どのような言葉をかけているのかが丁寧に書かれている。まさに実際にかかわってきた方々とのやり取りがある。
症例としてさまざまな疾患や背景をお持ちの方が紹介され、具体的なかかわり方を学ぶことにつながる。多くのコミュニケーションの具体的な方法に加えて、コミュニケーションの意義を学ぶことができる。
面接では、総合された情報から生活史を理解し支援が始まる。「仮説」「対応」「ポイント」の詳細が書かれ、著者がどのようなことを考えてかかわっているかを、実際に目の前で見ながら解説を受けているかのように学ぶことができる。
「薬物療法」では、具体的な処方内容よりも、著者の姿勢や考え方が学べる。「精神療法」では、これが「人を癒すということか」と共感する。発達障害への支援やトラウマ治療にも触れ、まさに今の臨床の悩みを解消してくれる。
もう1つ感じたのは、そのエピソードに登場する方たちが、生活者としての人生を感じさせる言葉で表現されていることである。生活している情景が浮かび、感情が伝わってくる。疾患への治療ガイドラインや方法を学ぶことも大切であるが、支援の対象である方を「患者」としてだけ診るのではなく、1人の人として、かけがえのない人生を歩んでいる方として診るということ。その基本があればこそ、その方が病になって支援者と出会った時、支援者が何をする人なのかを学ばせてもらえる。学びというよりも感じさせてくれると表現したほうが適切かもしれない。それは、青木先生が後に続く後輩に伝わるように語りかけるように書かれているからだと思う(あとがきを読んで、やっぱり……と思った)。まさに副題にあるように、「私の伝えたい精神科診療の基本」の書なのだ。
(『精神看護』2017年9月号掲載)
書評者: 加藤 忠史 (理化学研究所精神疾患動態研究チーム・シニアチームリーダー)
評者が研修医だった頃,精神科診療の基本は『精神科診断面接のコツ』(神田橋條治,岩崎学術出版社)や『予診・初診・初期治療』(笠原 嘉,診療新社),『精神療法の実際』(成田善弘編著,新興医学出版社)などの本で勉強した。その後,精神疾患啓発が進んで受診のハードルが低下したこと,事例化が早くなったこと,統合失調症の軽症化などの変化に加え,発達障害の考え方など精神医学自体も変化してきた。上記の名著が伝える精神科診療の基本に変化はないが,現代の研修医が基本を学ぶのに適した本とは何だろうか。
まさにその答えがこの本である。タイトルは系統的な原則論との印象だが,実際には,豊富な実例が紹介され,青木省三教授の診療に何か月か陪席して,治療経過を見届けたかのような味わいがある。患者さんの待合室での様子の観察や呼び込み方など,隅々まで気配りされた丁寧な診察の様子を垣間見ることができる。
症状を対象化させることについては,症状をくっきりとさせる,患者さんの“困り感”を育む,医師―患者関係は,“患者さんの症状は実は治療者の表情を映し出す鏡かもしれない”など,精神科診療の基本がわかりやすい言葉で語られている。
また,精神科治療が外傷的となりうるという重要な点について,多くのページを割いて述べ,紹介状記載による先入観で患者さんからパーソナリティ障害的言動を引き出してしまう危険性への警告や,「内容は話さなくてよいけれど,何か困っていることがありますか?」「私の話したことで,後になって心配になっていることはないですか?」といった具体的な言葉のかけ方,“患者さんの体験と自身の体験が連続的なものであるという認識こそが,外傷的な治療となることへのブレーキとなる”といった心構えも大変有意義である。
そして,期待通り,発達障害圏の人の診療やトラウマという視点など,現代的な課題についての記載は特に充実している。近年,「悪口を言われている」などと受診する人の多くは発達障害の反応性の状態であることや,かろうじて生きてきた発達障害の人が,自分を守ってくれる存在を失い,社会性を求められて抑うつ状態になるといった事例を紹介し,発達障害圏の人の診療のコツを示している。
発達障害の特性は初診で際立ちやすく,代診は診断や治療方針の見直しのためにも意義深い,といった指摘や,「あなたの趣味や考えは,今はあまり理解してくれる人がいないかもしれないけど,(中略)これからは少しずつ楽なほうにむかっていく」(p.132)という声掛けなど,さりげない診療の工夫が満載である。
以前は患者さんと距離を置くことが重視されたが,最初からあっさりしている現代の若者に対しては,むしろ親身になることを勧めているというのも,医師のメンタリティーの変化も考慮が必要なのか,と納得した。
豊富な症例を読むたびに,自らが経験したケースが思い起こされ,あのとき,こういうアプローチもできたかな,などといろいろ考えさせられる。研修医が初期に読む本として最適であることはもちろん,シニアな精神科医でも,必ず何かの発見がある本だと思う。
精神医学の不明確な点をどう理解すべきかが語られた一冊
書評者: 松﨑 朝樹 (筑波大講師・精神神経科)
こころに問題を抱える者を前にして,われわれはどのように診療に当たっているだろうか。明確な項目や基準が挙げられた診断基準の使用が普及しつつあり,さまざまな精神障害に対する治療のガイドラインも作成されていることからすれば,すべきことは明確になったように見える。しかし,精神科の医療の全てが明確になったわけではない。精神医学で扱われるものが人のこころや人生である以上,そこには人間的な理解や関わりが必要とされ,アルゴリズムやガイドラインに書かれている事などは実際に必要となる精神科の臨床の一部でしかない。では,精神科に関わる医療者の正しいあり方とはどのようなものだろうか……そんな精神医学における不明確な点をどう理解し,どう対応すべきか,それが語られたのがこの本である。
解説は実際の臨床に沿って始められる。初めて精神科の病院を訪れた者に対してどのように話を始めるべきか,診療情報提供書や問診票を手に何を思うべきか,患者の様子から何を知ることができるのかなど,情報をどう拾い上げ,その精神障害や人物,人生をどう理解し,どう診断を下し,その診断とどう向き合うべきだろうか。診断を下した後,患者と関係を作り,維持し,治療的に関わる中,さまざまな言葉や薬を手に,どのように寄り添い,回復へと導き,その方向を見定めるべきだろうか。さらには患者の中には怒る人もいれば,自殺を試みる人もいれば,話が止まらない人もいるが,どのように対処すべきだろうか。そのような実臨床におけるさまざまな物事につき,ときに極めて細やかに,ときに大局的な視点から理解を助けるよう,あるときには非常に理論的に,あるときには非常に具体的に語られている。
精神医療の正しいあり方につき語られる上で,個人的な考えが語られるだけであったり,学問ばかりで血の通わぬものだったりするようではいけない。先輩の背中を見ながら時間をかけて独自に体得してきた者も多いとは思われるが,正しい理論に基づいた事を学ぶ機会は限られる。そんな中,豊富な臨床経験を積みながら,同時に精神医学に学問として向き合ってきた著者だからこそ書けたこの本は大きな助けとなるであろう。さまざまな状態や障害,さまざまな局面の症例が挙げられる中,丁寧に書かれた解説は,まるで青木先生の外来に陪席し,病棟での診察に同行しながら解説を受けているかのようである。そこから臨床に生かせるアイデアや考え方について学べる事は多く,迷ったとき,困ったとき,臨床家としてさらに一歩前へと進みたいときに何らかの答えを与えてくれることだろう。
新しく精神科医として学び始めた者にとっては良い教科書となり,もう既に精神科医として経験を積んできた人にとっても改めて患者との関わり方を今一度見直す良い機会が得られる一冊といえよう。
患者の日常・生活に絶えず目を注ぐ精神科臨床の極意
書評者: 滝川 一廣 (学習院大教授・心理学)
著者,青木省三先生の日々の診療の姿が目に浮かぶ本である。さまざまな知恵や工夫が語られているけれども,それを知識として覚えるよりも,その姿を思い浮かべながら,つまり,診療に陪席しているつもりで読んでいくとよい。陪席しているかのように読み進められる希有な診療の書である。
症例が数多く出てきて,その多くが「症例→仮説→対応→ポイント」というかたちで語られている。「症例」を読んだところでいったん本を置いて,自分ならどんな仮説を持ちどう対応するだろうかと考えてから(できればメモしておいて)先を読むことをお薦めしたい。臨床家として力を伸ばすのに役立つし,著者青木先生の診療への理解も深まるだろう。陪席とは“見学”することではなく“参加”することである。これはそのように参加的に読むべき(それができる)本であり,著者の読者への願いもそこにあると思う。参加的に読めば,ここにあるのはマニュアル的なノウハウではなく,個々の患者や状況へのその都度の理解から生み出される配慮や工夫であることがよくわかる。
本書の診療に特定の技法やプログラムは出てこない。治療理論が説かれるわけでもない。では無手勝流や行き当たりばったりかといえば,もちろん違う。診療の基底に流れているのものは何だろうか。ぴたっと言い当てる言葉がみつからなくもどかしいが,あえて“日常性”と呼んでみたい。
「次の方,どうぞ」,患者を診察室に招じ入れて話を聴く。5分で済むことも,20分,30分のときもある。いつも真剣に耳を傾ける。話が終わって診察室を出る姿を見送りながら,その患者に思いを馳せる。そうした毎日を5年,10年,15年と重ね,それはすっかり日常の営みとなって治療者のこころの底に根付いている。そうした日常の連なりと重なりから生み出されるある感覚や居ずまいのようなものが,青木先生の臨床を貫く一本のしなやかな筋金になっている。何らかの高度な(ある意味で“非日常的”な)専門技術の駆使によってプロフェッショナルたらんとするのも一つの方向だけれども,青木先生はそれとは別の方向に自身の臨床を鍛えてこられたと思う(もちろん,専門技術を持っておられないという意味ではない)。
この“日常性”は,“生活性”と言い換えてもよいかもしれない。青木先生が絶えず目を注ぐのは,患者の「日常」,すなわち“生活”である。患者がどんな生活体験をしてきて,今どう生活しているのか? そこで何にぶつかっているのか? その生活を少しでもよきものとするにはどうしたら? その患者にとってよき生活とは? そして人間の“生活”とはひとりで成り立つものではない。そこまで視野に入れた手助けとは? 暮らし向きのありよう(実生活)から日々の哀歓のありよう(精神生活)まで,患者の生活を深くまなざそうとする姿勢が臨床の基本線となっている。
また,“常識性”という言い方もできるかもしれない。捻りに捻った解釈も,入り組んだ晦渋(かいじゅう)な説明付けも,あっと驚くパラドックス的アプローチも出てこず,理解の仕方も働き掛けも,とても常識的なものである。“常識”とは“ありきたりの表面的理解”や“流布されわたった一般通念”を意味するのではなく,私たちの生活意識や日常感覚に照らして無理のない,確かな納得を持って共有できる理解(common sence)のことを指す。日常性と生活性とに裏打ちされた深い“常識性”が,患者の生活やこころをより広がりを持つもの,より自由なものへと開き得るのである。
ワクワクしながら読む小説のように(雑誌『精神看護』より)
書評者: 村本 好孝 (精神看護専門看護師/精神科認定看護師/認定看護管理者/フリーランス看護師(株式会社ここから))
初めて手にして読み始めた時に一番に感じたのは「読みやすさ」である。まるで楽しい小説を読み進める時のように、ワクワクしながらもスムーズに入っていけた。
患者や家族が最初に出会うのは「受付のスタッフ」であると著者は書く。いかに一緒に働くスタッフを大事に考えているか、スタッフの専門性を大切にしているかがわかる。
自分自身は看護師であるが、本書を読みながら、自分が支援していることや考えていることが間違っていないと感じることができた。その時に、少し「ほっ」とする自分がいた。日々の臨床では、どうしても自分たちのやっていることが「本当にいいのか……」と思う機会が少なからずあるからだ。
本書には、著者が日々の臨床で患者や家族にかかわる時に考えていること、聞いていること、また、診るためにどのような工夫をしているのか、どのような言葉をかけているのかが丁寧に書かれている。まさに実際にかかわってきた方々とのやり取りがある。
症例としてさまざまな疾患や背景をお持ちの方が紹介され、具体的なかかわり方を学ぶことにつながる。多くのコミュニケーションの具体的な方法に加えて、コミュニケーションの意義を学ぶことができる。
面接では、総合された情報から生活史を理解し支援が始まる。「仮説」「対応」「ポイント」の詳細が書かれ、著者がどのようなことを考えてかかわっているかを、実際に目の前で見ながら解説を受けているかのように学ぶことができる。
「薬物療法」では、具体的な処方内容よりも、著者の姿勢や考え方が学べる。「精神療法」では、これが「人を癒すということか」と共感する。発達障害への支援やトラウマ治療にも触れ、まさに今の臨床の悩みを解消してくれる。
もう1つ感じたのは、そのエピソードに登場する方たちが、生活者としての人生を感じさせる言葉で表現されていることである。生活している情景が浮かび、感情が伝わってくる。疾患への治療ガイドラインや方法を学ぶことも大切であるが、支援の対象である方を「患者」としてだけ診るのではなく、1人の人として、かけがえのない人生を歩んでいる方として診るということ。その基本があればこそ、その方が病になって支援者と出会った時、支援者が何をする人なのかを学ばせてもらえる。学びというよりも感じさせてくれると表現したほうが適切かもしれない。それは、青木先生が後に続く後輩に伝わるように語りかけるように書かれているからだと思う(あとがきを読んで、やっぱり……と思った)。まさに副題にあるように、「私の伝えたい精神科診療の基本」の書なのだ。
(『精神看護』2017年9月号掲載)
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。