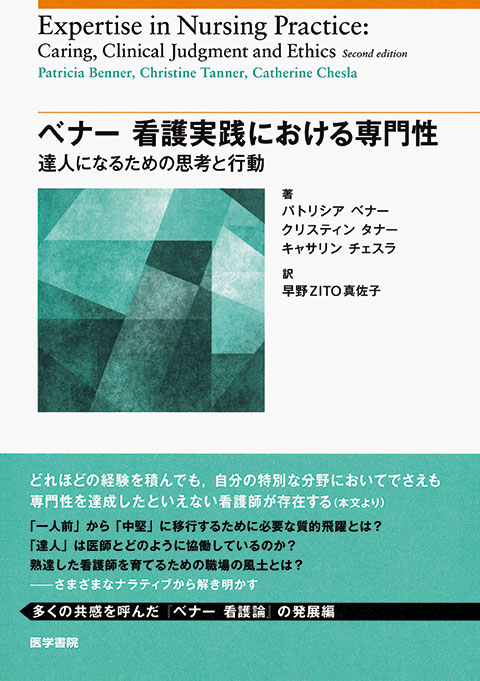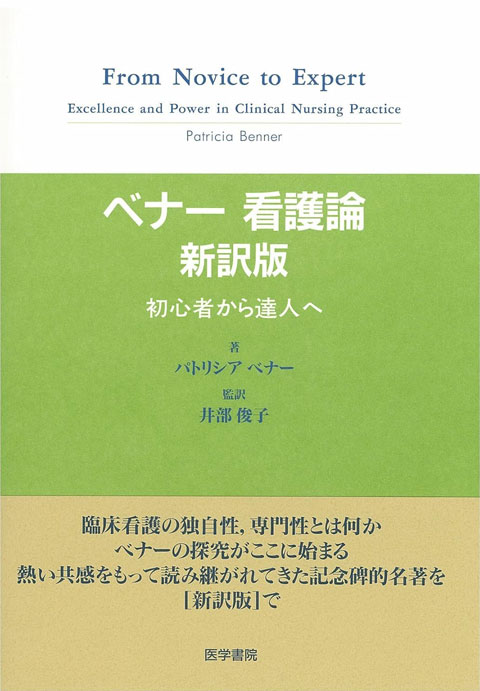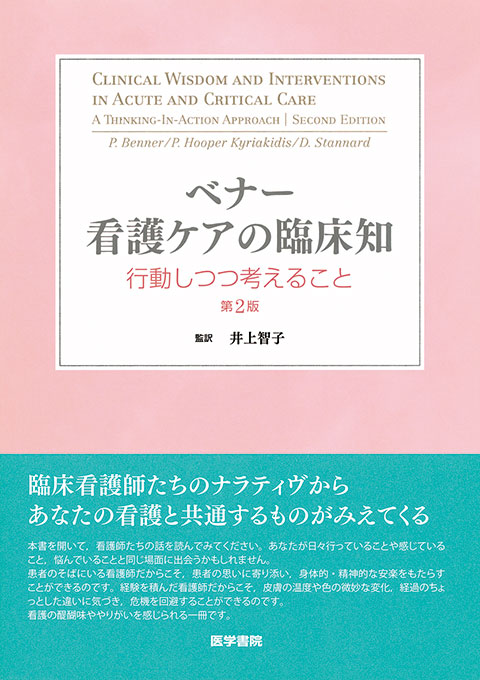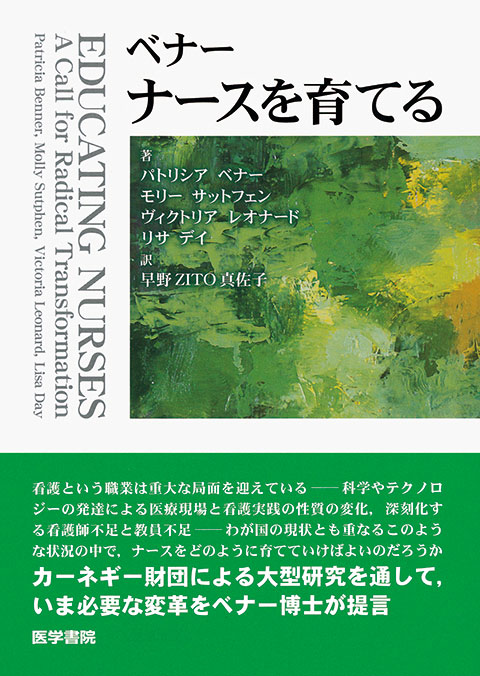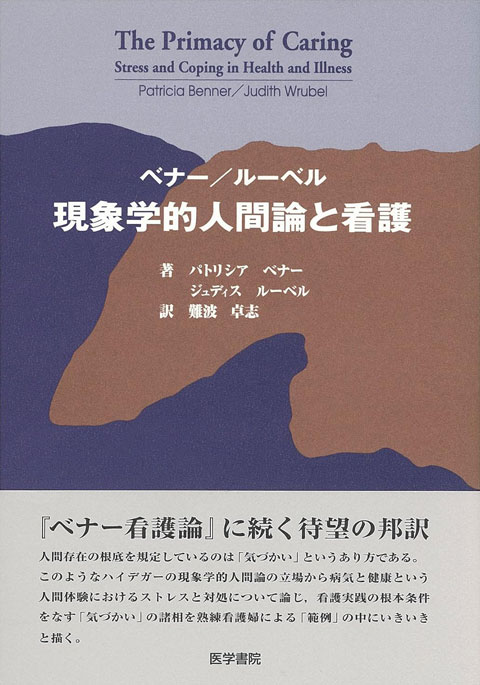ベナー 看護実践における専門性
達人になるための思考と行動
初心者・新人・一人前・中堅・達人は、臨床現場でどうふるまっているのか
もっと見る
| シリーズ | 看護理論 |
|---|---|
| 著 | パトリシア ベナー / クリスティン タナー / キャサリン チェスラ |
| 訳 | 早野 ZITO 真佐子 |
| 発行 | 2015年10月判型:A5頁:724 |
| ISBN | 978-4-260-02087-9 |
| 定価 | 6,160円 (本体5,600円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
本書(原書初版)が1996年に出版されて以降,多くの議論や対話,研究,実践的プロジェクトが生み出されてきた。とりわけ,新卒の看護師に対するインターンシップやオリエンテーションのプログラムの開発に大きく貢献し,同時に,より経験のある看護師の臨床実践をさらに進展させるようなプログラムの開発にも役立ってきた。看護師免許取得前の学生に対する看護教育プログラムにおける刷新や,そのような看護教育の実態に関する広範囲な研究に対しても,広く情報や導きを提供してきた。初版は,ドイツ語とノルウェー語に翻訳され,米国やその他多くの国で,実践や教育現場で使用されてきた。
本書で報告する研究は,スキルの獲得と看護実践に埋め込まれた知識の明瞭化を調査した三大研究のうちの1つである。第一の研究は,初版が1984年に,また第2版が2000年にアディソンウエズリー社から出版されたパトリシア・ベナーの画期的な著書『ベナー看護論—初心者から達人へ』(From Novice to Expert : Excellence and Power in Clinical Nursing Practice )である。第二の研究は,1994年に研究結果が発表され,本書の初版として1996年に出版されたものである。第三の研究は,1999年にその結果を発表した『ベナー 看護ケアの臨床知—行動しつつ考えること』(Clinical Wisdom and Interventions in Acute and Critical Care : A Thinking-in-Action Approach )である。
これら三大研究はすべて,ドレイファスのスキル獲得モデル(ドレイファスモデル)に基づいて行われた。応用数学者であるスチュアート・ドレイファス Stuart Dreyfus と哲学者であるヒューバート・ドレイファス Hubert Dreyfus は,チェス競技者,空軍のパイロット,陸軍の戦車操縦者および指揮官を対象とした研究を行い,スキル獲得のモデルを開発した(Dreyfus & Dreyfus, 1977;Dreyfus & Dreyfus, 1979;Dreyfus & Dreyfus, 1986)。ドレイファスモデルは発展的なもので,状況下での実践行動と経験的学習に基づいている。ドレイファス兄弟は,私たちのこれら3つの研究のそれぞれに,コンサルタントとして参加した*。* ドレイファスのスキル獲得モデルに従った研究の統合は,ベナーによってなされた(2005年)。
最初の研究である『ベナー看護論—初心者から達人へ』は,新卒看護師とそのプリセプターのペア21組に対するインタビューに基づいたものだ。さらに,経験のある看護師51人,新卒看護師11人,そして4年次の学生5人へのインタビューや実践現場での観察も行った。後者は,異なる教育や経験レベルにおける看護パフォーマンスの特性をさらに正確に詳細に記述するために行った。のちに『初心者から達人へ』として知られるようになったこの研究は,1978年から1981年に実施され(Benner, 1981, 1982),ドレイファスモデル(Dreyfus, 1982;Dreyfus & Dreyfus, 1979, 1986)を活用し,同時にその発展にも貢献した。ドレイファスモデルは,複雑でまだ十分な証拠で説明されていない分野における長期にわたる経験的学習を扱うものだ。このモデルは,コンピュータの専門性の連続的モデルとは対照的なものだ。コンピュータ・モデルは,秩序立ったもので,状況から切り離された要素1つずつを最初から定義し積み重ねていくものだ。一方,ドレイファスモデルは,状況に関する深い背景的(人間的)理解とその経時的関連性からスタートするものだ。このモデルは,特性的なモデルではなく状況的なものだ。焦点を当てるのは,特定の状況下における実際のパフォーマンスとその結果だ。このモデルは,特定の状況下でのパフォーマンスの変化が長時間にわたって比較されるという点において発展的なものだ。熟達したパフォーマンスを生み出す人の特性や能力に焦点を当てたり,それを同定するものではない。このモデルは,状況下における熟達した態度と知識の活用に焦点を当てている(Benner, Sutphen, Leonard-Kahn, & Day, 2010)。
他の実践領域と同じように,看護は,複雑で状況に左右される領域なので,“応用”領域に還元してしまうことは不可能だ。医学と同様に,看護実践は,複雑で,多様性があり,十分な証拠で説明されていないものだ。つまり,臨床家は,長時間にわたって,患者の反応や臨床症状の特質における変化に注意すると同時に,関連性の変化にも注意しなければならない。病状の経過のちょっとした変化や逸脱が,患者の臨床症状の特質を劇的に変化させてしまうかもしれない。よい実践を行うには,看護師は,実践者として優れた倫理的態度を発達させていかなければならないし,科学的証拠と技術の発達がもたらす情報に基づいて,よい臨床判断を行わなければならない。看護は,医学のように科学を活用する実践だ(Montgomery, 2005)。実践はその場にあって,技術,科学,理論を活用する。実践は,そのプロセスでその専門領域の規律を形成していく。しかしながら,最終的には,実践は,実際の状況において,知識を使い,その場で機能するものでなければならない。
医学や看護の科学は幅広く,複数の学問領域を拠りどころとしている。看護や医学で要求される知識やスキルを活用するには,特定の実践状況を解釈する能力やその状況との知的対話が要求される。生化学的,物理学的,生物学的,生理学的プロセスという基礎科学,特定の治療法や技術の研究や発展,さらに臨床試験などが,医学や看護の実践で使われる関連性ある幅広い科学を形成している。
実践の改善は,実際的な経験的学習と科学的実験の両方にかかっている。根拠に基づく看護や医学では,特定の臨床状態の治療に関する最善の実践をとりまとめて推奨するために,臨床試験の結果やその他の研究の結果の統合を模索する。しかしながら,科学的意思決定の論理と個々の症例やある特有の患者グループの治療を行う実践者たちの論理は,必然的に異なる。実践者は,患者の状態の変化やそのことに関する臨床家の理解の変化を通じて,特定のことがらについて経時的に理由づけをしていく。個々の症例における実践は,十分な証拠で説明されているものではないので,つまり科学で説明できないバリエーションにも対応するものなので,関連性のある科学を知的に選択し活用するためには,実践者は説得力のある臨床的論証* を展開しなければならない。臨床家が特定の臨床例に関して説得力ある臨床判断を行うには,顕著な徴候,症状,そして治療への反応を認識する鋭い知覚が必要だ。* 訳者注:clinical reasoningは,本邦では通常「臨床推論」と訳されるが,「推論」という言葉のイメージによって著者らの意図が誤解されることを避けるため,本書ではあえてその訳語を「臨床的論証」に統一した。著者らの意図は,けがや病気への患者の反応や,治療に対する反応について,経時的に思考し,理解し,推論し,結論を導くことのすべてを含んでいる(推論は,臨床的論証の一側面)。また,変化について経時的に行動しながら考えることで,「実践的論証(practical reasoning)」と言い換えることもできる。
患者の臨床的変化を一定の時間にわたって認識し把握するには,変化する状況下での論証という論理が必要となる(Benner, 1994d;Taylor, 1993)。臨床家は,これを,患者の傾向と病気や回復の軌跡を追うことだと理解している。これは,連続する変化のアウトカムに関する論証の一形態だ。患者の変化は,改善された,安定している,あるいは悪化しているとして,一定の時間にわたって評価されなければならない。臨床家は,これをその患者の“傾向を認識すること”とよぶ。実践には,標準化とアリストテレス Aristotle がテクネー(techne)と称した技術に影響される側面がある。バイタルサインの標準的な測定やラボの検査は,テクネーと称することのできる臨床アセスメントの事例である。しかし,そのテクネーをうまく行うための熟練と技巧は,経験に基づいていることが必須かもしれないということにも留意すべきだろう。患者特有の反応が考慮されなければならない状況,患者の顕著な変化を認識する鋭い知覚が要求される状況,関係性や判断が細やかに調整され巧みな対応が必要とされる状況などでは,テクネーとフロネーシス(phronesis)(スキル,判断,人格,英知に基づいた状況下での行動)のどちらも欠くことはできないのだ。
優れた臨床判断と臨床的知識の中心には,特定の症例からの経験的学習が必ず存在している。誤った判断は再考され,特定の症例では修正されなければならないし,異常性と特異性が認識されなければならない。ドレイファスモデルは,この種の複雑で証拠をもって明確に説明されていない,長い時間にわたる経験的学習を扱うものである。その焦点が,特定の状況における実際のパフォーマンスやアウトカムに置かれているために,このモデルは,どちらかといえば状況的モデルといえる。特定の状況におけるパフォーマンスの変化が,経時的に比較できるという点で発展的なものだ。しかしながら,それは,優れたパフォーマンスを行う人の具体的な特性や才能に焦点を当てたり,それを認識したりするものではない。
実践としての看護には,アリストテレスのいうテクネーとフロネーシスの両方が必要だ。テクネーは,手続き的で科学的な知識によって把握されるものだ。その知識は,秩序立っていて,明白で,特定の患者のために必要なタイミングと微調整を除けば,確実なものである。これとは対照的に,フロネーシスは,実践者のコミュニティに存在している,優れた実践者が行う実際的な論証の類である。優れた実践者は,継続的に経験的学習を重ね,優れた実践のために努力し,常に実践を改善し続ける(Benner, Hooper-Kyriakidis, & Stannard, 2000;Dunne, 1997;Gadamer, 1975;MacIntyre, 1981;Shulman, 1993)。テクネー,あるいはアウトカムを生む活動というものは,手段-目的の合理性によって支配される。つまり,メーカーとかプロデューサーが,アウトカムを生み出す手段に習熟することによって,生み出されるものを支配することになる。それとは対照的に,フロネーシスは,実践の中に存在する。そのために,手段-目的の合理性のみに依存することはできない。なぜならば,人の行為は,特定の状況において善を行うための関心によって支配されるからだ。そこで行動の指針となるのは,関係性の中に存在していることと特定の人間的問題を見極めることでなければならない。
技術と合理的で技術的な細かい知識だけでは,病気やけがで脆弱になっている人々をケアするために必要な,対人関係的・関係性的責任,洞察力,状況下での可能性に注意を向けることはできない。そこにはフロネーシスが必要となるのである。病気の人をケアする際に,手段と目的は,密接なかかわりをもつ。臨床家と患者が,お互いに心を傾け呼応し合うことによって,視野や世界が開けたり,それらを再構成したりもできる。そこに新たな可能性が生まれるのだ。
ドレイファスモデルが示唆するように,経験的学習には,事前に特定された明瞭な状況下で十分に確立されている知識を巧みに適用し,テクネーを用いる熟達者としての姿勢ではなく,関心を抱いて直接的にかかわろうとする学習者の姿勢が必要なのだ。経験的学習では,開かれた姿勢とものごとにすぐに反応する姿勢が学習者に要求される。学習者がそうした姿勢をもつことによって,その学習者の実践は,時間を経るにつれて改善されていくのだ。ドレイファスモデルが指摘するように,状況に合った実践・状況へ自在に反応する実践を構築していく学習者は,過去の具体的な経験に照らし合わせて全体的状況を認識することを学ぶのである。
私たちは,“特別な懸念事項がある症例”として状況へ対応することは,優れた実践の論理にとって非常に重要だと考える。ブルデューが指摘(Bourdieu, 1990)するように,状況の性質を理解することは実践的論証の核であり,臨床的論証はその実践的論証の一形態である。臨床的論証とは常に,患者の状態の移り変わりや患者の状態の変化や懸念を通してずっと,特定のことがらについて経時的に論証することだ。たとえば,臨床家は,この臨床状況は,心臓の“ポンプ”不全によるものなのか,体液喪失によるものなのかを認識し,その状況の本質を明瞭にするためにさらなるアセスメントを行ったりする。
熟達した実践者は,ものごとが暗黙の見込み通りに推移していない場合に,それを認識できるように,背景についての自分の理解を流動的または半透過的なかたちで維持することを学んでいるものだ。ブルデュー(Bourdieu, 1990)と同様に,私たちもまた,“特定の懸念事項がある症例”として状況へ対応することは,優れた実践の論理の中枢だと理解した。臨床実践は,医療チーム内で行われるものだ。たとえば,チェス競技や車の運転などといったスキルが要求される他のいくつかの状況では,熟達者が,行動を起こす前に自分の見地を明瞭に言語化する必要はない。それに対して,看護では,医師による適切な介入を得るために,症例を明確に言語化することが要求される。看護師の見地と根拠が明確に説明できなければならない。しかし,医師と看護師のどちらにも,自分の臨床的解釈を他の臨床家に明確に伝えることが要求される。医師が不在の時に起こった緊急事態に際しては,看護師が医師の事前指示書やプロトコルを使ったり,通常の看護実践の範囲を超えて対応することもあるが,看護師はその理由を明確に言葉で説明できなければならない。そのような対応は,患者の生存のために重要である時には予期されていることであり,弁護できるものだ。予想外の状況,つまり暗に周りが抱いている全体的な期待に患者の回復が沿っていない状況,を識別することは,熟達者の実践の証でもある。このことは,1984年の『ベナー看護論—初心者から達人へ』での研究内容を検証しさらに拡大した本研究を読むにあたって,背景に存在する情報として欠くことができない。
初心者(novice)段階のスキル獲得は,看護では一般的に,看護学生の臨床教育初年度において生じる。初心者段階の教育を凝縮したものをここに挿入する。看護学生はスキル獲得において初心者レベルのままで卒業できる,という誤解を払拭したいと思う。初心者レベルのままで,看護学校での学業を終え,看護の資格試験であるNCLEX-RN(National Council Licensure Examination-Registered Nurse)を受けることなど,誰にもできるはずがない! 1996年の研究では,学士課程の学生を研究対象とはせず,臨床実践を行っている免許を有する看護師のみを対象とした。したがって,本書では,新人(advanced beginner)——就業1年目の新卒の看護師と対照するために,スキル獲得の初心者段階をここに含めて紹介する。
【初心者:教育初年度】
スキル獲得の初心者段階において,学生は,臨床状況への基礎的アプローチや理解に関する経験的背景を全くもっていない。たとえば,そうした学生にとって,特定の患者に対するある一定範囲の医学介入や看護介入のアートやスキルは,未体験のものだ。教育者は,初心者が認識できるような状況の特徴や属性について十分に説明しなければならない。学生には,明確なパラメータやガイドラインを提供する。
経験ある臨床家なら,この評価は不適切,あるいは厳格すぎると考えられるあらゆる状況を即座に思い浮かべることができるだろう。しかし,異なるさまざまな臨床状態における体液バランスの重要性について学ぶまでは,初心者には,安全に進めていくための明瞭な指示が提供されるのだ。その際の原則やガイドラインには,ものごとを認識するために事前の経験を要求するようなものは含まれてはならない。規則やガイドラインは,臨床状況において,状況に埋め込まれた具体的なことがらについて学ぶために,安全な出発点を提供するものでなければならない。体液バランスは顕著なものだが,初心者が学ばなければならないのは,特定の患者の体液バランスにみられる特定の顕著さだ。
規則に支配される初心者の行動は,非常に限定されたもので柔軟性に欠ける。学生は,教科書に示された事例と実際の臨床事例とを比較したり一致させたりする訓練を受ける。実習室でマネキンを使って簡単に行うことができるスキルでも,実践では調整が必要になってくる。実際の患者は,落ち着いている場合も,非常に興奮している場合もあるので,その状況に応じて,コミュニケーションや安心感を与える態度や言葉かけなどのスキルが必要となるからだ。指導者は,患者をケアする状況の選択を注意深く行わなければならない。患者の状態が比較的安定していて,かつ変化の可能性についても指導できるような状況が必要だからだ。指導者は,学生がどのようなことを予期すべきかを予測する。そして,学生たちは,通常,標準的な看護計画に従って,計画されたケア活動を行っていく。指導者やその患者を担当する看護スタッフは,予期すべきことと禁忌を学生に明確に提示すべきだ。学生は,特定の状況におけるバイタルサインの意味について,指導者や看護スタッフと一緒に確認しなければならない。その特定の患者に対して,一定範囲の関連のある徴候や症状を,関連性という観点から確認し評価しなければならない。多くの徴候や症状(たとえば,嗜眠状態,皮膚緊張度,精神状態など)は,さまざまな患者を診た経験ののちに初めて認識し評価することができるものだ。初心者である学生は,患者対応の経験が非常に限定されているので,将来を予測する能力も当然非常に限定されている。通常,学生は,教科書にあるような典型的な予測を頼りにしなければならない。
ドレイファスモデルでは,初心者を“不合格の”実践者とか“欠陥がある”実践者とみなしたりしない。人間皆に共通することだが,経験と実践的知識以上のものはもち得ない新たな領域への新参者としてとらえる。学生は,必要な科学的および理論的背景を備えた最良の初心者,あるいは少なくとも積極的にかかわろうとする,良心的で,勤勉な初心者となる可能性を秘めている。そして,学生の経験レベルを考慮すれば“よくやっている”と評価される可能性もある。この段階におけるスキル獲得は,看護や医学など特定の臨床領域に埋め込まれている実践的な臨床的知識がどれほど複雑なのかを示している。初心者段階について考察する1つの方法は,その複雑さと幅の広さを認識することである。
『ベナー看護論—初心者から達人へ』が出版されなければ,世界各地の現場で働く看護師が,臨床における専門性の獲得や看護実践の領域についての明瞭な言語化に関してどのように反応するのか,誰も予測できなかっただろう。『初心者から達人へ』は,フィンランド語,ドイツ語,日本語,スペイン語,フランス語,デンマーク語,スウェーデン語,ロシア語,オランダ語,ポルトガル語に翻訳されている。
『ベナー看護論—初心者から達人へ』と本書は,世界各地における多くの看護学会,看護カリキュラム,多くの病院の臨床促進プログラムの情報源となってきた。看護師たちは,『ベナー看護論—初心者から達人へ』と本書『看護実践における専門性—達人になるための思考と行動』は,自分たちが臨床における看護実践について常に知ってはいたけれども,それを明確に表現できなかったことに言葉を与えてくれたとコメントしている。
本書は,『ベナー看護論—初心者から達人へ』(1984,2000)で始めたプロジェクトに光を当て,それを拡大するものだと確信している。『ベナー看護論—初心者から達人へ』に多少の変更を加え,多くのニュアンスを追加した。本書では,臨床実践の獲得についてより厚みのある記述をしており,臨床的知識,臨床的探究,臨床判断,および卓越した倫理的態度の本質について,これまでよりはるかに拡大した説明を提供している。本書は,病院に勤務する看護師130人を対象として行った6年間の研究に基づいたものだ。その130人のほとんどがクリティカルケア領域の看護師である。この研究で,私たちは,看護師の主体的な行動の本質を検証することによって,その知覚と行動が,実践のコミュニティによってどのように形成されるかということについて新たな洞察を得ることができた。ここでいう主体的な行動とは,特定の臨床状況で行動するための思慮分別と可能性である。「問題や状況への積極的な取り組み」と看護スキルとして必須である患者や家族に対する「主体的なかかわりのスキル」との相違をより明瞭に理解できるようになった。これら実存的なかかわりのスキル——治療の重要な局面や回復の時期において,患者や家族との適切な距離感を知覚すること——は,経験を通じ時間を経るに従って徐々に学んでいくものだ。実際,患者や家族へのかかわりのスキルは,看護の専門性を得る上で中心的なものだと主張したい。なぜならば,脆弱な人々の健康を促進させるには,問題への取り組みと個人的かかわりという実存的スキルの両方が必要になるからである。この研究を通じて,私たちは,臨床的意思決定と倫理的意思決定の相互の結びつき,つまり,実践者個人のよいアウトカムとわるいアウトカムに関する概念や卓越性のビジョンが,どのように臨床判断と行動を形成するか,ということを理解できるようになった。
この研究報告によりいっそうの統合性を保つために,各章の最後,そして付録Aで使われた方法論の記述の最後に解説を付記することとした。解釈のために使用したデータと方法論の提示は,この研究の正当性に密接にかかわっているために,現在は入手可能だが,本書の初版刊行時にはまだ公表されていなかった研究データを改めて解釈して,本書に追加するということはしないことにした。ただ,更新された知見に基づいて,その新たな知識が影響を与える2つの章を加筆修正した。また,本研究が実際に実践にどのような影響を与えたかという理解も加えた。さらに,初版刊行時以降に理解するようになった示唆についても加筆した。初版刊行時以降,スキル獲得,臨床的論証,行動しながらの思考に関する研究は,それまでより拡大されてきているが,今後は,本研究がどのような場に関連性をもつのかということへの言及がなされていくだろう。
本書としてまとめた第二の研究では,スキル獲得のそれぞれの段階* における新たな側面を発見したが,特に一人前レベル(competent)の段階が臨床での学習においては非常に重要だと考えるに至った。この段階は,学習者がパターンを認識し始めなければならない時期であり,次の中堅レベル(proficient)になるために,状況によって対応が導かれるようにならなければならない時期だからだ。また,中堅レベルの段階は,達人への移行期としてとらえるようになった。本研究では,一人前レベルから中堅レベルへの移行をコーチングするために,一人前レベルの段階における積極的な教育と学習の重要性を指摘した。一人前レベルの看護師が離職せずに定着するということは,現場における看護職全般の維持と看護実践の向上に非常に大きく貢献するものだ。一人前レベルの段階の看護師は,多くの疑問と新たな課題に遭遇する。この段階に達した看護師は,パフォーマンスが新たな域へ到達していて,文字通り新たな課題や軋轢に気づくからだ。この時期に達人レベルの看護師がコーチングを提供することは,価値ある投資だと考える。一人前レベルから中堅レベルへの移行期において,看護師がよくある困難に直面し,それゆえに最初の職場を辞めてしまえば,それは,中堅レベルや達人レベルへの移行に必要な時間を先延ばしにしてしまうだけだ。* 訳者注:ベナーはスキル獲得の段階を5つのレベルで表した。(1)初心者レベル(novice),(2)新人レベル(advanced beginner),(3)一人前レベル(competent),(4)中堅レベル(proficient),(5)達人レベル(expert)。
本研究を通して,実践の理解,変化する状況下における論証の例示,意図・意味・懸念についてのコミュニケーション,実践を記憶し対話するコミュニティの創出において,ナラティブの共有,あるいはストーリーを語ることが果たす役割がより明瞭になった。実際の臨床事例についてのナラティブは,看護実践の核である日常の臨床やケアリングの知識を明らかにする。そのストーリーを語り,それについて議論することによってト,看護師の懸念,恐れ,希望,会話,問題が明らかにされ,保存されていく。ストーリーは,直線的なものではなく,どちらかといえば挿話や余談に入っていくことを許すもので,前向きの思考と回顧的思考の両方をとらえる。なぜなら,語る人がそのストーリーの結末を知っているからだ。ゆえに,ナラティブは,変化する状況下で起こる実践的な臨床的論証をよりよくとらえることができる。実践者たちは,初心者から熟達した実践者へと成長するにつれて,社会に根づいた実践の中での経験を通じて,顕著で重要な臨床状況についてのナラティブと記憶を構築していくものだ,ということを私たちは学んだ。経験を通して,さまざまな具体的な状況は整合性をもつようになり,実践者が,改善や悪化の感覚を発達させたり,類似と相違を認識したりするのに役立つようになる。また,共通する意義と実践に参加しているという感覚を発達させるのにも役立つ。他の人の実践のナラティブを聞くことによって,実践者たちは,繰り返し起こる顕著で重要な状況や共通する臨床実態と課題(問題)を認識できるようになる。
本書の読者の中には,実際のできごとについての一人称の経験についての臨場感あふれるナラティブは,他と全く共通性がなく,主観的で,一般化するのは不可能だ,と誤った推測をしている人もいるかもしれない。しかし,ナラティブ理解の論理は,実践的知識と実践的論証に適合するものであり(Benner, Sutphen, Leonard-Kahn, & Day, 2010;Sullivan & Rosin, 2008),社会的に組織化された実践の中で繰り返し起こる状況を理解するのに大いに役立つものである。それは,生物学において,ある特定の動物の一般的な生の営み,特異性,習性,またその動物のスタイルやその動物が状況に関連して起こす行動などを理解するためには,その動物の生息地と個体の生の軌跡を理解することが必要だということに似ている。臨床実践においても,同僚の臨床家が一般的に繰り返し起こる臨床状況をどうとらえ,それらにどう向き合っているかを理解するためには,同じような理解のプロセスが必要になる。このレベルの知識は,一般的なものと,個別の状況下での臨床的論証の特異性・行動・緊急性との間にある溝を埋めるものとなる。公式の抽象的で一般的な知識は必要だ。しかし,どんな専門職的実践においても,それだけでは十分ではない。たとえば,根拠に基づいた臨床研究から一般化できることを活用するには,実践者は,その特定の状況にどの根拠がどのような関連性をもっているのかを識別しなければならない。ナラティブは一般的に,特に読者がそのナラティブが生じる領域についての知識をもっている場合は,非常に有効だ。ナラティブがもつ意味について読者グループ内に異見はあるかもしれないが,語る人が設定したストーリーの状況の範囲内で考えるように指導された場合は,読者グループは,そのナラティブの意味について非常に高いレベルの同意に達することができる。それは,ピアレビューで行われる臨床促進プログラムで実証されている。『ベナー看護論—初心者から達人へ』刊行後の25年間に,看護実践とそれを取り巻く状況は大きく変わった。看護の核となるケアリング実践については,看護師不足のまっただ中の1984年に明確に記述された。ケアリング実践とは,単なる感傷や態度などではなく,熟達した関係性と実践のノウハウだという新たな認識で,明瞭に記述された。それは,教師や看護師など女性の職業に埋め込まれた知識が,認識され始めた時期でもあった。1984年,看護師免許を有しない補助的スタッフは,まだ病院にはあまりいなかった。そして,医療のシステムは比較的安定していた。商業主義と商品化の流れは,医療業界にすでに入り始めていたが,2009年のそれと比較すれば,まだまだよちよち歩きの状態だった。本書の初版が刊行された1996年,医療は,非常に不確かな医療改革のまっただ中にあった。医療費の削減が,治療や診断のための検査などにおいてではなく,主としてケアの領域で模索され実行されていた時期だったため,本書の初版は,ケアの質に対する重要な道しるべになると考えた。1996年は,医療費を削減するために,それまで看護師が行っていた多くの仕事を担わせるべく,教育レベルの低い人を雇用し訓練するという傾向が頂点に達していた。ただ,さすがにこのやり方には,患者のモニタリングと安全においては限界があるという認識はいくらかあった。持続的なモニタリングと機敏な臨床判断が必要とされる不安定な患者の病態管理では,看護師の“その患者を知る”能力(Tanner, Benner, Chesla, & Gordon, 1993)を失うことなしに,また患者の変化について早期の重要な警鐘を認識する専門性を失うことなしに,他者に委譲できる仕事はほとんどない。
急性期ケアにおける実践は,1996年当時よりはるかに複雑なものになっている。一般内科外科病棟に勤務する看護師に関するイーブライトらの研究(Ebright, 2003, 2004)は,たえず優先順位を入れ替えながら行う仕事,数多くの解釈なしでは遂行するのが難しい仕事,そしてそのような試練が看護判断や患者ケアに否定的な影響を与える可能性について指摘している。ポーター-オグレイディ(Porter-O'grady, 2001)は,看護において何をどう教えるかということに大きな変更を加えなければ,既に存在しなくなった実践に対する準備教育を行い続けることになるだろう,と警告している。
本書は,西洋的伝統においてふたをしてしまいがちなこと,つまり,熟練したノウハウは,単なる知識の適用ではなく,それ自体が1つの知識の形態だ,ということを明らかにするものだ。経験を積んだ臨床家は,教室では身につけることができない種の知識を習得している。本書が,科学や科学技術を教えたいという強い願いによって覆い隠されてしまいがちな,隠れている臨床的知識と臨床的探究を明らかにすることを期待している。私たちは科学や科学技術をおとしめようとしているのではない。規律ある探究や倫理的態度のための場をつくることを模索しているだけだ。そういったものが,個々の患者や家族のためのケアリング実践において,科学や科学技術を安全に提供することにつながるのだ。私たちは,変化する状況下における実践的な論証を教える,より大きく正当な場を創出したいと思っている。
1996年に原書初版が刊行されて以来,本書の研究者は皆,それぞれに研究を継続している。パトリシア・ベナーは,本書の適時性と重要性は,自身がカーネギー財団の依頼で行った研究によって確認されたと述べている。ベナーらは,複雑で,責任が重く,リスクが多く潜む看護という仕事に対して,現在の看護師は十分な教育を受けてはいないということを,その研究で教育の側から例証した。看護師のストーリーは,看護師が熟練したノウハウを高度なレベルで実践する時に,どのようなことを達成することが可能で,また,そこにはどのような危険が潜んでいるのかを明らかにしてくれる。本書は,学校から現場へと移行する時期の教育プログラムをより効果的なものにする道筋を提供するものだ。また,新卒看護師の教育のために活用される教育プログラムの必要性だけでなく,一人前レベルや中堅レベルの看護師や仕事に復帰したいと思っている看護師のための教育プログラムの必要性も例証している。第6章で,ジェーン・ルービン Jane Rubin は,看護師側の誤解が,臨床判断とは,よく定義された選択肢のうちどれが妥当かを単に合理的に推測することだ,と看護師に考えさせてしまいかねないと指摘し,それがどのように起こるかを説明している。そして,そうした誤解は,いくぶん,合理的で技術的なやり方で考えられるあまりに狭義な教育に原因があるとしている。臨床的論証に対するこれらの狭い教育的アプローチでは,かかわりのスキルを見過ごしたり,患者の臨床上の問題やそれらの問題のために患者が抱え込む苦悩を認識したり解釈したりする上での関係性の側面を見過ごしがちだ。 看護教育改革の必要性を長く主張してきたクリスティン・タナー Christine Tanner も,オレゴン州における新たな教育システムであるオレゴン看護教育コンソーシアム(The Oregon Consortium for Nursing Education;OCNE)を開発する際に,この仕事(本書)の重要性と適時性を悟った(Gubrud-Howe et al., 2003;OCNE, 2008;Tanner et al., 2008)。OCNEは,オレゴン医療科学大学と同州の複数のコミュニティカレッジ* の協働の結果,生まれた新たな看護教育制度だ。OCNEは,看護教育の力量を拡大していくこと,持ち上がってきた医療ニーズによりよく対応できるようカリキュラムを変革すること,看護実践におけるスキル獲得と学習するという科学の進展に関して,本研究を頼りにしながら実践分野のために適切な教育方法を活用すること,そして,今日の実践の現実を反映するように臨床教育を改革することを決めている。OCNEのプロジェクトは,新たな教育法の開発とそれを試すフィールドにまで本研究を拡大適用しながら,オレゴン州全域で看護教育に携わる教員たちと協働するすばらしい機会を提供している。
* 訳者注:米国全州に存在する州立の短期大学。
『ベナー看護論—初心者から達人へ』と同じように,本研究は,スキル獲得の研究であると同時に,臨床看護の知の本質を研究に基づいて明瞭に表現している。この研究は,それ自体,医学,ソーシャルワーク,教育,作業療法学,理学療法学など他の実践領域にも関連性をもっていることを証明している。すべての事例は看護を中心としたものだが,科学・科学技術・倫理によって導かれる原理原則に基づいた実践から,積極的な論証を通じて蓄積された実践知によって導かれる対応に基づいた実践への前進は,他のあらゆる領域の実践者にも関連性をもつものであり認識されうるものだろう。それは,実践を行う看護師の専門性(知識,判断,技など)の形成にいたる実際的な実践の記録である。
【研究概要】
本書は,1988年から1994年にかけて実施した,急性・重症ケア病棟で提供された看護実践の解釈的研究に基づいたものである。研究は,パトリシア・ベナーとクリスティン・タナーによって計画され,ヘレン・フルド信託財団に研究助成金を申請した。計画段階からかかわった共同研究者は,ヒューバート・ドレイファスとスチュアート・ドレイファスであった。その看護実践研究へのアプローチについて,ここにごく短い概要を示す。研究の設計および実施における,私たちの関心と行動に関する詳細な議論は付録Aに示した。
研究を構成した4つの主な目的は,以下の通りである。
| ■ | 達人の実践に埋め込まれた実践的知識を明らかにすること |
| ■ | クリティカルケア看護の実践におけるスキル獲得の本質を記述すること |
| ■ | 看護実践における専門性を開発するにあたって,組織上の障害物と資源(リソース)になるものを同定すること |
| ■ | 専門性の開発を促す教育的戦略の確認に着手すること |
他のあらゆる解釈的研究と同様に,このプロジェクトは,初期においては,この4つの指針となる目的によって構成されたが,それに縛られるものではなかった。これからの数ページで,この主要な設問に関する研究結果を説明し,研究の初期の目的をはるかに超越した中心的テーマとナラティブを明らかにする。
研究デザインは,看護実践のすべての側面が可視化されるようにするには,その実践にどのような方法でアプローチすべきかという関心の影響を受けた。この研究デザインでは,私たちが以前に行った看護実践(Benner 1984a;Benner & Wrubel, 1989)と臨床判断(Benner & Tanner, 1987;Tanner, 1989, 1993)に関する解釈的研究から学んだことをさらに拡大した。また,他に関心を抱いたのは,人生のさまざまな段階にいて抱える疾患もさまざまな患者に対して,異なるレベルの看護師によって,地理的状況もタイプもさまざまな組織で提供される実践に近づくことだった。
クリティカルケア領域の看護師の日常の実践とスキルに接触するために,解釈的現象学(interpretive phenomenology)(研究のより詳細な説明については付録Aを参照)を活用した。この方法を用いた目的は,研究対象となった看護師の実践にみられる意味と行動に関する特徴的なパターンを説明することであった。その際には,研究対象となった看護師がどのような状況の中で働いているか,またその経歴や特別な関心事などを考慮した。形式や一般的な実践の特徴を把握することではなく,むしろ,情報提供者の看護師にみられる意味と行動に固有で顕著なパターンを明瞭にすることを試みた。このアプローチは,以下の特徴をもつ。
| (a) | 実践のナラティブを収集するために,既に検証されている形式を使う。 |
| (b) | テキストから理論的に抽出したものに焦点を当てるのではなく,情報提供者から直接得たテキストから解釈される意味や関心事に焦点を当てる。 |
| (c) | 解釈において仲裁が必要な論争が生じた場合,継続的に情報源に立ち戻って自己批判的で自己修正的な姿勢をとる。 |
| (d) | 複数の読み手が同意し,総意として承認した解釈を創出する(Benner, 1994b;Packer & Addison, 1989;van Manen, 1990)。 |
本研究の情報提供者は,米国の最西部の2地域に位置する7病院と東部1地域に位置する1病院,計8病院における集中治療室(ICU)と一般病棟で実践している130人の看護師で構成されている。看護師は,新生児集中治療室(NICU),小児集中治療室(PICU),成人対象の集中治療室に勤務している者から選ばれた。成人対象の集中治療室で働く看護師は,外科系集中治療室(SICU),内科系集中治療室(MICU),冠疾患集中治療室(CCU),そして一般集中治療室にそれぞれ同じくらいの割合で分布するように選んだ。私たちは比較的同質なグループをサンプルとしたので,対象となった看護師の98%は最低でも学士号を取得していた。選ばれた看護師たちが勤務する病院は,大半は第3次救急病院であったが,なかには地域病院,および退役軍人病院もあった。
看護師たちは,それぞれ期待されたレベル(新人から達人)から上司によって選ばれた。その際に,上司には経験年数を考慮に入れるように依頼した。そして,経験年数5年以上の看護師の場合,その実践の質を考慮して選択するように依頼した。新人および一人前レベルの看護師の場合は,実践のばらつきは自然に把握できるだろうと予測した。しかし,経験を積んだ看護師の場合,指導者あるいは師長に,実践5年以上の看護師で,非常に優れていると考えられる看護師と,同じくらいの経験をもち安全であるがケアの提供については模範的とまではいえないと考えられる看護師を特定してもらうことによって,ばらつきを把握することにした。最終的には,経験1年以内の看護師25人,経験2~5年の看護師35人,経験5年以上で達人と認識できる看護師44人,経験5年以上で実践経験は積んでいると考えられるが達人とは認識できない看護師26人で構成された(情報提供者の詳細については付録Bを参照)。
クリティカルケアを必要とする患者をケアする看護師の日常の経験とスキルに接近するために,ナラティブ・インタビューと参加観察という2つの主要なアプローチを使った。ナラティブ・インタビューでは,同じくらいの看護実践を積んだ4~6人の看護師に対する小グループインタビューを,3セッションを通じて繰り返し実施した。看護師たちには,特定の患者に対して最近行ったケアのナラティブを提示するように求めた。また,積極的に質問したり不明瞭さを明確にしたりすることによって,情報提供者から完全なナラティブが引き出されるような支援を依頼した。実践を理解するための第二のアプローチは,それぞれの病棟で直接ケアを提供する48人の看護師に対する,2~4時間の観察だ。観察中のインタビューと直接討論は,すべて録音され,解釈のためのテキストを作成するために,一字一句忠実にテープ起こしされた。
テキストの解釈は,以下によって構成された。
| ■ | 研究チームの一部によって行われたそれぞれのインタビューの解釈 |
| ■ | 特定の問題を提起した部分のテキストに関する小グループによる解釈 |
| ■ | 初期の質問によって解釈したものをチーム全体で検証した大グループによる解釈 |
解釈のプロセスでは,テキストを繰り返し検討した。テキストに記述されたもの全体を理解するために,そこに記述されたことで最も顕著で重要なことを理解するために,そして,もし詳細な記述であれば,その記述の全容を理解するために,テキストを繰り返し検討した。解釈を継続するにあたり,それぞれの患者についての個別のナラティブ,個別の看護師の全体的な看護実践,同じレベルの看護師の実践,同じ組織で実践を行う看護師の実践,そして特定のテーマに括ることができるナラティブグループなど,複数の分析が考慮された。研究チームの中の小グループは,研究の特定の側面に注意して,特定のテキストの解釈に焦点を置いた。
看護師やその他の臨床家が実践において知っていることを,私たちは言葉で再表現できたと期待している。私たちは,脇に置かれがちなケアリング実践をここに示した。読者が本書を読むことによって,実践の社会的な価値と,看護師が行うケアリングの仕事,診断的仕事,そして治療的仕事に内在する知識とを,本当に真剣に考えなければならないと思ってくれることを期待する。また,他の領域の実践者たちが,私たちのこの対話に加わってくれることを期待する。そうすることで,私たちが一般の人々のためによりよいケアリング組織を設計することができればと願う。学校で,家族で,社会事業の場で,また法廷でも,そのような組織が設計されることを希望する。そして,弱者の保護,成長の支援,そしてよりよい市民権の促進が生じるあらゆる場所において,そのような組織が設計されることを期待したい。
Benner, P. (1982). From novice to expert. American fournal of Nursing, 82, 402-407.
Benner, P. (1984a; 2001 2nd Edition). From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Menlo Park, CA: Addison-Wesley.
Benner, P. (1984b). Stress and satisfaction on the job: Work meanings and coping of mid-career men. New York: Praeger.
Benner, P. (1994b). The tradition and skill of interpretive phenomenology in studying health, illness, and caring practices. In P. Benner (Ed.), Interpretive phenomenology: Embodiment, caring and ethics in health and illness (pp. 99-127). Newbury Park, CA: Sage.
Benner, P. (1994d). The role of articulation in understanding practice and experience as sources of knowledge. In Tully & D. M. Weinstock (Eds.), Philosophy in a time of pluralism: Perspectives on the philosophy of Charles Taylor (pp. 136-155). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Benner, P., Hooper-Kyrikides, P, Stannard, D. (2000). Clinical wisdom and interventions in critical care: A thinking-in-action approach. Philadelphia: W. B. Saunders.
Benner, P., Sutphen, M., Leonard-Kahn, V., & Day, L. (2010). Educating nurses: A Call for Radical Transformation. San Francisco: Jossey-Bass and Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching and Learning.
Benner, P., & Tanner, C. (1987). Clinical judgment: How expert nurses use intuition. American Journal of Nursing, 87, 23-31.
Benner, P., & Wrubel, (1989). The primacy of caring: Stress and coping in health and illness. Menlo Park, CA: Addison-Wesley.
Bourdieu, P. (1990). The logic of practice. (R. Nice, Trans.). Stanford, CA: Stanford University Press. (Original work published in 1980)
Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1986). Mind overmachine, the powerofhuman intuition and expertise in the era ofthe computer. New York: Free Press.
Dreyfus, S. E. (1982). Formal models vs. human situational understanding: Inherent limitations on the modeling of business expertise. Office, Technology and People, 1, 133-155.
Dunne, (2004). Arguing for teaching as a practice. In Dunne & P. Hogan (Eds.), Education and practice upholding the integrity of teaching and learning (pp. 170-186). Oxford: Blackwell Publishers.
Ebright, P. R., Patterson, E. S., Chalko, B. A., & Render, M. L. (2003). Understanding the complexity of registered nurse work in acute care settings. Journal of Nursing Administration, 33 (12), 630-638.
Ebright, P. R., Urden, L., Patterson, E., & Chalko, B. (2004). Themes surrounding novice nurse near-miss and adverse-event situations. Journal of Nursing Administration, 34 (11), 531-538.
Gadamer, H. (1975). Truth and method (G. Barden & Cumming, Trans.). New York: Seabury.
Gubrud-Howe, P., Shaver, K. S., Tanner, C. A., Bennett-Stillmaker, Davidson, S. B., Flaherty-Robb, M., et al. (2003). A challenge to meet the future: Nursing education in Oregon, 2010. Journal ofNursing Education, 42 (4), 163-167.
MacIntyre, A. (1981). After virtue. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
Montgomery, K. (2005). How doctors think: Clinical judgment and the practice of medicine. New York: Oxford University Press.
Oregon Consortium for Nursing Education. (2007). Update on progress Retrieved August, 20, 2008, from http://www.ocne.org/media/update-on.progress.pdf
Packer, M. & Addison, R. B. (1989). Entering the circle: Hermeneutic investigation in psychology. Albany, NY: SUNY Press.
Porter-O'Grady, T. (2001). Profound change: 21st century nursing. Nursing Outlook, 49, 182-186.
Shulman, L. S. (1993). Teaching as community property. Change, 25, 6-7.
Sullivan, W. M., & Rosin, M. S. (2008). A new agenda for higher education: Shaping a life of the mind for practice. San Francisco: Jossey-Bass.
Tanner, C. (1989). Using knowledge in clinical judgment. In C. Tanner & C. Lindeman (Eds.), Using nursing research (pp. 19-34). New York: National League for Nursing.
Tanner, C. (1993). Rethinking clinical judgment. In N. Diekelmann & M. Rather (Eds.), Transforming RN education (pp. 15-41). New York: National League for Nursing.
Tanner, C. A., Benner, P., Chesla, C., & Gordon, D. (1993). The phenomenology of knowing a patient. Image: The Journal of Nursing Scholarship, 25, 273-280.
Tanner, C. A., Gubrud-Howe, P., & Shores, L. (2008). The Oregon Consortium for Nursing Education: A response to the nursing shortage. Policy, Politics, and Nursing Practice, 9 (3), 203-209.
Taylor, C. (1993). Explanation and practical reason. In M. C. Nussbaum & A. Sen (Eds.), The quality of life. Oxford: Clarendon Press.
van Manen, M. (1990). Researching lived experience: Human sciencefor an action sensitive pedagogy. Ontario: Althouse.
目次
開く
寄稿者略歴
謝辞
はじめに
第1章 スキル獲得における理論と実践の関係
第1段階:初心者レベル
第2段階:新人レベル
第3段階:一人前レベル
第4段階:中堅レベル
第5段階:達人レベル
解説
第2章 現場に入る:新人の実践
新人看護師の臨床の世界
新人看護師の臨床での主体的な行動
教育的・環境的示唆
要約
解説
第3章 一人前の段階:分析・計画・直面する時期
一人前になる
臨床の世界
仕事を組織化する
臨床的理解を発達させる
臨床学習と倫理的学習における感情の役割
主体的な行動への意識
経験的学習と失敗への対処
教育的示唆
苦しみ,コーピング,かかわりのスキルの学習に直面する
要約
解説
第4章 中堅レベル:達人への移行期
推移の中でのかかわりながらの論証
状況に感情を合わせる:なされるべきことをする
変化する関連性と状況に基づいた対応
主体的な行動
かかわりのスキルを学ぶ
教育的示唆
要約
解説
第5章 達人の実践
臨床の世界
主体的な行動
要約
解説
第6章 クリティカルケア看護における臨床的知識と
倫理的に判断する能力の発達を妨げるもの
実践の構造
臨床判断
倫理的に判断する能力
臨床における倫理的で主体的な行動
付記
解説
第7章 臨床判断
ナラティブで明らかにされた臨床判断の側面
要約
合理的モデルが引きつけるもの
実践的論証と臨床判断
要約
解説
第8章 社会的に埋め込まれた知識
蓄積された専門性と複数の視点の力
具現化されたスキルとその場にどのように存在するかについての模範を示す
要約
卓越性についての集合的なビジョンと当然と思われている実践の共有
信頼と空気の力
要約
解説
第9章 臨床的・倫理的専門性におけるケアリングの
優位性と経験・ナラティブ・コミュニティの役割
ナラティブのテーマ
学習のナラティブ
ナラティブの機能とコミュニティ
実践の性質と機能
解説
第10章 熟達した日常の倫理的態度を教え学ぶ際に専門性の現象学が示唆すること
熟慮するということ
具体性と一般性を考慮する上での熟達した倫理的態度の関連性
専門性の現象学が医療倫理に示唆すること
解説
第11章 看護師-医師の関係:臨床的知識の交渉
職種間の境界の不明瞭化
形式的な科学知識の台頭による臨床的知識の失墜
経験の役割
疾患の人間的側面,苦しみ,痛み,恐れ,軋轢を隠す
交渉のスキル
要約と結論
解説
第12章 基礎看護教育への示唆
学部教育におけるナラティブの役割
病気のナラティブの解釈
臨床実践をナラティブで語る
新卒者からの教訓
かかわりのスキルを学習する
社会的に埋め込まれた実践として看護を理解する
本研究が挑んだ前提
理論と実践の関係
臨床判断の本質
クリティカルシンキングと臨床的論証の融合
看護教育における画期的変革に向けて
臨床的論証を教える
倫理的態度として看護を教える
要約
第13章 看護管理と実践への示唆
実践の崩壊に関するシステムの資源の確認
看護管理への示唆
組織の設計と再構築への示唆
チームの構築と臨床促進プログラム
臨床実践の発達と学習を促進するためにナラティブを活用する
臨床学習のための組織的風土を創出する
臨床的知識を発達させるような患者ケア記録を設計する
ケア提供者に再びかかわりをもたせる
要約と結論
謝辞
付録A 背景と手法
付録B 看護情報提供者について
付録C インタビューおよび観察のための基礎的質問
文献
訳者あとがき
索引
書評
開く
書評者: 山本 則子 (東大大学院教授・健康科学・看護学)
本書はベナー,タナー,チェスラによる『Expertise in Nursing Practice : Caring, Clinical Judgment and Ethics』(第2版,2009年)の邦訳で,原著は『From Novice to Expert』(第2版,2001年)1) と(『Clinical Wisdom and Interventions in Acute and Critical Care』(第2版,2011年)2) の間に書かれている。看護師のスキル獲得の5段階について,『ベナー看護論』の枠組みがさらに詳細に検討されており,最後には,今回の知見に基づき今後の看護教育のあり方を提言している。クリティカルケア領域の看護師130名へのインタビューと参与観察によるデータを,解釈学的現象学の手法を用いて分析した結果である。
看護実践を,各種理論の専門的活用という視点だけで理解することに,ベナーは一貫して警鐘を鳴らす。看護は,生物学的知識や心理社会的な理論を用いつつも,個別の文脈において患者への深い共感と善をなす態度の基で具体的に展開される実践であり,経験的な学習の蓄積により初めて成長できる。ベナーらは,看護実践の知や専門性は形式理論にすることはできないと主張し,代わりに看護を特徴付ける中心的なテーマとナラティブおよびその解釈を紹介している。テーマの言葉に説得力がある。
分析は多岐にわたり,なるほどと思う点がいくつもあった。看護師の成長にとって「一人前」からの学びと「中堅」への移行が重要であること。エキスパート看護師の臨床判断は原理原則やエビデンスにのっとった機械論的な思考過程ではないこと。このような機械論的な思考は「初心者」や「新人」の思考モードであって,スキル獲得の段階を踏むにつれ,臨床判断は個別事例の文脈の中に埋め込まれた思考プロセスそのものとなり,さらに,意識的な思考プロセスを経ない直観的な判断になること。また,医療チームの中でのコミュニケーションによって学ぶ知識と看護師の成長〔「ナラティブを通じて他者の経験から学ぶ」(p.347),「卓越性についての集合的なビジョンと当然と思われている実践の共有」(p.365)〕についての記述も興味深かった。
本書は達人レベルの看護実践の検討解説にとどまらず,看護教育への提言に進んでいる。病気のナラティブや新人・達人のナラティブを教育に用いること,講義室での理論的学習と現場での経験的学習を近付けること,かかわりのスキルを学習すること,社会的に埋め込まれた実践として看護を理解すること,倫理的態度として看護を教えることなどが主張されており,日本の看護学教育が今後深く学ぶ必要がある内容と思われた。
分厚い翻訳書で全文を読み通すのは大変だし,内容は平易とは言い難い。しかし,看護実践に対する深い理解と言語化,現象学的人間観に基づく看護実践と看護がなし得ることへの深い洞察,研究にとどまらずその知見を看護教育に活用してゆく積極性など,ベナーという研究者に学ぶことがいかに多いかを改めて感じた。本書もいくつもの箇所でそうだそうだと思いあたり,語り合いたい同僚の顔が次々と浮かんだ。日本の看護にもこのような分析がいつか生まれることを願う。
2) パトリシア ベナー.他.ベナー 看護ケアの臨床知——行動しつつ考えること.第2版.医学書院;2012.
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。