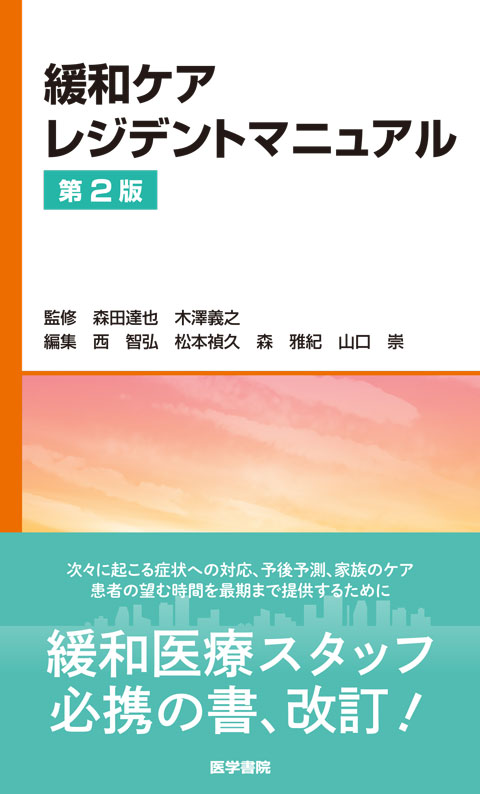終末期の苦痛がなくならない時,何が選択できるのか?
苦痛緩和のための鎮静〔セデーション〕
鎮静を、深く知る!
もっと見る
終末期の苦痛に対応する手段には何があるのか。眠ることでしか苦痛を緩和できないとしたら、私たちは何を選択できるのか。手段としての鎮静の是非を考える時、その問いは「よい最期をどのように考えるのか」という議論に帰着する。
鎮静の研究論文を世界に発信してきた著者が、鎮静を多方面から捉え、臨床での実感を交えながら解説する、鎮静を深く知るための書。
| 著 | 森田 達也 |
|---|---|
| 発行 | 2017年02月判型:B5頁:192 |
| ISBN | 978-4-260-02831-8 |
| 定価 | 3,080円 (本体2,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
本書のテーマは,「死亡直前の苦痛に対応する手段には何があるのか」であり,手段としての鎮静(セデーション,苦しい時に睡眠薬や麻酔薬を使用して眠ること)の是非である。
「がんになったら苦しい」 vs. 「がんになっても痛み(苦しみ)は完全に取れる」…この二極論はどちらもある程度正しく,どちらもある程度間違っている。実際のところは,「がんになれば,苦しいところは(健康な時よりは)増える。苦痛に対応する方法はそれなりにあって,そこそこ苦痛を和らげることはできる場合も多いけれど,苦痛を完全にはなくせないこともある」。これが筆者が体験し,国際的な研究知見の告げる妥当な(と筆者は思う)いまの時点の結論である。
不必要にがんの苦痛を怖がらせる「壮絶!! がんとの闘い」のようなステレオタイプの見出しの並ぶ雑誌もどうかと思うが,「がんでも全く苦しくない」が事実とは筆者には信じられない。実際,筆者が出会う患者さんたちは,「患者さんの望むようには,苦しみを0にしてあげられなかった」ことが少なくない。これが,普遍的な事実なのか,あるいは,筆者の緩和治療の技術が未熟なのかはわからないが…。
本書は,終末期医療について考えるすべての人向けに,「死亡直前の苦痛に対応する手段には何があるのか」,特に鎮静についての理解を深めてもらいたいという願いから書いた。鎮静の位置づけについては,1990年に国際的に初めての学術的な議論が起きて以来,今日に至るまで,海外では着々と質の高い議論が続けられている。しかし,筆者が見る限り,国内の議論はここ30年近く一向に深まらない。どうしてなのかその正確な理由は筆者にもわからない。おそらくは,実際に現場を体験する人が限られているためイメージが持ちにくいこと,海外で盛んに研究論文が発表されるにもかかわらず正確にその意図を伝えている国内向けの記事が少ないこと,領域が医学から生命倫理,死生学まで幅広いため相互の共通言語が少ないことが考えられる。したがって,本書は,通常の医学書よりもやや広範な読者を想定し,特に現場に立たされることの少ない人文系の諸氏にも理解しやすいように努めた。想定している主な読者は,鎮静について考えたい医師,看護師など医療関係者,生命倫理学・哲学・死生学・法学関係者,学生や一般の方々である。
いままさに患者さんやご家族の立場として読まれる方もいらっしゃるかと思いますが,本書は本来的には,学術的な問題として,「死亡直前に緩和されない苦痛に対応する手段として鎮静は適切なのか」を検討する題材としてもらうことを意図したものです。表現がダイレクトになっているところが多いかと思いますので,もし読まれる場合には,その点,おゆるしをお願いします。
本書が,我が国において「一向に深まらない」鎮静についての議論を,少しずつ深めることのできる1つのきっかけ,最初の一歩となれば筆者としてはありがたい。そして,最終的には,日本の中で,終末期の苦痛に対する方向性,コンセンサスを,個人の考えや経験からだけではなく,広く国際的な知見を含めて討議できるようになることを願っている。
最後に,医学書院の品田暁子さんへの謝意を記しておきたい。筆者がこいつはすごいな,と思う編集者はいまのところ2名いる。彼女はそのひとりだ。初めて会ったのは築地の国立がん研究センターの喫茶店で,「少しでいいから面会お願いします」と資料を抱えてやってきた。全身から,「世の中にない本を作りたい」オーラがひたひたと,しかし力を持って立ちのぼっていた。彼女には編集という枠はそもそもあるのかないのか,筆者の言いたいことを理解して,原論文にこつこつ当たって図表の作成を進めてくれた。筆者の他の本と同じように,彼女がいなければ本書は確実に世に出ていなかった。
筆者が専門とする緩和ケア臨床は文字通りチーム医療であり,医師1名ではたいしたことができない。いつも誰かに助けられ,なんとか緩和ケア医は生き延びている。本書にあっても,筆者だけでは成り立たなかった部分を0から形作ったのは彼女の信念に基づいた働きである。信念を持った人は貴い。重ねて,最上級の感謝を示したい。
2016年12月
森田達也
本書のテーマは,「死亡直前の苦痛に対応する手段には何があるのか」であり,手段としての鎮静(セデーション,苦しい時に睡眠薬や麻酔薬を使用して眠ること)の是非である。
「がんになったら苦しい」 vs. 「がんになっても痛み(苦しみ)は完全に取れる」…この二極論はどちらもある程度正しく,どちらもある程度間違っている。実際のところは,「がんになれば,苦しいところは(健康な時よりは)増える。苦痛に対応する方法はそれなりにあって,そこそこ苦痛を和らげることはできる場合も多いけれど,苦痛を完全にはなくせないこともある」。これが筆者が体験し,国際的な研究知見の告げる妥当な(と筆者は思う)いまの時点の結論である。
不必要にがんの苦痛を怖がらせる「壮絶!! がんとの闘い」のようなステレオタイプの見出しの並ぶ雑誌もどうかと思うが,「がんでも全く苦しくない」が事実とは筆者には信じられない。実際,筆者が出会う患者さんたちは,「患者さんの望むようには,苦しみを0にしてあげられなかった」ことが少なくない。これが,普遍的な事実なのか,あるいは,筆者の緩和治療の技術が未熟なのかはわからないが…。
本書は,終末期医療について考えるすべての人向けに,「死亡直前の苦痛に対応する手段には何があるのか」,特に鎮静についての理解を深めてもらいたいという願いから書いた。鎮静の位置づけについては,1990年に国際的に初めての学術的な議論が起きて以来,今日に至るまで,海外では着々と質の高い議論が続けられている。しかし,筆者が見る限り,国内の議論はここ30年近く一向に深まらない。どうしてなのかその正確な理由は筆者にもわからない。おそらくは,実際に現場を体験する人が限られているためイメージが持ちにくいこと,海外で盛んに研究論文が発表されるにもかかわらず正確にその意図を伝えている国内向けの記事が少ないこと,領域が医学から生命倫理,死生学まで幅広いため相互の共通言語が少ないことが考えられる。したがって,本書は,通常の医学書よりもやや広範な読者を想定し,特に現場に立たされることの少ない人文系の諸氏にも理解しやすいように努めた。想定している主な読者は,鎮静について考えたい医師,看護師など医療関係者,生命倫理学・哲学・死生学・法学関係者,学生や一般の方々である。
いままさに患者さんやご家族の立場として読まれる方もいらっしゃるかと思いますが,本書は本来的には,学術的な問題として,「死亡直前に緩和されない苦痛に対応する手段として鎮静は適切なのか」を検討する題材としてもらうことを意図したものです。表現がダイレクトになっているところが多いかと思いますので,もし読まれる場合には,その点,おゆるしをお願いします。
本書が,我が国において「一向に深まらない」鎮静についての議論を,少しずつ深めることのできる1つのきっかけ,最初の一歩となれば筆者としてはありがたい。そして,最終的には,日本の中で,終末期の苦痛に対する方向性,コンセンサスを,個人の考えや経験からだけではなく,広く国際的な知見を含めて討議できるようになることを願っている。
最後に,医学書院の品田暁子さんへの謝意を記しておきたい。筆者がこいつはすごいな,と思う編集者はいまのところ2名いる。彼女はそのひとりだ。初めて会ったのは築地の国立がん研究センターの喫茶店で,「少しでいいから面会お願いします」と資料を抱えてやってきた。全身から,「世の中にない本を作りたい」オーラがひたひたと,しかし力を持って立ちのぼっていた。彼女には編集という枠はそもそもあるのかないのか,筆者の言いたいことを理解して,原論文にこつこつ当たって図表の作成を進めてくれた。筆者の他の本と同じように,彼女がいなければ本書は確実に世に出ていなかった。
筆者が専門とする緩和ケア臨床は文字通りチーム医療であり,医師1名ではたいしたことができない。いつも誰かに助けられ,なんとか緩和ケア医は生き延びている。本書にあっても,筆者だけでは成り立たなかった部分を0から形作ったのは彼女の信念に基づいた働きである。信念を持った人は貴い。重ねて,最上級の感謝を示したい。
2016年12月
森田達也
目次
開く
| Prologue | これは通常の治療なのか? 鎮静なのか? 安楽死なのか? -現場のもやもや |
| Part 1 鎮静を議論する上で知っておくべきこと | |
| Chapter 1 | いまのところのまあまあコンセンサスがある鎮静の定義 |
| Chapter 2 | 鎮静の歴史的経緯-大枠をつかむ |
| Chapter 3 | 鎮静を議論する上で知っておきたい基盤となる知識1: 倫理原則 |
| Chapter 4 | 鎮静を議論する上で知っておきたい基盤となる知識2: 鎮静は死を早めるのか? |
| Chapter 5 | 鎮静を議論する上で知っておきたい基盤となる知識3: 日本と世界の現状 |
| Chapter 6 | 鎮静を議論する上で知っておきたい基盤となる知識4: 現象学の考え方-そもそも真実はあるのか? |
| Part 2 考察 発展的に議論する | |
| Chapter 7 | 臨床医学がするべきこと1: 鎮静を考える前に 「誰が行っても及第点のとれる苦痛の緩和方法」を標準化せよ |
| Chapter 8 | 臨床医学がするべきこと2: 「鎮静」を実施する時の方法を標準化せよ |
| Chapter 9 | 倫理・法学・臨床家がするべきこと1: はっきりとしたシロとはっきりとしたクロは明確にせよ |
| Chapter 10 | 倫理・法学・臨床家がするべきこと2: グレーゾーンでの意思決定の仕方のひな形を作れ |
| Chapter 11 | 基礎医学がするべきこと: 死亡直前の苦痛の体験を科学的に解き明かせ |
| Chapter 12 | 日本人みんなが考えるべきこと: どういう最期の迎え方がいいのか? を真剣に考えよう |
| Epilogue | 現場のもやもやをすっきりさせる -最初の事例に立ち返る |
安楽死・自殺幇助・自殺・持続的深い鎮静についての筆者個人の考え
索引
書評
開く
「グレーゾーン」で悩む全ての医療者のために
書評者: 田代 志門 (国立がん研究センター社会と健康研究センター生命倫理研究室長)
現代の医学書としては珍しく「古典(クラシック)」になり得る本ではないか。言い換えれば,この本は今後数十年にわたり,鎮静に関する議論の出発点であり続けるだろう。もちろん,このテーマに関しては著者のものを含め,数多くの学術論文が書かれてきた。英語圏では論文集も3冊ほど出ている。しかしいずれも専門家向けであり,また鎮静の議論の全体像を提示するものではない。これに対して,本書は世界で初めて,「苦痛緩和のための鎮静」という,しばしば難しい倫理的判断を伴う医療行為の全体像を明らかにした本である。これは鎮静の問題が狭い「業界」の話ではなくなりつつある現在,大きな社会的意義がある。まずは日本語でこれを読める喜びをかみしめたい。
さて,この本の優れた点はいくつかあるが,ここでは2つに絞って述べておきたい。本書は大きくは前半(Part1)と後半(Part2)に分かれており,前半部は議論の前提となる知識の共有に割かれ,後半部ではそれに基づく著者の考察が展開されている。この前半部で特に秀逸なのが,鎮静概念とその倫理的正当化をめぐる過去30年の論争史を丁寧にまとめた箇所である。もちろん,併せて最新の医学的な知見も手際よく整理されており,医療者にとっては「明日から使える」知識も多く得られる。とはいえ,もし本書が単なる「最新の情報」の整理に終始しているのであれば,時とともにその内容は古びていくだろう。しかし「概念」や「歴史」に関する記述はそう簡単には古くはならない。「古典」と言ったのにはそういう意味がある。
もう一つこの本が優れているのは,鎮静と向き合う臨床家の「迷い」が丁寧に書かれている点である(著者の言葉でいえば「グレー」な判断がこれにあたる)。鎮静は論争的な医療であるし,それは今後数十年たってもそう大きくは変わらないのではないか。実際,意識を低下させることなく苦痛を緩和することができるのであれば,患者・家族も医療者も迷いなくそちらを選ぶだろう。しかし他に苦痛を緩和する手立てがなく,これ以上の苦痛を与え続けることは許容されないという局面に立たされたとき,鎮静は一つの選択肢として立ち現れる。なかでも,ある程度の余命が期待される患者の意識を急速に低下させるタイプの鎮静の開始は高度に倫理的な判断を伴う。この本が優れているのは,こうした判断の難しさを率直に認めたうえで,思考停止や安易な決断主義に陥ることなく,可能な限り「合理的に」考え抜こうとしているところである。
ところで,振り返って考えてみれば,実は多くの医療行為はこうした「迷い」を含みながら日々行われているものである〔「どんな治療にもグレーゾーンがある」(p.134)〕。これは医療が途上的技術(halfway technology)である以上,ある種の宿命といってもよいかもしれない。その点で,本書が緩和ケアを専門とする医療者だけではなく,あらゆる領域の医療者に広く読まれることを願う。
個人の信念を越えて,鎮静を巡る議論をするために
書評者: 新城 拓也 (しんじょう医院院長)
本書が出版されるとほぼ同時に,雑誌『文藝春秋』では「安楽死は是か非か」というタイトルで特集が組まれた。90歳となった脚本家の橋田壽賀子が,「私は安楽死で逝きたい」と真情を吐露し,せめて死ぬ選択は自分でしたいと考えを述べている。また同時に企画されたアンケートでは,日本の知識人の過半数は安楽死に賛成していた。その理由として,苦痛からの解放,当人の尊厳のためという意見があった。
医療を今まさに受けている市民にも,尊厳死,安楽死という言葉は浸透し,議論の萌芽は週刊誌でも日常的に見つけることができるようになった。そして,「眠ったまま最期を迎える鎮静」も市民が知るようになった。
本書は,苦痛緩和のための鎮静について,研究の歴史を辿りながら,現在の状況について述べられている。鎮静は,タイトルの通り,終末期の苦痛がなくならない時に最後の苦痛緩和の手段として行われている。国内では,がん患者の苦痛に対して行われており,日本緩和医療学会からガイドラインも発表されている。著者は多くの研究の知見を紹介すると共に,現時点で何が言えるのかについてぎりぎりの地点まで読者を連れて行こうと試みている。
冒頭で,「これは通常の治療なのか? 鎮静なのか? 安楽死なのか?」と事例を示して現場の「もやもや」について紹介している。一般市民,緩和医療を専門としない多くの医療者には,鎮静は,安楽死と何が異なるかよくわからない。安楽死も鎮静も苦痛からの解放を目的としている以上,どちらも同じようなものなのではないか,鎮静は安楽死の代替行為ではないのかと心のどこかで思っているのだ。
しかし,緩和医療の専門家は,安楽死と苦痛緩和のための鎮静は,全く異なると認識している。いや,全く異なると考えたいと思っている。国内で行われた大規模な研究でも,鎮静は生命予後を短縮していないことがわかった。しかし,鎮静薬の投与方法,量が適切で緩和医療の経験が十分な医師が実施すれば,という前提である。
冒頭の「もやもや」の正体とは,鎮静を巡る議論の言葉を持ち合わせていない医療者が抱える,無知の証ともいえるのだ。著者は,患者の予測される予後,苦痛の強さ,治療抵抗性の確実さ,患者・家族の希望や価値観の4つの言葉を補助線として,鎮静という複雑な問題を整理する現実的な提案をしている。まだ国内では,鎮静をするべきだ,しないべきだという医療者同士の根本的な対立が続いている。しかし医療者の信念の対立を乗り越えるための議論を著者は望んでいるのだ。
私の知る著者は「本当に患者さんのためになる研究をしなくてはならない」と,常に医師としての姿勢がぶれることがない。医療者が観念的な議論をしている間にも,現実に患者は苦しみ続けている。「もやもや」している時間はそれほどないのだ。
書評者: 田代 志門 (国立がん研究センター社会と健康研究センター生命倫理研究室長)
現代の医学書としては珍しく「古典(クラシック)」になり得る本ではないか。言い換えれば,この本は今後数十年にわたり,鎮静に関する議論の出発点であり続けるだろう。もちろん,このテーマに関しては著者のものを含め,数多くの学術論文が書かれてきた。英語圏では論文集も3冊ほど出ている。しかしいずれも専門家向けであり,また鎮静の議論の全体像を提示するものではない。これに対して,本書は世界で初めて,「苦痛緩和のための鎮静」という,しばしば難しい倫理的判断を伴う医療行為の全体像を明らかにした本である。これは鎮静の問題が狭い「業界」の話ではなくなりつつある現在,大きな社会的意義がある。まずは日本語でこれを読める喜びをかみしめたい。
さて,この本の優れた点はいくつかあるが,ここでは2つに絞って述べておきたい。本書は大きくは前半(Part1)と後半(Part2)に分かれており,前半部は議論の前提となる知識の共有に割かれ,後半部ではそれに基づく著者の考察が展開されている。この前半部で特に秀逸なのが,鎮静概念とその倫理的正当化をめぐる過去30年の論争史を丁寧にまとめた箇所である。もちろん,併せて最新の医学的な知見も手際よく整理されており,医療者にとっては「明日から使える」知識も多く得られる。とはいえ,もし本書が単なる「最新の情報」の整理に終始しているのであれば,時とともにその内容は古びていくだろう。しかし「概念」や「歴史」に関する記述はそう簡単には古くはならない。「古典」と言ったのにはそういう意味がある。
もう一つこの本が優れているのは,鎮静と向き合う臨床家の「迷い」が丁寧に書かれている点である(著者の言葉でいえば「グレー」な判断がこれにあたる)。鎮静は論争的な医療であるし,それは今後数十年たってもそう大きくは変わらないのではないか。実際,意識を低下させることなく苦痛を緩和することができるのであれば,患者・家族も医療者も迷いなくそちらを選ぶだろう。しかし他に苦痛を緩和する手立てがなく,これ以上の苦痛を与え続けることは許容されないという局面に立たされたとき,鎮静は一つの選択肢として立ち現れる。なかでも,ある程度の余命が期待される患者の意識を急速に低下させるタイプの鎮静の開始は高度に倫理的な判断を伴う。この本が優れているのは,こうした判断の難しさを率直に認めたうえで,思考停止や安易な決断主義に陥ることなく,可能な限り「合理的に」考え抜こうとしているところである。
ところで,振り返って考えてみれば,実は多くの医療行為はこうした「迷い」を含みながら日々行われているものである〔「どんな治療にもグレーゾーンがある」(p.134)〕。これは医療が途上的技術(halfway technology)である以上,ある種の宿命といってもよいかもしれない。その点で,本書が緩和ケアを専門とする医療者だけではなく,あらゆる領域の医療者に広く読まれることを願う。
個人の信念を越えて,鎮静を巡る議論をするために
書評者: 新城 拓也 (しんじょう医院院長)
本書が出版されるとほぼ同時に,雑誌『文藝春秋』では「安楽死は是か非か」というタイトルで特集が組まれた。90歳となった脚本家の橋田壽賀子が,「私は安楽死で逝きたい」と真情を吐露し,せめて死ぬ選択は自分でしたいと考えを述べている。また同時に企画されたアンケートでは,日本の知識人の過半数は安楽死に賛成していた。その理由として,苦痛からの解放,当人の尊厳のためという意見があった。
医療を今まさに受けている市民にも,尊厳死,安楽死という言葉は浸透し,議論の萌芽は週刊誌でも日常的に見つけることができるようになった。そして,「眠ったまま最期を迎える鎮静」も市民が知るようになった。
本書は,苦痛緩和のための鎮静について,研究の歴史を辿りながら,現在の状況について述べられている。鎮静は,タイトルの通り,終末期の苦痛がなくならない時に最後の苦痛緩和の手段として行われている。国内では,がん患者の苦痛に対して行われており,日本緩和医療学会からガイドラインも発表されている。著者は多くの研究の知見を紹介すると共に,現時点で何が言えるのかについてぎりぎりの地点まで読者を連れて行こうと試みている。
冒頭で,「これは通常の治療なのか? 鎮静なのか? 安楽死なのか?」と事例を示して現場の「もやもや」について紹介している。一般市民,緩和医療を専門としない多くの医療者には,鎮静は,安楽死と何が異なるかよくわからない。安楽死も鎮静も苦痛からの解放を目的としている以上,どちらも同じようなものなのではないか,鎮静は安楽死の代替行為ではないのかと心のどこかで思っているのだ。
しかし,緩和医療の専門家は,安楽死と苦痛緩和のための鎮静は,全く異なると認識している。いや,全く異なると考えたいと思っている。国内で行われた大規模な研究でも,鎮静は生命予後を短縮していないことがわかった。しかし,鎮静薬の投与方法,量が適切で緩和医療の経験が十分な医師が実施すれば,という前提である。
冒頭の「もやもや」の正体とは,鎮静を巡る議論の言葉を持ち合わせていない医療者が抱える,無知の証ともいえるのだ。著者は,患者の予測される予後,苦痛の強さ,治療抵抗性の確実さ,患者・家族の希望や価値観の4つの言葉を補助線として,鎮静という複雑な問題を整理する現実的な提案をしている。まだ国内では,鎮静をするべきだ,しないべきだという医療者同士の根本的な対立が続いている。しかし医療者の信念の対立を乗り越えるための議論を著者は望んでいるのだ。
私の知る著者は「本当に患者さんのためになる研究をしなくてはならない」と,常に医師としての姿勢がぶれることがない。医療者が観念的な議論をしている間にも,現実に患者は苦しみ続けている。「もやもや」している時間はそれほどないのだ。