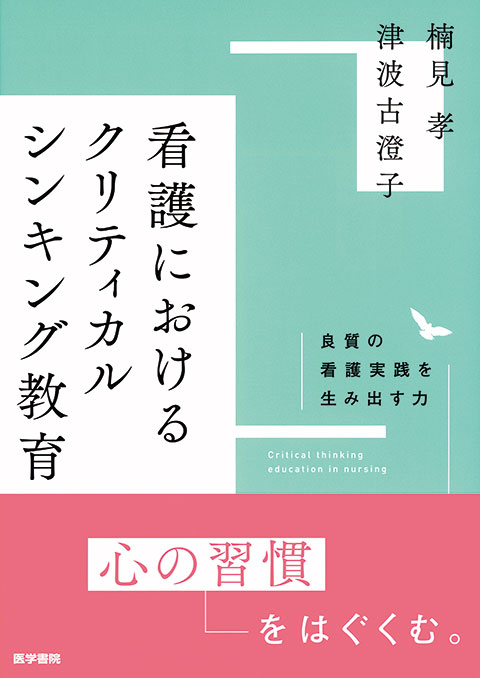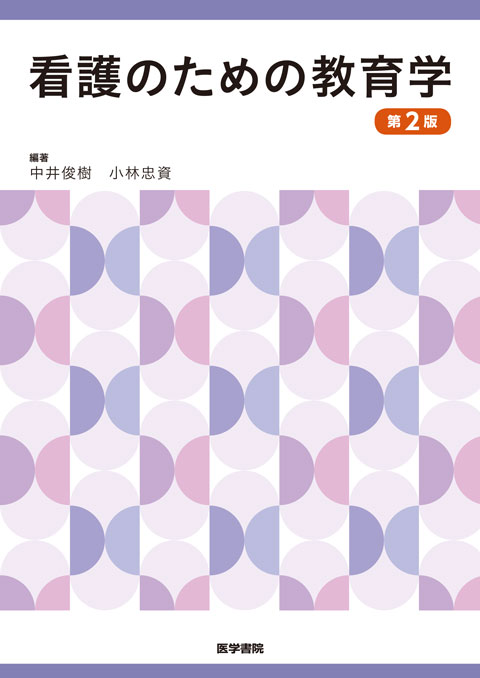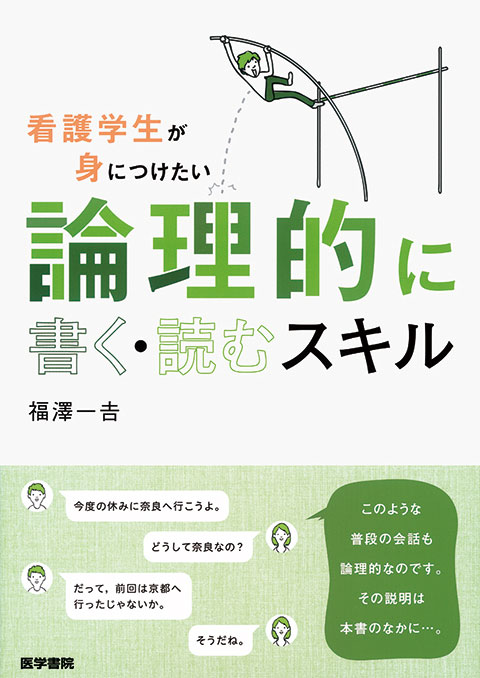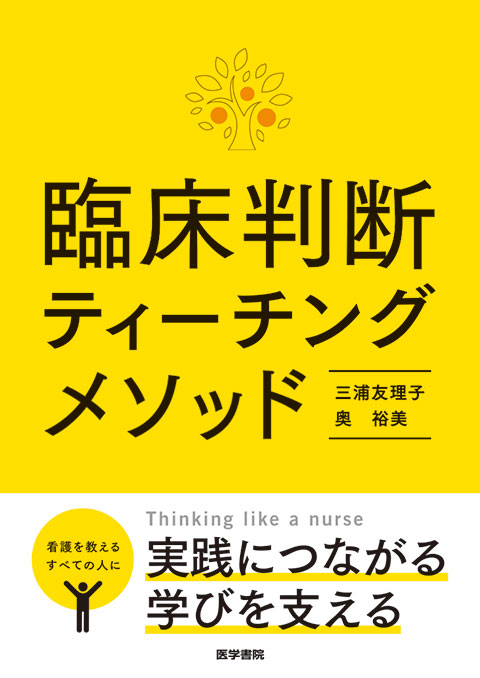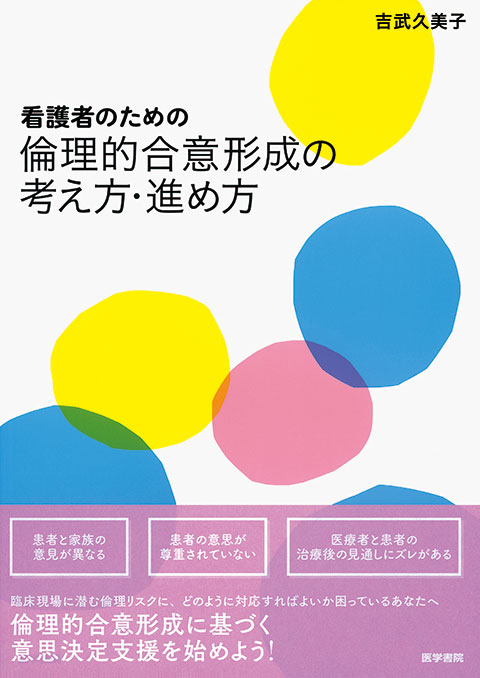看護におけるクリティカルシンキング教育
良質の看護実践を生み出す力
知識・技術の修得をめざす教育から、思考力・学びの態度をはぐくみ支える教育へ
もっと見る
看護師が自ら考え行動し、良質な看護を提供するうえで、クリティカルシンキング(批判的思考)は欠かすことのできない力の1つ。本書では、その思考力と態度の育成方法について、看護学、心理学の両分野から検討し、実践事例にもとづいて解説する。知識・技術の修得を目標とする従来の教育から、思考力・学びの態度をはぐくみ、学生自身の成長を支える教育へ。変わりゆく現場で日々模索を続けるすべての看護教育者、必携の書。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
本書の目的は,看護師が自ら考え行動し,良質な看護を提供するために,どのようなクリティカルシンキング(批判的思考)教育を実践すればよいのかを,看護学と心理学の両分野から検討することにあります。
クリティカルシンキングとは,第1に,相手の発言に耳を傾け,事実や気持ちを的確に理解・解釈する論理的思考,第2に,相手の考えだけでなく,自分の考えに誤りや偏りがないかを振り返る内省的思考です。具体的には,より良い看護を行うために,患者の情報を偏りなく集め,アセスメントを正確に行い,計画を立案し,適切な看護介入とその評価をするという看護過程において働いている思考です。こうした思考は心の習慣として身につけることによって,質の高い看護実践を行うことができるようになると考えます。
こうしたクリティカルシンキングを育成する看護教育については,日本では,1990年代後半からすぐれた翻訳書やオリジナルな本が出版されています。
本書がこれまでの本と異なる特色は,2つあります。
第1に,心理学に基づいてクリティカルシンキングのプロセスを看護過程に位置づけ,クリティカルシンキングに基づく思考力と態度の育成方法とその実践事例について述べている点です。とくに,職場に出てからの看護師の成長におけるクリティカルシンキングの役割に注目して,楠見が第1章で解説をしています。
第2に,米国の看護教育におけるクリティカルシンキング教育の変遷と動向を踏まえて,日本の看護教育に導入する際の困難,さらに,初年次から卒業時までの体系的なクリティカルシンキングを土台とした看護教育について述べている点です。とくに,上智大学総合人間科学部看護学科における実践例に基づいて津波古先生が,第2章から第4章において解説しています。
本書の対象は,主に,看護教育に携わっている教員,看護とクリティカルシンキング教育に関心をもつ研究者,さらに,看護師,大学院生,大学・専門学校の看護学生を考えています。本書を通して,看護教育に携わるみなさんに,看護においてクリティカルシンキングに基づく考える力と習慣が重要であること,そのためには,クリティカルシンキングを育む教育と評価が必要であることを伝えたいと考えています。さらに,本書を手がかりにして,読者のみなさんが,クリティカルシンキングに基づく実践を行うことによって,授業や看護の質を高め,学生や自らの成長につながることを願っています。
本書が,心理学者の私と看護学者の津波古先生との共著のかたちで,こうして実現したのは,私が津波古先生に招かれて,看護教育におけるクリティカルシンキングについて,2011~2013年の期間,3回にわたって上智大学総合人間科学部看護学科の教員を対象に講演したことが出発点です。これは本書の第1章のもとになっています。この時期は,同学科がスタートした時期とも重なっており,クリティカルシンキング教育を重視した体系的なカリキュラムがつくられ,その評価研究に協力する機会もいただきました。津波古先生には,看護教育に私がかかわる機会を与えてくださり,さらに共著者になっていただきましたことを,心から感謝申しあげます。
最後に,出版のきっかけをつくっていただいた七尾清氏,また,編集・制作にあたっては,医学書院の近江友香,野中久敬の各氏にお世話になりましたことを,お礼申しあげます。
2017年8月1日
楠見 孝
本書の目的は,看護師が自ら考え行動し,良質な看護を提供するために,どのようなクリティカルシンキング(批判的思考)教育を実践すればよいのかを,看護学と心理学の両分野から検討することにあります。
クリティカルシンキングとは,第1に,相手の発言に耳を傾け,事実や気持ちを的確に理解・解釈する論理的思考,第2に,相手の考えだけでなく,自分の考えに誤りや偏りがないかを振り返る内省的思考です。具体的には,より良い看護を行うために,患者の情報を偏りなく集め,アセスメントを正確に行い,計画を立案し,適切な看護介入とその評価をするという看護過程において働いている思考です。こうした思考は心の習慣として身につけることによって,質の高い看護実践を行うことができるようになると考えます。
こうしたクリティカルシンキングを育成する看護教育については,日本では,1990年代後半からすぐれた翻訳書やオリジナルな本が出版されています。
本書がこれまでの本と異なる特色は,2つあります。
第1に,心理学に基づいてクリティカルシンキングのプロセスを看護過程に位置づけ,クリティカルシンキングに基づく思考力と態度の育成方法とその実践事例について述べている点です。とくに,職場に出てからの看護師の成長におけるクリティカルシンキングの役割に注目して,楠見が第1章で解説をしています。
第2に,米国の看護教育におけるクリティカルシンキング教育の変遷と動向を踏まえて,日本の看護教育に導入する際の困難,さらに,初年次から卒業時までの体系的なクリティカルシンキングを土台とした看護教育について述べている点です。とくに,上智大学総合人間科学部看護学科における実践例に基づいて津波古先生が,第2章から第4章において解説しています。
本書の対象は,主に,看護教育に携わっている教員,看護とクリティカルシンキング教育に関心をもつ研究者,さらに,看護師,大学院生,大学・専門学校の看護学生を考えています。本書を通して,看護教育に携わるみなさんに,看護においてクリティカルシンキングに基づく考える力と習慣が重要であること,そのためには,クリティカルシンキングを育む教育と評価が必要であることを伝えたいと考えています。さらに,本書を手がかりにして,読者のみなさんが,クリティカルシンキングに基づく実践を行うことによって,授業や看護の質を高め,学生や自らの成長につながることを願っています。
本書が,心理学者の私と看護学者の津波古先生との共著のかたちで,こうして実現したのは,私が津波古先生に招かれて,看護教育におけるクリティカルシンキングについて,2011~2013年の期間,3回にわたって上智大学総合人間科学部看護学科の教員を対象に講演したことが出発点です。これは本書の第1章のもとになっています。この時期は,同学科がスタートした時期とも重なっており,クリティカルシンキング教育を重視した体系的なカリキュラムがつくられ,その評価研究に協力する機会もいただきました。津波古先生には,看護教育に私がかかわる機会を与えてくださり,さらに共著者になっていただきましたことを,心から感謝申しあげます。
最後に,出版のきっかけをつくっていただいた七尾清氏,また,編集・制作にあたっては,医学書院の近江友香,野中久敬の各氏にお世話になりましたことを,お礼申しあげます。
2017年8月1日
楠見 孝
目次
開く
はじめに
第1章 クリティカルシンキングの概念
001 クリティカルシンキングの育成:基礎的知識
1-1 クリティカルシンキングとは
1-2 クリティカルシンキングの歴史的背景
1-3 クリティカルシンキングのプロセスと構成要素
1-4 クリティカルシンキングの態度と知識
002 クリティカルシンキングの育成:教育実践と測定
2-1 クリティカルシンキングの教育がなぜ必要か
2-2 クリティカルシンキングの教育方法
2-3 クリティカルシンキング育成のための学習活動
2-4 クリティカルシンキングの評価
003 実践知の獲得を支えるクリティカルシンキング
3-1 仕事の熟達化による高度なクリティカルシンキング
3-2 熟達化のプロセス
3-3 仕事の熟達化における振り返り
3-4 仕事の熟達化に及ぼす経験学習態度
3-5 実践知を支えるスキル
004 実践から叡智へ
4-1 個人の発達における実践知と叡智の獲得
4-2 叡智の獲得とクリティカルなコミュニティの形成
4-3 すぐれた看護師を育てるために
第2章 看護教育におけるクリティカルシンキング
001 クリティカルシンキングの観点から看護教育を思考する
002 米国看護教育への導入
2-1 米国看護教育への導入の背景
2-2 看護実践の可視化
2-3 クリティカルシンキングと看護過程の類似性
2-4 米国看護教育評価機構による要請
2-5 クリティカルシンキングの領域固有性と看護の独自性
003 米国看護教育のクリティカルシンキング育成の変遷と動向
3-1 導入-定義と測定方法の模索
3-2 取り組みの評価-看護の独自性の明確化
3-3 再評価-習慣と認知スキルの育成
3-4 米国の取り組みから得られる課題と知見
004 看護教育のマインドセット
005 日本の看護教育におけるクリティカルシンキング
5-1 日本における現状
5-2 看護教育への定着の困難
5-3 課題と新しい知見
第3章 看護教育のカリキュラム・イノベーション
思考習慣・スキルとしての継続学習の推進と育成の方略
001 カリキュラム変革:クリティカルシンキングの育成をめざして
002 クリティカルシンキング・カリキュラムモデルの構築
2-1 カリキュラム作成
2-2 教育理念の基盤と3つの軸
2-3 卒業時到達目標の達成プロセス
003 学年進行に合わせたカリキュラムの構築
3-1 クリティカルシンキング育成の基盤となるもの
3-2 段階的な学び-クリティカルシンキングと良質思考
004 クリティカルシンキング育成の方法
4-1 汎用(general)アプローチを用いた事例
4-2 導入(infusion)アプローチを用いた事例
005 クリティカルシンキング育成を促進する概念-基盤学習
第4章 良質の看護実践とクリティカルシンキング
001 “問う”アート
1-1 基盤となる思考力の育成に向けたアプローチ
1-2 専門職としての思考の育成に向けたアプローチ
1-3 質問力を高める風土の形成
002 クリティカルシンキングのツールとしての看護過程がめざすもの
2-1 ツールあるいは方法としての看護過程
2-2 看護過程の積み重ねでめざす看護の力
2-3 看護過程とクリティカルシンキングの融合
2-4 初学者の段階別看護過程学習と専門家・熟達者の看護実践モデル
2-5 クリティカルシンキングに基づく看護過程モデル
終章 看護教育を超えて 看護師を支える良質の習慣的思考と良質の看護実践
001 “良質”とは何を指すのか
002 実践知としてのクリティカルシンキング
索引
第1章 クリティカルシンキングの概念
001 クリティカルシンキングの育成:基礎的知識
1-1 クリティカルシンキングとは
1-2 クリティカルシンキングの歴史的背景
1-3 クリティカルシンキングのプロセスと構成要素
1-4 クリティカルシンキングの態度と知識
002 クリティカルシンキングの育成:教育実践と測定
2-1 クリティカルシンキングの教育がなぜ必要か
2-2 クリティカルシンキングの教育方法
2-3 クリティカルシンキング育成のための学習活動
2-4 クリティカルシンキングの評価
003 実践知の獲得を支えるクリティカルシンキング
3-1 仕事の熟達化による高度なクリティカルシンキング
3-2 熟達化のプロセス
3-3 仕事の熟達化における振り返り
3-4 仕事の熟達化に及ぼす経験学習態度
3-5 実践知を支えるスキル
004 実践から叡智へ
4-1 個人の発達における実践知と叡智の獲得
4-2 叡智の獲得とクリティカルなコミュニティの形成
4-3 すぐれた看護師を育てるために
第2章 看護教育におけるクリティカルシンキング
001 クリティカルシンキングの観点から看護教育を思考する
002 米国看護教育への導入
2-1 米国看護教育への導入の背景
2-2 看護実践の可視化
2-3 クリティカルシンキングと看護過程の類似性
2-4 米国看護教育評価機構による要請
2-5 クリティカルシンキングの領域固有性と看護の独自性
003 米国看護教育のクリティカルシンキング育成の変遷と動向
3-1 導入-定義と測定方法の模索
3-2 取り組みの評価-看護の独自性の明確化
3-3 再評価-習慣と認知スキルの育成
3-4 米国の取り組みから得られる課題と知見
004 看護教育のマインドセット
005 日本の看護教育におけるクリティカルシンキング
5-1 日本における現状
5-2 看護教育への定着の困難
5-3 課題と新しい知見
第3章 看護教育のカリキュラム・イノベーション
思考習慣・スキルとしての継続学習の推進と育成の方略
001 カリキュラム変革:クリティカルシンキングの育成をめざして
002 クリティカルシンキング・カリキュラムモデルの構築
2-1 カリキュラム作成
2-2 教育理念の基盤と3つの軸
2-3 卒業時到達目標の達成プロセス
003 学年進行に合わせたカリキュラムの構築
3-1 クリティカルシンキング育成の基盤となるもの
3-2 段階的な学び-クリティカルシンキングと良質思考
004 クリティカルシンキング育成の方法
4-1 汎用(general)アプローチを用いた事例
4-2 導入(infusion)アプローチを用いた事例
005 クリティカルシンキング育成を促進する概念-基盤学習
第4章 良質の看護実践とクリティカルシンキング
001 “問う”アート
1-1 基盤となる思考力の育成に向けたアプローチ
1-2 専門職としての思考の育成に向けたアプローチ
1-3 質問力を高める風土の形成
002 クリティカルシンキングのツールとしての看護過程がめざすもの
2-1 ツールあるいは方法としての看護過程
2-2 看護過程の積み重ねでめざす看護の力
2-3 看護過程とクリティカルシンキングの融合
2-4 初学者の段階別看護過程学習と専門家・熟達者の看護実践モデル
2-5 クリティカルシンキングに基づく看護過程モデル
終章 看護教育を超えて 看護師を支える良質の習慣的思考と良質の看護実践
001 “良質”とは何を指すのか
002 実践知としてのクリティカルシンキング
索引
書評
開く
これからの看護基礎教育を考える上での示唆に富んだ一冊
書評者: 池西 靜江 (Office Kyo-Shien代表)
看護実践能力の中核となるのは,“専門的知識を活用して状況判断を行い,看護師としてどう行動すべきかを考える実践的思考力”であると思う。その育成方法は,これまで“看護過程教育”が主流であった。しかし,医療を取り巻く環境の変化で,従来型の看護過程教育は思考の型のトレーニングに終わり,実践に結び付かないものになっていた。そこで私はポスト“看護過程”を探していた。
数年前,楠見孝先生(京大大学院教授)の講演を聴講する機会を得て,看護過程の意義を再確認し,ポスト“看護過程”ではなく,看護過程を支えるクリティカルシンキング教育の充実にその答えがあるように思えた。20年近く前『基本から学ぶ看護過程と看護診断』(ロザリンダ・アルファロ-ルフィーバ,医学書院)を手にして以来しばらくの間マイブームを起こし,その後印象が薄れていたクリティカルシンキングに,再び光を当てたいと思った。
以降,私は楠見先生の数々の著書をひもとき,その理解を深めてきた。しかし,看護基礎教育,そして看護過程教育で,それをどう活かすのかについて,十分な答えが見いだせずにいた。そんな時,本書が刊行された。ワクワクとした期待を抱いて読み始めると,期待に反せず,これからの看護基礎教育を考えるのに必要と思われるいくつかの示唆が得られた。
1つ目は,カリキュラム改正が近々にあろうこの時期を踏まえ,カリキュラムへの提言があったことである。「いきなり専門科目や看護実践場面でクリティカルシンキングを活かそう,といっても無理な話である」(第3章,p.82)とあるように,カリキュラムの中で段階的に教える必要性と具体例が解説されている。楠見先生の行う“クリティカルシンキング育成の初年次ゼミ”などは,特に基礎分野教育において,十分参考になるものである。また,専門分野では「具体的場面での問題解決過程全体のなかで教えるほうが学習効果が大きい」とある(第2章,p.15)。講義,演習,そして臨地実習で,“看護場面”を教材にしたクリティカルシンキングのトレーニングを取り入れ,段階的・継続的な構築ができるとよいと思う。クリティカルシンキングの評価も早速活用してみたい内容である。
2つ目は,クリティカルシンキングと看護過程との類似性が示されている点である。クリティカルシンキングの中核となる“相手の話を傾聴し感情を理解すること”や“データに基づく偏りのない思考”は,個別的で最善の看護をめざす看護過程において,ことさら大切である。その基盤となるのが“推論の土台の検討”である。看護過程教育でこれをどう強化するかが課題であろう。また,第4章で,臨床判断モデルと基礎的な看護過程を,段階的統合と同時的実践知統合の2つの段階に分けて説明している点も興味深い。
3つ目は,本書で提示されるクリティカルシンキングの教育方法に,私の教育実践と共通するものが多かった点である。私は看護場面を教材にして,ワークシートを活用し自ら考え,他者と話し合う機会を多く導入している。さらに「発問」を通して学生の思考を促すことを心がけている。このような教育方法がクリティカルシンキングを培うものであることを再確認し,自信を得ることができた。
読み終えて,改めて,クリティカルシンキング教育は看護基礎教育に時間を割いて取り入れるべきものである,と実感する。
書評者: 池西 靜江 (Office Kyo-Shien代表)
看護実践能力の中核となるのは,“専門的知識を活用して状況判断を行い,看護師としてどう行動すべきかを考える実践的思考力”であると思う。その育成方法は,これまで“看護過程教育”が主流であった。しかし,医療を取り巻く環境の変化で,従来型の看護過程教育は思考の型のトレーニングに終わり,実践に結び付かないものになっていた。そこで私はポスト“看護過程”を探していた。
数年前,楠見孝先生(京大大学院教授)の講演を聴講する機会を得て,看護過程の意義を再確認し,ポスト“看護過程”ではなく,看護過程を支えるクリティカルシンキング教育の充実にその答えがあるように思えた。20年近く前『基本から学ぶ看護過程と看護診断』(ロザリンダ・アルファロ-ルフィーバ,医学書院)を手にして以来しばらくの間マイブームを起こし,その後印象が薄れていたクリティカルシンキングに,再び光を当てたいと思った。
以降,私は楠見先生の数々の著書をひもとき,その理解を深めてきた。しかし,看護基礎教育,そして看護過程教育で,それをどう活かすのかについて,十分な答えが見いだせずにいた。そんな時,本書が刊行された。ワクワクとした期待を抱いて読み始めると,期待に反せず,これからの看護基礎教育を考えるのに必要と思われるいくつかの示唆が得られた。
1つ目は,カリキュラム改正が近々にあろうこの時期を踏まえ,カリキュラムへの提言があったことである。「いきなり専門科目や看護実践場面でクリティカルシンキングを活かそう,といっても無理な話である」(第3章,p.82)とあるように,カリキュラムの中で段階的に教える必要性と具体例が解説されている。楠見先生の行う“クリティカルシンキング育成の初年次ゼミ”などは,特に基礎分野教育において,十分参考になるものである。また,専門分野では「具体的場面での問題解決過程全体のなかで教えるほうが学習効果が大きい」とある(第2章,p.15)。講義,演習,そして臨地実習で,“看護場面”を教材にしたクリティカルシンキングのトレーニングを取り入れ,段階的・継続的な構築ができるとよいと思う。クリティカルシンキングの評価も早速活用してみたい内容である。
2つ目は,クリティカルシンキングと看護過程との類似性が示されている点である。クリティカルシンキングの中核となる“相手の話を傾聴し感情を理解すること”や“データに基づく偏りのない思考”は,個別的で最善の看護をめざす看護過程において,ことさら大切である。その基盤となるのが“推論の土台の検討”である。看護過程教育でこれをどう強化するかが課題であろう。また,第4章で,臨床判断モデルと基礎的な看護過程を,段階的統合と同時的実践知統合の2つの段階に分けて説明している点も興味深い。
3つ目は,本書で提示されるクリティカルシンキングの教育方法に,私の教育実践と共通するものが多かった点である。私は看護場面を教材にして,ワークシートを活用し自ら考え,他者と話し合う機会を多く導入している。さらに「発問」を通して学生の思考を促すことを心がけている。このような教育方法がクリティカルシンキングを培うものであることを再確認し,自信を得ることができた。
読み終えて,改めて,クリティカルシンキング教育は看護基礎教育に時間を割いて取り入れるべきものである,と実感する。